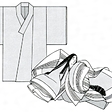精選版 日本国語大辞典 「小袿」の意味・読み・例文・類語
日本大百科全書(ニッポニカ) 「小袿」の意味・わかりやすい解説
小袿
こうちぎ
公家(くげ)女子衣服の一種。平安時代以来、高位の者の準正装として用いられた上着。垂領(たりくび)、広袖(ひろそで)形式で、袿(うちき)より袖幅がやや少なく、身丈が短い。袿を数領重ねた上に着て、改まったときには唐衣(からぎぬ)のかわりに小袿を着て裳(も)を腰につける。小袿姿の図として、『源氏物語絵巻』「宿木(やどりぎ)」の段の六の君、『紫式部日記絵巻』の中宮彰子(しょうし)があげられる。鶴岡八幡(つるがおかはちまん)宮蔵御神宝装束の小袿は鎌倉時代の遺品である。近世の小袿は袿とまったく同形で、中倍(なかべ)といわれる絹地を、表地と裏地の間に挟んで仕立てたものを称している。明治時代以後は皇后、皇太子妃、皇族妃、内親王が宮廷祭儀の軽重により、小袿に五衣(いつつぎぬ)、単(ひとえ)、長袴(ながばかま)、檜扇(ひおうぎ)の装束と、これから五衣を省いたものを用いる。
[高田倭男]
山川 日本史小辞典 改訂新版 「小袿」の解説
小袿
こうちき
女装で,肌着と表着(うわぎ)の間に着用する袿(うちき)を小型にしたてたもの。平安時代には女房装束を略す際,唐衣(からぎぬ)と裳(も)を省略し重ね袿姿にするが,時として袿の最上部をはなやかな織物にして裾短にしたて唐衣代とし,小袿と称した。鎌倉時代には小袖(こそで)に紅袴,単(ひとえ)に袿を3領または5領重ねた三衣(みつぎぬ)・五衣(いつつぎぬ)の上に着用し,改まったときは表着の上に小袿をつけた。鶴岡八幡宮の神服の小袿は表地に二陪(ふたえ)織物,裏地に縠紗(こめしゃ)を,中陪(なかべ)として平絹を加えた三陪の捻重(ひねりがさね)である。戦国期以降,女房装束が中絶し,表着も袿もすべて「おめり」と称する表地の周辺に裏地をのぞかせる様式になると,おめりの部分のわずかな幅に中陪をいれて三陪重らしくみせ,小袿と称するようになった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「小袿」の解説
小袿
こうちぎ
十二単 (じゆうにひとえ) の略装で,唐衣・裳の代わりに表着 (うわぎ) の上に着用した。表着・重袿 (かさねうちぎ) ・単 (ひとえ) などの袿類より,いくぶん小ぶりにつくられているので小袿という。男子の束帯に対する衣冠に相当する。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の小袿の言及
【袿】より
…つまり,表面に重ねて着ていたものを脱いで,内部に着ていた袿が表に出て,これが表着となったのである。袿は本来袷であったが,その襟,袖,裾の中間にさらに中倍(なかべ)という裂(きれ)を入れて,表,中,裏と重色目を3色に見せたものを小袿といった。高貴の女姓などは,この美しい小袿を着用した。…
【服装】より
…後世,十二単(じゆうにひとえ)と呼んだもので,ここに貴族的な優美な女装が完成された。これに対して,女子日常の服装として小袿姿,袿姿,小袖袴などの服装が行われた。小袿は礼装の唐衣に代わるものとされ,袿に表着を着て裳をまとった上にこれを着たり,また表着,裳を略してこれを着ることもあった。…
※「小袿」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...