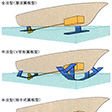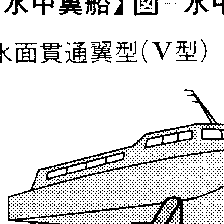精選版 日本国語大辞典 「水中翼船」の意味・読み・例文・類語
すいちゅうよく‐せん【水中翼船】
日本大百科全書(ニッポニカ) 「水中翼船」の意味・わかりやすい解説
水中翼船
すいちゅうよくせん
hydrofoil craft
高速船艇の一種。船体の下部から出た数本の支柱の下端に、船底面とほぼ平行に取り付けた翼板(水中翼。ハイドロフォイルともいう)によって生ずる揚力で船体を水上に持ち上げ、船体に受ける水の抵抗を減じて高速を得ようとするもの。原理的には航空機と同じである。前進の始めにおいては、一般の船と同様に船体の浮力で水に浮いているが、速力が増すにつれて水中翼の揚力が大きくなり、船体がしだいに押し上げられて水面を滑走し、さらに速力が増すと船体は水面から離れて、水中には翼板と推進器のみを残して高速運航する。
[茂在寅男]
特色
水中翼船は、(1)同馬力の一般船の約3倍の速力が得られる、(2)型によっては波浪の影響が少なく安定して高速が得られる、(3)自船がおこす波が非常に小さく周囲にかける迷惑が少ない、(4)運動性能がよく、旋回半径が小さく、発進や停止のための航走距離が短い、などの特長のために急速に普及した。その反面、(1)外洋航路には向かず、(2)波しぶきが激しく、(3)エンジン音や振動がうるさく乗り心地がよくない、などのことから普及には限界を生じた。また船体を大型にすると水中翼も大面積にせざるをえず、高速化には限界が生ずる。したがって、一般的には全重量400トンから500トン程度までとされている。
[茂在寅男]
沿革
実験船としては1906年、イタリアの技術者フォルラニーニEnrico Forlanini(1848―1930)が、スイスとの国境にあるマッジョーレ湖で試作実験を行ったのが最初である。この船は数枚の翼板を階段式に重ねた方式で、38ノット(時速約70キロメートル)の高速を得た。3年後、アメリカで一段水中翼方式の試作に成功し、1927年にはドイツで水面貫通方式が成功している。実用船としては、スイスのシュプラマール社が1952年に第一船を建造し、その後イタリア、ソ連、アメリカ、日本などで建造されるようになった。商業用としては、1956年、イタリア本土とシチリア島を結ぶ航路に就航したのが最初である。1957年にはソ連で最初の大型指向のコメタ‐M型(全長35メートル、幅6メートル、満載排水量59トン、速力32ノット、船客定員116人)が進水し、バイカル湖などで就航のほか、イタリアやモロッコにも輸出された。これを契機に各国で大型化が進み、1965年にアメリカのシアトルで進水した海軍用のプレーンビューは、満載排水量314トンで50ノットの高速を記録した。デンマーク、マルモ社の連絡船超PTS150‐MkⅢは、165トン、250人の旅客を乗せ速力40ノットでスウェーデン―デンマーク間に就航した。
水中翼船は高速性を生かして、対潜水艦用や水上艦艇迎撃用ミサイル艇など軍用にも使われている。アメリカのミサイル水中翼艇トーラス号(長さ40.5メートル、幅8.6メートル、速力48ノット、ウォータージェット推進、乗員21人)などが代表的である。
[茂在寅男]
型式と構造
高速航走時に水中翼の全部が水中に没している全没型と、翼の一部が水面上に出る半没型の二つがある。また翼の構造から、固定型と揚降型がある。
全没型はさらに、深度効果翼板型と潜没翼板型に分けられる。前者は浅海用で、水面下浅い一定の深度を自動的に保つようになっており、静水のみで有効である。後者は比較的波の荒い海面でも安定を得る効果があり、翼傾斜を自動的に調節する装置をもち、翼を水中深く潜没させる。両型式とも翼にフラップflap(昇降舵(だ))を備えていて、効果を高めるようになっている。
半没型は翼板のどこかで水面を貫くので、水面貫通型ともいわれる。階段式または梯子(はしご)式翼板型とV字形翼板型がある。前者は、何枚もの翼板を階段のように縦に重ねて取り付け、速度があがるにしたがって下部の翼板だけが水中に残る方式である。後者は、上部の開いたV字形かW字形の翼板をもつ方式で、速力の増大にしたがって浮かび上がり翼面積が減少する。船体傾斜時には復原作用があり、旅客用にもっとも広く普及した型である。
揚降式翼板は、高速で水中翼の揚力によって航走するフォイルボーンfoil-bornと、航続距離を要求される場合の船体浮力にのって航走するハルボーンhull-bornとの切り替えが自由にできるものである。このため、水中翼板取付け用支柱の根元が丁番(ちょうつがい)式になっており、翼板を水面上に引き上げることが可能である。
[茂在寅男]
日本での水中翼船
1962年(昭和37)日立造船(現、カナデビア)がスイスのシュプラマール社と技術提携して製造を開始したPT20型が最初で、以来他社でも製造、おもに伊勢(いせ)湾などの湾内や瀬戸内海などに導入された。大型では、アメリカのボーイング社が開発したジェットフォイル・ボートを1977年に佐渡汽船が日本で初めて導入、新潟―両津港間に就航した。2024年時点で、同航路には「ぎんが」(277総トン、全長23.44メートル、46ノット、船客定員244人)ほか2隻が就航している。
[茂在寅男]
改訂新版 世界大百科事典 「水中翼船」の意味・わかりやすい解説
水中翼船 (すいちゅうよくせん)
hydrofoil boat
船体下部の前後に,支柱(ストラット)によって取り付けられた水中翼をもち,水中翼の発生する揚力により船体を水面上に浮揚させて航走する船。水中翼をもつ船は,1861年にイギリスで初めて浮上航走したといわれ,1919年には,約70ノットの高速力を出した記録がある。近年の実用船では経済性などの理由により,船速は35~60ノット程度である。
水中翼(ハイドロフォイルhydrofoilという)の断面形状は流線形で,流れに対して迎え角をもつように航走すると,飛行機の翼と同じように,翼の上下面の圧力差により揚力を発生する。この揚力は,翼の迎え角や翼面積に比例し,速力の2乗に比例する。したがって,水中翼船では,低速時は通常の船と同じように水上を航行するが,船速が増すにつれて水中翼の発生する揚力が大きくなり,揚力が船体重量(全備重量もしくは排水量)とつりあう速力で船体は浮上し,翼走状態となる。
水中翼船の型式は,水中翼の形状により水面貫通翼型(面積制御型ともいう)と全没翼型(迎え角制御型ともいう)に分けられる。水面貫通翼型の水中翼船surface piercing hydrofoilは,船体に固定されたV型,あるいはW型の翼をもち,揚力を発生する翼部分が水面を貫通して水面の上下にあるため,翼走状態では,船体が上昇すれば翼面積が減少し,自動的に一定の揚力を保ちながら航走できる点に特徴がある。また,船体が横傾斜した場合でも,左右の翼面積の違いによる揚力の増減により,自動的に姿勢を戻す復原作用がある。一方,全没翼型水中翼船fully submerged hydrofoilでは,翼はつねに水面下にあるため,機械的に翼の迎え角を制御し,揚力を調節する自動安定装置が必要となるが,つねに船体の姿勢や浮上高さを検知し,高度な迎え角制御を行うことによって揺れを少なくすることができ,乗りごこちに優れる。また,翼面積を小さくできるため,抵抗が減少し,水面貫通翼型に比べて,より高速走行が可能となる。
水中翼船は,その高速性を生かして,軍用艇や旅客船として用いられている。軍用艇としては第2次世界大戦中ドイツで排水量81トンの水面貫通翼型が用いられたことがあるが,本格化したのは大戦後,アメリカで自動安定装置付きの全没翼型が開発されてからで,現在では高速ミサイル艇としてアメリカ海軍で就役している。旧ソ連でも,大型の軍用艇が建造されたが,水中翼型式は,前翼が水面貫通翼型,後翼が全没翼型フラップ付きである。商業艇としては,スイスのシュプラマール社の水面貫通翼型が広く採用されており,日本でも1961年以来瀬戸内海航路などに旅客船として就航している。また,全没翼型旅客船は,アメリカのボーイング社のジェットフォイルが佐渡航路に就航している。
水中翼船は,滑走艇に比べて高速性に優れるが,船体重量を水中翼の揚力で支えるため,船体が大型化するほど翼面積が大きくなり,高速を出すことが困難となる。一般には,全備重量400~500トン程度が経済的な大型化の限界であろうといわれている。
執筆者:国武 吉邦
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「水中翼船」の意味・わかりやすい解説
水中翼船
すいちゅうよくせん
hydrofoil boat
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「水中翼船」の意味・わかりやすい解説
水中翼船【すいちゅうよくせん】
→関連項目ジェット推進船|船
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
世界大百科事典(旧版)内の水中翼船の言及
【舟∥船】より
…バラストタンクへの注排水によって潜水,浮上を行い,細かい深度の調整には潜舵と横舵を用いる。 水中翼船は浮力の代りに水中翼に生ずる揚力によって船の重量を支える。水面貫通型の水中翼をもつ場合,船が傾斜すれば傾斜した側の水中翼面積が反対側より大きくなるため復原力を生ずる。…
※「水中翼船」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...