知能指数(読み)チノウシスウ(その他表記)intelligence quotient
精選版 日本国語大辞典 「知能指数」の意味・読み・例文・類語
ちのう‐しすう【知能指数】
日本大百科全書(ニッポニカ) 「知能指数」の意味・わかりやすい解説
知能指数
ちのうしすう
intelligence quotient 英語
Intelligenzquotient ドイツ語
quotient d'intelligence フランス語
略してIQという。知能検査の結果の表示法の一つ。ビネー式知能検査では、合格した問題の数あるいは合計得点を精神年齢(知能年齢)に換算する。しかし、精神年齢だけでは異なる年齢間の比較に不便であるから、1912年にシュテルンが示唆した知能指数を算出することが多い。知能指数は次の式によって求められる。
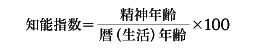
なお、年齢はすべて月齢に換算して計算する。知能指数は平均が100、標準偏差が15ないし16のほぼ正規分布に近い分布をすることが経験的に知られている。
しかし、15歳以上になると知能検査得点の上昇が鈍化し、暦年齢に比例しなくなる。したがって、知能指数(比率IQともいう)を用いると不合理な結果を生じる。そこで偏差知能指数deviation IQ(偏差IQ)が用いられる。これはウェックスラー式知能検査で初めて採用された方式であるが、同一年齢集団内の相対的位置を示すもので、次の式によって求められる。
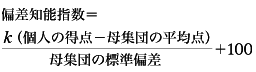
なお、kの値はウェックスラー式検査では15、スタンフォード改訂ビネー式検査(1960年版)では16、その他まれには20とする知能検査もある。身体的および環境的条件が激変しない限り知能指数は年齢が上昇しても大きく変わることはないと考えられてきた。しかし、同一個人を長期間追跡した研究は、知能指数がつねに恒常であるとは限らないことを示している。とくに、学童期以前の知能指数は変動しやすい。
集団的に求められた知能指数は人間、民族、性別による差があることが多くの研究によって確認されている。しかし、1960年代のアメリカでは、公民権運動の高まりのなかで教育や職業における知能指数による差別が批判の対象となった。そこで、特定集団に対する検査得点の偏り(バイアス)については、偏りの少ない検査の作成や差別を招かないような検査結果の利用方法がくふうされるようになった。
従来の知能検査は学習能力あるいは情報処理能力という認知的能力を測定するものと考えられてきたが、ガードナーHoward Gardner(1943― )は多様な知的能力を包括する多知能論を提唱した(1983)。これは言語的知能、論理的・数学的知能、空間的知能、音楽的知能、身体的・運動的知能、対人的知能、個人内知能の7種の知的能力を含んでいる。このなかの対人的および個人内知能に近い概念を1990年サロベイPeter SaloveyとマイヤーJ. D. Mayerは情動的知能emotional intelligenceとよんだ。その後ゴールマンDaniel Galeman(1946― )が『情動的知能』を単行本として出版し(1995)、これが週刊誌『タイム』にEQという用語で紹介されたために、EQが情動的知能を表す用語として定着した。EQはIQに対比するために使われた用語であるが、知能指数とは違いそれを測定する検査はまだ標準化されていない。なお、EQとは主として自己の情動を自覚し制御できる能力と他者の情動を推察し対応できる能力をさす。
[肥田野直]
『タイラー著、高田洋一郎訳『テストと測定』(1966・岩波書店)』▽『ダニエル・ゴールマン著、土屋京子訳『EQ こころの知能指数』(1998・講談社)』▽『佐藤達哉著『知能指数』(講談社現代新書)』
百科事典マイペディア 「知能指数」の意味・わかりやすい解説
知能指数【ちのうしすう】
→関連項目EQ
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
改訂新版 世界大百科事典 「知能指数」の意味・わかりやすい解説
知能指数 (ちのうしすう)
→知能
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
栄養・生化学辞典 「知能指数」の解説
知能指数
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「知能指数」の意味・わかりやすい解説
知能指数
ちのうしすう
「IQ」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の知能指数の言及
【精神年齢】より
…すなわち,子どもの知能得点がどの年齢の平均点に等しいかを調べることにより,精神年齢を決定するのである。精神年齢は,つねに生活年齢と比較されなければならないので,一般には,精神年齢と生活年齢との比を示す指標である知能指数が用いられている。精神年齢は,知能が年齢とともに発達していく範囲内(16歳ごろまで)でのみ意味を持つのであって,それ以上の年齢の知能水準を示すことはできないのが欠点である。…
【知能】より
…そこで一般には,知能とは知能テストで測定される能力であるという操作的定義(測定操作による定義)が,採用されている。 知能テストによって測定された結果は,精神年齢mental age(MA),知能指数intelligence quotient(IQ),知能偏差値T‐scoreなどによって表示される。たとえばビネ式知能テストでは,年齢別にテスト問題が配当されており,子どもがどの年齢相当の問題まで合格したかに応じて,その子どもの精神年齢が決定される。…
【知能テスト】より
…その測定結果は,一定の基準にてらして数量的に表示される。この場合,知能の一般的傾向を総括的にとらえる一般知能テストでは,精神年齢,知能指数,知能偏差値など,単一の指標であらわされるが,知能の特性により選択された下位検査にもとづいて各領域で働く知能を診断的にとらえる診断性知能テストでは,テスト得点がプロフィルとして描かれる。また,知能テストには,その施行様式からみて,個人を対象とする個別式知能テストと,集団を対象とする集団式知能テストとがあり,さらに問題構成様式からみて,主として言語を用いる言語式(A式)知能テストと,数字,記号,図形などだけによる作業式(B式)知能テストがある。…
※「知能指数」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...

