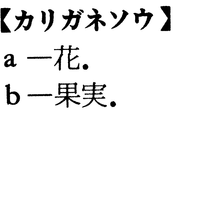カリガネソウ
Caryopteris divaricata(Sieb.et Zucc.)Maxim.
林のふちなどの草地に生える,クマツヅラ科の多年草。茎や葉にふれるといやな匂いがする。茎は四稜形で高さ1m内外,葉は対生し,卵形で鋸歯があり,長さ8~13cm,幅4~8cm,葉柄がある。8~9月ごろ,茎の上部の枝先にまばらな集散花序を作り,青紫色の花をつける。萼は緑色で小さく,5裂する。花冠は下半部が筒状で約1cm,先は4裂して大きく開口し,下側の裂片は反曲して少し長い。4本のおしべおよび花柱は長さ約3cm,花の外につき出して湾曲している。日本から朝鮮半島および中国にかけて分布する。和名は雁草の意味である。一名,帆掛草(ほかけそう)ともいう。いずれも花の形にもとづく。ダンギクC.incana Miq.は九州から中国大陸に分布する多年草だが,切花や花壇用に栽植される。また中国では風邪などに対して用いられる。
カリガネソウ属Caryopteris(英名bluebeard)は日本から中国,ヒマラヤにかけて分布し,約10種が知られている。
執筆者:村田 源
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
カリガネソウ
かりがねそう / 雁草
[学] Tripora divaricata (Maxim.) P.D.Cantino
Caryopteris divaricata (Sieb. et Zucc.) Maxim.
クマツヅラ科(APG分類:シソ科)の多年草。茎は高さ0.8~1.2メートル。全草に強い香りがある。葉は対生し、広卵形で先は鋭くとがり、縁辺に鈍い鋸歯(きょし)がある。8~9月、葉腋(ようえき)に花茎を伸ばし、集散花序をなして青紫色の花を開く。花冠の基部は筒状、先は唇形状に大きく開き、4本の雄しべと花柱が湾曲して花冠外へ長く飛び出る。北海道、本州、四国、九州の丘陵帯や山地帯の渓流の岸や日陰の林縁に生え、朝鮮、中国にも分布する。名は、花の形をカリ(雁)の飛ぶ姿に見立てたもの。カリガネソウは、かつてはダンギク属であったが1999年に新しくカリガネソウ属として分離した。
[高橋秀男 2021年8月20日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
カリガネソウ(雁金草)
カリガネソウ
Caryopteris coreana
クマツヅラ科の多年草。一名ホカケソウともいう。日本各地の山野に自生する。高さ 1m内外,茎は方形で直立し,葉は柄があって対生し,卵形で縁に鈍鋸歯がある。全草に悪臭がある。茎の上部には節ごとに分枝を生じ,紫色の唇形花をつける。花柱と4本あるおしべが長く突出している形からそれをガン (雁) や帆船にたとえて雁金草,帆掛草の名がつけられた。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
百科事典マイペディア
「カリガネソウ」の意味・わかりやすい解説
カリガネソウ
ホカケソウとも。クマツヅラ科の多年草。北海道〜九州,東アジアに分布し,山地のやや湿った所にはえる。全草に強い臭気があり,茎は四角形で直立し,高さ1m内外,卵形で長い柄のある葉を対生。8〜9月,葉腋から出る長い柄の先に紫色の花をまばらにつける。花冠は唇形(しんけい)で,おしべとめしべは長く,湾曲して外へ突き出る。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by