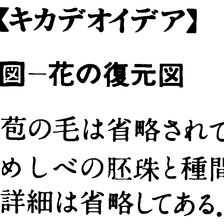キカデオイデア
Cycadeoidea
シカデオイデア,サイカデオイデアとも読む。ベネチテス目に属する化石植物の幹部に与えられた器官属名。幹は大小さまざまで,一般に球形もしくは短い円柱形。幹のまわりには,らせん状に配列する葉柄痕があり,その腋部(えきぶ)に両性花がつくが,花冠(花びら)はない。かつてこの植物をくわしく調べたアメリカのG.R.ウィーランドは,おしべの形はシダの葉に似ていて,これが花びらのようにみえると考えた。従来の教科書に掲載されているこの植物の復元図は,ウィーランドの考えによったものである。ところが最近,この植物を再びくわしく調べたアメリカのT.デリボリアスは,おしべはシダの葉のように広がったものではないことを明らかにしている。おもに北半球の白亜系からケイ化木状となって多産し,日本では岩手県および北海道の白亜系からの産出がよく知られている。どのような葉がついていたかはなお不明である。
執筆者:木村 達明
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
キカデオイデア
Cycadeoidea
裸子植物ソテツ綱ベネチテス目に属する化石植物。白亜紀前期に繁茂した。外形はソテツ類によく似ているが,花は被子植物のモクレン科のものに似た点がある。落葉のあとが菱形をし,螺旋状に配列する。葉柄痕の間には多細胞の鱗毛が密生する。葉柄痕には一定の輪郭にそろって並ぶ維管束が見られる。シダ類のように階紋仮道管をもつ。樹幹は分枝せず塊状のものが多い。直径 0.5m,長さ 4mという巨大なものも知られている。日本産のものからは,まだ花が見出されていないが,外国産のものには,多数の花(両性花)を葉腋にもつものが知られている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
百科事典マイペディア
「キカデオイデア」の意味・わかりやすい解説
キカデオイデア
シカデオイデアとも。中生代に繁茂した化石裸子植物。ソテツに近い。球状または樽(たる)形の幹をもち,頂部には長く堅い葉が茂り,シュロのような外観を示す。幹には鱗毛が多く,包葉や葉が厚いキチン質の表皮でおおわれるなど乾燥に耐え得る構造を示す。日本の白亜系からも産する。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内のキカデオイデアの言及
【被子植物】より
…ともに葉の化石で,葉脈の走り方より,前者は最古の双子葉植物,後者は最古の単子葉植物かも知れないといわれているが確かではない。花の由来を示すとみられる化石としては,ジュラ紀を中心として中生代に栄えたキカデオイデアCycadeoideaがある。これの有性生殖のための構造は,中心に雌花の集りがあり,それをとりまいて雄花の集りが,さらにそれらを胚珠や花粉囊をつけない葉状の器官がとりまき,あたかも,被子植物の雌蕊群,雄蕊群,花被のようにみえる。…
【函淵植物群】より
…葉や茎の化石は,シダ類4種,ソテツ類7種,球果類2種,被子植物4種などがあるが,植物群全体の姿はまだ十分に明らかにされていない。これらのうち[キカデオイデア]は茎の組織がよく保存されているベネチテス目(ソテツ綱)の化石で,日本では数少ないこの種の化石のうちの一つである。 ソテツ類の[ニルソニア]がかなり豊富であることから,函淵層群の中で,植物化石を含む地層をニルソニア層と呼ぶこともある。…
【被子植物】より
…ともに葉の化石で,葉脈の走り方より,前者は最古の双子葉植物,後者は最古の単子葉植物かも知れないといわれているが確かではない。花の由来を示すとみられる化石としては,ジュラ紀を中心として中生代に栄えたキカデオイデアCycadeoideaがある。これの有性生殖のための構造は,中心に雌花の集りがあり,それをとりまいて雄花の集りが,さらにそれらを胚珠や花粉囊をつけない葉状の器官がとりまき,あたかも,被子植物の雌蕊群,雄蕊群,花被のようにみえる。…
※「キカデオイデア」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by