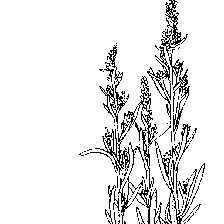ハハコグサ (母子草)Gnaphalium affine D.Don
目次 名称の由来 家の付近,道ばた,田畑 などでごく普通にみられるキク科 の越年草 。春の七草 のゴギョウ (オギョウ )として若い茎や葉を七草がゆに入れるので有名である。茎の高さは15~30cm,下の方でよく分枝する。葉は倒披針形で柔らかく,両面 に密に綿毛 がある。花期は4~6月。花は淡黄色の小さい頭花で,茎頂に散房状につく。総苞は長さ3mm,総苞片は3列で黄色。東南アジア,中国中南部から朝鮮,日本全土に分布する。ヨーロッパからインドにかけてハハコグサにきわめてよく似たG.luteoalbum L.が分布する。
ハハコグサ属Gnaphalium (英名cudweed)は世界中に広く分布し,約200種ある。アキノハハコグサG .hypoleucum DC.は山地 に生える一年草 で,茎の上部でよく分枝する。葉の表は緑色 ,裏は白綿毛で密におおわれている。花期が9~11月であるところから,和名 がつけられた。チチコグサ G.japonicum Thunb.も山野 や家の近くに普通な多年草 である。総苞は鐘形で長さ5mm,総苞片は3列で暗褐赤色を帯びる。花期は5~10月。根葉は線状倒披針形で花時 にもあり,葉の表は緑色,裏面 は白綿毛におおわれている。茎は花茎様で分枝せず,通常数本直立する。中国から朝鮮,九州~本州 に分布する。タチチチコグサG.calviceps Fern.は北アメリカ原産の帰化植物で,市街地の路傍 や荒地 に生える。茎下部 の葉はさじ形となるが,中部以上の葉は線状披針形である。頭花は長さ3mm強,総苞外片はほとんど無毛に近い。小山 博滋
名称の由来 《日本文徳天皇 実録》の嘉祥3年(850)5月条に,〈文徳帝の祖母および父の仁明帝が相次いで亡くなられたが,この年田野に母子草 が生じないという流言 が民間に飛んだ。これは母子両陛下の崩御 をあらかじめ告げたものである〉といった記事がみえ ,明らかに母子草と書かれている。したがって,従来のハハコグサのハハコを這子(はふこ)(室町時代以後の呼称 )とする説はあたらず,また〈冠毛がハハケルから〉という説も,古くは〈ホホケル〉を〈ハハケル〉といわなかったから成り立たない。奈良時代 に渡来した中国の本草書 《新修本草》に〈蘩学者 が〈白蒿〉(ハハコグサの誤称漢名)を〈蘩深津 正
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」 改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by
ハハコグサGnaphalium affine D.Don
キク科(APG分類:キク科)の二年草。白色の綿毛が多いので、全草が緑白色にみえる。茎は叢生(そうせい)し、高さ10~40センチメートル。根出葉は小形、花期には落葉する。茎葉は互生し、へら形または倒披針(とうひしん)形で長さ2~6センチメートル。4~6月、茎頂にやや密な散房花序をつける。頭花は中心に両性花、周囲に雌性花があり、いずれも結実する。総包は球鐘形で長さ3ミリメートル、総包片は3列で黄色。冠毛は黄白色で長さ約2ミリメートル。人里の道端や田んぼなどに普通に生え、日本全土、および東アジア、マレーシア、インドに広く分布する。
古くは「御形(おぎょう)」とか「ほうこ」とよばれた。春の七草に数えられるオギョウまたはゴギョウは、本種のことである。若い苗は食用となり、餅草(もちぐさ)にされた。
[小山博滋 2022年3月23日]
中国では3月3日の節句にハハコグサ(鼠麹草(そきくそう))の草餅(くさもち)を食べる風習は古くからあり、『荊楚歳時記(けいそさいじき)』(6世紀)には、黍麹菜(しょくきくさい)の名で出る。それが日本にも平安時代に伝わったとみえ、『文徳(もんとく)実録』には嘉祥(かしょう)3年(850)、母子草が生えず、草餅がつくれなかったところ、3月に文徳天皇の父仁明(にんみょう)天皇が、また5月に祖母の嵯峨(さが)皇太后が没し、母子草はその予言をしたという流言を記録する。
ハハコグサの語源は、母子(ははこ)の人形(ひとがた)を3月3日に飾り、供えた母子餅(ははこもち)にハハコグサを使ったからと『大言海』は説く。ハハコグサの別名である春の七草の御形(ごぎょう)も、人形(ひとがた)に関係することばとされる。御形の名は鎌倉時代後期の『年中行事秘抄』に初見する。
「花のさく心もしらず春の野にいろいろつめる ははこもちひぞ」 和泉式部(いずみしきぶ)
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ) 日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by
ハハコグサ(母子草)Gnaphalium multiceps
キク科の越年草で,ホウコグサ,オギョウ,ゴギョウともいう。アジアの熱帯から温帯まで広い分布をもつ。日本各地の路傍,田畑,人家の近くなどにごく普通にみられる。茎は基部で分枝して直立し,高さ 20~40cmとなる。葉は長さ2~6cmの線状倒披針形で両面とも白色の綿毛が密生する。春から夏にかけて,次々と茎の上部に淡黄色の頭状花を散房状につける。頭花には半球形の総包があり,周辺部には雌花が,中心部には両性花がある。ともに結実する。果実は黄白色の冠毛をもつ小型の痩果。春の七草 の1つ。幼苗は食用とされ,ヨーロッパには近縁の対応種としてよく似た G. luteo -album が知られる。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by
ハハコグサ
ホウコグサとも。キク科の二年草。日本全土,東アジアの熱〜温帯に分布し,路傍や家の近くにはえる。茎は高さ15〜40cm,下部でよく枝分かれする。葉は倒披針形で両面密に綿毛におおわれる。黄色の頭花は糸状の雌花と筒状の両性花からなり,4〜6月に開花。総包片は淡黄色となる。ゴギョウ(オギョウ)ともいわれ,春の七草 の一つ。葉を餅(もち)などに入れて食べる。総包片が暗褐色を帯びるチチコグサは多年生で,茎は分枝せず,葉は線形。
出典 株式会社平凡社 百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by
世界大百科事典(旧版)内の ハハコグサの言及
【海運業】より
… とくに大西洋海底電線(1858),スエズ運河(1869)の開通にたすけられ,イギリスのP&Oや[ブルー・ファンネル・ライン]のみでなく,フランスのメサジュリー・マリティーム会社(現,[ジェネラル・マリティーム]会社)やドイツの北ドイツ・ロイド汽船会社(NDL。現,[ハパーク・ロイド]会社)なども極東やオーストラリアに航路を延長し,大西洋航路でもアメリカのコリンズ・ラインやドイツのハンブルク・アメリカ汽船会社(HAPAG。現,ハパーク・ロイド会社)がキュナードその他のイギリス船主と激しい競争に入った。…
※「ハハコグサ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by
 蒿即白蒿〉とあるところから,当時の学者が〈白蒿〉(ハハコグサの誤称漢名)を〈蘩
蒿即白蒿〉とあるところから,当時の学者が〈白蒿〉(ハハコグサの誤称漢名)を〈蘩 蒿(はんはんこう)〉ともいうものと信じこみ,この草をハンハンコウと呼ぶうち,いつしかこれがハハコになり,母子草と書かれるようになったものであろう。
蒿(はんはんこう)〉ともいうものと信じこみ,この草をハンハンコウと呼ぶうち,いつしかこれがハハコになり,母子草と書かれるようになったものであろう。