日本大百科全書(ニッポニカ) 「かつら」の意味・わかりやすい解説
かつら
かつら / 鬘
自髪とは別の髪によって、自毛の少ない状態を補うものをいう。また、芸能界の男女および芸者の出仕の際に用いる扮装(ふんそう)用の仮髪をもいう。
[遠藤 武]
日本
かつらを「かもじ」というのは仮文字、つまり奥女中たちが用いた女房詞(にょうぼうことば)に始まる。わが国の古代社会では男も女も頭飾りを用いたり、髪を巻いたりしたが、それに用いる草はサネカズラ(五味)、クズ(葛(くず)かずら)、スイカズラ(忍冬)などのつる草であった。また芸能方面では猿楽(さるがく)、能、狂言などに蔓(つる)や鬘(つる)巻が使われた。江戸時代にかつらを歌舞伎(かぶき)の世界に取り入れたのは市村羽左衛門(うざえもん)で、1654年(承応3)『島原傾城買(けいせいかい)』を演じたおり、女鬘(おんなかつら)をかぶったのが初めといわれる。江戸時代後期になると男女のかつらが増え、男役のものには月代(さかやき)、坊主、頭物、甲羅(こうら)などに加えて、鬢(びん)、髷(まげ)などに付鬚(つけひげ)など100種以上がある。女方(おんながた)関係では世話物、御殿物、傾城あるいは芸者、下げ髪、蓑(みの)、元禄(げんろく)物あるいは丸髱(まるづと)、地髱など、これも100種以上がある。
現代使われている一般用のかつらは、婚礼のときの花嫁用、芸妓(げいぎ)たちの出仕用、また正月の晴れ着の際などに短い髪にかつらを足して新日本髪にするなどのほか、洋装の場合にも、好みの髪形にするため、また男性の場合は、薄い髪や禿(はげ)を隠すためなど、近来多方面に利用されている。
[遠藤 武]
演劇のかつら
演劇扮装(ふんそう)用のかつらは、日本では室町時代の能楽に始まる。種類は尉髪(じょうがみ)、姥髪(うばがみ)、女髪、喝食(かっしき)、赤頭(あかがしら)、白頭、黒頭、白垂(しろだれ)、黒垂など。製法は、クジラのひげを撚(よ)ったものに、人髪、馬尾(ばす)毛、麻などを一列に取り付けるという単純な細工だった。種類と製法が著しく進化したのは、江戸時代の歌舞伎(かぶき)からである。もっとも、初期の歌舞伎は俳優が自分の髪を結い替えるだけだったが、若衆(わかしゅ)歌舞伎が禁じられ、俳優が前髪を剃(そ)り落とすと、青頭を隠すための置手拭(おきてぬぐい)、野郎帽子などから、いろいろな役に扮するため仮髪によって補うことがくふうされた。まず、能楽の鬘にヒントを得た付髪(つけがみ)や前髪鬘が生まれたのは、1654年(承応3)という。延宝(えんぽう)(1673~81)ごろには、銅板製の頭型に、毛髪を蓑(みの)編みにした「蓑」を取り付ける技法が始まり、元禄(げんろく)期(1688~1704)から宝暦(ほうれき)期(1751~64)にかけて各役柄の鬘がつくられ、1803年(享和3)には初世尾上(おのえ)松助と鬘師友九郎の協力で、羽二重(はぶたえ)の繊維の間に毛髪を植え込んだ「羽二重鬘」が考案され、毛の生え際を写実的にみせる今日の形式がほぼ完成している。
[松井俊諭]
歌舞伎のかつら
製作順序は、演目と役が決まると「鬘屋」と「床山(とこやま)」(結髪師)が俳優や美術担当者と相談して形態を決め、まず鬘屋が俳優の頭にあわせ銅板を使って台金(だいがね)をつくる。台金づくりのうちで重要なのは、俳優の顔だちや役の性格に従ってこしらえる生え際、すなわち「刳(く)り」で、その巧拙が舞台の印象に大きな影響を与える。刳りのできた台金は、鬢(びん)、髷(まげ)、月代(さかやき)などの部分に毛を植えた蓑や羽二重を貼(は)り付ける。床山はこれらを指定の形に結い上げ、公演中は楽屋内の床山部屋に常勤して鬘の修理と保管にあたる。鬘に使う毛の材料は、本毛(ほんけ)(人髪)のほか、唐(から)毛(赭熊(しゃぐま)とよぶ獣毛)、熊毛、絹糸など。様式は、立役(たちやく)用では、台金の体裁によって、脳天の部分まで台金のある「甲羅物(こうらもの)」と、鬢から襟にかけた周囲だけに台金があり、脳天の部分は羽二重だけで月代を表す「髷物」とに分けられる。また、後頭部の体裁により、髱(たぼ)のある「袋付(ふくろつき)」と、髱をつけず油で固めた「油付(あぶらつき)」に分けられる。女方用では、毛の生え際の様式により、前述の蓑と羽二重の2種があり、髱の形をつくるのに髱金を入れる「丸髱」と、髱金を使わず櫛(くし)の技術だけでつくる「地髱」の2種にも区別される。
歌舞伎の各役に使う鬘は、これらの様式を根底にしているが、髷、鬢、甲羅などの各部分にも、形態によってさまざまの種類と名称がある。たいていの鬘は、それらの複合でできているが、概してその役の性格をもっともよく表している部分を強調してよぶことが多い。立役では、髷の形として生締(なまじめ)(主として裁き役の武士)、前茶筅(まえちゃせん)(時代物の若い武士)、棒茶筅(武将)、みより(侍一般)、切藁(きりわら)(勇者)、菱皮(ひしかわ)(怒った勇者)、銀杏(いちょう)(町人)、のんこ(侠客(きょうかく))、眼鏡(めがね)(三枚目の番頭)など、鬢の形として車(くるま)鬢(荒事(あらごと))、板(いた)鬢(荒事や大時代な役)、矢筈(やはず)(時代物の端敵(はがたき))など、甲羅の形として燕手(えんで)(敵役(かたきやく))、むしり(浪人・ならず者)、逆熊(さかぐま)(すごみのある浪人)、五十日・百日(大盗賊や妖術(ようじゅつ)使い)などがおもなものである。全部ひっくるめた名称として、王子(おうじ)(公家悪(くげあく)・謀反人)、撫(なで)付け(山伏・軍学者)、丸坊主・半坊主(僧一般)などがある。女方では、髷を主とした名称として、吹輪(ふきわ)(姫役)、片はずし(武家の妻女・局(つぼね))、文金(ぶんきん)(腰元・武家娘)、結綿(ゆいわた)(町娘)、勝山(かつやま)(世話女房)、伊達(だて)兵庫(傾城(けいせい))など、下げ髪のものに、錣(しころ)(御台(みだい))、喝食(かっしき)(貴婦人・能系統の女房)、馬のしっぽ(田舎(いなか)娘・女房)などがある。ほかに子役の鬘にもいくつかの種類があり、鬼、獅子(しし)などに使う赤・白・黒などの頭(かしら)や、種々の仕掛け物、付属物も多く用いられている。
なお、映画やテレビの時代物に使う鬘は、刳りに舞台劇以上の写実性が必要なので、羽二重のかわりに亀甲(きっこう)と称する網に毛を植えたものを台金に貼ってつくる。また、現代劇や西欧劇の鬘は、原則として台金がなく、目の粗い布に毛を植え、帽子状につくったものを使うことが多い。
[松井俊諭]
世界
紀元前30世紀のエジプト時代にすでに使用されていた、との記録がある。酷暑乾燥の気候風土から、男女を問わず高位高官の権勢のシンボルとしても、直射日光から肌を守るためにも多用された。材料としては馬のたてがみ、羊毛、植物、絹その他が使われ、螺旋(らせん)状にカールしたり、三つ編みにしてから蜜蝋(みつろう)で固めたり、染色して仕上げた。男性は頭を刈り込んでかぶったが、女性は短髪にするか真ん中で髪を分け、その上にかぶったりした。このスタイルは、中世、近世になって男性に、現代では女性の間でボブスタイルとして復活している。古代ギリシアでは、演劇用の仮面にそれぞれふさわしい色と形のかつらが用いられたり、古代ローマではもっぱら女性のおしゃれ用具として数多く使用された。とくにブロンドが好まれ、当時の未開地である北方ガリアのゲルマン人子女の髪が、大量にローマに送り込まれたという。
14世紀になると、フランスでかつらを意味することばも文献に登場してくるが、本格的には16、17世紀に入ってから隆盛を迎える。ブルボン王朝成立前のアンリ3世時代、染髪剤調合の失敗で王自身脱毛し、禿頭(とくとう)になってしまい、禿(はげ)隠しにかつらを使用、それを廷臣たちがまねたことが流行のきっかけになったらしい。イギリスのエリザベス1世はたいへんなかつら愛好家で、80個以上ものかつらを所有していたという。こうして16世紀後半からイギリス、フランスに広まり、17、18世紀にはとりわけ男子の権威の象徴として、またおしゃれの用具として大流行するに至った。ルイ14世は、40人ものかつら師を置き、毎朝欠かさず頭を剃(そ)り、さまざまのかつらをかぶったといわれる。そのころ代表的な末広がりの四角ばった全頭かつらは、中央で毛を分け、無数のカールが肩や背に流れ落ちるスタイルで、女性の長い髪に劣らないほどの流行をみせた。
女性用かつらは、全頭タイプでなく、付け毛や部分かつらとして、高く結い上げる髪形や豊かにカールやロールをして下げる髪に使用された。このスタイルは19世紀後半まで続いた。18世紀も後半になると、男子用の巨大な全頭かつらの人気も後退、軽便なかつらが流行するようになった。そして、当時の人々にとって、かつらは生活の必需品にまでなっていて、総体的には全盛期を迎えたといってよい。学者から役人、裁判官、商人、そして農夫に至るまで、それぞれの職種に定められた形で、経済状態に応じたかつらの買い求め方をした。17世紀以降、髪粉(かみこ)が使用され、白、グレー、ブロンドの順で尊ばれたが、それに使用される小麦粉が使用されすぎ、社会問題化したことも記録されている。
大隆盛を極めたかつらも、19世紀になると急速に衰え始めた。あまりに多数の人々が用い、虚栄心を満たせなくなったせいであろう。その後は20世紀に入ってもショートカットが流行するなど、ファッションから遠ざけられ、かろうじて男女の禿隠しに用いられる程度の、細々とした不遇時代が続く。しかし、化学繊維の発達と植毛技術の発展、高度経済成長の消費ブームとも相まって1958年にはアメリカで突如ブームがおき、日本にも上陸した。その後はファッション・ウィッグとして根強く生き続けているが、ひところの力強さはない。
今日のかつらは、全頭かつらと部分かつらに分けられる。また生え際、つむじからの自然感などをみると、機械編みより手編みのほうが高価で使用感もよいとされる。素材は化繊に比べて、明らかに人毛のほうが優れているし、スタイルの変形も可能で、便利である。
[横田敏一]
『松田青楓著『鬘』(1937・法木書店)』
カッラ
かっら
Carlo Carrà
(1881―1966)
イタリアの画家。ピエモンテ州アレッサンドリア県のクワルジェントに生まれる。初め室内装飾家として働き、1895年ミラノに出てブレラ美術学校に学ぶ。1910年マリネッティらの呼びかけに応じて未来派の運動に参加し、1912年にパリを皮切りにした国際巡回展に出品。この時期の代表作に『無政府主義者ガッリの葬礼』(1911年。ニューヨーク近代美術館)がある。また、美術雑誌『ラチェルバ』や『ラ・ボーチェ』を通じて未来主義の理論的支柱としても活躍した。しかし、やがてセザンヌやイタリアのプリミティブ絵画につながる形態に回帰し、1916年デ・キリコらと親交をもち、モランディとともに形而上(けいじじょう)絵画の有力な一員となる。そこでは『魅せられた部屋』(1917)などにおけるように、日常的な事物の「もう一つの」意味が探求される。1922年ごろ以降はアカデミックな静物や風景を描き、ミラノで没した。
[小川 煕]
カツラ
かつら / 桂
[学] Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc.
カツラ科(APG分類:カツラ科)の落葉高木。高さ25メートル以上にもなり、短枝が多い。葉は対生し、広卵形で長い柄があり、先は円く、基部は心臓形、縁(へり)に鈍い鋸歯(きょし)があり、裏面は粉白色を帯びる。5~7条の掌状脈がある。雌雄異株。花期は5月ごろ。花被(かひ)はなく、雄花は多数の雄しべがあり、葯(やく)は紅(くれない)色。雌花は3~5本の雌しべがあり、柱頭は淡紅色。果実は円柱形で湾曲する。日本全土の深山の谷沿いの林中に生え、中国には変種が分布する。漢字名の桂は、中国ではモクセイ科の植物のことである。近縁種ヒロハカツラは葉が大形で、樹皮には母種のような裂け目がない。
[古澤潔夫 2020年5月19日]
文化史
カツラに漢字の「桂」をあてるのは誤りで、桂は中国ではモクセイのことをさす。この混同は平安時代にまでさかのぼり、『和名抄(わみょうしょう)』は桂(モクセイ)の和名を女加豆良(めかつら)とする。花に芳香のあるモクセイが日本に渡来する以前に、中国からその知識だけが先行して伝わり、またカツラの木灰を抹香の材料に使ったことから、香りのある木として誤って桂の字をあてたのであろう。カツラの中国名は連香樹(レンシャンスウ)、あるいは五君樹(ウチンスウ)、または山白果(サンパイクオ)である。
[湯浅浩史 2020年5月19日]






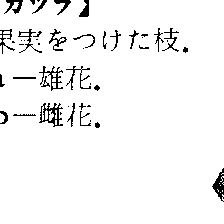

 】かつら
】かつら 草。
草。 」の
」の