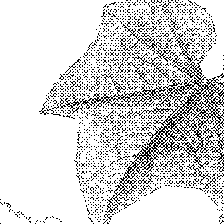ハヤトウリ (隼人瓜)
chayote
Sechium edule Sw.
ウリ科の宿根生つる草。たくさんなるのでセンナリウリともいう。熱帯アメリカ原産で,温帯から亜熱帯に広く栽培される。日本へは1916年ごろ,アメリカから導入されて鹿児島で試作したのが始まりで,薩摩隼人にちなんで命名された。その後,別途に白色種が旧農林省園芸試験場に導入された。現在鹿児島県,宮崎県の一部でまとまって栽培されるほかは,ほとんど自家用程度である。茎はつる性でよく伸びる。花は雌雄同株。果実は8~20cmの扁平な洋ナシ形で数本の縦溝がある。果色は白か緑で,果肉は緻密(ちみつ)である。大型の種子が果実の先端部寄りに1個存在し,この点でウリ科の植物としてはきわめて特殊である。繁殖は実生か根株を利用する。実生は果実のまま用い,萌芽したものを5月に植える。収穫は10月から降霜までの期間で,開花後15~20日で採果する。地下に塊根ができるので,冬季に防寒すれば毎年発芽生長する。果実は各種の漬物,酢の物,汁の実,煮食などに利用し,風味は淡白である。また若芽や肉質の根も食用になる。その他棚仕立てとして夏の日よけにも利用する。
執筆者:金目 武男
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
ハヤトウリ
はやとうり / 隼人瓜
[学] Sechium edule Swartz
ウリ科(APG分類:ウリ科)の多年草。おもに果実を食用とするために栽培される。茎はつる性で、長さ10メートルを超すほどになる。葉はやや五角形状で基部は心臓形、幅10~20センチメートル。雌雄異花。果実は西洋ナシ形で、色は黄白色または緑色、中に長さ5~6センチメートルの白色卵形の種子が1個ある。根はいも状に肥大してデンプン質。原産地はメキシコ南部から熱帯アメリカ地域で、ヨーロッパやアジアに伝播(でんぱ)したのは19世紀になってからである。現在は、熱帯を中心に広く栽培される。
日本には1917年(大正6)アメリカから鹿児島に導入され、薩摩隼人(さつまはやと)にちなんで名がつけられた。関東でも育つが、鹿児島や沖縄などが栽培の適地である。春に種子を果実ごと植え付ける。霜にあうと枯れるので、日本では一年草として栽培する。未熟な果実を漬物や酢の物、甘煮、汁の実とする。また、葉や若いつるを野菜として食べ、いもは食用や飼料として利用する。つるで帽子や籠(かご)を編む。
[星川清親 2020年2月17日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
はやとうり
鹿児島県で生産されるウリ。白色系と緑色系がある。実の形は洋ナシのように下膨れで、表面は凹凸があり、実の重さは500g~1kg程度である。果肉は緻密で、味わいはトウガンに似て淡白。「隼人瓜」の表記もある。1917年、日置郡永吉村(現在の日置市)で、同町の矢神氏がアメリカから持参したウリを試作したのが栽培の始まりとされ、その後南九州、高知県などに普及。漬物、煮物、炒め物などにして食する。県により「かごしまの伝統野菜」に認定されている。チャーテとも。
出典 小学館デジタル大辞泉プラスについて 情報
Sponserd by 
ハヤトウリ(隼人瓜)
ハヤトウリ
Sechium edule; pipinella
ウリ科の多年生つる植物で,熱帯アメリカの原産。日本には 1916年頃北アメリカから持込まれ,鹿児島を中心に暖地で栽培されるようになった。茎は長さ 10m以上になり,葉は膜質の広卵形で,長さ 10~20cmほどある。雌雄同株で,雄花は総状につき,雌花は雄花序と同一の葉腋に生じる。どちらも小型で白色の花冠をもつ。果実は長さ8~17cmのほぼ洋なし形で多肉質,食用とする。老蔓からは繊維がとれる。また塊根はデンプン質に富み,家畜の飼料となる。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
ハヤトウリ
熱帯アメリカ原産のウリ科のつる性多年草。初め鹿児島県に導入されたのでこの名がある。葉は広卵形でつるは棚にはわせると10mにも達する。花は雌雄同株で淡緑白色。果実は倒卵形で1株に数十〜数百個着生する。生食のほか薄く切って漬物などにする。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
ハヤトウリ
[Sechium edule].スミレ目ウリ科ハヤトウリ属の多年草.果実を食用にする.
出典 朝倉書店栄養・生化学辞典について 情報
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内のハヤトウリの言及
【十二支像】より
…いずれも鎧をまとい,刀を手にする武人の姿に表現され,この点が唐と異なっている。日本では,奈良の那富山墓にある[隼人石](はやといし)とよばれる獣首人身の石刻を,十二支像にあてる説がある。一方,鎌倉時代の仏像,[十二神将]像に十二支の動物をあしらったものがある。…
※「ハヤトウリ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by