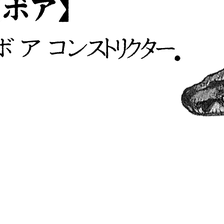精選版 日本国語大辞典 「ボア」の意味・読み・例文・類語
ボア
- 〘 名詞 〙 ( [英語] boa )
- ① ボア科の無毒のヘビ、ボアコンストリクターのこと。最大で全長三・六メートルぐらいで、ニシキヘビより小さい。背面は淡褐色の地に一五~二〇の暗褐色の横縞があり、側面では大形の斑の列をなす。南アメリカの熱帯森林に分布し、夜行性でネズミなどを捕食する。王蛇(おうじゃ)。
- ② 毛皮や羽毛などで作った細長い婦人用襟(えり)巻。また、コートなどの衿や裏、袖口などにつけたり、敷布などに用いる、毛皮やそれに似せた織物。
- [初出の実例]「駝鳥の襟巻(ボーア)に似てゐるでせう」(出典:三四郎(1908)〈夏目漱石〉四)
日本大百科全書(ニッポニカ) 「ボア」の意味・わかりやすい解説
ボア(Yve-Alain Bois)
ぼあ
Yve-Alain Bois
(1952― )
アルジェリア生まれの美術史家、美術批評家。フランスで活動したのちアメリカに拠点を移す。専門は近現代美術史で、この分野におけるフォーマリズム(形式主義)の再構築を目指す。
パリ大学に学び、さらにロラン・バルトの指導の下、1973年パリ高等学術研究院で修士号を、77年社会科学高等研究院で博士号を取得。
76年から79年にかけて、友人らとともに先鋭的な美術批評誌『マキュラ』Maculaを刊行。1960年代アメリカの美術批評家クレメント・グリーンバーグの批評をフランスに紹介する。哲学者や文学者たちの観念的な美術論が尊ばれるフランスの美術界では、作品の具体的で精密な分析は等閑視される傾向にあった。まさにそうした分析を行うグリンバーグを紹介することで、ボアはフランスの美術批評の状況に一石を投じようとしたのである。
その後しだいにアメリカに拠点を移したボアは、フランス以外の国でも美術史研究が抱えている問題点について、指摘せざるをえなくなる。90年に英語で刊行された主著である論文集『モデルとしての絵画』Painting as Modelの冒頭で、彼は「脅迫状」という比喩を用いながらその問題点を指摘する。彼によれば、美術史研究や美術批評を行う者には、何通もの脅迫状が舞い込んでくる。「理論主義」「反理論」「流行」「反形式主義」「社会的・政治的要請」「象徴性」……これらを考慮、あるいは遵守せよという暗黙の「脅迫」に対して、あからさまにではないけれども対抗してゆくのが自分の仕事だ、そうボアは述べた。
その彼が参照するのはグリーンバーグに代表される研究方法、つまり徹底して作品から見て取れるものだけに基づいて論を進めるフォーマリズム批評である。ただボアは、アメリカの抽象表現主義を頂点と見なすような、グリーンバーグ流の一貫した価値観・歴史観をも参照することはない。そうした価値観・歴史観の体系を完成させることよりはむしろ、個々の作品との、個別的な出合いから得られるものをすべて克明に暴き出すことをボアは選択した。
この選択によって彼の研究は、完成した作品の視覚的な「見え」を分析する「形態学」のレベルから、なぜその作品はその形態をとるに至ったのかという、形態をいわば下支えする「構造」分析のレベルに至る。こうして、たとえばマチスの色彩表現が独創的であるということの真の意味が、あるいはモンドリアンが『ニューヨーク・シティ』(1941~42)など後期の作品をカラーテープを編むようにして貼ることで構想したことの意味が、そして「北極と南極」とさえ形容されたマチスとピカソの作品がしばしば類似してしまうことの意味が、明らかにされる。マチスは西洋の画家で初めて色の感覚がその面積と不可分の関係にあり、したがって実際にその大きさで塗ってみなければ思ったような絵は描けないことを見抜いたのであり、モンドリアンは水平においた画面にテープを貼ることで、その絵画の、暴力的な、あるいは野蛮な物質性を感得していたのであり、マチスとピカソは互いに相手に影響されるままにあったというよりも、まるでチェスの勝負やタンゴを踊るときのように、お互いの出方、つまり作品を鋭くうかがい、ときにそれを強引に自分の作品のうちに取り込んでいった。そう説くボアはこの自身の研究方法を、「唯物論的フォーマリズム」と呼ぶ。
ボアはまた、こうした研究成果を著作だけではなくときに展覧会として示す、優れた企画者でもある。「マチスとピカソ」展(1999、キンベル美術館、フォート・ワース)もその一つであり、また97年にはロザリンド・クラウスと共同で近現代美術史の根本的な読み直しを提案する、「無形――使用の手引き」をポンピドー・センターで企画している。さらにはバーネット・ニューマンのカタログ・レゾネ(作家や美術館の作品の総目録)の作成などの、緻密で実証的な作業にも取り組むなど、多方面で活躍する研究者である。
[林 卓行]
『宮下規久朗監訳『マチスとピカソ』(2000・日本経済新聞社)』▽『Painting as Model (1993, MIT Press, Cambridge)』
ボア(潮津波)
ぼあ
tidal bore
大きな干満がある河口などで上げ潮(しお)の前面が切り立った形で崩れながら上流へ進む現象で、タイダルボア、潮津波(しおつなみ)、海嘯(かいしょう)などともいう。水深が浅い所では潮汐(ちょうせき)波の山が谷より速く進むために、山の前面が急で後面が緩やかになる。極端になると、波の先端(山の前部)が急勾配(きゅうこうばい)となり、逆巻いて崩れ、泡立ちながら勢いよく進む。海岸での磯波(いそなみ)(砕け波)と違って、ボアの通過後もかなりの時間にわたって背後の水面がどんどん上昇する。
ボアが発生するためには、河口での潮差が大きいだけでなく、河口がらっぱ状に開いていることなど地形的効果が必要である。また河川の流れがあると潮汐波の進行を遅らせるので、ボアの発生を容易にする。南米アマゾン川のポロロッカpororocaや、中国の銭塘江(せんとうこう/チエンタンチヤン)が有名で、高さ3メートル以上に達するボアが発生する。そのほかに、インドのフーグリ川、イギリスのセバーン川、カナダのペティコディアック川などもボアの発生することで知られている。なお、大きな津波が河川に進入すると、類似の現象(段波)が発生し、遡上(そじょう)することがある。
[岡田正実]
ボア(ヘビ)
ぼあ
boa
爬虫(はちゅう)綱有鱗(ゆうりん)目ボア科ボア亜科に属するヘビの総称。この亜科Boinaeの仲間は大形で無毒、ニシキヘビ亜科とは近縁であるがより原始的で、ほかの小形の3亜科をも含めボア科を構成する。ボア亜科には8属約21種が知られ、大半が南北アメリカに分布するが、マダガスカルボア属Acrantophisとサンジニアボア属Sanziniaの各1種はマダガスカル島に、パシフィックボア属Candoiaの3種はニューギニア島と、南太平洋の諸島に分布している。最大はアマゾン川流域に生息するアナコンダEunectes murinusで、最大記録は9メートル、さらにこの数値を上回る大きな個体の存在が推測されている。一方、最小はパシフィックボア類の全長約60センチメートルで、他種では2~4メートルほどである。ボア・コンストリクターBoa constrictorはこの亜科の代表種で、メキシコからアルゼンチン北部まで広く分布し、全長3~5.5メートル、頭部は小さいが胴が太く、体背面は細鱗に覆われ、美しい斑紋(はんもん)をもつ。森林、サバナから居住区付近にも生息し、胴で締める力が強い。餌(えさ)は小哺乳類(ほにゅうるい)、鳥、トカゲなどで、樹上または地上で待ち伏せしてとらえる。幼体以外は性質がおとなしく人間にもなれる。卵胎生で一度に20~60頭ほどの子ヘビを産む。南アメリカ北部に分布する樹上性のエメラルドボアCorallus caninusは、ニューギニア島産のグリーンパイソンChondropython viridisと形態、生態ともにそっくりで、系統の異なる2種が類似性を示す平行進化の好例とされる。
[松井孝爾]
改訂新版 世界大百科事典 「ボア」の意味・わかりやすい解説
ボア
boa
ボア科ボア亜科Boinaeに含まれる無毒ヘビの総称で,ニシキヘビ類(ボア科)に近縁の一群。約8属25種が知られ,大部分が南北アメリカに分布するが,マダガスカルボア属Acrantophis2種とサンジニアボア属Sanzinia1種がマダガスカルに,パシフィックボア属Candoiaの3種がニューギニアと南太平洋の諸島に分布している。最大はアマゾン流域に分布するアナコンダEunectes murinusで,最大全長が9mを超える。最小は全長約60cmのパシフィックボアで,他は全長2~4m。ボア類は頭骨の構造の違いや卵胎生である点などでニシキヘビ類と分けられるが,尾下板も1列で上唇板にはピット(頰窩(きようか))を欠く。
一般に知られるのは,単にボアとも呼ばれるボア属BoaのボアコンストリクターB.constrictorで,メキシコからアルゼンチン北部まで広く分布する。この属名は大プリニウスの《博物誌》にすでに見える大ヘビを意味することばBoaeにちなむ。全長3~4m,最大5.5mに達し,頭部は小さいが胴が太い。頭部から尾部にかけて体背面は細鱗で覆われ,美しい斑紋をもつ。熱帯降雨林やサバンナにすみ人間の居住区付近にも出没するが,幼体を除けば性質はおとなしく人にも慣れるので,ペットとして人気がある。鳥,トカゲ,小哺乳類などの獲物を樹上または地上で待ち伏せし,鋭い歯でとらえる。胴で締める力が強い。卵胎生で一度に20~60匹ほどの子ヘビを生む。
南アメリカ北部に分布する美しい緑色のエメラルドボアCorallus caninusは,全長約2m,樹上生でふつうは枝に胴を前後に振り分けて止まり,頭をその中央に置いている。体色斑紋や静止姿勢は効率的なカムフラージュとなり,近づく鳥やトカゲをとらえるが,本種に形態,生態ともにそっくりの種がニシキヘビ亜科にいる。それはニューギニア産グリーンパイソンChondropython viridisで,系統も産地も異なる2種が類似性を示す平行進化の例として知られる。コスタリカからアルゼンチンに分布するニジボアEpicrates cenchrisの体鱗は滑らかで,太陽に当たると斑紋が虹のように輝く。
執筆者:松井 孝爾
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
普及版 字通 「ボア」の読み・字形・画数・意味
【暮 】ぼあ
】ぼあ
 蝶飄零(へうれい)して、宿雨に
蝶飄零(へうれい)して、宿雨に き
き 
 凌亂(りようらん)して、秋
凌亂(りようらん)して、秋 を報ず
を報ず字通「暮」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ボア」の意味・わかりやすい解説
ボア
Boinae; boa
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「ボア」の意味・わかりやすい解説
ボア
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
海の事典 「ボア」の解説
ボア
出典 (財)日本水路協会 海洋情報研究センター海の事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内のボアの言及
【襟巻】より
…以来肩掛けは明治中期から防寒具として流行し,ねずみ色,えび茶,肌色などのネル地で上半身をくるむほどの大きさであった。今日では防寒,装飾など用途によって,また,大きさ,形などからショール,ストール,マフラー,スカーフ,ネッカチーフ,ボアなどがある。ショールは和装用として使われるものをいい,長方形が多い。…
【ポロロカ】より
…ブラジル,アマゾン川下流域でみられる現象で,英語でボアboreと呼ぶ。大潮時に現れる。…
※「ボア」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...