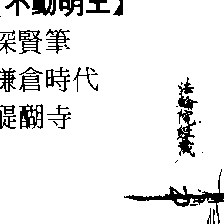精選版 日本国語大辞典 「不動明王」の意味・読み・例文・類語
ふどう‐みょうおう‥ミャウワウ【不動明王】
- ( 「不動」は[梵語] Acalanātha の訳語 ) 仏語。五大明王・八大明王の一つで、その主尊。大日如来が、いっさいの悪魔・煩悩を降伏させるために化現した教令(きょうりょう)輪身で、忿怒の相をとる。形相は色青黒く獰悪(どうあく)で、眼を怒らし、左は半眼、額に水波の相があり、右牙を上、左牙を外に出す。また右に降魔の剣を、左に羂索(けんさく)を持ち、火焔光背を背に岩上または瑟瑟座(しつしつざ)に座している。眷属として矜羯羅(こんがら)・制吒迦(せいたか)など八大童子をもつ。種々の煩悩・障害を焼き払い、悪魔を降伏して行者を擁護し、菩提を成就させ、長寿を得させるという。日本では平安初期の密教の盛行とともに尊崇され、今日に至る。不動尊。不動。〔大日本国法華経験記(1040‐44)〕 〔大日経疏‐一〇〕
 不動明王〈京都府青蓮院〉
不動明王〈京都府青蓮院〉
日本大百科全書(ニッポニカ) 「不動明王」の意味・わかりやすい解説
不動明王
ふどうみょうおう
ヒンドゥー教のシバ神の異名で、アチャラナータAcalanātaといい、漢音で阿遮羅嚢他(あしゃらのうた)とあてる。アチャラは無動尊の意。大日如来(だいにちにょらい)の命を受けて忿怒(ふんぬ)相に化身(けしん)したとされる像で、密教では行者に給仕して菩提(ぼだい)心をおこさせ悪を降(くだ)し、衆生(しゅじょう)を守る。五大明王、八大明王では中央に位置する主尊。709年(中国の景竜3)に訳出された菩提流支(ぼだいるし)訳『不空羂索神変真言経(ふくうけんさくじんべんしんごんきょう)』第9巻によると、右手に剣を持ち、左手に索(縄)を持つ不動使者としての所説を初出とする。しかし図像化の原型となったものは、725年(開元13)の善無畏(ぜんむい)訳『大日経(だいにちきょう)』の所説「不動如来使者は慧刀(えとう)、羂索を持ち、頂髪が左肩に垂れ、〔目は〕一目(いちもく)にして明らかに見、威怒身(いぬしん)で猛炎あり。磐石(ばんじゃく)上に安住し、額に水波の相があり、充満した童子形もある」による。不動明王像は9世紀初め空海によりわが国に伝えられたが、不動信仰が盛んになったのは円珍(えんちん)以降である。円珍自身も金人(きんじん)といわれる黄不動を感得し、また図像も請来(しょうらい)した。不動明王の図像は火生三昧(かしょうざんまい)(火の燃えるような境地)に入った状態を表現したもので、いっさいの罪障を摧破(さいは)し、動揺しないので、姿勢は不動を表す。不動明王を中心に矜迦羅(こんがら)・制吒迦(せいたか)童子を脇侍(わきじ)に配した三尊形式が多く、坐像(ざぞう)・立像とも一面二臂(にひ)像が主流。一面四臂像などの異形も図像(『図像抄』『覚禅(かくぜん)抄』など)として伝わっている。形像については、淳祐(しゅんにゅう)(890―953)の著『要尊道場観』によると、不動明王像には、十九観(十九想観ともいう)が表現されていると説く。(1)大日如来の化身。(2)明(みょう)(真言)のなかにアa、ロro、ハームhām、マームmāmの四字がある。(3)火生三昧に住する。(4)童子形で肥満。(5)頂に七莎髻(しちしゃけい)がある。(6)左に弁髪(べんぱつ)あり。(7)額に皺文(しゅうもん)あり。(8)左目を閉じ、右目を開く。(9)下歯、上の右唇を噛(か)み、下の左唇、外に翻じて生ずる。(10)その口を閉じる。(11)右手に剣をとる。(12)左手に索を持つ。(13)行人の残食を喫す。(14)大磐石に坐(ざ)す。(15)色醜くして青黒い。(16)奮迅忿怒する。(17)遍身に迦楼羅(かるら)炎がある。(18)変じて倶利迦羅(くりから)となり、剣を繞(めぐ)る。(19)変じて二童子となり、行人に給仕する。一を矜迦(こんが)羅、二を制吒迦という。十九観は『大日経』と『大日経疏(しょ)』によってつくられたという。
不動明王図像の変容は、鎌倉時代になると、信海(しんかい)様とよぶ剣をついて岩に休止する像や、走り不動のように剣を担ぐ像など全身が動的になる。忿怒の表現では、大師請来様では両眼を見開き、二牙を上あるいは下に(同方向に)突出するが、その図像が彫刻・絵画でも守られている。しかし時代が下ると、半眼半開(いわゆるすが目斜視)が多くなる。不動明王の宝剣は倶利迦羅竜(くりからりゅう)王がまとい付いたもので、『倶利迦羅竜王経』(『大正蔵経』所収、第21巻)に所説があり、石山寺に平安期の図像が伝存している。明王が念じる功徳(くどく)力により竜を駆使し、またその化身として三昧耶形である。
作例では三大不動の画像として青不動(青蓮(しょうれん)院、国宝)、黄不動(園城(おんじょう)寺、国宝)、赤不動(高野山(こうやさん)明王(みょうおう)院、国重文)が有名。不動法(息災・増益の修法)の本尊、また国家の安泰を祈る安鎮法として、成田山不動、目黒不動など全国に流布している。彫刻では教王護国寺(東寺)講堂、御影(みえい)堂の木造が最古の部類に属する。高野山の正智(しょうち)院の木彫は豊かな量感のある坐像として知られ、また南院の波切(なみきり)不動は空海帰朝の際守護したと伝える像として有名。鎌倉期に傑作が多く、快慶作の逸品が醍醐(だいご)寺にある。また不動明王を中尊に配置する仁王経曼荼羅(にんのうきょうまんだら)、安鎮曼荼羅があり、尊勝・弥勒(みろく)曼荼羅では下辺に描かれる。眷属(けんぞく)として八大童子を伴った不動八大童子も高野山(金剛峯寺(こんごうぶじ))に伝存する。
[真鍋俊照]
『渡辺照宏著『不動明王』(1975・朝日新聞社)』
改訂新版 世界大百科事典 「不動明王」の意味・わかりやすい解説
不動明王 (ふどうみょうおう)
サンスクリット名アチャラナータAcalanāthaの漢訳で,発音に従い阿遮羅囊他と記す場合もあるが,不動金剛明王,不動尊,無動尊,不動使者,無動使者とも訳す。もとはインド教のシバ神の異名で,仏教はこれを大日如来の使者としてとり入れた。如来の命を受けて忿怒の相を表し,密教の修行者を守護し助けて諸種の障害を除き,魔衆を滅ぼして修行を成就させる尊像とした。形像は,右手に剣,左手に羂索(けんさく)を持ち,青黒色の全身に火焰を負う姿が一般的である。頭髪は左肩に束ねて垂れ,早い時期の作例では両眼を見開き,2本の歯を表して唇をかむが,後には片眼を半開にして上下2歯を交互に表す例が多い。両界曼荼羅には胎蔵界の持明院(五大院)の中に描かれるほか,五大明王の一尊としても造像される。さらに単独で盛んに信仰され,変化に富んだ姿勢に表現された座像や立像の優れた作品が数多く伝えられている。その中でも黄色の肉身によって〈黄不動〉と呼ばれる滋賀園城(おんじよう)寺の立像,赤色の肉身をもち〈赤不動〉と呼ばれる和歌山高野山明王院の半跏(はんか)像,青色の肉身に表され〈青不動〉と親しまれる京都青蓮(しようれん)院の座像の3幅が特に著名である。〈赤不動〉と〈青不動〉には二童子が描かれるが,不動明王の眷属としては八大童子が造像されることが多い。その尊名には諸説あるが,図像集の《覚禅抄》には,慧光(えこう)童子,慧喜(えき)童子,阿耨達(あのくた)童子,持徳(しとく)童子,烏俱婆伽(うぐばか)童子,清浄比丘(しようじようびく),矜羯羅(こんがら)童子,制吒迦(せいたか)童子の八尊が説かれる。このうち矜羯羅童子と制吒迦童子のみを脇侍とした,《青不動図》などと同じ三尊形式の不動明王二童子像も多数造られている。なお八大童子の作例としは高野山金剛峯寺,東京観音寺の彫像が知られる。
執筆者:関口 正之
不動信仰
不動明王はインド,中国には遺品が少ないが,日本では平安時代初期以来の密教の盛行とともに,種々の異形をも生じながら尊像が数多く作られ,種々の煩悩を焼き尽くし,悪魔を降伏し,行者を擁護して菩提を得させる明王として信仰された。代表的な尊像として上記の三不動(黄不動,赤不動,青不動)のほかに,弘法大師(空海)の持仏と伝えられる教王護国寺(東寺)西院御影堂安置の秘仏,弘法大師が唐からの帰路海上に顕現し,天慶の乱,蒙古襲来の際にも活躍したという高野山南院の波切不動などがある。また,《栄花物語》は1027年(万寿4)9月に崩じた皇太后藤原姸子の五七日忌(三十五日の法事)に不動尊供養を行ったこと,《宇治拾遺物語》は比叡山無動寺の相応和尚が不動尊の加護を得て都卒天(兜率天)にのぼったこと,《源平盛衰記》は僧文覚が同尊のはからいによって,紀伊国那智の滝での三七日(21日)間の水行を成就したこと,などを述べる。関東では,武蔵国滝泉(りゆうせん)寺の目黒不動,下総国成田山新勝寺の本尊が著名で,目黒不動は慈覚大師円仁の作と伝え,新勝寺の本尊は弘法大師の開眼で平将門の乱の際に霊験があったと伝え,あつく信仰されている。
執筆者:和多 秀乗
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「不動明王」の意味・わかりやすい解説
不動明王【ふどうみょうおう】
→関連項目康尚|宅磨栄賀|明王
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「不動明王」の意味・わかりやすい解説
不動明王
ふどうみょうおう
Acala
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「不動明王」の解説
不動明王
ふどうみょうおう
五大明王・八大明王の一つ。サンスクリットのアチャラナータの訳で,不動威怒明王・聖無動尊・不動尊などと称する。大日如来の使者の教令輪身(きょうりょうりんじん)として,種々の悪や煩悩を降伏(ごうぶく)させるために忿怒(ふんぬ)の相を表し,牙をむいて,背に火炎を負う。右手に降魔(ごうま)の剣を,左手に羂索(けんじゃく)をもつ一面二臂(ひ)像が多いが,四面四臂や四面六臂もある。眷属(けんぞく)として,矜羯羅(こんがら)童子や制吒迦(せいたか)童子などの八大金剛童子がある。密教修法の一つである不動法の主尊として,平安時代以降盛んに用いられ,多くの不動尊像が描かれ,また造られた。彫刻では高野山南院の波切不動(重文)が有名。絵画では,園城(おんじょう)寺の「黄不動」(国宝),高野山明王院の「赤不動」(重文),青蓮院(しょうれんいん)の「青不動」(国宝)などが有名。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「不動明王」の解説
不動明王 ふどうみょうおう
大日如来の化身として,すべての悪と煩悩をおさえしずめ,生あるものをすくう。忿怒(ふんぬ)相で,右手に悪をたちきる剣を,左手に救済の索をもち,ふつう火炎を背負う。日本では平安時代初期からひろく信仰され,現在もつづいている。五大明王のひとつで,中央に位置する。不動尊ともいう。
世界大百科事典(旧版)内の不動明王の言及
【縁日】より
…7月16日は閻魔王の大斎日(だいさいにち)とも称し,地獄信仰と盆行事とが習合している。不動明王は,大日如来の使者として,密教系寺院や,修験道の守護神としてまつられたが,毎月28日が縁日,初不動は参詣者が多い。虚空蔵は,毎月13日が縁日で,4月13日(旧3月13日)を十三参りと称し,13歳の女子の参詣が多い。…
【八大童子】より
…不動明王につき従う8人の童子。八大金剛童子ともいう。…
※「不動明王」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...