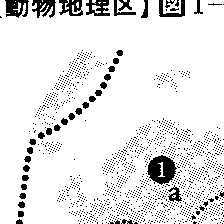日本大百科全書(ニッポニカ) 「動物地理区」の意味・わかりやすい解説
動物地理区
どうぶつちりく
動物区系地理学では、世界の陸地を現在の動物相の系統分類学的な異同に基づいて動物地理区に区分する。おもに基準にとられるのは哺乳(ほにゅう)類と鳥類であるが、場合により爬虫(はちゅう)類や両生類、淡水魚類を加えることもあり、また昆虫類に基づくこともある。一般に、1857年にスクレーターP. L. Sclaterが鳥類の分布から提案し、1876年にワラスA. R. Wallaceが陸生動物の分布状態に基づいて大成した区分が基礎とされており、近年の総説としては、脊椎(せきつい)動物全般に基づくダーリントンP. J. Darlingtonの著書(1957)がある。もっとも基本となるのは区regionで、その設定にはおもに科、もしくはそれより上位の分類群が用いられ、固有群の有無やそれが動物相で占める割合などが分類の基準とされる。区の上位に最高次の分類段階として界realmがあり、その下位には亜区subregionや地方provinceが設けられる。
地理区の分類の仕方には研究者によって若干の違いがあるが、次のように、三界六区に分けるのが一般的である。まず、世界の陸地は南界(オーストラリア)、新界(南アメリカ)、北界(ユーラシア、アフリカ、北アメリカ)の三界に大別される。次に南界はオーストラリア区、新界は新熱帯区、北界はエチオピア区、東洋区、旧北区、新北区に分けられ、これらの六区はそれぞれがいくつかの亜区に分割される。旧北区と新北区をあわせて全北区一区とし、両者をその亜区とする場合もある。また、東洋区とエチオピア区をあわせて旧熱帯区と称する場合もある。亜区のなかではオーストラリア区に含まれるニュージーランド(独立の区とする見解もある)と、エチオピア区に含まれるマダガスカルの固有度が強い。海洋島のなかにも、ハワイ諸島、ガラパゴス諸島などの特徴的な生物相を擁する島々があるが、地理区分上の扱いには諸説がある。また、南極圏は南界に、北極圏は北界に含まれるが、これらを独立の区とするか、亜区とするかといった点については定説がない。地理区の境界には推移帯が認められることもあり、なかでもセレベス(スラウェシ)島、モルッカ諸島、およびロンボク島以東の小スンダ列島を含む地域は、ワラセアとよばれ、東洋区とオーストラリア区との推移帯として著名である。また、メキシコ南部から中央アメリカに至る地域も、新北区と新熱帯区の推移帯として知られている。
動物地理区を分割するおもな要因は、動物の移動を妨げる過去および現在の地理的な障壁の存在と気候の違いである。上位の地理区の分類は主として地史を反映しており、下位になるにつれて気候や植生といった生態的な要因の影響が強くなる。六地理区のうち、オーストラリア区(南界)と新熱帯区(新界)は固有な動物群を多く含む独自の動物相を擁するが、それは、これらの大陸がほかの大陸から長期にわたって地理的に隔離されていたためである。逆に、現在はベーリング海峡によって隔てられている旧北区と新北区は、しばしば全北区として一括されるほど動物相に共通性があるが、これはこの二地域がごく最近まで地続きだったことによる。一方、北界の四区のなかでは旧北区と新北区、エチオピア区と東洋区の共通性が多く、南北方向での動物相の分化がみられるが、これは山脈や砂漠といった地理的な障壁の影響もあるが、それよりも熱帯と温帯という気候的な要因によるところが大きい。極地の動物地理区分上の扱いがまちまちなのも、気候的な条件の制約によって、著しく貧困な動物相しかもっていないことによる。動物群が違うと地理区の設定の仕方が異なることがあるが、動物群ごとに移動や分散の能力や、進化のスピードなどに違いがある以上、このような差異は当然であり、特定の地理区分体系や、境界線の位置を絶対視するべきではない。
[片倉晴雄]
改訂新版 世界大百科事典 「動物地理区」の意味・わかりやすい解説
動物地理区 (どうぶつちりく)
faunal region
zoogeographic region
動物の地理分布,すなわち各地の動物相は,大陸,島嶼(とうしよ)配置,気候帯,環境などの地史的要因に規制されるが,そういった動物相の特徴を基にした地理的区分。現在では,ヨーロッパ,アジアとアフリカを含めて旧世界,南北アメリカは新世界と呼び,ユーラシア大陸は旧北区,北アメリカは新北区,両者を合わせて全北区とし,アフリカはエチオピア区,インド,南アジアは東洋区,南アメリカは新熱帯区,オーストラリアは太平洋諸島を含めてオーストラリア区と呼ぶのが一般的である。動物地理区分の提唱はスクレーターP.L.Sclaterの鳥類(1858),哺乳類(1894)についてのものが最初で,A.R.ウォーレス(1876),T.H.ハクスリー(1868)などが続いたが,いずれも鳥獣の分類地理学的な検討に基づくものであった。ダールF.Dahlなどによる生態的環境区分を考慮し,北極圏,南極圏などを認める方式も提唱された(1925)。その後,それらを踏まえ,ダーリントンP.J.Darlington,Jr.が集大成した区分法もある(1957)。
各区の境界は,海峡,山脈,大河などの地理的障害,緯度的気候,林相,草原,砂漠などの生態的条件により,通常段階的な動物相,植物相の変化で示され,その境はしばしば提唱者の名で呼ばれる。例えば,東洋区とオーストラリア区の境にはウェーバー線とウォーレス線があり,その中間の移行部はワレーシアと呼ぶ。日本は南北に長く宗谷海峡は八田線,津軽海峡はブラキストン線,屋久島,奄美大島の間は渡瀬線として知られ,沖縄の宮古島と石垣島との間は蜂須賀(はちすが)線と呼ばれる。北海道はシベリア-サハリン系と中国東北部-本州系の鳥獣の混在地帯である。琉球諸島に沿っては南ほど北方(旧北区)系の種が減り,奄美大島のアマミノクロウサギ,ルリカケス,沖縄本島のノグチゲラ,ヤンバルクイナ,西表島のイリオモテヤマネコなどの特産種が隔離保存されているが,まだ熱帯種は少なく亜熱帯動物相を呈し,台湾に至り熱帯的な豊富な動物相となる。
大陸として地史的に隔離が古く最も独立性の高いのは南アメリカとオーストラリアで,島としてはニュージーランド,ニューギニア,マダガスカル,ガラパゴス,ハワイなどがあげられ,哺乳類の有袋類は真獣類の侵入のなかったオーストラリア,その侵入圧の弱かった南アメリカ,ニューギニアで適応分散し,走鳥類はアフリカ(ダチョウ),南アメリカ(レア),オーストラリア(エミュー),ニューギニア(ヒクイドリ),ニュージーランド(キーウィ,絶滅のモア)に特産する。キリン,カバ,シマウマ,レイヨウ類などはアフリカに,ライオン,ゾウ,サイなどはアフリカとインドに種を違えて熱帯分布し,トラはアジアの温・熱帯にまたがって生息し亜種的な分化を示す。バクは南アジアと南アフリカに分布する点で独特である。南アメリカとアフリカに限産するものは鳥類にヒナフクロウやシロカオリュウキュウカモなどがあるがまれである。
これらの例は,動物の地理分布が大陸や島の地史的な成立の古さや新しさを推定する重要な証拠となることを示し,動物地理学の目的もそこにあるといえる。
執筆者:黒田 長久
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「動物地理区」の意味・わかりやすい解説
動物地理区【どうぶつちりく】
→関連項目マカッサル海峡
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「動物地理区」の意味・わかりやすい解説
動物地理区
どうぶつちりく
「動物区」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の動物地理区の言及
【生物地理区】より
…各地の生物相の特徴を基にした地理的区分。動物,植物,さらにその分類群によって多少異なり,一般に動物の場合は動物地理区,植物の場合は植物区系と呼ばれる。古典的には分類学に基づき分類地理学的な区分がなされたが,近年では生態学的要素も考慮されるようになってきた。…
※「動物地理区」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...