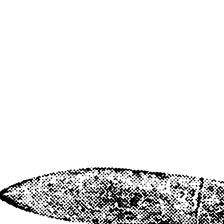精選版 日本国語大辞典 「戟」の意味・読み・例文・類語
げき【戟】
普及版 字通 「戟」の読み・字形・画数・意味
戟
人名用漢字 12画
(異体字)
14画
[字訓] ほこ・さす
[説文解字]

[金文]

[字形] 会意
正字は
 に作り、
に作り、 (かん)+戈(か)。
(かん)+戈(か)。 は旗竿(きかん)に偃游(えんゆう)(吹き流し)をつけた形。柄の先端に横刃を双出する形が
は旗竿(きかん)に偃游(えんゆう)(吹き流し)をつけた形。柄の先端に横刃を双出する形が と同形であるので、
と同形であるので、 に従う。〔説文〕十二下に「枝
に従う。〔説文〕十二下に「枝 るの兵なり」という。古くはまた棘(きよく)ともいい、〔左伝、隠十一年〕「棘を拔いて以て之れを
るの兵なり」という。古くはまた棘(きよく)ともいい、〔左伝、隠十一年〕「棘を拔いて以て之れを ふ」とあり、〔礼記、明堂位〕に「越の棘・大弓」の名がある。
ふ」とあり、〔礼記、明堂位〕に「越の棘・大弓」の名がある。[訓義]
1. ほこ、先端に横刃の双出するほこ。
2. ほこのようにまがる、ほこのように刺す。
3. たて。
[古辞書の訓]
〔和名抄〕戟 保古(ほこ) 〔名義抄〕戟 ミツマタナルホコ・ホコ・ホコノサキ・ハヤク
[語系]
戟kyak、据kia、
 kiokは声義近く、
kiokは声義近く、 はかたく持つこと。指先に力を加えることを拮据という。
はかたく持つこと。指先に力を加えることを拮据という。[熟語]
戟衣▶・戟衛▶・戟援▶・戟架▶・戟
 ▶・戟
▶・戟 ▶・戟給▶・戟戸▶・戟胡▶・戟鉤▶・戟叉▶・戟
▶・戟給▶・戟戸▶・戟胡▶・戟鉤▶・戟叉▶・戟 ▶・戟
▶・戟 ▶・戟支▶・戟手▶・戟盾▶・戟
▶・戟支▶・戟手▶・戟盾▶・戟 ▶・戟
▶・戟 ▶・戟肘▶・戟舞▶・戟吻▶・戟鋒▶・戟
▶・戟肘▶・戟舞▶・戟吻▶・戟鋒▶・戟 ▶・戟門▶・戟吏▶
▶・戟門▶・戟吏▶[下接語]
戈戟・弓戟・剣戟・句戟・交戟・刺戟・持戟・杖戟・奪戟・刀戟・倒戟・兵戟・陛戟・矛戟・列戟
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
改訂新版 世界大百科事典 「戟」の意味・わかりやすい解説
戟 (げき)
jǐ
中国の西周時代以後に多く使用された武器で,戈(か)と合わせて句兵(こうへい)といわれる。基本的には戈と矛(ほこ)を組み合わせた形式で,青銅製が多いが,戦国時代後期になると鉄製のものが現れる。西周時代前・中期の河南省濬県辛村の西周墓からは,矛と戈が合鋳された刺援同体式の戟と,殷後期に使用された長刀と戈を組み合わせた鈎戟といわれるものが出土している。後者の類例はまれである。春秋時代後期の河北省唐山県の墓などからは,戈と矛が別体の刺援異体式の戟が出土し,これ以後,戦国時代にかけての戟はこの形式が中心になる。異形式では内(ない)後端に鈎(かぎ)をつけたものもみられる。漢時代の戟は普通は鉄製であるが,最も古い鉄製戟の出土は,河北省易県燕の下都44号墓から出土したもので,戦国時代後期にあてられる。鉄戟の場合,柲(ひつ)を通すための銅筒(柲帽)が胡に付着している。戟は敵を撃刺と斬るという戈の働きに,矛の突く働きを兼ねたものである。
執筆者:杉本 憲司
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「戟」の意味・わかりやすい解説
戟
げき
ji
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の戟の言及
【武器】より
…ここまでくれば,武器というより,兵器と呼ぶにふさわしい。【渡辺 昌美】
【中国】
[戈,戟,矛など]
古代中国で青銅製の武器として主流を占めたのは戈(か)と戟(げき)であった。戈は先端が三つに分かれており,一つが木製の柄に固定する部分で,あとの二つが鋭利になっていた。…
※「戟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...