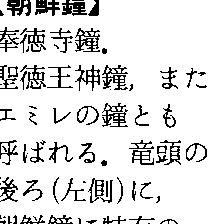精選版 日本国語大辞典 「朝鮮鐘」の意味・読み・例文・類語
ちょうせん‐がねテウセン‥【朝鮮鐘】
改訂新版 世界大百科事典 「朝鮮鐘」の意味・わかりやすい解説
朝鮮鐘 (ちょうせんしょう)
朝鮮半島で製作された一群の梵鐘で,他にまったく比類のない特殊な型式を備えている。まず,竜頭が単頭で,その頸を半環状に曲げて懸吊(けんちよう)の役目を果たし,また,竜頭の背後に密着して〈旗挿し〉(甬(よう))という円筒状のものが立つ。次に,和鐘のように,鐘身に大小長短の区画が施されず,その代りに鐘身の上端と下端とに,唐草文とか宝相華文(ほうそうげもん)が浮彫された装飾帯がめぐらされる。その上端帯の下縁には,乳郭が4ヵ所あり,凹字形をした各郭内に3段3列9個の乳を配列する。さらに,鐘身の下半の空白部には,2ヵ所あるいは4ヵ所の撞座(つきざ)がある。乳郭と撞座との間には,飛天像を陽鋳している。朝鮮鐘の祖型は,中国唐代の寺院の梵鐘にあるが,朝鮮半島では,統一新羅時代に製作が開始され,独自に展開した。現存する最古の在銘鐘は,五台山の上院寺のもので,唐の開元13年(725)にあたる。朝鮮鐘は,統一新羅時代に出現して以来,高麗,李朝にもその伝統型式を残した。高麗鐘は,新羅鐘に比して小型化し,全体に文様が粗雑になり,また,卍字形の雷文のような新しい要素がみられる。やがて,〈旗挿し〉が高くなるなど,変化をとげる。ついには,乳郭の代りに上半部に菩薩像,下半部に鐘銘や八卦(はつけ)図などを陽鋳するものが現れ,元の影響が看取できる。李朝鐘は,製作手法がさらに拙劣になり,また,撞座がなくなったり,天人像に代わって菩薩像が顕著になるなどの特色を備える。日本にも南北朝時代から多数将来され,渡来した在銘鐘の最古のものである福井県常宮神社鐘や高麗鐘の岡山県観音院鐘など40数口が現存している。
→梵鐘
執筆者:西谷 正
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「朝鮮鐘」の意味・わかりやすい解説
朝鮮鐘
ちょうせんしょう
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の朝鮮鐘の言及
【梵鐘】より
…中国鐘には鐘身の裾がヨーロッパのベルのように開き,波状などに作るものがある。また朝鮮鐘は袈裟襷がなく,鈕の竜頭(りゆうず)後方に装飾的な筒(旗挿または甬(よう))を付すものが多い。なお現存する梵鐘のうち,在銘の最古のものは,中国,南北朝陳の太建7年(575)銘のもの(奈良国立博物館)で,和鐘では戊戌年(698∥文武2)の銘をもつ京都妙心寺の鐘,朝鮮では唐の開元13年(725)銘の上院寺鐘が古い。…
※「朝鮮鐘」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...