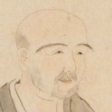関連語
日本大百科全書(ニッポニカ) 「盤珪永琢」の意味・わかりやすい解説
盤珪永琢
ばんけいようたく
(1622―1693)
江戸前期の禅僧。法名は「えいたく」とも読む。元和(げんな)8年3月8日、播州揖西(ばんしゅういっさい)郡浜田村(兵庫県姫路市)に生まれる。赤穂(あこう)・随鴎(ずいおう)寺の雲甫(うんぽ)(1568―1653)について出家得度、雲甫の寂後、備前(岡山県)三友寺の牧翁(?―1694)に参じてその法を嗣(つ)いだ。出家得度後、各地に知識を尋ねて歴参、とくに長崎の崇福(そうふく)寺に来日した道者に参謁したことは、新たな明(みん)風の禅に接する機会となった。人はだれでも生まれながらに不生(ふしょう)の仏心を具有するという不生禅を説いて、平易な説法をもって教えを各地に広めた。公案(こうあん)禅の形骸(けいがい)化を厳しく批判した点、その禅風は日本禅宗史上において特異な意味をもつ。元禄(げんろく)6年9月3日、72歳をもって、開創した播州・龍門(りょうもん)寺に寂した。弟子は僧俗あわせて5万余人に及んだと伝える。大法正眼国師と勅諡(ちょくし)される。
[古田紹欽 2017年9月19日]
『赤尾龍治編『盤珪禅師全集』(1987・大蔵出版)』▽『鈴木大拙編・校『盤珪禅師語録』(岩波文庫)』▽『鈴木大拙著『禅思想史研究――盤珪禅』(1943・岩波書店)』
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「盤珪永琢」の意味・わかりやすい解説
盤珪永琢
ばんけいえいたく
[没]元禄6(1693).9.3.
江戸時代中期の臨済宗僧。 17歳で出家。各地を遍歴したのち,万治2 (1659) 年竜門寺の開山となる。寛文 12 (72) 年勅命によって妙心寺に移り,元禄3 (90) 年仏智弘済禅師の号を賜わった。不生禅を主張,行住坐臥そのままが坐禅であることを教えた。宗派の別なく多くの人々が彼の講筵に列し,弟子の礼をとる者5万余人と伝えられる。法語に『盤珪仏智弘済禅師聞書』 (2巻) ,『弘済禅師法語』 (2巻) などがある。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「盤珪永琢」の解説
盤珪永琢 ばんけい-ようたく
元和(げんな)8年3月8日生まれ。臨済(りんざい)宗。備前(岡山県)三友寺の牧翁祖牛(ぼくおう-そぎゅう)の法をつぐ。長崎で明(みん)(中国)の道者超元(どうじゃ-ちょうげん)にまなんだ。寛文元年郷里の播磨(はりま)(兵庫県)浜田に竜門寺を創建。人はだれでも不生不滅の仏心をもつという「不生禅」を説いた。元禄(げんろく)6年9月3日死去。72歳。諡号(しごう)は大法正眼国師。著作に「盤珪禅師法語」など。
367日誕生日大事典 「盤珪永琢」の解説
盤珪永琢 (ばんけいようたく)
江戸時代前期の僧
1693年没
出典 日外アソシエーツ「367日誕生日大事典」367日誕生日大事典について 情報
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...