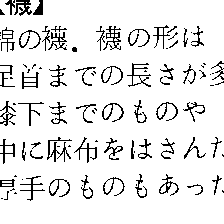改訂新版 世界大百科事典 「襪」の意味・わかりやすい解説
襪 (しとうず)
絹や錦の2枚の足形の布を縫い合わせてつくられた靴下。足袋のような底やこはぜはなく,上方につけた2本の紐で結び合わせる。奈良~平安時代の礼服(らいふく),朝服などに各種の沓(くつ)とともに用いられた。中国唐代の襪(べつ)が伝わり,これをシタクツと呼び,さらにシタグツ(下沓)の音便でシタウズからシトウズとなった。《和名類聚抄》には〈襪,和名之太久豆足衣也〉とある。襪は錦,綾,絁(あしぎぬ),布(麻)を表地に,白絁,生絁を裏地に多く用いた。〈衣服令〉によると,皇太子,親王,諸王,諸臣,内親王,女王,内命婦(ないみようぶ)などが礼服には錦の襪,朝服・制服には白絹の襪をはくよう定められていた。布の襪は写経所の経師,装潢(そうこう)(表具師),校生(こうしよう)(誤字を正す人)に支給されたが,その他一般の人々がこれを用いることはなかった。
執筆者:潮田 鉄雄
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「襪」の意味・わかりやすい解説
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「襪」の意味・わかりやすい解説
襪
しとうず
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の襪の言及
【襪】より
…奈良~平安時代の礼服(らいふく),朝服などに各種の沓(くつ)とともに用いられた。中国唐代の襪(べつ)が伝わり,これをシタクツと呼び,さらにシタグツ(下沓)の音便でシタウズからシトウズとなった。《和名類聚抄》には〈襪,和名之太久豆足衣也〉とある。…
※「襪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
ユーラシア大陸、北アメリカ大陸北部に広く分布し、日本では北海道にエゾヒグマが生息する。成獣は体長2メートル以上、体重300キロにもなり、日本最大の陸生動物として知られる。雑食性で草や木の実、サケ、シ...