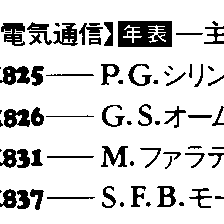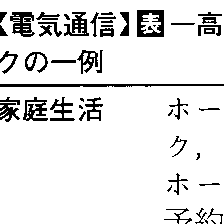精選版 日本国語大辞典 「電気通信」の意味・読み・例文・類語
でんき‐つうしん【電気通信】
- 〘 名詞 〙 電気を利用して、音声・文字・画像などを送ること。電気による通信の総称。電話、電信、放送、ファクシミリなど。〔現代大辞典(1922)〕
改訂新版 世界大百科事典 「電気通信」の意味・わかりやすい解説
電気通信 (でんきつうしん)
electrical communication
電気通信の歴史はすでに1世紀半以上にも及んでおり,現在も高度情報社会の実現に向けてとどまるところなく発展を続けている。G.S.オームがオームの法則を発見したのは1826年,M.ファラデーが電磁誘導現象を発見したのは31年である。これらをもとにして64年J.C.マクスウェルは電磁場理論を大成し,電磁波の存在を理論的に示し,88年にはH.R.ヘルツが電気火花により電磁波の存在を実験的に実証した。電気通信の歴史はこのような電気磁気学の基礎が築かれつつある時代にすでに開始されている。例えば電信機は1829年にロシアのシリングP.L.B.Schilling(1786~1837)により実現されており,静止画像を伝送するファクシミリの原形は43年にイギリスのベインAlexander Bain(1810-77)が発明し,基礎的な実験も行われていた。電話についてはその原理を54年にベルギーのブールサールCharles Bourseul(1829-1912)が提案し,61年にはドイツのライスJohann Phillip Reis(1834-74)が実験を行っている。
電信の始まり
電気通信の実用化は電信から始まっている。1837年にニューヨーク市立大学の美術教授であった画家のS.F.B.モースが実用的な電信機を発明し,文字や数字を符号化して伝達する方式を考案した。これが電気通信の事実上の幕あけといってもよいであろう。19世紀にはすでに鉄道が発達し,海外貿易も盛んになってきており,通信の効用や必要性が高まっていた。これを背景としてその後電信は急速に発展し,19世紀末ころまでには世界的規模の電信網も形成されるに至っている。すなわち,44年にはワシントン~ボルティモア間の電信回線が開通し,51年にはドーバー海峡海底電信回線の敷設にも成功している。そして58年には大西洋横断の海底電信回線が敷設された。これは当初は高圧信号を送ったために絶縁不良などの原因で3ヵ月後には不通になってしまったが,その後微弱信号検出方式などの開発により65年ころから本格的実用化の時代に入っていった。日本では73年に東京~長崎間の電信回線が開通し,その後これはシベリア経由でヨーロッパにまで延長されている。さらに太平洋横断海底電信ケーブルも1906年には開通された。
当時,まだ真空管も発明されておらず,増幅技術も存在していなかった時代に,このような世界的な規模の通信網が形成できた理由は,情報を符号化して伝送したところにあると考えられる。情報を1,0の系列に符号化して伝送すれば,伝送回線で減衰した信号を効率的に受信できるばかりでなく,また伝送回線の途中で減衰した信号を元どおりに復元する再生中継も可能になるからである。すなわち,中継所で電信技師が信号をいったん受信したのち,あらためて再送信を行えば信号は元どおりに再生することができ,このような操作を繰り返せばどんな遠方にでも容易に通信が行えることになるのである。電信による距離と時間の克服は予想以上の社会的効用をもたらすことになり,これが電信網の発展の主要因と考えてよいであろう。この符号通信技術の基本的な考え方は,電信技師が再生中継器に変わってはいるが,現在のディジタル通信方式にも引き継がれており,さらに将来の通信技術の発展に対してもますます重要なる役割を果たしていくものと期待されている。
→電報
電話の始まり
電気通信網の第2の転換期は,1876年,A.G.ベルの実用的電話機の発明から開始される。翌77年には炭素送話器を用いて感度を高め,伝送距離の拡大を可能にした改良形電話機がT. A.エジソンにより発明された。この方式は今日なお広く使われている電話機の基本原理をなしている。電話は電信とは異なり,人間の音声をそのまま電気信号に変換して伝達する方式であるので,だれでもすぐ使えるというのが最大の特徴である。このような特徴から,電話業務は電信とは違って当初から不特定多数を加入者とする公衆通信網の形式で開始されている。電話機発明の翌77年にはすでにボストンにおいて電話業務が開始された。日本でも同年電話機が輸入されて実験が開始され,78年には警察用電話として実用化されている。
世界最初に商用化された電話交換機は磁石式と呼ばれる手動交換機である。これは交換手が交換操作を行う方式であるが,78年にはアメリカのニューヘブン市に設置されている。90年には日本においても電話交換規則令が発せられ,ベルギーから輸入された手動交換機を用いて東京と横浜において交換業務が開始されている。このときの電話加入者は全体で220名であった。電話がしだいに普及し,一般化されていくにつれ,正確で迅速なる接続,昼夜の別なきサービス,通信の秘密保持の要求もでてくるようになり,交換手の介入が問題になってきた。このような要求にこたえて89年,当時葬儀屋を営んでいたといわれるストロージャーA.B.Strawger(1847-1905)により機械式の自動電話交換機が発明された。これがストロージャー式交換機であり,92年にはインディアナ州北部のラ・ポルト市で商用化が開始されている。この方式はその後いろいろと改良され,ニューヨークなどの大都市に本格的に採用されるようになったのは1920年代に入ってからのことである。日本では関東大震災によって東京,横浜における手動交換設備が壊滅したのを機会に自動化が開始された。26年にストロージャー式の流れをくむステップ・バイ・ステップ交換方式と呼ばれる自動交換機がイギリスおよびドイツから輸入され,それぞれ東京および横浜において採用された。さらに日本において自動交換機の国産化が始まるのは30年ころからである。すなわち,30年には英米系のストロージャー式の国産化が始まり,これは以後A形自動交換機と呼ばれるようになった。ドイツのジーメンス式をモデルとして34年に国産化された方式がH形自動交換機であり,以後第2次世界大戦直後までこの2方式を中心として日本の電話網が建設されていったのである。
伝送技術の発達
電信と電話の違いの一つは,電信の場合には符号化されたディジタル通信方式であったために,当初から長距離通信が可能であったのに対し,電話の場合には信号波形をそのまま伝送するアナログ伝送方式をとらざるを得なかったために,増幅技術がなかった当初においては経済的に構成しうる伝送範囲は限られていたことである。したがって電話は地域的に限定された通信網として出発せざるを得なかった。その電話網が今日の世界的な規模にまで発展し得たのは,増幅器の発明と多重通信技術による伝送路の効率的利用によるものといってよいであろう。その基礎となるものは,1906年のデ・フォレストL.de Forestによる三極真空管の発明,10年のスクワイアGeorge Owen Squier(1865-1934)による搬送電話方式の発明,15年のハートリーRovert von Louis Hartleyによる真空管発振器の発明,17年のキャンベルGeorge Ashley Campbellによるフィルター理論の完成などであろう。
通信伝送路として最初に実用化された方式は電柱に多数の銅線を張りめぐらした裸線方式であった。裸線方式は伝送損失が比較的に少ない特徴をもってはいたが,広い空間を占有するうえに,外界からの影響を受けやすく,雑音などの伝送特性に問題が多かった。そこで1910年ころからは,絶縁した銅線対を多数束ねて作るケーブル線路が用いられるようになり,これによって安定な通信回線が構成できるようになった。しかしケーブル線路の問題の一つは,長距離回線になると減衰が著しくなることである。当初はこの減衰を電気回路的に補償する方式として1900年にピューピンMichael Idyorsky Pupin(1858-1935)により発明された装荷ケーブルが用いられた。これはケーブルのところどころに装荷線輪と呼ばれるコイルを直列に挿入し,線間容量による信号減衰を等化補償するものである。この方式と真空管中継増幅器を併用することにより長距離通信網が実現可能になったのである。しかしながら,装荷ケーブル方式は伝送周波数帯域幅が限定され,したがって多重通信方式には適さなかった。そこで再び装荷線輪を取りはずし,多重通信を意図して32年に松前重義により提案された方式が無装荷ケーブル方式であり,これはその後内外における重要電話幹線網に広く採用されることになった。
ラジオやテレビ放送では一つの空間を伝送路とし,搬送周波数をかえて多数のチャンネルを同時に伝送している。このような方式を周波数分割多重通信という。無装荷ケーブルでも周波数分割多重通信が可能であるが,1対の線路で運べる電話回線はせいぜい数十通話が限度である。2本の針金をより合わせて作る線路対を多数束ねて作ったケーブルを平衡形ケーブルというが,平衡形ケーブルでは周波数が高くなると線路対間の漏話が問題になる。したがって漏話による周波数帯域幅の制限により,多重度をあまり高くとることができないのである。この問題を抜本的に解決した方式が同軸ケーブルである。同軸ケーブルは細い銅管を外部導体とし,この中にこれと絶縁した中心銅線を通した形のケーブルであり,外部導体の遮へい効果から高周波における漏話を著しく小さくできるのが特徴である。同軸ケーブル方式は第2次大戦後に広く実用化されるようになり,これと合わせて電子回路技術の進歩により多重度も向上した。現在では1万通話以上の電話回線を1条の同軸ケーブルで伝送する高多重の搬送多重通信方式も実用化されている。
有線通信方式である同軸ケーブル方式と並んで発達した無線通信伝送方式にマイクロ波通信方式がある。これは周波数が数GHz(1GHz=109Hz)から十数GHzの極超短波を搬送波とする多重通信方式である。このような高周波になると電波の伝搬特性は光の特性に近づき,到達範囲は見通し内に限られてくるが,周波数帯域幅が広くとれ,外来雑音の影響が少なく,安定な伝送特性をもつことから無線通信網の主体はこのマイクロ波通信方式がもっとも広く採用されている。マイクロ波通信技術はレーダーの開発と並行して第2次大戦中から戦後にかけて急速に発達したものであるが,現在では同軸ケーブルと並んで,長距離市外電話網における2大構成要素の一つになっている。
トランジスターは48年にW.B.ショックリーやG.L.ピアソンらによって発明された。これを機として開発が進められた半導体電子回路技術の進歩は著しく,通信伝送分野にも大きなインパクトを与えている。搬送多重通信の分野では多重度の増大,装置の小型化,高信頼化により機能を著しく向上させただけでなく,システムの経済化にも大きく貢献した。しかしそれ以上の貢献は通信システムのディジタル化を可能にしたことであり,これによって電気通信網に新しい幕あけをもたらすことになるのである。音声信号のような連続波形,つまりアナログ信号でも,これを電信のような1,0符号の系列,つまりディジタル信号に変換して伝送することができる。このような変換をパルス符号変調PCM(pulse code modulationの略)という。PCMの発想は1937年にリーブズAlec H.Reevesにより提案され,これにより安定で信頼性の高い通信が可能になることが知られていた。しかし回路が相当に複雑化するために真空管時代においては実現不可能とされていた。これを実現可能としたのが半導体電子回路技術である。62年にアメリカのベル研究所で24多重のT-1方式と呼ばれるPCM多重通信方式が開発された。日本においても65年にPCM-24方式が完成した。その後,多重度もしだいに向上され,現在では1万多重以上のPCM多重通信方式も実現されている。ディジタル通信方式は電話だけでなく,データ通信,画像通信などにも広く活用されているが,その理論的基礎を与えたのは1948年にC.E.シャノンによって創始された情報理論であろう。これはその後通信理論として発達し,通信技術全般にも少なからぬ影響を与えている。
大陸間にまたがる国際通信には従来から海底同軸ケーブル方式や衛星通信方式が用いられてきた。海底同軸ケーブル方式は56年に敷設された大西洋横断ケーブルTAT-1方式が最初であるが,その後日本とアメリカを結ぶ太平洋横断ケーブルTPC-1,TPC-2方式など,各所で広く活用された。さらに,人工衛星が打ち上げられるようになり,国際通信の主流は人工衛星のほうに移っていった。通信用に用いられている衛星は,赤道上空の高度3万5860kmのところに地球の回転と同期して東回り回転するものであり,相対的に地上とは静止位置を保っている。このような衛星を静止衛星といい,静止衛星を中継所としてマイクロ波通信を行う方式が衛星通信方式である。1個の静止衛星は地球表面のほぼ1/3をカバーすることができ,したがって赤道上空の3ヵ所に打ち上げた静止衛星で全世界がほぼカバーされる。国際電気通信衛星機構インテルサットの管理するインテルサット衛星は,現在大西洋,インド洋,太平洋の3ヵ所に打ち上げられている。65年に打ち上げられたインテルサット1号系の通信衛星が商用通信衛星の最初であるが,国際通信需要の増大とともにしだいに大型化され,現在のインテルサット6号系の衛星は48台のトランスポンダー(中継装置)を搭載し,電話換算6万8000回線とテレビ2回線分の伝送容量をもつに至っている。
時代はさらに転回し,現在はすでに次の世代の通信方式ともいうべき光通信の時代に入っている。これは光を用い,髪の毛ほどの細いガラス繊維からなる光ファイバーを伝送媒体とする通信方式である。光も電磁波の一種であるので電気通信の延長線上に位置づけられる方式であるが,従来の方式と比べると,光ファイバーのもつ低損失の伝送特性,広帯域の周波数特性,低漏話で外来電気雑音の影響を受けないすぐれた耐雑音特性,温度依存性の少ない安定性,細心性による多対化やケーブル敷設工事の容易性など,光通信には多くのすぐれた特徴があり,画期的な通信伝送方式として広く活用されるようになった。これにより,従来の電気的方式では経済性の点から実現が困難とされている動画像通信を含む広帯域通信網も実現されつつある。
歴史的には,1954年にC.H.タウンズが遠赤外領域の電磁波を発生するメーザーを発明し,同じ原理で光の発振が可能であることを予言した。60年にはT.H.メイマンがルビーを使ってレーザーを発明した。これにより周波数と位相がそろった光が得られるようになり,光通信への道が開かれたのである。今日の光通信用光源として広く用いられている半導体レーザーは西沢潤一らにより予測されていたが,62年アメリカにおいて実現されている。
光ファイバーは胃カメラ用の伝送媒体などに古くから使用されていたが,伝送損失が1000dB/km以上もあり,当時は通信には使えないものと思われていた。しかし66年にK.C.カオは光ファイバーの低損失化を示唆する歴史的論文の発表を行い,これをもとにしてアメリカのコーニング・グラス社は70年に伝送損失20dB/kmの光ファイバーを実現した。これは全世界に一大ショックを与え,これをきっかけとして研究は急速に進展した。現在,日本はこの分野においては世界最高級の技術レベルを保っており,79年には電電公社(現,日本電信電話(株))において損失0.2dB/kmの理論限界に近い光ファイバーが実現されている。
光通信システムの開発の点でも日本は世界をリードしている。1975年には32メガビット/sの光画像伝送システムが製作された。通信回線への導入は81年ころから始まり,現在では10ギガビット/s(電話換算で約16万回線分の伝送容量をもつ)の超高速光通信システムも実現されている。
光ファイバー伝送方式は,現在国内幹線系はもとより,大洋横断海底ケーブルの主流方式になっている。技術の進歩によりケーブルコストもしだいに低下し,いずれ通信網のあらゆる分野に使用されることになるであろう。日本では2010年の完成を目ざして全国加入者線の光ファイバー化が進められている。
光通信方式と並んでこれからの新しい通信伝送媒体として期待されているものに国内用衛星通信方式がある。通信衛星打上げ技術の進歩により,衛星通信は国際通信のみならず,国内通信用にも用いられるようになってきた。衛星通信方式はきわめて多量の伝送容量をもつ。また,距離に依存しない柔軟性の高い通信網が構成でき,網構成の可変性,放送的な情報伝達など,地上網とは違った新しい通信システムの構成も可能になる。その適用領域としては,新規通信サービスの全国的早期導入,移動体用通信伝送,地上網災害時のバックアップ網,離島僻地対策など,さまざまな用途が期待されている。現在すでに衛星通信システムのディジタル化も始められており,マルチビームを用い衛星に交換機を搭載した交換機搭載ディジタル衛星通信方式もいずれ実現されることになるであろう。日本においても国内用通信衛星CS-2が83年に打ち上げられており,商用化の時代はすでに始まっている。
交換技術の発達
交換技術は1889年にストロージャーが機械式の自動交換機を発明して以来,およそ100年の歴史を経過しているが,この間,回転スイッチなどを用いた進行運動形の機械式交換機から,接点を格子状に並べて格子スイッチを構成し,これを電磁リレーを用いた制御装置で集中的に制御する共通制御形の電磁リレー式交換機を経て,制御系にコンピューターを用いた電子交換機へと発展し,現在ではディジタル多重伝送技術を応用し,タイムスロットの時間的な入換えによってスイッチングを行う効率的で融通性の高いディジタル電子交換機が各国において広く採用されるようになってきている。交換技術の進展は国情によってかなりの差があり,一般論的に説明するのはむずかしい。ここでは日本の技術の変遷を中心に説明することにする。
日本で自動電話交換機の国産化が始まったのは1930年ころからである。これはストロージャー式の流れをくみ,回転スイッチを用いた機械式交換機であった。この種の方式は,加入者が回すダイヤルのパルスによって直接的に1桁ずつ回転スイッチを動作させながら,縦続的につなげられている多段のスイッチを順々に動作させて交換接続を行うことから,一般にステップ・バイ・ステップ交換方式と呼ばれている。日本においてはこのステップ・バイ・ステップ交換方式を用いて,第2次大戦直後に至るまでに一応の市内電話網を構成してきた。しかし,この方式は交換制御機能が低かったために市外電話網には適用できず,当時の市外電話には交換手の操作による手動交換機が用いられていた。
戦後,全国自動即時接続の気運が高まり,これにこたえるべく新しく開発,実用化された方式がクロスバー交換方式である。この方式は通話スイッチ回路にクロスバースイッチと呼ばれる開閉形の格子スイッチを用い,制御部には電磁リレーを用いた共通制御方式が採用されている。開閉形のクロスバースイッチには雑音が少なく,安定な通話特性をもった貴金属接点が使用でき,このため通話特性は飛躍的に改善され,多段の中継交換接続を要する長距離市外網にも十分に耐える特性が実現された。制御系は共通制御方式によって集中化されているために,高価な市外伝送系を有効に利用するための迂回中継によるルート選択制御や,複雑な料金体系をもった市外料金の自動課金,あるいは効率的な保守試験を含むシステムの高信頼化など,制御機能は大幅に向上し,これによってはじめて全国自動即時化が達成可能になったのである。クロスバー交換方式は最初スウェーデンで生まれ,その後アメリカで発展した方式である。日本はこれらを参考とはしているが,日本の国情に適合すべく独自の方式が開発され,55年ころから実用化が開始された。65年から75年にかけての10年間は日本の電気通信網の高度成長時代である。この10年間で電話台数は当初の1000万台から4000万台へと飛躍的に向上した。1970年代末ころまでにこのクロスバー交換方式を中心として全国自動即時化も100%達成されている。
技術の進展はめまぐるしい。上記のように急速に開発されたクロスバー交換機も,やがて次代を担う電子交換機に置きかえられることになった。電子交換方式とは,従来の交換機が電磁リレーや機械式スイッチを用いて構成されていたのに対して,これを電子回路を用いて構成した交換方式である。その研究開発の歴史は古く,1939年に電電公社の前身である逓信省工務局において松前重義の提唱で電子交換研究会として発足したのが世界最初であり,42年にはサイラトロンと呼ばれる電子管を用いた小実験機が試作されている。第2次大戦後,半導体や磁性体などの新しい電子素子の実用化と,コンピューターとともに進歩した電子論理回路技術の発達につれて研究はいっそう具体化され,アメリカやヨーロッパ諸国も研究に加わって多種多様な方式が試作された。日本においても戦後直ちに研究が再開され,53年に大阪大学において冷陰極放電管を用いた実験機,次いで電電公社においてパラメトロンを用いた実験機,さらに57年には東京大学において日本最初の時分割形全電子交換機AO-1が試作された。その後,世界各国で各種の方式が研究されたが,電子交換方式の実用化のきっかけを作ったのは蓄積プログラム制御方式の採用であった。蓄積プログラム制御方式をひと口でいえば万能形のコンピューターで制御する交換制御方式といってもよいであろう。プログラム制御によって交換制御に万能性,可変性を与えようというのがこの方式の基本的発想である。これによっていろいろな新しい通信サービスの導入が容易になる。ハードウェアの統一標準化が行いやすくなって経済的な交換機が構成可能になる。障害検出の自動化や故障個所の自動診断など保守運用上のメリットも高められる。この意味から蓄積プログラム制御方式は交換方式に一大変革を与えるものとして注目されるようになったのである。蓄積プログラム制御方式を用いた商用電子交換機としては,65年アメリカのニュージャージー州にあるサカサナ市で開局されたNo.1ESSが世界最初である。
通信網の高度成長時代を終えた日本においても,次代の発展に備えて新しい通信サービスの開拓の必要性にせまられるようになってきた。このころに生まれた考え方に総合通信網構想があった。これは電話のみならず,データ通信,画像通信,移動体通信など,各種の通信サービスを総合一体的に処理することにより,新しい通信需要の開拓を行うとともに,高度情報社会の実現に備えようという考え方である。このような多彩な通信サービスを具体的に実行するのは交換機である。その交換機には万能性や可変性が必要になる。それにこたえうる方式が蓄積プログラム制御方式というわけである。日本においても72年にD10形自動交換機と呼ばれる蓄積プログラム制御形電子交換機が東京,大阪,名古屋に開局して,ようやく商用化時代に入っていったのである。現在はさらに次代のディジタル交換機の時代に入っているが,これについてはあとで説明する。
データ通信技術の発達
ディジタルコンピューターの起源は,第2次大戦中に高射砲の弾道計算を直接の目的として,アメリカのペンシルベニア大学において研究開発されたENIACと呼ばれる電子管式ディジタル計算機といわれている。その後,半導体論理回路技術,磁性体記憶回路技術の発達は,電子計算機のみならず,情報処理技術全般を急速に発展させていった。理論面では,1945年にJ.フォン・ノイマンによって提案された蓄積プログラム制御の概念によりその基礎が確立され,この方式がもつ万能的で融通性の高い情報処理機能はこの分野の技術の発展に重要なる役割を果たしている。
この情報処理技術の発達は電気通信網にも大きな影響を与えつつある。その一つが情報の伝送と情報の処理を一体化したデータ通信方式の実現である。本格的なデータ通信の実用化は52年にアメリカの航空会社が建設した座席予約システムが世界最初であろう。日本においても59年に国鉄(現JR)の座席予約システムMARS-1が作られた。これらはいずれも中央の専用的な情報処理装置にそのシステム専用の特殊端末をつなげて構成したものであったが,しだいに処理装置に汎用コンピューターが用いられるようになり,さまざまなデータ通信システムが構成されるようになった。これは1958年にコンピューターの新しい使い方であるタイムシェアリングの考え方がマッカーシーJ.McCarthyにより提案され,これにより多数の端末が中央のコンピューターを共同利用できる汎用性の高いデータ通信システムが構成できるようになったからである。データ通信システムは,当初は個々の事業体あるいは関連事業体群が,専用回線を使用して中央に設置したコンピューターと分散設置されたデータ通信端末間を結合してデータの伝達,処理を行う,いわば閉じた通信システムとして発達した。例えば銀行のオンラインシステム,交通機関の座席予約システム,製造会社の在庫管理や受注販売管理システム,行政あるいは一般事務の集中管理システム等々である。現在ではデータ通信はこのような専用システムとしてだけでなく,一般不特定多数の間にも拡大されつつある。例えば,不特定多数の人々を対象とした各種の案内,予約サービス,情報検索サービス,金融サービス,クレジットサービス,医療情報サービス等々である。これらのデータ通信サービスは今後一般大衆の間にもしだいに広く普及されていくであろう。これらのデータ通信を実行するには公衆データ通信網が必要である。現在日本においてはDDXと呼ばれる国内データ交換網や,VENUSと呼ばれる国際データ交換網などが運用されている。
高度情報社会の実現に向けて
21世紀における高度情報社会の実現に向けて,現在,電気通信技術は新たなる局面を迎えつつある。現在の工業化社会は物質的な豊かさをもたらした。これから人間の欲求はさらに高度化,多様化していき,物質的欲求から精神的豊かさへと拡大していくであろう。豊かな国民生活の実現,経済の効率化や活性化の促進,社会機能の高度化,国際間の連帯や協調の促進などを,情報通信手段をベースとして実現していこうというのが高度情報化である。このような時代には表に示すような新しい通信ネットワークが,家庭生活,社会生活,企業活動,国際活動など,あらゆる分野に浸透していくであろう。現在すでにニューメディア,データベース,付加価値通信網VAN(value added networkの略)にみられるような情報の産業化,オフィスオートメーションネットワークにみられるような産業の情報化も始まっており,一般家庭を対象としたホームオートメーションネットワークの研究も開始されている。
このような多彩な通信サービスを実現するためには通信網と情報処理システムの有機的な結合が必要である。音声,データ,画像などのあらゆる通信情報を総合的に処理しうる伝送,交換システムも実現されなければならない。その実現手段がディジタル技術であり,とくにディジタル交換機の果たすべき役割は大きい。
ディジタル交換とは伝送部門で広く用いられているディジタル多重通信方式の考えをスイッチングに応用し,時分割的に多重化されたディジタル信号のタイムスロットを時間的に入れ換えることによって交換を行う方式である。その起源は,1959年にアメリカで試作されたESSEXと呼ばれる実験用PCM交換機が世界最初であるが,同年東京大学においてもこれとはやや原理を異にする並列PCM交換方式が提案されている。68年にはイギリスにおいて商用に設計されたPCM交換機の現場実験も行われた。しかし,ニーズや部品技術の開発の必要もあって,具体的に実用化が始まったのは80年代に入ってからである。日本においては83年から商用化が開始されている。
伝送系と交換系をディジタル技術で一体化すれば安定性,信頼性,経済性に富む通信網が構成できる。これをディジタル統合網という。音声,データ,画像など,いずれの情報もディジタル符号化すれば,すべて1,0の符号系列に変換される。したがってディジタル統合化により通信サービスの総合化も容易になる。このようにして各種の通信サービスを総合一体的に処理する通信網を総合網という。さらにディジタル統合網は,同じディジタル技術をベースとしている情報処理や通信処理技術との両立性が高い。またこれからも急速に発展が予想されるLSI電子回路技術や光通信技術との親和性も高い。したがって,ディジタル統合網を用いれば情報処理をも含めた各種通信サービスの総合化が可能になり,将来の発展も十分に保証されるであろうというわけである。これを国際的には総合サービスディジタル網ISDN(integrated services digital networkの略)といっている。NTTではこれを高度情報通信システムINS(information network systemの略)と呼んでいる。
ISDNはディジタル統合網をベースとして,音声,データ,画像などの各種の通信メディアを総合化した通信網である。この通信網のもう一つの特徴は国際的に標準化されていることである。1988年に国際標準の合意がえられ,世界各国において商用化が開始された。
現在広く使用されているISDNは電話用PCMの伝送速度である64kbpsを主体として構成されている。21世紀は映像通信時代といわれている。映像情報の伝達には数十Mbpsから数百Mbpsの超高速伝送が必要になる。それを可能にする高速・広帯域交換方式としてATM(asynchronous transfer mode)交換方式がすでに実現されている。光交換方式の研究も盛んに行われている。現在,これらの交換方式を軸として,音声からハイビジョンに至るあらゆる通信メディアを総合化する広帯域ISDNの開発が積極的に進められている。
執筆者:秋山 稔
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「電気通信」の意味・わかりやすい解説
電気通信
でんきつうしん
telecommunication
電気を利用した通信の手段一般をいう。通信の手段としては、古代から煙、光、音などが使用されてきたが、19世紀初頭の電池の発明により、電気を用いる通信手段が次々と開拓され、より速く、より遠く、より正確にという欲求から種々の発明が生まれた。
最初の実用的な電気通信は1837年、アメリカのS・F・B・モースによる電信の発明である。その後、1876年には電話機がアメリカのA・G・ベルによって発明され、電気通信は飛躍的に発達した。伝送方式としての有線方式は裸線(むき出しの銅線)からケーブル、同軸ケーブルへと発達し、現在では光ファイバーケーブル方式が一般的である。また、無線方式については、電波の存在が1864年にイギリスのJ・C・マクスウェルによって予言されていたが、通信への利用は1896年のイタリアのG・マルコーニによる無線電信の実験からであった。実用的な無線方式の利用は、1910年代から長波による船舶との通信や、1920年ごろからの中波のラジオ放送などをはじめ、その後、短波、極超短波、マイクロ波、ミリ波と発達を続け、現在ではテレビはもちろんのこと携帯電話、カーナビゲーション、無線LAN(ラン)など多様な目的に使われている。有線、無線とも、その発達の背景には、真空管、トランジスタ、IC(集積回路)、LSI(大規模集積回路)などの電子デバイス、そして半導体レーザーなどの光デバイスなどの数々の発明があり、今日では電気通信の種類、通信の速度、やりとりされる情報量は飛躍的に増大し、日常の生活に多大な貢献をしている。
[坪井 了・三木哲也]
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「電気通信」の意味・わかりやすい解説
電気通信
でんきつうしん
telecommunication
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の電気通信の言及
【通信】より
…印刷の発達は,しだいにパーソナル・コミュニケーションの分野にある郵便にもダイレクト・メールの増大といった影響をもたらすようになった。 19世紀には電信,電話が相次いで発明され,これによって電気通信が通信を主導する時代がもたらされることとなった。まず1844年S.F.B.モースによって電信が実用化され,おりからの鉄道の発展と相まって,電信網はめざましい伸展を示した。…
※「電気通信」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...