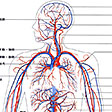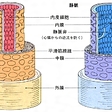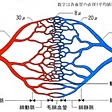精選版 日本国語大辞典 「静脈」の意味・読み・例文・類語
じょう‐みゃくジャウ‥【静脈】
- 〘 名詞 〙 ( [オランダ語] Aders の訳語 ) 体の末梢部および肺から心臓へ血液を送りこむ血管。脈壁は比較的薄くて弾力性に乏しく、各部に静脈弁を備えて血液の逆流を防ぐ。体の各部分から起こって心臓の右心房へはいるものと、肺から出て左心房に入る肺静脈とがあり、前者の血液は静脈血であるが後者の血液は動脈血である。狭義には肺静脈を除いていう。静脈管。せいみゃく。
- [初出の実例]「かの静脈と云って、血を心の臓へ輸(おく)りかへす脈管へつたって」(出典:志都の岩屋講本(1811)下)
- 「うらさびしき女にあひて手の甲の静脈(ジャウミャク)まもる朝のひととき」(出典:あらたま(1921)〈斎藤茂吉〉日日)
せい‐みゃく【静脈】
- 〘 名詞 〙 体内各部の血液を心臓に送る血管。じょうみゃく。〔改正増補和英語林集成(1886)〕
日本大百科全書(ニッポニカ) 「静脈」の意味・わかりやすい解説
静脈
じょうみゃく
全身の血液を毛細血管から心臓へと運ぶ血管をいう。全身の静脈はその走る部位によって浅静脈と深静脈に分けることができる。浅静脈はいわゆる皮下静脈で、皮下組織中を動脈とは平行せず単独で走っている。皮下静脈は皮膚を通して青白くみえ、その走行は皮膚表面からもわかる。皮下静脈は浅層の組織からの血液を集め、深静脈と連絡している。肘(ひじ)の前面にある肘(ちゅう)正中皮静脈や前腕正中皮静脈などは太い皮下静脈で、静脈注射によく用いられる。下腹部や下腿(かたい)後面の皮下静脈は、深静脈の血流障害により静脈血がたまりやすく、膨らんでミミズのようにうねうねと蛇行しているのをみることがある。これが静脈瘤(りゅう)とよばれるもので、中年以後の女性、とくに老人や妊婦に多くみられ、立ち仕事に従事する者にも好発する。
深静脈は一般に動脈に伴って同じ結合組織性被膜内に包まれて走っている。太い動脈(鎖骨下動脈、腋窩(えきか)動脈、大腿動脈、膝窩(しっか)動脈)の場合は静脈は1本だけ平行に走り、それより細い動脈(上腕動脈、橈骨(とうこつ)動脈、尺骨(しゃくこつ)動脈、脛骨(けいこつ)動脈、腓骨(ひこつ)動脈)では通常、静脈は対(つい)をなして動脈の両側を走る。これを伴行静脈とよぶ。また、特殊な器官(頭蓋骨(とうがいこつ)、脊柱管(せきちゅうかん)、肝臓)の静脈は動脈に伴行しない。
静脈が周囲の組織と癒着して血管の内腔(ないくう)がとくに広くなっている部分を静脈洞とよび、この部分には静脈血がたまって血流は遅くなる。静脈が細かく枝分れして網の目をつくっているのが静脈網で、これが立体的に構成されたものを静脈叢(そう)とよぶ。さらに静脈叢が非常に緻密(ちみつ)に構成されている場合には海綿体とよぶ。静脈壁の構造は、動脈と同様に内側から内膜、中膜、外膜の3層を区別することができる。同じ太さの静脈と動脈とを比べると、一般に静脈のほうが薄くて弾性線維や平滑筋線維も少ない。内膜は1層に配列する内皮細胞層と縦走の平滑筋線維、中膜は輪走の平滑筋線維、弾性線維と結合組織など、外膜は縦走筋線維、弾性線維と結合組織から構成されている。
静脈は一般にその太さによって、細静脈、小静脈、中等大の静脈、太い静脈に分けられる。直径が1ミリメートル以下の細静脈・小静脈では3層の膜を区別しにくいが、1ミリメートル以上の中等大の静脈ではやや外膜が発達し、太い静脈では内膜、外膜が発達し、厚くなっている。また、直径が2ミリメートル以上の中等大の静脈や太い静脈の内部には至る所に静脈弁がある。これは内膜が折り返されたもので、血液の逆流を防ぐ働きをもっている。静脈弁は、一般には半月形の弁が2枚相対しているが、小さい静脈では1枚の場合もある。静脈弁は手足の静脈に多く、静脈瘤が下肢にできやすいのもこのためである。なお、頭蓋の静脈、頸静脈(けいじょうみゃく)、臍静脈(さいじょうみゃく)、肝静脈、肺静脈、子宮の静脈や門脈には弁がない。
動脈は毛細血管を経て静脈に移行するのが一般であるが、毛細血管を介しないで直接、細動脈と細静脈がつながる場合がある。これを動静脈吻合(ふんごう)(誘導循環)とよび、指腹部の皮膚、鼻粘膜に発達している。動静脈吻合は、血流を迅速にして温度を調節するという役割をもっている。また、頭蓋腔内の静脈は太い静脈につながるほか、頭蓋骨を貫いて頭部の皮静脈と結合しているが、これを導出静脈という。静脈壁の栄養供給は栄養血管、つまり脈管の血管がこれを行う。静脈には動脈と同じように神経が分布しているが動脈に比べ少数である。
[嶋井和世]
改訂新版 世界大百科事典 「静脈」の意味・わかりやすい解説
静脈 (じょうみゃく)
vein
体組織,器官から血液を心臓に運びこむ血管。ヒト以外の脊椎動物でも,その構造はヒトの静脈の構造に共通するところが多い。動脈に比べ,一般に結合組織が多く平滑筋は少ない。円口類のヤツメウナギでは静脈系がきわめてよく発達するが,そのほとんどは壁に平滑筋を欠き,内皮細胞基底面をおおう基底膜も部分的にみられるにすぎない。多くの無脊椎動物では,脊椎動物の静脈に相当する構造のものはない。心臓の発達する多くの軟体動物や甲殻類では,体組織からの血液は,心臓周囲に広がる大きな組織間隙(かんげき)(囲心腔)に集められ直接心臓に入る。環形動物,節足動物,尾索類の血行路の一部は,その筋層の収縮による蠕動(ぜんどう)運動によって血液循環の動力源(心臓)となっているが,これも組織間隙から直接血液を集めている。いずれにも脊椎動物の静脈に相当する固有の血管構造はない。しかし,例外的に頭足類の一部では,えらから血液を集め心臓に注ぐ静脈がある。
→血管系
執筆者:中尾 泰右
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「静脈」の意味・わかりやすい解説
静脈【じょうみゃく】
→関連項目血管|静脈麻酔|動脈|リンパ管
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「静脈」の意味・わかりやすい解説
静脈
じょうみゃく
vein
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の静脈の言及
※「静脈」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...