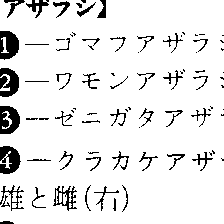改訂新版 世界大百科事典 「アザラシ」の意味・わかりやすい解説
アザラシ (海豹)
seal
earless seal
Seehund[ドイツ]
鰭脚(ききやく)亜目アザラシ科Phocidaeに属する海獣の総称。食肉目のうち水中生活に適応した哺乳類。11属19種が知られている。体は紡錘形で,前肢が短く後肢が後方に向かう点で鰭脚亜目中のアシカ科,セイウチ科と異なる。四肢は毛で覆われる。吻(ふん)部はアシカほどとがらず耳介を欠く。陸上では四肢歩行ができず,前肢と体幹部によりはって移動するのみである。左右の後肢を合わせ,ちょうど魚が尾びれを振って泳ぐように左右に振って泳ぐ。犬歯は比較的小さい。毛は粗毛状で,アシカ科ほど密でないが,セイウチ科より多い。オットセイの仲間のような下毛はほとんどない。新生子は新生子毛を有する。とくに北半球の海氷上で繁殖する種では毛足の長い真っ白な新生子毛を有する。白い新生子毛は保護色と体温放散防止の役をする。
体の大きさは分布と関係している。南極海のように食物が豊富なところに分布するアザラシは大型で,ミナミゾウアザラシの雄は体長4.4m,体重3.2t,雌は体長2.8m,体重680kgになる。ヒョウアザラシも雌雄ともに体長2.7m,体重500kgになる。カニクイアザラシ,ロスアザラシ,ウェッデルアザラシともに2mを超え大型である。小型の種は分布域の限定されたところに多く,もっとも小型の種は陸封されたバイカルワモンアザラシとカスピカイワモンアザラシで体長1.2~1.3m,体重50~60kgである。
北半球に14種,南半球に5種が分布し,そのうち海氷域には12種,陸岸域には7種がすむ。南半球では種分化を促す陸地の障壁が北半球ほど複雑でないため種類が少ない。北半球では,北太平洋にクラカケアザラシ,アゴヒゲアザラシ,ゴマフアザラシの3種,北大西洋にハイイロアザラシ,ズキンアザラシ,タテゴトアザラシの3種,両方にワモンアザラシ,ゼニガタアザラシの2種が分布する。北半球の低緯度地方にはモンクアザラシ類3種とキタゾウアザラシが分布し,カスピ海やバイカル湖にもワモンアザラシ類2種が分布する。南半球ではすべてが南極海に分布し,流氷域にヒョウアザラシ,カニクイアザラシ,ロスアザラシが分布する。南極大陸周辺の定着氷域(周年とけたり流れたりしない海氷)にはウェッデルアザラシが分布する。ミナミゾウアザラシは南極海の島々を中心に分布する。アザラシ科すべての生息数は約2700万頭といわれている(1979)。南極産が多く,1700万頭で,そのうちの1500万頭がオキアミを主食とするカニクイアザラシである。もっとも生息数が少ないのはモンクアザラシ類で,カリブカイモンクアザラシは絶滅が伝えられているし,チチュウカイモンクアザラシは500~600頭,ハワイモンクアザラシは約1000頭と推定されている。
生態
アザラシは必ず海氷上か陸上で休息し,繁殖する。外敵からの防御手段をもたないため,繁殖はきわめて短期間に集約的に行われる。繁殖期は海氷繁殖種で3~4月,陸上繁殖種で5~6月(南半球では9~12月)である。親子関係は2~6週間と短期間で終了する。その代り40~50%の脂肪含有のミルクを与えることにより,新生子の成長を早めている。雄と雌の関係は海氷繁殖種と陸上繁殖種で異なり,狭い洋上の小島で,時を同じくして繁殖する陸上繁殖種では雄どうしの闘争が起こり,勝った1頭の雄と多数の雌によりハレムが形成される。ハレム形成種では性的2型(雄と雌で形態が異なること),雄は雌より非常に大きい。ゾウアザラシの雄の鼻孔が風船のように膨らむのも性的2型である。海氷繁殖種ではこのような繁殖形態も性的2型もほとんど見られない。食物はおもにプランクトン,魚類,イカ・タコなどの頭足類であるが,アゴヒゲアザラシは長いひげで海底の二枚貝をさがし出し好んで食べる。ヒョウアザラシは泳いでいるペンギンや海鳥,さらにアザラシの幼獣も食べる。
アザラシと人間
アザラシは現在19種が地球上広範囲に生息し,各地で直接人間の活動と接触する場を有している。とくに北半球の中・高緯度地方のアザラシ(ワモン,ハイイロ,ゴマフ,アゴヒゲなど)は有史以前からつい最近に至るまで生活資源として狩猟の対象にされてきた。しかし,この狩猟は自己消費的で,小規模であり,資源的にも安定していた。大航海時代を経て産業革命時代に至ると,人間の活動は急速に拡大発展し,アザラシさえも大きな経済的価値をもつに至る。
人類によって最初に絶滅させられたアザラシは,コロンブスをはじめ航海者によって乱獲されたカリブカイモンクアザラシである。その後も毛皮や皮下脂肪を目的とする商業的捕獲により何種類かが絶滅寸前になっている。18~19世紀には南極にまでその活動は及んでいる。しかし,自然保護の立場からこれらの自由捕獲は,伝統的にアザラシを生活の基盤としてきたエスキモーなどを例外として,国際条約でほとんど禁止され,保護されるようになった。しかし一部では,北大西洋のタテゴトアザラシのように大規模な商業捕獲が続けられている種もある。
一方でアザラシは人間の漁業活動と深刻なかかわり方をもっている。近年の漁業は生産効率を高め,漁業資源を高い効率で利用するため,魚類を餌とするアザラシは漁業活動の対立者とされる。また漁具などに被害を与えるじゃまものとされる。ここには自然保護,野生動物保護の立場と漁業関係との深刻な対立がある。
執筆者:内藤 靖彦
民俗
アイヌ語ではトゥカラtukarと総称する。アザラシはアイヌにとって重要な獲物であったから,アゴヒゲアザラシ,ゴマフアザラシなどの種類とともにその年齢別に細かい名称の違いが見られ,場合によっては神とも呼ばれるが,tukarはそれらの総称である。オホーツク海周辺で子を育て,北海道から東北地方に回遊する。体に斑紋があるのでアシカ,オットセイ,トドなどと区別され,その毛皮は細工しやすいため袋物などを製するが,薄いので敷物には利用されなかった。アイヌは脂肪を利用し,また和人と交易する毛皮として価値を認めた。日本人がこの皮を知ったのはおそらく平安朝以来のことで,奥羽地方からの貢物にはしばしば水豹の皮が記録され,アザラシという名詞もこのころ日本語として発生したものと思われる。小笠原流では射礼(じやらい)にこの皮を使用するから,中世にはかなりその交易があったのであろう。
執筆者:千葉 徳爾
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報