改訂新版 世界大百科事典 「主語述語」の意味・わかりやすい解説
主語・述語 (しゅごじゅつご)
文法や論理学の用語。その概略については,日本ではすでに小学校の国語教育で〈何が(は)どうする〉〈何が(は)どんなだ〉〈何が(は)何だ〉の〈何が(は)〉に当たるものを主語,〈どうする〉〈どんなだ〉〈何だ〉に当たるものを述語という,と教授するほどで,一般にも周知の用語である。だが,特に文法上の主語は,多少掘り下げて考えると,さほど明快な概念ではなく,特定の一言語についてさえ,研究者によってとらえ方に差があることが少なくない。まして一般言語学的に(言語一般を対象として)主語の概念規定が確立しているわけではなく,ようやく最近それへの見通しも多少開けつつあるもよう,という程度が実状である。
形式論理学と文法
そもそも主語・述語とは,形式論理学における命題〈AはBである〉のA(それについて語るところのもの)およびB(Aについて語る事がら)に当たるものを,アリストテレスがそれぞれギリシア語でhypokeimenon,katēgoroumenonと表現したことにさかのぼるという。これが,その後ラテン語でそれぞれsubjectum,praedictumと表現され,論理学および文法の用語としてしだいに定着,今日のヨーロッパ諸言語でも継承され(たとえば英語subject,predicate),また他の言語でも用いられるようになり,日本でも主語・述語と訳してきたものである(形式論理学では主辞・賓辞とも,文法では主部・述部とも訳す)。当初のヨーロッパでは論理学と文法は密接な(元来は未分化ともいえる)関係にあり,共通の用語となったのだが,しかし,両者は目標も対象も異なる学問である(文法は今日では言語学の一部として位置づけられている)。特定の言語を超えてただ〈AはBである〉という形の命題だけを扱う形式論理学では,主語・述語を上のように約束すればよいにしても,各言語のさまざまの文型を対象とする文法においては,はたして文法上の主語・述語とは何かをあらためて問う必要がある。
ヨーロッパ諸言語の主語・述語
実際には,ヨーロッパ諸言語(厳密にはインド・ヨーロッパ語族の言語。以下同様)の伝統的な文法では,そのような吟味を十分行わぬまま,いわば形式論理学の主語・述語の延長のような趣で文法における主語・述語もとらえてきたふしがある。だが,その文法上の主語・述語とされてきたものは,実は論理学を離れて純粋に今日の言語学(文法理論)の観点から吟味し直してみても,確かに妥当な(そう認められるだけの根拠をもつ)もののようである。
すなわち,(1)主語とされてきた文成分は,意味やシンタクスや形態の上で他の文成分(目的語,補語,副詞句等)とは明らかに区別されるに足る諸々の特徴を備えている。特に,(1)動作をあらわす単純な文(能動文)においては,意味的にその動作主に相当する,(2)シンタクスの上で原則として不可欠である,(3)その人称や数(すう)に対応して動詞の形態が変化する,(4)これらの言語では一般に,代名詞や名詞(あるいはその冠詞)がいわゆる格変化(格)を行うが,そのうち最も基本的と認められる格(主格)の形態であらわれる,という特徴を兼ね備えている点で(ただし現代英語では,(3)はbe動詞のときは認められるものの他の動詞についてはわずかに三人称単数現在の場合に,また(4)の格変化は代名詞の場合に,それぞれとどめているだけではあるが),際だった文成分だと認められる。また,(2)その文成分が典型的には文頭に位置し,文や節からそれを除いた残りの部分が文法上一つのまとまりをなす(文の文法的な構造上,両者の間に大きな切れ目があって全体が二分される)という趣が強い。以上のような状況を備えたヨーロッパ諸言語が,文法上,当該の際だった文成分を主語と呼んで他の文成分と別格に扱い,一般に,残りを述語と呼んで文を二分してきたのは,確かに自然なことであると首肯(しゆこう)される。
文法上の主語とは,このように細かい吟味の上に立って規定していくべきもののようで,簡単に定義できるようなものではなさそうである。伝統的には,文法上の主語に対しても,一般に,論理学と同様〈それについて語るところのもの〉式の定義が与えられてきたが,この定義は実は近似的に成り立つ程度のものにすぎない(その不備に気づいてからは,他の定義が論議されたり,不備を補うべく普通の文法上の主語のほかに心理的主語,論理的(意味的)主語などの概念が提唱されたりもしてきたが,それらについては省略する)。ただ,定義等はともかく,文法上の主語の認定の仕方(実際にどのような文成分を主語と認めるか)自体に関しては,ヨーロッパ諸言語の場合,先ほどのような際だった文成分が存するため,まず問題なく大方の一致を見てきた次第である。
他の言語の主語・述語
他の言語については,一般に,ヨーロッパ諸言語の主語・述語にならってその言語の主語・述語をとらえようとすることが多いようである。だが,ヨーロッパ諸言語とシンタクスが異なったり,先ほどのような諸特徴を兼ね備えた文成分がなかったりすれば,主語・述語とは何か,場合によってはその認定からして問題になり得る。
特に,能格言語と呼ばれるタイプの言語の場合がそうである。ヨーロッパ諸言語の場合は,意味的に前掲(1)-(1)に当たる文成分(以下単に〈仕手〉と呼ぶ)は,動詞が自動詞の場合にも他動詞の場合にも形態的に同じ格((4)で述べた主格)で示され,他動詞の場合には,その動作を受ける意味をあらわす文成分(以下〈受手〉と呼ぶ)がこれとは別の格(いわゆる対格(目的格))で示されるのに対し,能格言語ではこうではない。すなわち自動詞の場合の〈仕手〉と他動詞の場合の〈受手〉とが形態的に同じ格(主格あるいは絶対格と呼ぶ)で示され,他動詞の場合の〈仕手〉がこれとは別の格(能格と呼ぶ)で示されるのである。つまり他動詞の場合には意味上の〈仕手〉と形態上の主格とが合致しない((1)(4)の基準が合致しない)わけで,いずれを主語と見るかが問題となるのである。
日本語の主語
日本語の場合も,主語はその認定からして問題になる。冒頭に見たように〈何が(は)〉に当たるものと述べるだけでは実は不十分で,これに増減を行う必要があるのだが,たとえば, 〈太郎も来た〉〈子どもしかいない〉〈君の読んだ本〉〈僕行くよ〉などのゴシックで示される部分の類は,〈が〉〈は〉を伴わないが主語と見る,
〈太郎も来た〉〈子どもしかいない〉〈君の読んだ本〉〈僕行くよ〉などのゴシックで示される部分の類は,〈が〉〈は〉を伴わないが主語と見る, 〈手紙はもう書いた〉〈少しはできる〉のゴシック部分の類は主語と認めない,などの点ではまず一致を見ているものの,
〈手紙はもう書いた〉〈少しはできる〉のゴシック部分の類は主語と認めない,などの点ではまず一致を見ているものの,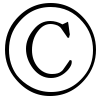 〈水が飲みたい〉や
〈水が飲みたい〉や 〈僕はうなぎだ〉(料理を注文する場面で)などのゴシック部分の類をどう見るか,
〈僕はうなぎだ〉(料理を注文する場面で)などのゴシック部分の類をどう見るか, 〈象は鼻が長い〉〈魚は鯛がいい〉のような文をどう分析するか,などについては研究者の間でも論議がある(なお
〈象は鼻が長い〉〈魚は鯛がいい〉のような文をどう分析するか,などについては研究者の間でも論議がある(なお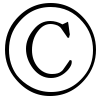 の類については,学校文法では一般に主語と扱ってきた)。
の類については,学校文法では一般に主語と扱ってきた)。
しかも,どのように認定しても,日本語の主語は,先に見たヨーロッパ諸言語の主語とはかなり性質が異なることに注意せねばならない。すなわち,前掲の特徴(1)-(1)は備えているものの,(2)(3)は備えておらず,(4)も(典型的には〈が〉という格助詞を伴うとか,その〈が〉が省略されやすい,という特徴がこれに当たると見るにしても)顕著ではない。また,(2)も明白には認められない。主語が文頭に来ない場合も少なくないし,文頭に来ても,たとえば〈太郎が花子に次郎を紹介する〉において,(a)〈太郎が〉のあとに大きな切れ目があり,ここで二分されて,残りが一つのまとまりをなす((2)が成り立つ)と見るべきか,(b)〈太郎が〉〈花子に〉〈次郎を〉の三つの文成分が対等のようにして〈紹介する〉に係る((2)が成り立たない)と見るべきかは,実は存外明快ではない。〈が〉でなく〈は〉を用いればその直後に大きな切れ目がある((2)が成り立つ)といえようが,〈が〉の場合には(b)のようにも思われよう。これら諸点から,日本語の主語は,ヨーロッパ諸言語とは異なり,文法上,他の文成分(〈~を〉〈~に〉等)に比べて明らかに区別されるに足る際だった特徴を備えてはいないように見える。
ちなみに,現代の論理学(述語論理学)では,上文のあらわす事態をR3(a1,a2,a3)の形の命題であらわす(R3=紹介する,a1=太郎,a2=花子,a3=次郎)。R3は述語と呼ばれ(Rの右下の3は三者間の関係をあらわすという意),a1,a2,a3は項と呼ばれる。各項は,役割は違うが対等の資格で事態の成立に関与すると見るわけで,述語に対して,各項をいずれも主語と呼ぶ向きもあるほどである。もちろん事態と言語表現は(あるいは論理学と文法は)必ずしも並行するとは限らない(ヨーロッパ諸言語で上の事態を能動文で表現するとすれば,各項のうちa1の太郎に当たる文成分だけが文法上際だった特徴を有し主語と呼ばれることはすでに見た通りである)。だが,上掲のような日本語の文では,先の諸点から,文法上も述語論理学の事態のとらえ方に似て,三つの文成分が対等かそれに近いような印象を受ける。
とすると,〈太郎が〉だけを主語と呼び〈花子に〉〈次郎を〉を連用修飾語と呼んで区別する必然性は,意味的にはともかく純粋に文法の観点からは薄くなるわけで,そもそも日本語で文法上の概念として主語を立てる(まして,学校文法のように〈水が飲みたい〉の類まで含める)ことに,どれほど意義・根拠があるのか,という問いさえ実は提起されてきたのである。
一般言語学的な主語(および日本語の主語)についての最近の見通し
このように,言語によっては,主語とは,それほど明白なものではない。しかし,一方,最近の言語学の進展によって,日本語や能格言語も含めて一般言語学的な意味での主語とはいかなるものかという問題に少しずつ迫っていけそうな,概略次のような見通しも出てきたもようである。
すなわち,最近ではシンタクスや意味に関して実に細やかな諸々の現象(一例だけあげれば,再帰代名詞は同じ文中のどのような名詞を指し得,どのような名詞を指し得ないか,という点など)にも注意深く目を向けるようになってきた。そのような観点から,種々の言語において主語的だと思われるような文成分をあらためて吟味してみると,実は,それらはそうした細やかな諸現象に関して,やはり他の文成分とは明らかに区別されるに足るような特徴を示す(上例でいえば,たとえばある言語では再帰代名詞が指し得るのは一般に文中の主語の位置の名詞に限られる,など)という状況がしばしば見いだされるようなのである。そこで,一般言語学的に,そのようないわば主語的な特徴とでもいうべきものをいくつか指定することができ(その中にはたとえば先ほどの(1)-(1)~(4)のような際だった諸特徴も含まれよう。いわばそのあとに続く(5)(6)……として,たとえば今触れた,再帰代名詞に指され得るというような類の比較的地味な諸特徴を加えていき,かなりの数にのぼりそうである),各言語の主語は,それら諸々の特徴のすべてではなくとも,そのうちいくつかを備えたものとしてとらえ得るのではないか,というような見通しである。
このような見方に従うと,先ほどの能格言語では,一般に,(1)の〈仕手〉に当たる文成分(自動詞の場合には主格,他動詞の場合には能格で示されるもの)が,他のいくつかの主語的な特徴を備えているようで,これを,形態上のアンバランスにかかわらず,主語と見るのが妥当なもようである。
また,日本語についても,これまで一般に主語と呼んできたものに,さらに多少の増減を行ったある種の文成分の集合(たとえば〈君には才能がある〉の〈君には〉のごときを加え,逆に〈才能が〉のごときを除く。また前掲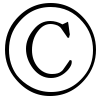 の〈水が飲みたい〉の〈水が〉の類を除く。あとは普通にいう主語とほぼ重なる)を考えると,実はこれが主語的な特徴(たとえば再帰代名詞〈自分〉に指され得るなど)をいくつか備えているようで,こう修正したものを新たに主語と呼ぶ動きもすでに一部の研究者の間では興っている。つまり,日本語の主語も,こう修正した上で,細やかな諸現象に照らして見れば,他の文成分に比べて文法上区別されるに足る特徴をいくつか有する,いわば相対的に際だった文成分であって,他とまったく対等なわけではない,ということになる。ただ,ヨーロッパ諸言語の主語ほど際だった主語ではないという点は,依然認めねばなるまい。
の〈水が飲みたい〉の〈水が〉の類を除く。あとは普通にいう主語とほぼ重なる)を考えると,実はこれが主語的な特徴(たとえば再帰代名詞〈自分〉に指され得るなど)をいくつか備えているようで,こう修正したものを新たに主語と呼ぶ動きもすでに一部の研究者の間では興っている。つまり,日本語の主語も,こう修正した上で,細やかな諸現象に照らして見れば,他の文成分に比べて文法上区別されるに足る特徴をいくつか有する,いわば相対的に際だった文成分であって,他とまったく対等なわけではない,ということになる。ただ,ヨーロッパ諸言語の主語ほど際だった主語ではないという点は,依然認めねばなるまい。
以上のように特徴の束というとらえ方にとどまらざるを得ないにせよ,一般言語学上の主語の概念を明らかにしていければ興味深い。
述語
このようにして種々の言語で主語が認定されるにしても,それが前掲の(2)を満たすとは限らない。ヨーロッパ諸言語では(2)を満たすため文や節を主語・述語と二分してきたが,(2)を満たさない場合には,主語・述語を相対するものとしてとらえるのは妥当ではない。
そのような場合,文や節の核となる動詞等だけ(いわば述語論理学の述語に当たるような文成分)を述語と呼ぶことが多い。日本語でも,(2)については前述のような次第なので,文や節の末尾の動詞等だけ(先ほどの文でいえば〈紹介する〉の部分)を述語と呼ぶ(少なくとも第一義的にはそうする)のが普通である。もちろん,(2)を満たすヨーロッパ諸言語の場合にも,この意味での述語に当たるものを考えることは可能であり,これらの言語ではそれ(すなわち二分法的な意味での述語のうち特にその核となる動詞の部分だけ)を特に述語動詞predicate verbと呼ぶことがある。
この意味での述語ないし述語動詞は,まさに文の構造上(意味構造上,あるいはシンタクス上も),要(かなめ)といえるものであり,主語も実はその要に係る一つの文成分にすぎない(述語論理学の命題で考えれば,文法上の主語も,述語に関与する一つの項にすぎない)。先ほど来,主語が他の文成分に比べ多少とも際だった文成分である旨述べてきたが,それは(今の意味での)述語に係る他の文成分に比べて,という意味である。主語はその点では〈主〉だが,実はむしろ(今の意味での)述語のほうがさらに〈主〉であることに留意を要する。
なお,日本語でも,文が(2)を満たす(あるいは,そう見なす)場合,文全体を主語・述語に二分してとらえることも行われる。
主部・述部,主語・述語
ちなみに,日本語についても,ヨーロッパ諸言語についても,二分法的な意味での主語・述語には,代りに主部・述部という語をあて,その主部から修飾語等を除いたものを特に主語,述部から修飾語等を除いたもの(日本語の場合,先ほどの,核となる述語。ヨーロッパ諸言語の場合,副詞句等は除いても目的語や補語は含めることが多い)を特に述語と呼んで,訳語を使い分ける場合もある。
主語・主格・動作主・主題
なお,従来は主語・主格・動作主(主体)・主題などの各語を厳密に使い分けずにきた面があるが,最近の言語学では,これらを明確に区別する。主語subjectは,上述のように簡単には規定できないが,ともかく,すぐれてシンタクス上の概念という色彩が強い。これに対し,主格nominativeは形態上の概念で,日本語でいえば格助詞〈が〉を伴うもの(広い意味では,表面的には〈が〉となっていなくとも,そこを格助詞であらわすとすれば〈が〉となるはず,というものも含めることがある)。〈水が飲みたい〉の〈水が〉の類も主格ではある。一方,動作主agentは意味上の概念で,意図的な動作の主体(仕手)をいう。また,主題topicとは,話手・書手がそれについて何かを述べようとするもの,といういわば語用論上の概念だが,日本語では形の上でも一般に助詞〈は〉を伴って表現される。これら四つは(前二者については助詞まで含めていうことが多く,後二者については含めない,という細かい点は今おくとして),互いにそのいくつかが重なり合うことも多い。たとえば〈太郎は走った〉の〈太郎(は)〉は,主語で,主格(広義の)で,動作主で,主題である。だが,常に重なるとは限らず,概念として区別すべきものである。
執筆者:菊地 康人
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

