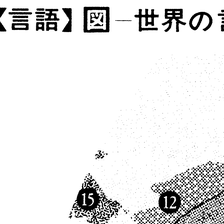精選版 日本国語大辞典 「言語」の意味・読み・例文・類語
ごん‐ご【言語】
げん‐ご【言語】
- 〘 名詞 〙 人間の思想や感情、意思などを表現したり、互いに伝えあったりするための、音声による伝達体系。また、その体系によって伝達する行為。それを文字で写したもののこともいう。ことば。げんぎょ。ごんご。最近では手話による伝達体系をも含めることがある。〔広益熟字典(1874)〕
- [初出の実例]「言語(ゲンゴ)が通じないといふ訳でもないのに」(出典:内地雑居未来之夢(1886)〈坪内逍遙〉九)
- [その他の文献]〔論語‐先進〕
言語の語誌
江戸時代までは漢音よみの「ゲンギョ」と呉音よみの「ゴンゴ」とが並行して用いられてきたが、明治初年に、両語形が混交して「ゲンゴ」が誕生した。「語」はゴと読まれる熟語がほとんどであったので、「ゲンゴ」が一般化するようになって「ゲンギョ」は姿を消し、「ゴンゴ」は、「言語道断」などの特定の慣用表現に残って使われている。
改訂新版 世界大百科事典 「言語」の意味・わかりやすい解説
言語 (げんご)
人間同士の意思伝達の手段で,その実質は音を用いた記号体系である。〈ことば〉ということもあるが,〈ことば〉が単語や発話を意味する場合がある(例,〈このことば〉〈彼のことば〉)ので,上記のものをさす場合は,〈言語〉を用いた方が正確である。また,人間以外のある種の動物の〈言語〉をうんぬんすることも可能ではあるが,その表現能力と,内部構造の複雑さおよびそれとうらはらの高度な体系性などの点で,人間の言語は動物のそれに対して質的なちがいを有している。
人間社会における言語の存在のしかた
言語がどのような形で人間社会の中に存在するのか,すなわち,その社会における発話行動の総体の中に存在するのか,あるいはその社会の成員の脳裏に存在するのか,について種々の議論があったが,正確には,まさにその二つの形をとって存在しているというべきであろう。個々の,意思伝達のための発話行動をとってみると,そこには偶発的なものや個人的なものが当然含まれてはいるが,その発話行動が複数の人間の間の意思伝達の一局面である限り,その中に意思伝達を可能にする,その社会一般に認められたもの(社会習慣)が含まれているはずである。その社会におけるそうしたものの総体が,言語の一つの姿である。その社会に生まれた(あるいは,加入した)個人は,そのような姿をとって存在する言語を習得しない限り,その言語の話し手とはなりえない。しかし,そうした言語も,それを習得した個人の集合である言語社会が存在しない限り,存在しえないし,その(一部の)具体的あらわれである発話行動自体が生起しえない。したがって,個々の成員の脳裏に蓄積された言語(あるいは,言語意識)も,言語のもう一つの姿である。この二つの姿は,互いを自己にとって不可欠な相手として,互いに支えあっている。
言語の機能
言語は,上述のごとく,人間の意思伝達の手段であるが,機能としてはそれに尽きるものではない。思考を支える手段,自己の感情の表現手段,あそびの一手段といった機能をあげることができる。しかし,そのことによって,言語の本来の機能が意思伝達の手段であることを否定することはもちろん,軽視することもできない。まさにそういうものとして言語は発生し発達し,また,そういうものとして人間社会を成立させてきたのである。
また言語が,思考を支える手段という機能を有することは次のように説明される。人間は,その集団的な認識活動の結果を言語のあり方・構造に反映させてきた。したがって,言語は人間の認識やその発展である思考を支え,補助できる力を本来的に有しているのである。
音声言語と文字言語
以上は,いわゆる〈音声言語〉について述べたものだが,このほかに〈文字言語〉を有する社会がある。文字言語は,本質的には,音声言語の補助手段として成立し,音声言語に依拠して存在してきたものであるが,音声言語の方はそのあらわれ(発話)がすぐ消え去ってしまうのに対し,文字言語のあらわれは長く(あるいは永久的に)残るという特色を有するため,人間社会にとって音声言語にはない重要な意味をもっている。すなわち,書いた時点にその場に居合わせなかった人々にもその内容を知らしめることを可能にし,知識の譲渡,さらには,印刷術の発達によって知識の普及に大きな役割を果たす。したがって,近年,かつては無文字社会であった社会が文字を用いるようになる例が増えている。ただし,すべての言語社会が文字言語をもつようになったという状況にはほど遠いものがあり,また,文字言語を有する社会においても,それを使用できる人口が限られているなどの問題がある。また,文字言語そのものの性格から生ずる問題点も指摘される。その一つは,音声言語との乖離(かいり)傾向である。その最大の理由は,文字言語の方はいったん定まるとなかなか変化しにくいのに対し,音声言語の方は時とともに変化してゆくことにある。その乖離が進みすぎると,文字言語の方を改革する動きが生ずる。もう一つの理由は,文字言語が多くの場合,その国(地域)の支配的な方言に立脚して定まるという点にある。すなわち,それ以外の方言の話し手にとっては自らの音声言語とその文字言語が初めから乖離したものなのである。
言語の構造
言語は,おおむね次のような構造を有している。
文法
発話の基準となる単位として〈文〉という単位が存在する。文は,理論的には長さの制限をもたず,また,その数も無数であるが,一定の構造(あるいは,いくつかの構造のうちのいずれか)を有する。文は,最終的には〈単語〉の列から成り立っている(こういう状態を〈分節〉と呼ぶことが多い)。たとえば,日本語の〈電車が来ましたよ〉は,〈電車〉〈が〉〈来る〉〈ます〉〈た〉〈よ〉という六つの単語の列から成り立っている,といえる。単語は,個々の言語において何を単語と認めるかで難しい問題があるけれども,どの言語にも存在する単位であり,どの言語社会においてもその数はおそらく数千を下らないであろう。ただし,数は多いけれども一応有限であり,有限個のものを組み合わせることによって無数の文が成立可能になるわけである。単語はその機能(つまり,文の中のどこにあらわれうるか)のちがいに基づいて,いくつかの範疇(単語の範疇を〈品詞〉と呼ぶ)のいずれかに所属し,そうした範疇のどれに所属しているかがわかればどのように用いうるかがかなりわかる状況を呈している。ある品詞に属する単語が,意味のちがいを伴って(あるいは,伴わずに)そのあらわれる位置によってその語形の一部を,その品詞に特有の形で交替させることがある。これを〈屈折〉(〈活用〉〈曲用〉などという術語も用いられる)と呼ぶ。屈折には,語形のある部分を1個所,かつ,それを全体として交替させるというものと,ある部分に交替しうる複数の要素が並んでいるもの,2個所以上で交替を示すものなどがある。このような交替する要素は〈接辞〉と呼ばれるが,正確を期するためには〈屈折接辞〉とでも呼ぶべきである。屈折接辞は,音形のちがいを無視して意味の同じものを同一物と考えると,ある品詞に属する単語(の本体,すなわち〈語幹〉)には原則としてそのすべてに直接もしくは間接的に接続しうる。その際かなり強く結びつくことを特色とする。一方,単語と呼びうるものにも,独立度の弱い(たとえば,それだけでは発話しにくい)ものがあり,別の言語の屈折接辞のような役割を果たすものがある。ただし,単語というべきか屈折接辞というべきか区別するのが困難な場合がある。さて,単語が単語同士で結びついて直ちに文を構成するのでなく,多くの場合,単語でもなく文でもない中間的な結びつきを形成する(先ほどの文では〈電車が〉とか〈来ましたよ〉)。このような結びつきにも範疇が認められる(文法研究で〈名詞句〉とか〈述語〉とかの術語を用いる場合,このような結びつきが,中間的なものであれ一つの単位として機能していることと,それらが範疇に分属していることを前提としている)し,また,文自体にも範疇区分をうんぬんすることができる。単語にどのようなものがあり,どのように結びついて最終的に文を形成するか,逆にいえば,文がどのようなものから成り立っていて,最終的にはどのような性格をもった単語の列に分析されるか,といったことの総体を〈文法〉と呼ぶ。文法というのは,言語の中で意味が関与する分野における規則性・法則性の総体であるともいえる。
なんらかの意味に対応する音形のうち,それ以上分析できないものを〈形態素〉と呼ぶ。単語が意味を有するものにそれ以上分析できなければ,それは同時に形態素でもあるが,上述の語幹(それが分析不能の場合),屈折接辞も形態素である。さらに,〈お金〉の〈お-〉のようなもの,〈金持〉の〈金-〉のようなものも形態素にはいる。しかし,これらはそれが結びつきうる相手が個別的にしか規定できない(〈-金〉が名詞(〈家〉)のように見えるからといって,〈お家〉とは普通いわない)し,その全体の意味も部分の意味から完全に予測できるものではない(〈金持〉は,お金をたくさん所有している人のことだが,〈太刀持〉は,太刀をたくさん所有している人ではない)。こうした種類の形態素の結びつき方をも文法に含めて考える説もあるが,このような本質的には個別的なことがらは,規則性の総体としての文法とは趣を異にしている。しかし,それぞれの言語には〈複合語〉〈派生語〉の構成のしかたに一定の傾向(〈造語法〉)があり,それが既知の要素を用いて単語の数を増加させる上での有効な手段となっている。
文の構造がいかなるものであるかは,もちろん言語によって異なっている。しかし,人間の認識と言語との関係から,次のようなことは一般的にいえそうである。我々が外界を認識するとき,一挙にすべてを認識するのでなく,その一〈局面〉(たとえば,向こうから電車が近づいてくるといった局面)を他から切り離した形で認識する。その際その局面を認識の上で切り離すことを可能にするその局面の特徴とは,主としてその局面におけるなんらかの運動である。したがって,そのような運動にあたるものが,そうした局面に対応する言語的単位すなわち文の中に原則として必ず含まれていなければならず,かつ,原則として一つであるはずである。すなわち,〈述語〉(〈主語・述語〉の項を参照)と呼ばれうるものが,どのような言語でも文の必須成分としてあることが推測される。また,基本的には,述語があらわす運動となんらかの直接的関係にあるもの(つまり,その運動と同一局面に含まれるもの)をあらわす成分が同じ文に含まれうるものである,ということもできよう。このように考えると,文の構造と人間の論理形式とはともに〈局面の構造〉に規定された表裏一体のものということができる。ただし,論理形式の方は一義的であることを要求されないし,むしろある範囲の中で多様なものと考えられるのに対し,文の構造の方は一つとはいわないまでも,言語ごとに少数の種類に固定されていなければならない(そうでないと使いこなせない)ので,文の構造は多様な論理形式の一つもしくは少数を言語的に固定したものだといえよう。したがって,一つの言語の文の構造に対応する論理形式も,別の外国語の文の構造に対応する論理形式も,人間のそれとして存在するものであり,たとえば日本語の文の構造がある外国語のそれに異なるからといって,日本語を非論理的な言語とするような議論はまったくの妄言にすぎないし,他の言語についても同様である。
音韻
次に,言語の音の面に注目すると,単語(あるいは,形態素)は,意味を無視するならば,さらに小さい単位から成り立っている。音の面での最小単位を〈音素〉と呼ぶ。各言語はそれぞれある数(通常,十数個から数十個)の音素を保有し,それらを順に並べて単語などの音形を構成している(こういう状態も,〈分節〉と呼ばれる)。たとえば,〈船〉はh,u,n,eの四つの音素が一つずつこの順に並んでいる。同一音素はできうる限り同じ音であらわれる。すなわち,そのあらわれる位置によって前後とのつながりをスムーズにするような変異はあるが,それ以外の点では同一音であろうとする。音素は,平面的に並んで一挙に単語の音形を構成するのでなく,ある中間的まとまりを構成し,それが単語などの音形を構成するという状況を呈する。そのような中間的まとまりを〈音節〉と呼ぶ。音節の性格,構造は各言語によって異なるが,遠くまでよく聞こえるが発音にエネルギーを要する音(〈母音〉)を中心に,あまり遠くまで聞こえないが発音にエネルギーを要しない音(〈子音〉)をその前(または前後)に配置するという形が最も一般的である。ただし,あらゆる言語において母音と子音の区別が明確だというわけではない。各言語における母音の数は,多くて10をあまり超えない範囲にある。また,どの言語でも,音素の並び方にその言語固有の制限を有する。どのような音を音素とするかは言語によって異なるが,たとえば〈唇を用いる閉鎖音〉(破裂音)に有声音と無声音(bとp)の区別があれば,他の閉鎖音にも同種の区別があるといった,調音器官の運動形態の種類を比較的少なくしつつ多くの音を保有しようとする傾向が認められる。また,言語によって,同一単語内で,ある母音のあとにはある種の母音だけが立ちうるといった現象が認められることがある(〈母音調和〉)。
単語(あるいはそれより少し小さいか大きいもの)の音形に,音素の区別に関係するものとは異なる音的特徴(強弱差とか高低差)が〈かぶさって〉いるような状況が認められる。これを〈アクセント〉と呼び,強弱が有意味的なものを〈強弱アクセント〉とか〈ストレス・アクセント〉,高低差が有意味的なものを〈高低アクセント〉あるいは〈ピッチ・アクセント〉と呼ぶ。さらに,別の音的特徴が用いられることもありうる。長さの等しい単語の間にアクセントの対立があれば,それだけで単語と単語を区別できることになる。アクセントがどの程度に複雑であるかは言語によって非常に異なり,単語の長さが決まればアクセントは一定という単純なもの(例,フランス語や日本の〈一型アクセント〉の方言)から,きわめて複雑な(ただし,高度に規則的でもある)ものもある。
また,文全体あるいはその一部(ただし,かなり大きい部分)に〈かぶさる〉音的特徴を〈イントネーション〉と呼ぶ。多くの場合,音の高低の変化を実質とし,また,多くの場合その末尾の特徴で判別できる。なんらかの意味に対応する(たとえば,疑問文のイントネーションなど)ことが多い。
意味
単語は,固有名詞および若干の例外を除き,ある一つの事象をあらわすのでなく,多くの(理論的には無数の)事象を一つの単語であらわすようになっている。また,単語の音形と意味の間には,若干の例外(〈擬声語〉〈擬態語〉など)を除き,特別のア・プリオリな関係は存在しない(これを,〈記号の恣意性〉と呼ぶことがある)。しかし,一つの単語をとってみると,その単語によってあらわされうるすべての事象には,その単語によってはあらわされえない事象には総体としては含まれない共通性が認められる。いわば,単語は,決して個々の事象に対応しているのでなく,このようなある種の共通性(の総体)に対応しているのである。ある単語によってあらわされうるすべての事象に含まれる共通性,もしくは,その共通性の人間の脳裏における反映としての〈観念〉が,単語の〈意味〉と呼ばれてきたものである。単語のあらわす事象には,名詞の場合のように事物といえるようなものや,動詞のように動作・運動といえるものや,その他ある種の関係等々がありうるが,いま見た点では共通である。ただし,単語の音形と意味との対応が人間の意識を通じて成立するために,現実には存在しない事象をあらわす単語(〈幽霊〉など)やきわめて主観的な感情に対応する単語(〈嫌い〉とか〈オヤオヤ〉とか)もあり,また,現実に存在する事象をあらわしても,なんらかの感情のからむ単語(たとえば,〈野郎〉など)もかなりある。
ある音形であらわされうるすべての事象に含まれる共通性(その音形が同一の単語なら,この共通性はその単語の意味にあたる)をすべて含む事象が,その音形によってはあらわされえないものの中に存在することがある。その場合,その音形は音形としては同一であるが,意味は一つではありえない。すなわち,単語としても一つではありえないことになる。そのような場合,〈同音異義〉と呼ぶ。同音異義には,偶然生じたものと,ある単語の音形が,もとの意味となんらかの形で似た意味をあらわすものとしても用いられるようになって(〈転用〉)生じたもの(これを特に〈多義〉と呼ぶことがある)があるが,ある特定時期の言語という観点(つまり,その言語の過去の事情を考慮しない観点。話し手大衆の観点である)から見ると,この両者に本質的差異は存在せず,明確な境界を引くこともできない。しかし,転用(を起源とする同音異義の存在)ということが許されていることは,比較的少ない語形で多くのことをあらわす上で大きな意味をもっている(〈同音語〉の項を参照)。
単語と単語の,あるいは,一方もしくは両方が単語の列であるものの結びつきによってできあがる全体の意味は,その構成部分の意味にその結びつき方(あるいは,それら構成部分の属する範疇)の意味が付け加わったものである。文全体の意味も同様に(ただし,イントネーションの意味も付け加わって)できあがる。このような文も,それがあらわしうるのはただ一つの特定の事象(ある局面)でなく,ある共通性をもった無数の局面をあらわすことができるのである。
言語と方言
言語を一つの記号体系と考える場合,完全に等質的な体系を仮定することが多いが,実際にはそのような等質的な言語の存在は期待できない。すなわち,方言差が大なり小なりどの言語にも存在する。方言差は時とともに拡大され,ついには二つの方言の間で相互理解が不可能になり,もはや二つの方言ではなく二つの独立した言語になる。ただし,言語と方言の区別は科学的にはほとんど不可能である。というのは,A方言とB方言,B方言とC方言の間は相互理解が可能でありながら,A方言とC方言ではそれが不可能だといった状況がいくらでもあるからである。また,独立の正書法を有するかどうか,一つの国の国語となっているかどうか,独自の名称を与えられているかどうか,などを言語と方言の区別とすることもあるが,相互理解が可能かどうか(全体的ちがいがどの程度であるかをはかる尺度として適当なものの一つである)という尺度にひどく違反する結果が出ることが多い。このように,言語と方言の厳密な区別は不可能であるが,一方,いかなる規準から見ても別個の言語であるものと,いかなる規準からも同一言語の方言であるものとは確かに存在し,この区別は有効でないわけではない。
方言の主たるものは,地域のちがいによる方言であるが,〈社会的方言〉も存在する。ある階層,ある職業,ある人間集団に固有の〈方言〉のことである。それらの中には,その地域で通常話される言語(あるいは,地域的方言)を基礎として,一部に特殊な語彙や特殊な発音のしかたなどを取り入れたにすぎないものも多い。
言語と方言の区別が不可能なので,世界にいったいいくつの言語があるかをいうことはできない。2000台から3000台の数値が示されることが多いようであるが,一つの言語と認める基準をかえることによって数は大きく変動する。同一地域内に複数の言語が存在する場合,相互の意思疎通のために〈共通語〉が発達することがある。もとからある言語の一つが共通語となることもあるし,一種の混合語(ピジン・イングリッシュなど)が生ずることもあり,また,性格的にその中間のものが生ずることも多い。ある地域の共通語を母語として話す集団が存在しない場合,その共通語はいろいろな意味で不安定で等質性を欠く。一方,本来は一種の混合語として生じたものでも,母語として話す集団が生ずれば,一般の言語と同じ安定性を急速に獲得する。共通語のうち公的に使用することを認められたものを〈公用語〉といい,国として公的に使用する言語を〈国語〉と呼ぶ。
言語の変化
言語は時とともに変化するが,その際その根幹部分は比較的ゆっくりと,枝葉部分は比較的速く変化する。前者には,音韻,文法,それに身近な語彙などが含まれ,後者には語彙のうちのより文化的なものなどが含まれる。
音韻面の変化のうち,音素の変化は,音素が一つの単位として機能していることを反映して,通常やはり各音素単位で起こる。すなわち,たとえばpがbに変化するとすれば,その変化はその言語のすべてのpのあらわれに関して起こる。ただし,常に画一的に起こるとは限らず,条件(何の前とか何の後とか)によってちがった変化が生ずることも多いが,いずれにしても規則的である。これを〈音韻変化の規則性〉と呼ぶ。音韻変化の規則性は,いくつかの別の性格の変化によって乱されることがある。たとえば,他の単語などの音形との〈類推〉による変化もしくは変化抑制,特定の単語に個別的に起こる変化などがそれである。また,文法的に非常に異なる位置にある同一音素のあらわれは,ちがった方向の変化を被ることがある。
単語の意味の変化は,そのあらわす事象の範囲が広まったり狭まったり,似てはいるが別のものに変わったりするが,また既述のような〈転用〉も,本質的には既存の音形を用いての新たな単語の創造であるが,それが起こり,その後にもとの単語が消滅すれば,ある一つの単語に意味変化が起こったかのように思わせるものである。また語彙変化は,ある事象をあらわす単語が類似の事象をあらわす別の単語に取って代わられる現象である。上述のごとく,身近な語彙ほど変化が起こりにくい。
言語変化は,その言語の内的要因によって起こるだけでなく,他の言語(方言)からの影響によって起こることも多い。やはり枝葉部分によく起こる。他の言語(方言)から単語を受け入れて用いるようになることを〈借用〉と呼ぶ。一般には,政治的・文化的に高い集団の言語(方言)からそうでない方に単語が借用されてゆく傾向があるが,集団同士の接触の形態によって種々の例外的事態が生ずる。他の言語(方言)からの影響は,ある人間集団の〈言語の取替え〉にいたる場合がある。その際,多数者の中に少数者が取り込まれて多数者の言語を取り入れる場合は,その言語自体にあまり大きな変化が起こらないことが多いが,少数者の言語をその地域の多数者が取り入れる場合には,もとの言語の根幹部分がかなり残ることが多く,もとの言語の音韻をそのまま残して新しい言語をそれに適用させて話すようになることもある。
言語の変化は,その言語の発展の一局面であるといえる。しかし,どうなることが発展であるかというと,語彙の増加による言語の表現能力の向上といった,誰にでも発展とわかるものを除くと,たいへん難しい問題である。母音の数をとっても,ある時期に増加するものもあればある時期に減少を示すものもある。したがって,何を発展とするかを言語の根幹部分について明言できるには,どのような構造が言語として最良なのかという困難な問題を解かねばならず,現時点での言語に関する知識では,それは多分不可能であろう。
同一言語の方言差の発展として生じた複数の言語は互いに〈系統関係〉を有するといい,もとの言語を〈祖語〉と呼ぶ。互いに系統関係を有する言語の集合を〈語族〉と呼ぶ。一つの語族の中で,その祖語より分岐してできたいくつかの言語の一つを祖語とする言語の集合を〈語派〉と呼ぶ。同一祖語より分岐してあまり時間が経過しない場合(おそらくは数千年を超えない場合),上述の音韻変化の規則性によって,その二つの言語の音形と意味の似た単語同士の間に〈音韻対応(の通則)〉が認められる。すなわち,それらの単語(の音形)同士に関して,原則として初めから終りまで,該当個所の音同士が他の単語同士でも確認できる対応を示す現象である。ただし,あまり時間がたちすぎたり,一方もしくは両方の言語が他の第三の言語の影響を受けすぎたりすると,こうした音韻対応は見いだしがたくなる。世界各地域の言語の系統関係の研究は,進歩してはいるが,問題も数多く残され,意見のちがいもよく目だつ(〈比較言語学〉の項を参照)。
言語の発生
言語は,猿から人間への進化の中で,共同して生活手段を獲得し,また集団で自らを守るために必要な,相互の意思伝達の手段として成立してきたものと考えられるが,それが成立するための条件としては,第1に知能の発達(認識能力,概念化能力ならびに音をある観念に対応させることを可能にする能力の発達),第2に発音・調音器官の発達(口の,堅いものをかみ砕く役割からの基本的解放を伴う,音をかなりの種類発音し分ける能力の発達),およびそれに対応する聴覚(微細な差異を聞き分ける能力)の発達が考えられる。しかし,言語が具体的にいつどのように成立したかを知ることは,現時点での知識からは不可能である。
原始状態の言語がどのようなものであったかを,現存する言語の対照研究・比較研究から推定するのは,現存の言語があまりに高度に発達しすぎているために,たいへん困難であり,既述の二つの〈分節〉のどちらが相対的に先行して成立してきたのかについても確答を与えることができない。また,言語が1個所で発生した(単発生説)のか複数個所で発生した(多発生説)のかを証拠をもって判定することも不可能であるが,上述の議論から推察できるごとく,言語を必要とする状況が存在し,言語の成立を可能にする条件がそろっていれば,長時間を要するとしても言語を合法則的に生み出すことは可能だと考えられるので,単発生でなければならないとする理由は見いだしがたい。
→記号 →言語学
執筆者:湯川 恭敏
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「言語」の意味・わかりやすい解説
言語
げんご
「言語」という語は多義である。大脳の言語中枢に蓄えられた語彙(ごい)と文法規則の体系をさすこともあり、その体系を用いる能力としてとらえることもある。一方では、抽象的に、すべての人間が共有する言語能力をさすこともあるし、個々の個別言語をさすこともある。
[国広哲弥]
定義
基本的な定義としては、人間が共有する言語体系を取り上げるのが普通で、「一次的には音声、二次的には文字を用いて、感情・情報・要求などを伝える機能を果たす、社会習慣的に定められた記号の体系」ということになる。人間の能力としてとらえられた場合は、さらに2種類に分けられる。一つは体系の知識であり、語彙知識と、文法的な文をつくり、また理解する能力からなる。もう一つは、具体的な使用場面で適切な言語表現を用いることのできる使用能力である。この2種類の能力は、自動車の比喩(ひゆ)を用いて説明するならば、エンジン、ハンドル、ギア、アクセル、ブレーキの操作方法を知っているのが体系知識に相当し、交通規則、道路状況への対処の仕方を知っているのが使用能力に相当する。言語も自動車も、両方の能力がそろっていないと使うことができない。言語能力を行使して産出したものを言語とよぶこともある。
ミツバチのダンスやサルの鳴き声をさして「動物“言語”」とよぶことがあるが、これはあくまで比喩であって、人間言語とは大きく隔たっている。両方ともに記号であることには変わりはないが、人間言語の記号のみが有する特色として次のものがあげられる。
〔1〕言語記号を構成する音声と意味の結び付きには必然性がない。「バカ」という音声に、日本語では〈馬鹿(ばか)〉という意味が結び付けられているが、スペイン語では〈雌牛〉という意味が結び付けられている。これを言語記号の恣意(しい)性という。
〔2〕大部分の語はさらに小さい音声単位(=音素)に分割され、比較的に少数の音声単位を組み合わせることにより、多数の語をつくりだせるようになっている。この語をさらに組み合わせて、無限に近い数の異なった文をつくりだすことができる。これは言語の「二重分節性」とよばれる。
〔3〕音声単位、語などの言語要素は、それぞれ共通点と相異点に基づいて体系を構成している。日本語の五十音図はその一例である。これを言語の体系性という。
[国広哲弥]
音声言語と文字言語
世界中の言語をみると、音声のみあって文字をもたない言語はあっても、その逆の場合はなく、一個人をとってみても同じことがいえる。したがって、言語の媒体は、一次的には音声ということになる。しかし、一部の聾唖(ろうあ)者のような特殊な場合には、音声抜きで文字言語が習得されることがある。また、普通の言語とまったく同じというわけではないが、手話もある。音声言語は、文字言語に比べて、その到達距離、将来への保存の点で強く制約されてはいるが、労力が少なくてすみ、かつ両手を使うことができ、暗い所や、注意をよそに向けている相手に対しても用いることができるという長所がある。
音声言語は、相手の表情・身ぶり・姿勢などを見ながら、対面対話の状態で用いられるのが本来の姿である。この場合、視覚的に伝えられる情報は予想以上に豊かである。言語が異なると、身ぶりやその意味が異なることがあるので、注意を要する。電話対話や暗闇(くらやみ)での対話では、視覚による情報伝達ができないので、声の調子やことば遣いで肩代りしなければならない。文字言語を用いる場合は、声の調子で伝えられる部分もことば遣いに変えなければならない。対面対話に付随する場面の状況も欠けているので、文字言語による表現は、対面対話で用いられる言語表現よりもはるかに複雑で、表現のていねい度もあがるのが普通である。
一般に文字言語は保守的であり、音声言語との差異は、放っておけば、時の流れとともに開いてゆく。そこで、言文一致運動とか、仮名遣いの現代化などによって、ときおり音声言語に近づける必要が生じる。
[国広哲弥]
言語の機能
ある具体的な場面で話し手が音声を発し、それが聞き手によって受け取られ、話し手が伝えようとした意味が理解されたとき、「発話」という行為が成立する。発話行為によって産出された言語表現も「発話」とよばれることがある。発話は文字どおりの意味を伝えると同時に、別種の機能も果たすのが普通である。それは「発話意図」と「発話効果」に分けて考えることができる。発話意図としては、次のようなものがある。
(報告)きのう旅行から帰ってきました。
(説明)このボタンを押すと、戸が開きます。
(信念)あの人は潔白だと信じています。
(指示)この書類のコピーをつくってください。
(要求)〈子供が親に〉何か食べたい。
(申し出)お引っ越しのときは手伝いに行きます。
(約束)この本は来月中にお返しします。
(決心)今日からたばこをやめる。
(疑問)これは何だろうか。
(疑念)どうも胃の調子がおかしい。
(詫(わ)び)すみません。
(感謝)すみません。
(許可)どうぞお入りください。
このような発話意図が聞き手に理解されたとき、それはさらに聞き手の心理状態や行動に影響を及ぼすことが多い。そのとき発話効果が生じたことになる。人混みのなかで「すみません」と詫びの発話をし、人が道をあけてくれたら発話効果が生じたことになるが、効果がつねに生じるとは限らない。以上のような発話行為は、下図のような重層構造をなしているとみることができる。
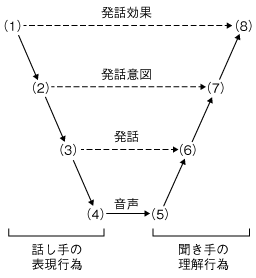
(1)から(4)までが話し手の表現行為encodingで、(5)から(8)までが聞き手の理解行為decodingである。
これまで触れてきた言語機能は、なんらかの意味内容の伝達を基盤とするものであったが、それと並んで重要なのは言語の社会的機能である。人は対話を交わすことによって社会的に結び付けられる。「こんにちは」などの挨拶(あいさつ)にみられるように、意味内容はなくても、ことばを交わすだけでその機能は発揮される。隠語・職人語・専門語などは、意味内容はあるが、一般の人にはわかりにくい語である。これらの語を交わすことによって、特定のグループに属する人々は、仲間関係を確かめ、また仲間意識を強める。この機能を果たすのは、特定の語に限らず、ある言い回し、発音の仕方も含まれる。不必要に難解な専門語を用いた文章は、執筆者の専門家であることの表明意図が、内容伝達に先行するものであるといえよう。
言語はまた遊びの道具としても用いられるという機能をもっている。例としては、しりとり、駄洒落(だじゃれ)、回文(かいぶん)、謎(なぞ)などがある。
言語は、暗示によって身体状況に影響を及ぼす機能も有している。医者から「なんでもありません」といわれて急に元気になったり、催眠術にかかったりするのがその例である。
[国広哲弥]
言語の構造
言語はさまざまな種類の構造の複合体である。すでに触れた音声単位の体系も、広義の構造のなかに含まれる。日本語共通語の、子音音素の体系の主要部分は次のようになっている。
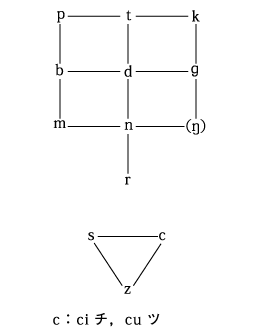
音声単位は同時に一つしか発音できないので、音声言語は、時間の流れに沿って、1本の線条体として実現される。その線条体は語の連結からなっているが、その上にかならずなんらかの文法構造が重ね合わされている。たとえば「主部―述部」「直接目的語―他動詞」「修飾語―被修飾語」「補語―動詞」のようなものである。文法構造を構成する単位は文法的カテゴリーとよばれる。文法構造は多くの場合、階層構造をなしている。下図がその一例である。
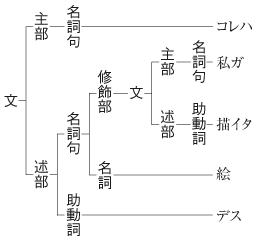
各文法的カテゴリーが占める位置では、前後関係によって多かれ少なかれ制約はあるが、他のいくつかの語と入れ替えられる。
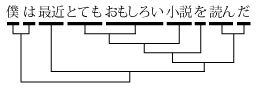
たとえば、上の文例で、「最近」のかわりに「きのう・以前に・昔」など、「おもしろい」のかわりに「退屈な・楽しい・痛快な」などを入れることができる。このように、同じ文法的位置で入れ替えうる語の集まりは、品詞を同じくし、意味的にも共通部分が多いので、一つの構造をなしているといえる。文法構造が1本の線条をなしているのに対して、この構造はどれか一語が選ばれたら、他の語は背景に引っ込んでしまうという関係にある。したがって、「代入関係・選択関係」をなすといわれたり、語彙の部分構造をなしているといわれたりする。厳密を期す場合は、この関係は「体系」とよばれ、線条的な構造と区別される。同一の体系に属する語の間の意味的関係には、類義、反義、上下(=階層的)、部分全体などがある。場合によっては、体系がどういう構造を含んでいるかによって、個々の語の意味が変わってくる。同じく成績評価語の体系であっても、「秀‐優‐良‐可」と「優‐良‐可‐不可」とでは、おのおのの評語の意味が異なる。
一つの文以上に視野を広げると、対話の構造、段落の構造、小説の構造などがみえてくる。これらはまとめて「談話discourse構造」とよばれる。
[国広哲弥]
言語構造の連続と非連続
言語の構造は、非連続的な要素の対立関係のうえに成り立っている。しかし、言語の隅々まで非連続的であるわけではない。分かち書きをしない日本語では、語と語の切れ目がはっきりしないことがある。「外出着」は一語であろうか、「外出」「着」の二語であろうか。発音が同じでも異なった漢字をあてる和語、たとえば「覚める」と「醒(さ)める」は別々の語であろうか、それとも多義的な一語であろうか。語の連結の仕方の適切さの場合も、微妙な中間段階がある。「おいしい‐ごはん」「うまい‐めし」はいいが、「うまい‐ごはん」「おいしい‐めし」はすこしおかしい。「おなかがすく」「はらがへる」はいいが、「おなかがへる」「はらがすく」はどうか。いいようでもあるし、すこしおかしいと感じる人もあろう。
[国広哲弥]
言語構造の等質性と異質性
言語の構造を明らかにするには、分析資料をできるだけ等質的に整える必要があると考えて、同一方言の同一の文体で用いられる言語という純粋な状態を対象とすることに努力を払う一つの研究法がある。しかし、現実には、一個人をとってみても、場合によって、さまざまな文体を使い分けたり、混用したり、また理由もなく用法がゆれたりする。また、同一の方言地域内でも、まったく同じ言語をもっている人は2人といないといえる。言語の等質性は一つの分析方法上の仮構と考え、別途にゆれや異質性をそのまま統計的に分析する研究法も考え出されている。
[国広哲弥]
言語変化
言語はつねに変化している。変化の速度は一様ではなく、そのときの社会状況により左右され、また言語によっても異なりうるが、一つの変化が言語全体に行き渡る過程は、初めがゆっくりで、途中は早く、終わりはまたゆっくりになるという型をたどることが、多くの場合に観察されている。変化の原因としては、流行とか外国語の影響などの社会的なもの、労力の経済を求める生理的・心理的なもの、言語構造の不均衡を直そうとする言語的なものなどが考えられるが、多くの場合、複合的に作用する。変化は何かのきっかけによって始まり、個人から個人へ、語から語へと逐次に伝わってゆくのであり、けっしてひと月かふた月の間に一挙に完了するというものではない。変化が始まる前には、その素地が、すでに言語内に整っているのが普通である。たとえば、最近の日本語共通語では、受身と可能の両方を表す「られる」が、「られる」(受身)と「れる」(可能)に分化する現象が目だっているが、それ以前に、長年にわたって両形を区別する方言の話者が東京に移住してきて、徐々に数を増していたということが考えられる。一方では、東京で、「られる」を用いて二つの異なった意味を表すことの不便さも感じられていたということもあろう。
従来、類推は変化の要因の一つと考えられていたが、これは言語の均勢を増すとともに、労力経済にもかなうものである。幼児の言語習得の不完全さに変化の要因を求める考え方もあるが、幼児が成長するにつれて訂正されるのが普通であるから、有力な原因とはなりにくい。
変化の進行中は、旧形と新形が併用される。これは、一般の人には「乱れ」と映るのが普通であるが、言語につねにみられる自然な現象であり、単なる「ゆれ」とみるのが妥当であろう。言語は、一方的に昔の複雑な状態が「崩壊」して単純化に向かうわけでもなく、「乱れ」が進んで混沌(こんとん)状態に陥るわけでもない。統一と分化の微妙な均衡を保ちながら、人間の必要を満たす方向に変わってゆくものとみられる。
[国広哲弥]
言語の接触
二つの言語がなんらかの形で接触した場合、いろいろの現象が生じる。
〔1〕語彙、表現法などが借入される。借入語の意味は、原語の意味の一部であったり、変化しているのが普通である。
〔2〕異言語社会に移住したりした場合、個人は二重言語話者となることがある。
〔3〕互いに通じない言語を話す二つのグループが、商業上の必要から、伝達手段を求め、まにあわせ的な第三の言語をつくりだすことがある。これは、その地域に広まっている英語・フランス語などの文明語を基盤とした、きわめて単純な構造をもつもので、「ピジン」pidginとよばれる。ピジンを聞いて育った子供たちがそれを母語としたとき、ピジンはクレオール化したという。「クレオール」creoleは、日常のすべての用を弁じる必要があるところから、基盤文明語から語彙や文法を取り入れて補強するので、構造はピジンに比べて豊かとなる。この補強がさらに進むと、基盤文明語にますます近づくことになり、結果としてクレオールは消滅する(decreolized)。
[国広哲弥]
『『講座 言語』全6巻――柴田武編『第1巻 言語の構造』、池上二良編『第2巻 言語の変化』、南不二男編『第3巻 言語と行動』、千野栄一編『第4巻 言語の芸術』、西田龍雄編『第5巻 世界の文字』、北村甫編『第6巻 世界の言語』――(1980~81・大修館書店)』
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「言語」の意味・わかりやすい解説
言語
げんご
logos; language
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「言語」の意味・わかりやすい解説
言語【げんご】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
普及版 字通 「言語」の読み・字形・画数・意味
【言語】げんご
 ぜず。嗜欲同じからず。~東方を寄と曰ひ、南方を象と曰ひ、西方を狄
ぜず。嗜欲同じからず。~東方を寄と曰ひ、南方を象と曰ひ、西方を狄 と曰ひ、北方を譯(えき)と曰ふ。
と曰ひ、北方を譯(えき)と曰ふ。字通「言」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
世界大百科事典(旧版)内の言語の言及
【構造言語学】より
…構造言語学ないし構造主義言語学ということばは,ふつう1920年代から50年代にかけてヨーロッパとアメリカに生じた革新的な言語学の諸流派を総称するのに用いられるが,具体的にはプラハの音韻論学派(プラハ言語学派),コペンハーゲンの言理学グループ,アメリカの記述言語学の諸集団およびそのどれにも属しない諸学者の多種多様な主張や見解が含まれる。最大公約数的な理論上の特徴をあえてあげるならば,言語を記号学的体系と認め,あらゆる言語に普遍的な最小の記号単位の数や組合せの面での相違が言語体系の構造の差異を作ると考えて,各言語の精密かつ全面的な構造的記述の理論と実際を追求する立場といえよう。…
【ブルームフィールド】より
…アメリカの言語学者。シカゴ出身。…
【二重分節】より
…言語学の用語。フランスの言語学者A.マルティネの言語理論の根幹をなす認識。…
【品詞】より
…文法用語の一つ。それぞれの言語における発話の規準となる単位,すなわち,文は,文法のレベルでは最終的に単語に分析しうる(逆にいえば,単語の列が文を形成する)。そのような単語には,あまり多くない数の範疇(はんちゆう)(カテゴリー)が存在して,すべての単語はそのいずれかに属している。…
【方言】より
…また〈ソラ〉とか〈ヨム〉のような地域差のない要素も,地域差のある要素と同様に,ある地域の言葉として〈方言〉の一部をなす。
[方言と言語]
〈方言〉はまた,〈言語〉の下位区分でもある。ふつう,言葉がまったく通じないほど違うのは言語としての違いで,少しでも通じる場合が方言としての違いとされる。…
【文字】より
…言語を視覚的に表す記号の体系をいう。
【音声言語と文字言語】
言語行動には,音声を素材とする〈音声言語行動〉と,文字を素材とする〈文字言語行動〉とがある。…
※「言語」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...