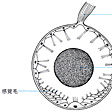精選版 日本国語大辞典 「平衡感覚」の意味・読み・例文・類語
へいこう‐かんかくヘイカウ‥【平衡感覚】
日本大百科全書(ニッポニカ) 「平衡感覚」の意味・わかりやすい解説
平衡感覚
へいこうかんかく
ヒトは皮膚感覚や深部感覚、視覚を除いても、直進加速度や回転加速度を感ずることができる。この感覚を平衡感覚あるいは前庭感覚という。平衡感覚によって、生体は全身の姿勢と運動、全身の空間における相対的位置などが感知される。また、姿勢と運動の平衡や眼球運動も、平衡感覚によって反射的に調整される。
平衡感覚の受容器は、内耳内に存在する骨迷路にあって互いに直交している三つの半規管(三半規管)と前庭器官(卵形嚢(のう)と球形嚢)とにある有毛細胞である。すなわち、回転運動は半規管膨大部にある膨大部頂の有毛細胞によって、また、直進運動は前庭器官の平衡斑(はん)(卵形嚢と球形嚢の内壁の一部にある楕円(だえん)形部分)にある有毛細胞によって感じられる。これら有毛細胞に分布している前庭神経は、蝸牛(かぎゅう)神経と合流して延髄の前庭神経核と小脳に終わっている。二次ニューロンには脊髄(せきずい)に下行するものと、上行して眼球運動を統御する脳神経運動核に達するものとがある。しかし、視床を経て大脳皮質に上行する経路は、まだ十分には明らかにされていない。
平衡斑に配列する有毛細胞には、平衡石(平衡砂(さ)・耳石(じせき))とよぶ結晶状の小体がのっている。頭を傾けたり、体が直進運動をすると、有毛細胞に対して平衡石の相対的移動がおこり、有毛細胞の受ける圧力やその作用方向が変わる。これによって頭の位置の変化や体の直進運動が感知されるわけである。また、体が回転運動をおこすと、半規管内の内リンパはその慣性のために流動が遅れ、回転方向と逆方向に膨大部頂を傾けることとなる。その結果、有毛細胞が興奮し、前庭神経のインパルス発射頻度が変わる。しかし、回転が停止すると、内リンパは慣性のために回転方向に流れ、膨大部頂は回転方向と同方向に傾く。半規管は、互いに直交し、左右に三つずつあるため、回転運動は三次元に解析される。このため、体の任意方向の回転に対して、その方向と程度とが正しく感知されることとなる。
回転運動の始めと終わりとにみられる眼球に特有な急激な運動を「眼振(がんしん)」(眼球振盪(しんとう))という。すなわち、眼球は注視物を追って回転方向とは反対の方向にゆっくりと動き始め、この追跡運動が終わりかかると、急に回転方向と同じ方向に動き、新しい注視物をみつける。このような眼球のゆっくりした運動と速い運動との繰り返しが眼振である。眼振は、体が回転運動中にあるとき、視線を注視物に固定する反射運動である。また、体温より温かいか、または冷たい液体を外耳道に入れると、体温との温度差が内リンパの対流を招き、膨大部頂に運動がおこる。この結果、眼振(これを温熱性眼振という)、めまい、吐き気などの反射に伴う症状を呈することがある。このほか、前庭器官が過度に刺激されると、吐き気、血圧の変動、発汗、蒼白(そうはく)、嘔吐(おうと)などのおこることがある。船酔いなどがその例である。なお、めまいとは、現実に回転運動が行われていないのに感じられる回転感覚である。
[市岡正道]
動物と平衡感覚
動物が重力の方向に定位したり、力学的平衡を保ったりするために必要な感覚を平衡感覚といい、この感覚の基礎となる受容器を平衡受容器または平衡器官(平衡器)という。もっとも普遍的にみられる平衡器官は、外胚葉(はいよう)の陥入による小嚢の内面に感覚毛が生えたもので、平衡胞とよばれる。平衡胞の中には通常1個の平衡石または一塊となった平衡砂があり、それが異なる場所の感覚毛に触れることによって動物の体軸の傾きが受容される。刺胞動物のクラゲや軟体動物の平衡胞の感覚毛は、運動性小器官のものとほぼ同じ構造をもつ繊毛である。脊椎(せきつい)動物前庭装置の卵形嚢および球形嚢の有毛細胞には、動毛といわれる繊毛と、不動毛といわれる微絨毛(じゅうもう)がある。節足動物の平衡胞にある感覚毛は、体表の感覚子と同様のクチクラ装置をもった剛毛である。脊椎動物の平衡器官は重力に対する体軸の方向および直線加速度運動の受容器である前述の前庭装置のほかに、回転運動の受容器である半規管がある。平衡感覚は視覚と密接な関係があり、半規管が刺激されれば眼球の運動(眼振)がおこり、また回転運動感覚の錯覚によりめまいを生ずる。
[村上 彰]
改訂新版 世界大百科事典 「平衡感覚」の意味・わかりやすい解説
平衡感覚 (へいこうかんかく)
sense of equilibrium
動物はふつう重力に対して一定の姿勢や運動方向を保持し,重力の方向に対して傾きが変わったときこれを補償するように体を動かす。このようなつりあい状態を保つのに必要な感覚は,視覚,触覚,さらに自己受容覚とよばれる筋肉や関節から生ずる内部感覚など種々の感覚の総合からなっているが,多くの動物では重力受容器として特殊化した平衡器からの平衡(感)覚が重要な役割をはたしている。平衡器はヒトを含む脊椎動物では内耳の前庭迷路器官にあり,頭部の静的位置をおもに検出する前庭囊と,動的位置変化にともなう加速度を検出する半規管とからなっている(三半規管)。前庭囊は耳石器ともよばれ,無脊椎動物の平衡胞と共通の構造,機能をもつ。半規管は一つの基部からたがいに直交する3平面上にある3個の半円弧の環(円口類では1~2個)を派生した管状の器官で,それぞれの管の一端に瓶とよぶ膨大部があり,その内腔に有毛受容細胞の繊毛がゼリー状の物質に包まれてできた扇状のクプラが管軸と直角に立っている。半規管内腔を満たした内リンパ液は,加速度運動に対し,とり残されて管壁と相対運動をおこし,クプラを傾けて有毛細胞を刺激し,これにつながる前庭神経の活動に変化を生じさせる。クプラの傾きの方向により活動が増加または減少し,その程度は傾きの大きさによって決まる。このことと三つの半規管の方向分担とによって,体のあらゆる方向への加速運動を検出する。
無脊椎動物の平衡器はふつう平衡胞であり,重力受容器として静的位置検出に適した構造をもっている。最下等のクラゲから扁形動物,環形動物,軟体動物,甲殻類まで同一原理によるものが見いだされる。平衡胞は体表などの陥入による胞状の構造で,その内面に有毛受容細胞の繊毛,甲殻類では受容細胞につながるキチン質の毛からなる感覚毛があり,その先端に付着あるいは自由移動する平衡石(耳石)をのせている。この感覚毛と平衡石のある部分を斑(はん)(聴斑)とよぶ。平衡石は胞内部に分泌されたカルシウム質のものであることが多いが,カニ,エビなどでは平衡胞は第1触角の基節にあって毛でおおわれた小孔を通じて外部と導通し,平衡石は脱皮のたびごとに外部からとり入れる砂粒からなっている。平衡石は胞内液と比重が異なるので,傾斜によって移動し,重力分力による剪断(せんだん)力が感覚毛に直角に作用してこれを傾け,受容細胞の活動をひきおこす。体の傾き方向の検出は,左右対の平衡胞をもつものでは活動の左右差にもよるが,一般には斑内の感覚毛の配列が規則的なので,ある傾きでは特定部分の感覚毛の活動のみが増加,減少することによっている。傾斜角の大きさは,感覚毛の傾きの大きさによる活動度の大小で検知される。活発に遊泳するカニでは平衡胞感覚毛の一部は平衡石に付着せず,自由に動くことができ,胞の一部も変形して円環状の空間をつくり,この中で内液が加速運動のさい動いて半規管と同じはたらきをする。検出された傾斜方向,角度は平衡感覚情報として中枢をへて,体の各部の筋肉を協調的に動かし,眼球(眼柄),付属肢などの動きによって姿勢をもとに戻す補償反射運動をひきおこす。移動運動中の動物では,この結果として重力に対して正または負の方向への移動(重力走性)があらわれる。体が傾斜していないときも平衡器受容細胞は一定の活動をしている。この活動は体が傾いたときに増加あるいは減少という形で生じる変化の背景となるいわゆる背景活動の役割をはたすほか,体の各部の姿勢維持に必要な筋緊張を保持する役割もはたしている。
昆虫はある種の幼生をのぞき平衡胞を持たないが,それでも重力走性を示すものが多い。水生昆虫では体表面に付着した気泡の移動を触角その他にある感覚毛が,陸生のものでは頭部や腹部の重力による垂下を屈曲部にある感覚毛が検知して平衡覚としている。ゴキブリなどでは尾角上にある感覚毛のうち棍棒(こんぼう)状のものが,重力感覚器として役だっているとされている。ハエ,カなど双翅(そうし)類には飛行中の平衡保持のため後翅の変形した平均棍とよぶ器官がある。
執筆者:久田 光彦
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「平衡感覚」の意味・わかりやすい解説
平衡感覚【へいこうかんかく】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「平衡感覚」の意味・わかりやすい解説
平衡感覚
へいこうかんかく
vestibular sensation
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
四字熟語を知る辞典 「平衡感覚」の解説
平衡感覚
[使用例] 一種の神経障害を起こし、ひどい不眠症になって平衡感覚すらがあやしくなり[堀田善衛*記念碑|1955]
[使用例] それは一種の綱渡りのようなものだが、彼のような商売を十年以上も続けている以上、そうした時の平衡感覚は第二の本能のようになっていて、無意識にしゃべっていても、そう大きく踏み外すことはないはずであった[柴田翔*彼方の声|1970]
出典 四字熟語を知る辞典四字熟語を知る辞典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の平衡感覚の言及
【耳】より
…信号はここから大脳皮質聴覚野へと送られる。聴覚
【平衡感覚のしくみ】
平衡感覚は内耳の三半規管および耳石器によって感受される。三半規管の膨大部には感覚細胞である有毛細胞があり,この上にクプラcupulaをのせている。…
※「平衡感覚」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...