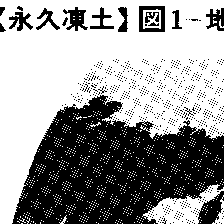翻訳|permafrost
共同通信ニュース用語解説 「永久凍土」の解説
永久凍土
高緯度地域や高山帯で、複数年にわたって凍結状態が続く土壌。北極圏を中心にロシアのシベリアや北米に広がる。地球が寒冷だった氷河期に形成され、厚さは数メートルから数百メートルになる場所もある。夏は地表部の氷が解ける。溶解が進むと凍土内に閉じ込められている有機物が温室効果ガスの二酸化炭素(C〓(Oの横に小文字の2))やメタンとなって大気中に放出され、温暖化が一段と進む要因になる。(チュラプチャ共同)
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
精選版 日本国語大辞典 「永久凍土」の意味・読み・例文・類語
改訂新版 世界大百科事典 「永久凍土」の意味・わかりやすい解説
永久凍土 (えいきゅうとうど)
permafrost
少なくとも連続する2冬とその間の1夏を含めた期間より長い間,凍結状態にある土のこと。冬に気温が0℃以下になると土が凍る。ひじょうに寒い所では凍った土が夏に溶けきらないうちに,次の冬がやってきて,再び地面から凍り始め,下の凍土につながる。そして凍土の温度が下がり,さらに下方へと凍結が進む。溶けたり凍ったりするのは,ごく表層の活動層だけで,その下には永久に溶けることのない土,永久凍土がある。その分布は現在,シベリア,アラスカ,カナダ北部,中国奥地に広くひろがり,面積は21×106km2で,地球上の全陸地の14%を占める。永久凍土の厚さは,北へ行くに従い厚くなる。北極海岸のアラスカのバロー(年平均気温-12.4℃)で300~400m,シベリア内陸部のヤクーツク(年平均気温-10.1℃)で250mである。
永久凍土地帯でも表層の活動層のために植生がみられる。北極海岸は高木のないツンドラ帯で,内陸に入ると樹林が現れる。年間降水量は,北極海岸のツンドラ帯で150mm,内陸の樹林帯で300~400mmである。永久凍土地帯には次のような特異な地形や氷塊が見られる。(1)構造土 地表面に見られる規則的な凹凸模様の繰返しで,模様の形状から円形土,網状土,多角形土,階段土,線伏土に分けられる。(2)氷楔 活動層と永久凍土との境界面から下に向かって頂点を下に,地中にくさびを打ち込んだ形の氷塊。(3)ピンゴpingo 平らな湿地帯の中にぽつんと盛り上がる小丘で,丘の内部には氷が詰まっている。高さは数mから60mくらいまである。(4)アラスalas シベリアのヤクーツク周辺に多く見られる地形で,樹林帯中にぽつんと開ける皿状のくぼ地である。くぼみの深さは1mから10mどまり,広さは直径数十mから数kmに及ぶ。なかには湖をなすものもある。(5)集塊氷 海岸や湖岸の崖に露出している巨大な氷塊で,通常,地表より2~5m下へ延びて,30mくらいにも及ぶ。その横のひろがりは,数十mから1kmくらいにも及ぶ。凍土層からは1万~15万年前のマンモスが凍ったまま掘り出されており,古い時代からずっと凍ったままであることを示している。
執筆者:木下 誠一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
最新 地学事典 「永久凍土」の解説
えいきゅうとうど
永久凍土
permafrost
少なくとも継続して二冬とその間の一夏を含めた期間より長い間,0℃以下の凍結状態を保つ土壌または岩石(凍土)。シベリアやアラスカなどの北半球高緯度地域に広く分布し,全地表の14%(2.1×107km2)を占める。永久凍土は,その面積比から,次の三つの地域帯に区分される。1)連続的永久凍土(continuous permafrost):90~100%,2)不連続的永久凍土(discontinuous permafrost):50~90%,3)点在的永久凍土(sporadic permafrost):10~50%。面積比10%未満は局地的な(isolated)永久凍土に分類される。中緯度ではチベット高原など標高の高い地域に分布し,山岳永久凍土と呼ばれる。日本では北海道の大雪山,富士山,立山に山岳永久凍土が確認されている。永久凍土の南限(下限高度)は年平均気温−2℃に一致する。年平均気温が0℃を上回る場所でも,風穴がつくる低温環境によって非成帯的な永久凍土が形成されることがある。永久凍土層の存在は,土木・建築・農業などの障害となるほか,排水不良や融解による地盤の不等沈下などの原因となる。
執筆者:近堂 祐弘・福田 正己・澤田 結基
出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「永久凍土」の意味・わかりやすい解説
永久凍土
えいきゅうとうど
permafrost
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「永久凍土」の意味・わかりやすい解説
永久凍土
えいきゅうとうど
地温が夏の間も高くならず、少なくとも1年以上連続的に0℃以下の地温状態を保っている土壌や岩石。パーマフロストpermafrostともいう。北極を中心とするカナダ、アラスカ、シベリアなどの高緯度地域と南極大陸に広く分布し、その全面積は全陸地面積の23%(約3500万平方キロメートル)に及ぶ。永久凍土のある地域では、夏に地表面付近がわずかに溶けるだけで、地下はつねに凍結しているため、周氷河地形とよばれる独特の地形が発達する。永久凍土地域の植生は一般に貧弱で「ツンドラ植生」とよばれる。永久凍土の厚さは最大で600メートルにも達することがある。永久凍土は気候の寒冷な高山でもみられ、日本では富士山頂と北海道の大雪山で発見されている。
[小野有五]
百科事典マイペディア 「永久凍土」の意味・わかりやすい解説
永久凍土【えいきゅうとうど】
→関連項目周氷河地形|ツンドラ|プトラナ高原|メタン・ハイドレート
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
岩石学辞典 「永久凍土」の解説
永久凍土
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...