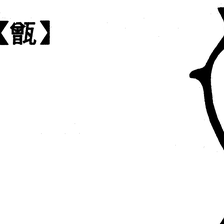精選版 日本国語大辞典 「甑」の意味・読み・例文・類語
こしき【甑】
そう【甑】
- 〘 名詞 〙 こしきのこと。
改訂新版 世界大百科事典 「甑」の意味・わかりやすい解説
甑 (こしき)
米などを蒸すための土器。木製品としても存在し,蒸籠(せいろう)とよばれる。円筒形か鉢形の器の底に1個ないし数多くの蒸気孔をあける。底に直接,布や藁を敷くか,底から少し上に簀の子(すのこ)をはめるかして,米などをのせる。水をいれた別の器の上に甑を重ね,火熱による熱い蒸気で蒸しあげる。中国では新石器時代に稲作地帯(浙江省河姆渡(かぼと)遺跡第3層,馬家浜文化)に出現し,竜山文化には,甑と下の器(鬲(れき))とをひとつの土器として作った甗(げん)も出現した。朝鮮半島での初現は,おそらく3~4世紀。この系譜をひき,日本では5世紀に須恵器の器種として甑が現れ,そして土師器の器種として普及し8世紀まで継続した。ただし5~8世紀の集落遺跡で出土する煮炊き用土器の大半を占めるのは,ふつうの鍋,甕であって,甑の個体数はつねに少ない。この事実は,日本古代に日常に米を蒸して食べたとする常識をくつがえすものであって,真相は,日常は煮炊きして食べ,祭りなど特別の機会のみに蒸して食べたのだろう。これは,現代においても,赤飯や餅を作り酒を作る際にのみ米を蒸すことと比較できよう。《万葉集》の山上憶良の〈貧窮問答歌〉に〈許之伎〉にクモの巣が張っている,とあるのは,祭りにさえ米が蒸せないことを意味するのではないか。なお,弥生時代の底部有孔の土器を甑とする解釈も疑わしい。そして仮にそう認めるにせよ,弥生人が甕で米を直接煮炊きするのが一般的だったことは確実である。
執筆者:佐原 眞
醸造用の甑
醸造原料を蒸すため釜の上にはめる簀の子つきの木製ないし金属製の円筒。清酒用の甑は釜からの飛沫(ひまつ)で簀の子上の米がぬれないよう甑と釜の間に穴をあけた厚板(女郎板(じよろいた))をおき,穴にかぶせた〈こま〉で蒸気を四方に分散させるよう改良されている。中国を含めた東アジアの蒸留酒製造用の甑は円筒の上に冷水をいれた平鍋をのせる。ヤシ酒などは釜に入れて加熱し,発酵した餅麴(もちこうじ)や清酒粕は簀の子上に堆積し釜からの水蒸気で加熱し,アルコールを含む蒸気を平鍋の底で冷やし,凝縮する焼酎を集めて管で甑外に取り出す。日本でも大正初期まで焼酎の製造に使われていた。
執筆者:菅間 誠之助
冶金用の甑
銑鉄を溶解する炉で,形が炊器の甑に似ることから名づけられた。古くから使用されていたが,現在ではほとんどキュポラ(溶鉄炉)に置き換えられている。構造および操業方法はキュポラとほとんど同じで,主として鋳鉄の溶解に用いる。炉は鋳鉄製で,高さは比較的低く,一体ではなくて3段または4段に分かれており,鋳物工場の床の上に直接積み重ねて継目を目塗りして操業する。溶解能も小さく,1溶解ごとに積み換えて,修理をする必要がある。また長時間の操業が困難であり,溶解温度も比較的低いので,良好な溶湯が得がたい。銅合金の溶解にも甑が利用されることもあるが,特殊な場合である。
執筆者:梅田 高照
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「甑」の意味・わかりやすい解説
甑
こしき
穀物などの蒸し器。鉢形または甕(かめ)形の器の底に、下の器から沸いた湯気をあげる穴をあけ、中に簀子(すのこ)や麻布を敷き、蓋(ふた)をして食物を蒸す。弥生(やよい)時代の土器にもみられたが、5世紀のころ、朝鮮南部を経て角(つの)状の把手(とって)のある大型の土製の甑が伝来し、土製の釜や竈(かまど)と組み合わせて使用された。山上憶良(やまのうえのおくら)は、「竈(かまど)には火気(けぶり)ふき立てず甑には蜘蛛(くも)の巣かきて、飯炊(いいかし)ぐ事も忘れて」と詠んでいる。甑では米を蒸して強飯(こわめし)、蒸し米を干して糒(ほしいい)、杵(きね)で搗(つ)いて餅(もち)をつくる。稗(ひえ)は蒸してから搗いて殻を除き飯にする。そのほか、団子、ちまきを蒸すとか、酒造やみそづくりにも用いられる。平安時代に曲物(まげもの)の甑が出現し、のちに桶(おけ)の甑となり、江戸時代には蒸籠(せいろう)の発達をみた。
[木下 忠]
山川 日本史小辞典 改訂新版 「甑」の解説
甑
こしき
穀粒を蒸すのに用いる道具。底に1個ないし2個以上の穴をあけたり,簀(す)を敷き,湯釜の上にのせ蒸気を通して蒸す。古くは土製で,古墳時代の住居跡から竈(かまど)とともに出土する。木製の甑は,橧または と書き,コシキとよんだ。弥生・古墳時代の土製から,平安後期頃には底なしの曲物(まげもの)や薄板を井桁に組んだ箱型のもの(蒸籠(せいろう)とも)にかわっていたようである。稲作とともに日本に伝来したものと考えられる。米の食べ方は,古くは甑で蒸した蒸飯(むしめし)で強飯(こわいい)であったが,姫飯(ひめいい)とよばれるやわらかい炊飯(たきめし)には鍋が使用されるようになった。
と書き,コシキとよんだ。弥生・古墳時代の土製から,平安後期頃には底なしの曲物(まげもの)や薄板を井桁に組んだ箱型のもの(蒸籠(せいろう)とも)にかわっていたようである。稲作とともに日本に伝来したものと考えられる。米の食べ方は,古くは甑で蒸した蒸飯(むしめし)で強飯(こわいい)であったが,姫飯(ひめいい)とよばれるやわらかい炊飯(たきめし)には鍋が使用されるようになった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
百科事典マイペディア 「甑」の意味・わかりやすい解説
甑【こしき】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「甑」の意味・わかりやすい解説
甑
こしき
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「甑」の解説
甑
こしき
底部に孔を有する深鉢形をし,弥生時代に出現。古墳時代になると,甑・釜・かまどが1組としてつくられた。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
関連語をあわせて調べる
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...