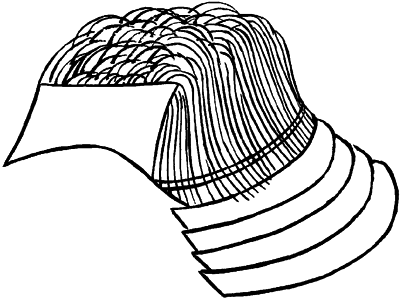関連語
精選版 日本国語大辞典 「総髪」の意味・読み・例文・類語
そう‐ごう‥がう【総髪】
そう‐はつ【総髪・惣髪】
そう‐がみ【総髪】
普及版 字通 「総髪」の読み・字形・画数・意味
【総髪】そうはつ
 髮より
髮より 介を
介を き 奄(たちま)ち四十年を出づ 形迹、
き 奄(たちま)ち四十年を出づ 形迹、 に憑(よ)りて
に憑(よ)りて くも 靈府長く獨り
くも 靈府長く獨り (しづ)かなり
(しづ)かなり字通「総」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「総髪」の意味・わかりやすい解説
総髪
そうはつ
幕末から明治維新にかけて、男子に行われた髪形。月代(さかやき)を剃(そ)り上げることなく、髪全体を束ねたところからの名称。さらに、髪を束ねずに、後方になでつけたものをもいう。この髪は公家(くげ)、医者、学者、山伏、あるいは明治維新に活躍した志士たちが結った。公家は、紫組紐(くみひも)で髪を束ねるのが特色である。志士たちは、国事に日夜東奔西走している関係から、月代を剃る本多髷(ほんだまげ)よりも、手のかからぬ髪形を必要としたためである。
[遠藤 武]
[参照項目] |
百科事典マイペディア 「総髪」の意味・わかりやすい解説
総髪【そうはつ】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...