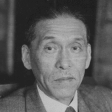芦田均内閣
あしだひとしないかく
(1948.3.10~1948.10.15 昭和23)
民主党総裁芦田均を首班とする民主党、日本社会党、国民協同党の三党連立中道内閣。片山哲(かたやまてつ)内閣総辞職後、野党の日本自由党は首班を要求、民主・社会・国協各党内の対立も絡み、複雑な多数派工作のすえ、衆議院が芦田を、参議院が吉田茂(日本自由党)を指名、両院協議会でもまとまらず、憲法第67条2項により芦田が選ばれた。財界やGHQ(連合国最高司令部)民政局はそれを支持したが、世論調査での支持率は低かった。芦田内閣は外資導入による経済再建を政策の基本とした。それは、日本をアジアの工場にしようとするアメリカの対日占領政策の転換に即応していた。そのため全逓を中心とする三月闘争をGHQの力で抑え、マッカーサー書簡を受けて公務員の争議権を奪う政令二〇一号を公布するなど、労働攻勢を鎮める政策をとった。この間、民主、社会両党とも離党者が続出し、昭電疑獄事件で西尾末広ら閣僚が逮捕されるに及び総辞職した。
[宮﨑 章]
『富田信男著『芦田政権・二二三日』(1992・行研)』
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
芦田均内閣
あしだひとしないかく
民主党総裁芦田均を首班とし,片山哲内閣と同様に民主・社会・国民協同の3党連立内閣(1948.3.10~10.15)。社会・国協両党首は入閣せず,社会党左派から2人が入閣。外資導入による経済再建を重点政策としたが,与党が弱体でGHQの権威を支えとして施策を進めた。発足直後の全逓を中心とする3月闘争はGHQのスト禁止のマーカット覚書で切り抜け,1948年(昭和23)7月22日のマッカーサー書簡にこたえ,公務員の争議権を剥脱する政令201号を公布。西尾末広前副総理や栗栖赳夫(くるすたけお)経済安定本部長官ら主要閣僚が昭電疑獄事件などに関連して逮捕され,10月7日総辞職した。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内の芦田均内閣の言及
【対日占領政策】より
…1945年8月14日のポツダム宣言受諾から,52年4月28日の対日平和条約発効までの期間は連合国(実質的にはアメリカ)によって日本の動向が決められた。この占領期の政策全般を対日占領政策,ないし占領政策というが,ここでは政策にとどまらず,世相にいたるまでこの時代の諸相を概括する。 ポツダム宣言の第7項は〈右の如き新秩序が建設せられ且日本国の戦争遂行能力が破砕せられたることの確証あるに至る は連合国の指定すべき日本国領域内の諸地点は吾等の茲に指示する基本的目的の達成を確保する為占領せらるべし〉と連合国の占領を定めており,日本占領のための連合国軍最高司令官にはアメリカのマッカーサーが任命された。…
は連合国の指定すべき日本国領域内の諸地点は吾等の茲に指示する基本的目的の達成を確保する為占領せらるべし〉と連合国の占領を定めており,日本占領のための連合国軍最高司令官にはアメリカのマッカーサーが任命された。…
※「芦田均内閣」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by