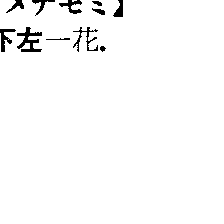メナモミ
Siegesbeckia pubescens Makino
山野に普通にみられるキク科の一年草。全体に腺毛がある。茎は高さ60~120cm,上部に毛が密生する。葉は卵形で,縁にあらい鋸歯があり,両面に長い毛が密生している。花期は9~10月。茎上部が分枝し,全体として大型の円錐状の花序を作る。花は直径2cmくらいの頭花で,花柄に腺毛がある。総苞片は5枚で開出し,狭いさじ形で柄のある腺毛を有する。花床には小花に対応する鱗片状苞葉があり,これにも腺毛が生えている。これらの腺毛は粘液を分泌し,種子を動物につけて散布するのに役立つ。頭花の周辺に雌性の舌状花が1列あり,中央部に両性の筒状花があり,いずれも実る。メ(雌)ナモミの名はオ(雄)ナモミに対して,外見がやさしいことによる。オナモミも総苞にかぎ状のとげが発達し,衣服にくっつき易い。〈ナモミ〉はくっつく意味の〈なずむ〉から転化したものといわれている。
執筆者:小山 博滋 メナモミや近縁のツクシメナモミS.orientalis L.(英名holy herb)は,中国では全草を豨薟(きけん)の名で薬用にする。腫毒,中風,血圧降下に効があるという。若葉はゆでて苦みをとり,食用にする。
執筆者:堀田 満
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
メナモミ
めなもみ
[学] Sigesbeckia pubescens Makino
キク科(APG分類:キク科)の一年草。茎は直立し、高さ0.5~1.2メートル、上部は開出毛を密生する。葉は対生し、卵形または三角状卵形で、三行脈がある。花期は9~10月。舌状花は黄色で長さ約3ミリメートル、先端は3裂する。総包片は5枚でへら形、腺毛(せんもう)があって粘着する。痩果(そうか)は長さ約3ミリメートルで、刺(とげ)がない。若いときの外観はオナモミに似るが、オナモミは単性花で、果実に刺(とげ)がある。メナモミは山地や市街の草地に生え、北海道から九州、および朝鮮半島、中国大陸中南部に分布する。
[小山博滋 2022年5月20日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
メナモミ
Siegesbeckia pubescens
キク科の一年草。アジア東部の温帯から暖帯に分布し,関東地方より西の山野に普通にみられる。茎は直立し 1m内外の高さになり,紅紫色を帯びていて葉とともに開出毛が密生する。葉は柄があって対生し,長さ 10~20cmの卵状円形で3本の葉脈が目立つ。秋,茎の先端および上部の葉腋から葉柄を出し,黄色で小型の頭花を多数つける。総包には脱落性の腺毛があって粘液を分泌し,人や動物などに付着して運ばれ,種子を散布する。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
メナモミ
キク科の一年草。日本全土,東アジアの温〜暖帯に分布し,山野にはえる。茎は分枝し,高さ60〜120cm,上部には毛が密生。9〜10月,舌状花と筒状花からなる,径約2mmの黄色の頭花を開く。頭花の基部につく5個の総包片は長さ約1cmで腺毛があり,衣服などについて種子を散らす。果実は長さ3mm内外,4稜があって無毛。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by