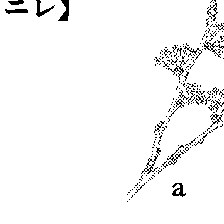ニレ (楡)Ulmus
目次 神話 ニレ科 Ulmaceae ニレ科ニレ属は北半球の温帯 と暖帯に約20種を産し,すべて落葉ないし半常緑の高木で葉の基部が左右不整である。日本でニレというとふつうハルニレ をさすが,ほかにアキニレ とオヒョウ がある。英語のエルム elmはヨーロッパニレ U .minor Mill.(=U .campestris L.)やセイヨウニレU .glabra Hudsonをさし,街路樹 として植えられる。濱谷 稔夫
神話 北欧神話によれば,神々はニレとトネリコ から,人類最初の女エンブラEmblaと最初の男アスクAskrを創造したという。イギリスなどでは中世以降,ニレにブドウのつるをはわせる習慣が生じ,この取合せを縁物(えんもの)とみなしたところから,結婚や良縁のシンボルともなった。ギリシア神話 では,冥界 から妻エウリュディケを連れ戻せなかったオルフェウス が,悲しみに暮れて弾いた竪琴 の力でこの世に生じた木とされるほか,ブドウとの関連からディオニュソス (バッコス )の聖木とも考えられた。また夢の神モルフェウスMorpheusとも結びつけられ,その下で眠る者は悪夢に襲われるという。荒俣 宏
ニレ科Ulmaceae 双子葉植物,約15属200種が北半球温帯から南半球亜熱帯 にかけて分布 する。ケヤキ ,エルム(ニレ類)やエノキ 類など街路樹として有用なものが多い。すべて高木または低木 。しばしば当年 の枝に頂芽を欠き,側芽から翌年の枝を伸ばすものがある。葉はふつう互生し,単葉 でときに左右が不整。早落性の托葉がある。花は小さく,両性または単性で,葉腋(ようえき )に集散花序をなすか,雌花 だけを単生する。花被片は4~8個がときに合生し,これと向かい合って4~8本のおしべ がある。子房 は上位で,2個の心皮がふつう1室をつくり,花柱は先が2裂する。果実は堅果または石果で,翼のできることもあり,1個の種子 を入れる。ニレ科はクワ科やイラクサ科に近縁 で,ふつう二つの亜科に分けられる。ニレ亜科は両性花 をもち堅果をつくるもので,北半球に多く,ニレ属ほか3属が属する。エノキ亜科は雄花 と両性花か雌花をもち,石果を結ぶもので,エノキ,ケヤキ,ムクノキ ,ウラジロエノキ などの諸属が含まれ,熱帯,亜熱帯に多い。ニレ科の高木種には,街路樹,緑陰樹として植えられるものが多い。また多くの属は,木目の美しい有用材を産し,家具材として重用される。樹皮 の靱皮(じんぴ)繊維が強く,縄などを作る。アツシ を作るオヒョウもこの科に属する。濱谷 稔夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」 改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by
ニレUlmus
ニレ科(APG分類:ニレ科)ニレ属の総称。落葉または半常緑高木。葉は2列に並んで生じ、互生し、単葉で基部は左右非相称、縁(へり)に鋸歯(きょし)がある。花は葉に先だって開くことが多く、両性で小形、花被(かひ)片は4、5裂する。雄しべ は花被片と同数で、紅紫色を帯びる。子房は普通は1室。果実は翼果で、開花後2~3週間で成熟する。北半球の温帯および熱帯アジアの山地に約45種ある。日本にはハルニレ(変種にコブニレ 、ツクシニレがある)、アキニレ、オヒョウが野生し、中国原産のノニレU. pumila L.がときに栽培される。エルムelmは、狭義にはヨーロッパニレU. procera Salisb.をさすが、一般にはニレ属の各種類をさす。日本ではハルニレをエルムとよび、北海道の低地に多く、春の新芽の多さが喜ばれる。樹皮をはぐとぬるぬるするので、ニレの名は「滑(ぬ)れ」に由来するといわれる。
[伊藤浩司 2019年11月20日]
アイヌの神話では、アイヌの人祖アイヌラックルは、雷神とハルニレの間に生まれた。ハルニレは自身の皮で着物をつくり、アイヌラックルに着せたという。かつてハルニレの樹皮からも衣服をつくったらしいが、アイヌの代表的な織物のアツシ(厚司)は、おもに近縁のオヒョウから編む。オヒョウの樹皮を帯状に剥(は)ぎ、温泉や沼に十数日水浸したのち、残った繊維質をよく水洗して、繊維を得た。一方、ハルニレの繊維は弱く、色も黒いので、オヒョウに混ぜて模様づけに織り込んだり、細く裂いて乾かした皮をかみ、柔らかくして一種の靴下をつくった。またアイヌ神話では、火の神がハルニレから生じたとされる。これはかつてハルニレの木で発火台と発火棒をつくり、こすり合わせて火を得ていたことに由来しよう。北欧神話では、大地を創造したオーディンが、ニレに魂を吹き込み、最初の女性エンブラを誕生させたという。『延喜式(えんぎしき)』(927)にはニレ皮を搗(つ)いて粉を得るとあり、古くはニレの内皮を干して臼(うす)で粉にし、食用にした。中国の『斉民要術(せいみんようじゅつ)』(6世紀)には、ニレの種子を搗いて粉にし、酒と醤(ひしお)をあわせてつくった楡子醤(にれのみのひしお)が載る。ニレの材は中国では椀(わん)、甕(かめ)、車両に重宝され、『斉民要術』には、子が生まれると、幼樹20本を植えれば、結婚の際、結納(ゆいのう)や持参金はそれでまにあうと記述されている。
[湯浅浩史 2019年11月20日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ) 日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by
ニレ(楡)Ulmus spp.; elm
ニレ科の落葉高木。ハルニレ U. davidiana var. japonica とその近似種の総称。北半球の温帯を中心にオウシュウニレ,アメリカニレ,シナニレなど 20種ほどの同属植物がある。日本にはハルニレ,アキニレ U. parvifolia ,オヒョウ U. laciniata の3種が自生する。ハルニレは北海道や本州北部に多く,北海道大学構内のものが有名である。樹高 20~30mで幹の樹皮は縦に裂け目が入る。葉は楕円形で先端がとがり,左右は不対称である。春に,黄緑色の小花を多数集めて開花し,種子が翼の上部にある。アキニレは本州中部以西から南に分布し,花や実が秋につく。葉はハルニレより小さく,長さ2~5cmで種子は翼の中央部につく。オヒョウは特に北海道に広く分布し,葉は大きく上部が3つに分れて中央片は尾のように長く伸びる。皮の繊維は強く,「あつし」と呼ばれるアイヌの衣装はこれからつくったものである。なおアキニレは街路樹や盆栽にもよい。中国では樹皮を薬用,木の汁を塗料にする。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by
ニレ(楡)【ニレ】
ふつうハルニレをさす。ニレ科の落葉高木。日本全土の山地にはえるが,四国,九州には少ない。東アジアにも分布。葉は長さ3〜15cm,倒卵形で基部が左右不同,厚く表面はざらつき,縁には鋸歯(きょし)がある。3〜5月,葉の出る前,前年の枝に褐紫色の小さな両性花を密につける。果実は長さ1cmほどでうちわ状の翼があり,6月,淡褐色に熟す。材は弾性に富み,建築,器具,細工物とし,樹は庭木とする。ニレは滑(ぬ)れの意で,皮をはげば粘滑なのに由来。本州中部〜沖縄にはえるアキニレは,葉が小型で長さ2.5〜5cm,9月ごろ淡黄色の花を開く。街路樹や庭木とする。
出典 株式会社平凡社 百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by
世界大百科事典(旧版)内の ニレの言及
【ハルニレ(春楡)】より
…北地では堂々とした大木のみられるニレ科の落葉高木(イラスト)。アイヌの祖神アイヌラックルはハルニレ姫と雷神の間から産まれたと伝承されている。…
※「ニレ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by