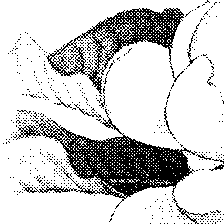ホオノキ
ほおのき / 朴木
[学] Magnolia obovata Thunb.
Magnolia hypoleuca Sieb. et Zucc.
モクレン科(APG分類:モクレン科)の落葉高木。枝はまばらにつく。葉は枝先に偽輪生状につき、倒卵形または長楕円(ちょうだえん)形で大きなものは長さ80センチメートル、日本産木本種中最大の葉の一つである。裏面は白色を帯びる。5~7月、枝先に径20センチメートルに達する大きな淡黄白色花を開き、強い芳香を放つ。日本の固有種で、山野に普通に生え、南千島、北海道から九州の温帯~暖帯上部に分布する。材は高級有用材で、柔らかくて狂いが少ないため、家具調度品などに用いられ、朴歯(ほおば)の下駄(げた)は有名である。公園、庭園樹としても植栽される。
[植田邦彦 2018年8月21日]
幹の皮を和厚朴(わこうぼく)といい、中国産厚朴の代用とする。漢方では鎮痛、鎮咳(ちんがい)、利尿、健胃剤として腹痛、腹満、胸満、慢性気管支炎、喘息(ぜんそく)などの治療に用いる。おもな成分はアルカロイドのマグノクラリン、精油のマチロールなどである。中国産厚朴はコウボク(マグノリア・オフィキナーリス)M. officinalis Rehder et Wilsonとその変種の幹の皮で、品質はきわめてよく、値段も甚だしく高価である。
[長沢元夫 2018年8月21日]
本種の中国語である厚朴に、平安時代の『本草和名(ほんぞうわみょう)』は保々加之波乃岐(ほほかしはのき)、『和名抄(わみょうしょう)』は保々乃加波(ほほのかは)をあてている。古くは飯を盛る器に使われ、『万葉集』には大伴家持(おおとものやかもち)が「皇神祖(すめろき)の遠代御代(とおみよみよ)は い布(し)き折り酒(き)飲みきといふそ このほほかしは」(4205)と、天皇や天皇の祖先がホオの葉を筒状に折って酒を飲んだと詠み、祭儀のおりなどにホオの葉の酒器が存在していたことが知られる。平安時代の『栄花(えいが)物語』では、樹皮がかぜ薬に使われた記述がある。また、木曽義仲(きそよしなか)は、餅(もち)をホオの葉に包んだホーッパ餅を兵に持たせ、攻め上ったという。ホーッパ餅は現在も木曽地方で6月5日の月遅れの節句につくられている。ホオの葉はいけ花にも早くから用いられ、『立花大全(りっかだいぜん)』(1683)には、大葉に用いる類のなかに、朴葉(ほおば)が名を連ねている。
[湯浅浩史 2018年8月21日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
ホオノキ (朴の木)
Japanese white bark magnolia
Japanese umbrella tree
Magnolia hypoleuca Sieb.et Zucc.
山野に普通なモクレン科の落葉高木。枝先に大きな葉が輪生状について傘のようで,その先に白い大きな花をつけ,強い芳香を放つ。高さ30m,胸高直径1.2mもの大木になる。枝はまばらにつき,その間を長さ80cmにもなる倒卵形の大きな葉がうめる。主として河川沿いの土壌の深い平坦地に見られる。日本固有で南千島,北海道,本州,四国,九州に分布する。材は軟質で均一なため細工がしやすく,家具調度品によく用いられ,また朴歯の下駄は有名。木炭も上質で金銀の研磨に使う。葉の芳香と大きいことを利用して,飯を盛ったり,有名な朴湯・朴葉味噌が作られ,地方によってはかしわもちとは朴葉餅を指す。近縁の中国産の厚朴(こうぼく)M.officinalisの樹皮は健胃剤等の漢方薬として有名だが,その代用に使われることもある。公園樹としても利用する。
執筆者:植田 邦彦
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
ホオノキ(朴の木)
ホオノキ
Magnolia obovata
モクレン科の落葉高木。日本の特産種で,各地の山地の林中に生える。幹は直立してそびえ高さ 20m,直径 1mにも達し,帯白色の樹皮をもつ。上方でまばらに分枝した枝には,倒卵形で長さ 30cmに達する大きな葉をやや輪生状に集めてつける。葉の裏は粉をふいたように白い。また若芽は赤みを帯びて美しい。5月頃,枝の端に径約 20cmもの帯黄白色の花をつけ,強い香気を放つ。花弁,おしべ,めしべとも多数あり,タイサンボクの花に似ている。秋に長楕円形の果実となり,中に白い糸を引く赤い種子ができる。材は柔らかく黄色みを帯び,版木,刀の鞘,下駄の歯などに使われる。また古くから葉を握り飯や味噌などを包むのに用いた。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
ホオノキ
モクレン科の落葉高木。北海道〜九州の山地にはえる。冬芽は筆の穂の形に似て大型。葉は枝先に集まり,倒卵状長楕円形で長さ20〜40cm,やや厚く裏面は白い。5〜6月,枝端にかおりのよい径約15cmの花を開く。花弁は9枚内外で淡いクリーム色。おしべは多数で花糸は赤く葯は黄白色,めしべも多数。果実は長楕円体で10〜11月,紅紫色に熟し,内から赤い種子を出す。材を器具,下駄の歯などとし,樹を庭園樹とする。大きくてかおりのよい葉は朴葉味噌に使われ,古くは食物を盛るのに利用された。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
ホオノキ
モクレン科ホオノキ属の落葉広葉樹。漢字では朴柏。英名はmagnolia。ホオ、ホオガシワともいう。材質は緻密で均質。軽軟材で、切削などの工作は容易に出来る。狂いは少なく、材の保存性は低い。 漆器素地、版木、製図板、定木材、などが良く知られる。その他、器具材、建築用の装飾材、箱材、家具材などでも使用される。。
出典 リフォーム ホームプロリフォーム用語集について 情報
Sponserd by