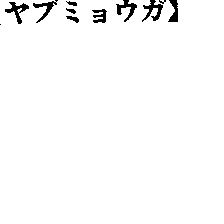ヤブミョウガ
Pollia japonica Thunb.
照葉樹林の林下に生えるツユクサ科の多年草。花序をつけていないときには外見がミョウガによく似ている。本州(関東以西)~九州,朝鮮,中国大陸,台湾に分布する。茎は高さ50~100cmで,上部は円錐花序となる。地下には細い根茎がある。葉は互生し,長さ20~30cm,幅3~6cm,表面はやや光沢があり葉裏に細毛がある。通常,茎の中ほどに集まってつく。ただし無花個体では葉は集まらず,やや2列互生状でミョウガに似る。花は8~9月に咲き,白色で径7~10mm。内花被と外花被が各3枚あり,外花被は宿存性。雄花と雌花があり,雌花には短い不稔のおしべがある。おしべは6本,子房は3室で各室に少数の胚珠がある。果実は球形で径約5mm,青く熟す。液果状で裂開しない。漢方ではヘビや虫にかまれた際や打身のぬり薬の原料とする。このぬり薬は腰痛にも効くといわれる。
ヤブミョウガ属Polliaは十数種からなる小さな群で,東アジアからアフリカにかけての熱帯・亜熱帯域を中心に分布する。
執筆者:矢原 徹一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
ヤブミョウガ
やぶみょうが / 藪茗荷
[学] Pollia japonica Thunb.
ツユクサ科(APG分類:ツユクサ科)の多年草。茎は直立し、数枚の葉を互生するが、おのおのの葉の節は接近しているので輪状にみえる。葉は狭長楕円(だえん)形で長さ20~30センチメートル、幅3~7センチメートル、平行脈があって先はとがり、上面はざらつく。7~9月、茎の先に密錐(みっすい)花序をつけ、全体の高さ0.5~1メートルになる。花序は数段にわたって輪生状に枝をつけ、おのおのの枝は集散状に花をつける。軸と枝には短い毛があってやや粘る。同じ株に両性花と雄花がつく。萼片(がくへん)は3枚、円形で厚みがあり白色。花弁も3枚あり卵形で長さ約5ミリメートル、白色で薄い。雄しべは6本。両性花では花柱が中央に出ているが、雄花では花柱は短く子房も退化して小さい。子房は初め白色で、発達すると茶色になり、熟すると径が約5ミリメートルの球形で光沢のある藍青(らんせい)色になる。液果のようにみえるが子房壁は薄く、のちに不規則に破れる。種子は黒色で表面にいぼ状の突起がある。暖帯林の下に生え、関東地方以西の本州から、九州、および中国大陸南部、台湾に分布する。名は、葉がミョウガと似ているためであるが、ミョウガの葉序は2列互生なので明らかに区別できる。
[山下貴司 2019年6月18日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
ヤブミョウガ(藪茗荷)
ヤブミョウガ
Pollia japonica
ツユクサ科の大型多年草。本州以南および東アジアに分布し,暖地の林内に生える。茎は直立し,花序とともに高さ 50~100cmとなり,根茎は横に伸びる。葉は狭長楕円形で長く,上面はざらつき,下方につく葉は鞘状となる。8~9月に,円錐状に短毛がある集散花序を頂生し,白色の花を数段に輪生状につける。果実は球形,藍紫色に熟し,乾いても裂開しない。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
百科事典マイペディア
「ヤブミョウガ」の意味・わかりやすい解説
ヤブミョウガ
ツユクサ科の多年草。本州(関東以西)〜九州,中国の山野のやや湿ったところにはえる。茎は直立し高さ70cm内外,上部に長楕円形の葉が接近して互生する。夏〜秋,茎の上部に5〜6層になった円錐花序を出し,径8mmほどの白色花を開く。1株に雌花と雄花をつけ,ともに花弁3枚,おしべ6本。果実は球形で,藍(あい)色に熟す。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by