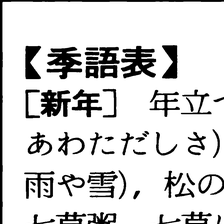精選版 日本国語大辞典 「季語」の意味・読み・例文・類語
き‐ご【季語】
- 〘 名詞 〙 連歌、俳諧、俳句で、四季それぞれの季節感を表わすために、句によみこむ語。季ことば。季のことば。四季のことば。季の題。季題。
季語の補助注記
短歌雑誌「アカネ」で明治四一年(一九〇八)に大須賀乙字が用いたのが最初といわれる。
日本大百科全書(ニッポニカ) 「季語」の意味・わかりやすい解説
季語(主要な季語)
きご
山下一海編
(1)主要な季題(季語)を選んで、小規模の歳時記を構成した。
(2)見出しの季題の下に、(三春)とするのは、春季全般にわたるもの、(初春)(仲春)(晩春)はそれぞれその時期のものであることを示す。夏・秋・冬についても同様である。
(3)見出しの季題の下の[ ]内に、同義・同類の季題を示した。
(4)各季は、歳時記の慣例に従って、時候・天文・地理・生活・行事・動物・植物に分け、それぞれの季題を五十音順に掲げた。
(5)例句の作者名で、俳名だけを記すものは江戸時代の俳人、姓名を記すものは明治時代以降の俳人である。
【春】
時候
暖か(あたたか) (三春)[春暖(しゅんだん)・ぬくし]
暑くもなく、寒くもない、春の快適な温度である。
暖かや背の子の言葉聞きながし <中村汀女>
麗か(うららか) (三春)[うらら・うらうら・麗日(れいじつ)]
春の光のもと、すべてのものがやわらかく明るく輝いてみえるようすをいう。
うららかや猫にものいふ妻のこゑ <日野草城>
啓蟄(けいちつ) (仲春)[地虫穴を出(い)づ・蟄雷・虫出しの雷]
二十四気の一つ。二月節。いまの3月6日ごろにあたる。そのころ蟄虫(冬の間土中に潜み隠れている種々の虫の類)が一斉に動きだして外に出てくるという。蟻(あり)・地虫などの昆虫のほか、蛇・蜥蜴(とかげ)・蛙(かえる)などもいう。
水あふれゐて啓蟄の最上川(もがみがは) <森澄雄>
春暁(しゅんぎょう) (三春)[春の曙(あけぼの)・春曙(しゅんしょ)]
春の明け方には心ときめくような美しさがある。東の空がしだいに明るくなり、暖かい日差しが空の雲を浮かび上がらせる。
春暁の夢のあと追ふ長まつげ <杉田久女>
春昼(しゅんちゅう) (三春)[春の昼]
眠気を誘うようなのんびりした春の昼間。大正時代以降に確立した季語である。
妻抱かな春昼の砂利(じゃり)踏みて帰る <中村草田男>
早春(そうしゅん) (初春)[春早し・春淡し・春浅し・浅き春]
立春ののちも、しばらくはまだ寒さが厳しい。しかし木々の芽の膨らみに、雲のたたずまいに、水の流れに、春の気配が感じられる。
早春の庭をめぐりて門を出(い)でず <高浜虚子>
長閑(のどか) (三春)[のどけさ・のどやか・のどけし]
おだやかに晴れた春の日の、のんびりしたようすをいう。
長閑さや鼠(ねずみ)のなめる角田川(すみだがは) <一茶>
花冷(はなびえ) (晩春)[花の冷え]
桜が咲くころは天候が変わりやすく、急に寒くなることがある。それを花冷という。とくに京都地方の花冷がよく詠まれる。
花冷や障子の外の嵐山(あらしやま) <富安風生>
春(はる) (三春)
立春から立夏の前日までが春。おおよそいまの暦の2月、3月、4月、旧暦の1月、2月、3月にあたる。春は草木が芽吹き、花が咲き、自然がとくに美しい。入学や就職・転勤など、人の生活にも変化が多くみられる。
おもしろやことしの春も旅の空 <芭蕉>
春の暮(はるのくれ) (三春)[春の夕(ゆうべ)・春夕(しゅんせき)]
春の夕暮のこと。ただし古くは暮春、つまり春の終わりの意味に用いた。そのどちらの意味で用いられたかはっきりしない場合も多い。
誰(た)がための低きまくらぞ春の暮 <蕪村>
春の日(はるのひ) (三春)[春日(しゅんじつ)・春陽(しゅんよう)]
春の一日のことでもあり、春の太陽のことでもある。どちらかをさす場合と、どちらとも決めがたい場合がある。いずれにしても、うららかで暖かい感じである。
春の日や暮れても見ゆる東山 <一茶>
春の夜(はるのよ) (三春)[夜半(よわ)の春]
春の夜は、しっとりとして暖かく、ものうい感じである。なにかロマンチックなできごとにでも出会いそうな気がする。
春の夜やぬしなきさまの捨車 <暁台>
春めく(はるめく) (初春)[春きざす・春動く]
早春のまだ寒いなかに、しだいに春らしい兆しがはっきりしてくること。
春めくやどの家も灯を消さずある <滝春一>
彼岸(ひがん) (仲春)[中日(ちゅうにち)・彼岸会(え)・彼岸参(まいり)]
春分と秋分を中日として、その前後3日ずつの7日間をいう。俳句でただ「彼岸」といえば春の彼岸のこと。秋の彼岸は「秋彼岸」という。もともと梵語(ぼんご)の波羅(はら)の訳語で、煩悩を越えた悟りの境地をいう。この時期、寺や墓に参り、仏事を行う。「暑さ寒さも彼岸まで」といわれる快適な季節である。
毎年よ彼岸の入(い)りに寒いのは <正岡子規>
日永(ひなが) (三春)[日永し・永き日・遅日(ちじつ)]
春になって日没が遅くなり、めっきり日が長くなったように感じられることをいう。
鶏(にはとり)の座敷を歩く日永かな <一茶>
行く春(ゆくはる) (晩春)[春の別れ・春の名残(なごり)・春の行方]
春が終わろうとするのを、惜しむ気持ちでいったもの。
行く春を近江(あふみ)の人と惜しみける <芭蕉>
ゆく春やおもたき琵琶(びは)の抱ごころ <蕪村>
余寒(よかん) (初春)[残る寒さ・春寒・春寒し]
寒が明け、立春を過ぎても、なお残る寒さのことをいう。寒さと暖かさが、交互に重ねられて春が深くなるものである。立秋を過ぎた時期の暑さを「残暑」というのに対応する。
関守の火鉢小さき余寒かな <蕪村>
立春(りっしゅん) (初春)[春立つ・春来(きた)る]
中国古来の暦法では、一年を二十四気七十二候に分けて、それを重要な基準としたが、立春はその二十四気の第一の正月節。旧暦では一年の始まりの元日の前後にあたったが、いまの暦では2月の上旬で、節分の翌日。暦のうえではこの日から春になるわけだが、実際にはまだ寒さが厳しいことが多い。
さざ波は立春の譜をひろげたり <渡辺水巴>
天文
淡雪(あわゆき) (三春)[かたびら雪・牡丹(ぼたん)雪]
春になって降る解けやすい雪。大きくぼってりした感じの雪。地に着くとすぐ解けてしまうこともある。うっすらと積もったようでも、やがて解けてしまう。
淡雪や女雛(めびな)は袂(たもと)うち重ね <臼田亜浪>
朧月(おぼろづき) (三春)[月朧・朧]
水蒸気の多い春の夜気のなかで、ぼんやりとやわらかな感じに見える月。
大原や蝶(てふ)の出(い)で舞ふ朧月 <丈草>
ぬかるみに夜風ひろごる朧かな <渡辺水巴>
陽炎(かげろう) (三春)[糸遊(いとゆう)・野馬(やば)・陽焔(ようえん)]
春の日差しに温められて、水蒸気が地面から立ち上るとき、それを通して見える物体や風景がちらちらと揺れ動く現象をいう。
陽炎や名もしらぬ虫の白き飛ぶ <蕪村>
霞(かすみ) (三春)[薄霞・遠霞・朝霞・夕霞]
春、大気中の水蒸気のために、遠くのほうがぼんやり見える。そのようすを、霞がたつ、霞がかかる、霞がたなびく、などという。
春なれや名もなき山の薄霞 <芭蕉>
馬借りてかはるがはるにかすみけり <蓼太>
風光る(かぜひかる) (三春)
うららかな春の日のなかを吹き渡ってくる風を、光るように感じたもの。江戸時代後期以後の季語。
風光る入江のぽんぽん蒸気かな <内田百閒>
春雷(しゅんらい) (三春)[初雷(はつらい)・春(はる)の雷(らい)・虫出しの雷(らい)]
雷は夏季とされているが、とくに春のうちに鳴るものをいう。初めて鳴る雷を「初雷」といい、そのころ地中の虫が地上に出て活動を始めるので「虫出しの雷」という。
あえかなる薔薇(ばら)撰(え)りをれば春の雷 <石田波郷>
菜種梅雨(なたねづゆ) (晩春)
3月下旬から4月上旬にかけて、菜の花の咲くころに、梅雨のようにしとしとと降る雨。
唄(うた)はねば夜なべさびしや菜種梅雨 <森川暁水>
花曇(はなぐもり) (晩春)
桜が咲くころは暖かく、どんよりと曇っていることが多い。それを花曇という。
ゆで玉子むけばかがやく花曇 <中村汀女>
春風(はるかぜ) (三春)[春の風・東風(こち)]
暖かく、やわらかに吹いてくる春の風。東風が多く、雨を伴うこともある。
春風や堤ごしなる牛の声 <来山>
東風(こち)吹くや耳現はるるうなゐ髪 <杉田久女>
春雨(はるさめ) (三春)[春の雨]
細かい雨がしとしとと降り続くこの季節特有の雨。草木の芽を伸ばし、花を開かせる雨といい、ひと雨ごとに暖かくなるともいう。
春雨や蜂(はち)の巣つたふ屋ねの漏(もり) <芭蕉>
春雨や小磯(こいそ)の小貝ぬるる程 <蕪村>
別れ霜(わかれじも) (晩春)[晩霜(ばんそう)・忘れ霜・名残(なごり)の霜]
春の終わり、暖かくなったあとで急に気温が下がることがあり、そのときに発生する霜。「八十八夜の別れ霜」ということばがあるように、八十八夜(立春から88日目)のころ、思いがけずに霜が降りることがあり、そしてそれが最後の霜になるという。
別れ霜昨日こぼした炭の粉に <細見綾子>
地理
苗代(なわしろ) (晩春)[苗代田・代田(しろた)・親田(おやだ)]
稲の種をまいて、田植のための苗を育てる田のこと。幅1メートルから1メートル半ほどの短冊形にくぎって苗代田をつくることが多い。びっしりと緑を敷き詰めたように苗の伸びた苗代田は美しい。
苗代を見て来て心美しき <松本たかし>
春の海(はるのうみ) (三春)[春の湖(うみ)・春の渚(なぎさ)・春の磯(いそ)]
暖かい微風の吹く、穏やかな海である。もちろん春の嵐(あらし)に荒れることもあるが、のどかな明るさに春の海の本意がある。
春の海ひねもすのたりのたりかな <蕪村>
水温む(みずぬるむ) (三春)[春の水]
春になって、池や川の水がなんとなく暖かくなってきたようなようすをいう。
これよりは恋や事業や水温む <高浜虚子>
よれよれにうつる手摺(てすり)や春の水 <野村泊月>
山笑う(やまわらう) (三春)[春の山]
春の山の木々が芽吹き、潤いを帯びて、明るい日の光の下で、笑みを浮かべているように見えることをいう。冬の「山眠る」に対応している。
故郷(ふるさと)やどちらを見ても山笑ふ <正岡子規>
春の山屍(かばね)を埋めて空(むな)しかり <高浜虚子>
雪解(ゆきどけ) (仲春)[雪消(ゆきげ)・雪解道(ゆきげみち)・雪滴(ゆきしずく)]
冬の間降り積もっていた雪国の雪が、春の暖かさによって解け始めること。雪国の雪解は仲春以後である。
ゆきどけや深山(みやま)曇りを啼(な)く烏(からす) <暁台>
ひとつ家の灯の漏れてゐる雪解(ゆきげ)かな <日野草城>
生活
海女(あま) (晩春)[磯(いそ)海女・沖(おき)海女]
海辺では、海女が海に入るのが春のしるしのように思われるから、春の季題とされている。陸からすぐ海に入るのを磯海女、舟で沖に出てから海に入るのを沖海女という。
鮑(あはび)とる海女の垂乳(たれち)をかなしめり <篠田悌二郎>
草餅(くさもち) (仲春)[草の餅・蓬(よもぎ)餅]
蓬の葉をゆでて、餅に搗(つ)き込んだもの。美しい緑色になり、独特の風味が出る。餡(あん)を包んだり、黄粉(きなこ)をまぶしたり、あるいはさっぱりとしょうゆ味で食べたりする。
草餅の濃きも淡(あは)きも母つくる <山口青邨>
汐干(しおひ) (晩春)[汐干狩・汐干潟(しおひがた)・汐干船]
春の彼岸のころは、潮の干満の差が大きく、磯浜(いそはま)が遠く干上がり、時候もよいので、浅蜊(あさり)や蛤(はまぐり)をとりに出かけ、一日を戸外で遊ぶ。それを汐干狩といい、古くからあった習わしである。「汐干」だけでも汐干狩を意味する。
ふり返る女心の汐干かな <蓼太>
春愁(しゅんしゅう) (三春)[春愁(うれ)う・春恨(しゅんこん)・春怨(しゅんえん)・春かなし]
ものうい春に感じる哀愁の思い。そこはかとない愁いもあれば、かなり強い恋情といったものもあろう。
春愁のまぼろしにたつ仏かな <飯田蛇笏>
酌むほどに酔ふほどに春の愁濃き <日野草城>
春眠(しゅんみん) (三春)[春睡(しゅんすい)・春眠し]
春の夜や明け方、眠り心地がよくてなかなか目が覚めないことをいう。中国唐代の孟浩然(もうこうねん)の詩に「春眠暁を覚えず」とあるが、季題としては新しく、近代のもの。
春眠の覚めつつありて雨の音 <星野立子>
凧(たこ) (三春)[紙鳶(いかのぼり)・奴凧(やっこだこ)・凧合戦・凧日和(たこびより)]
凧は正月に揚げたり、5月の節供に揚げる地方もあるが、一般には春の遊びとされた。
山路(やまぢ)来て向ふ城下や凧の数 <太祇>
凧(いかのぼり)きのふの空のありどころ <蕪村>
種蒔(たねまき) (晩春)[種蒔く・種おろし・籾(もみ)蒔く]
稲の種である籾を苗代(なわしろ)に蒔くこと。もともと種蒔というだけで籾を蒔くことを意味したが、近ごろは「物種蒔(ものだねま)く」(花や野菜の種を蒔くこと)と同じ意味で用いることもある。
掛け抱(いだ)く嚢(ふくろ)大きく種蒔くかな <中村草田男>
茶摘(ちゃつみ) (晩春)[一番茶・茶摘女・茶摘唄(うた)・茶山]
飲料用の茶の芽を摘むこと。早いものは4月中旬から摘み始めるが、最盛期は八十八夜(立春から88日目)から2、3週間の間。最初の15日間を一番茶とし、四番茶まである。
山門を出(で)れば日本ぞ茶摘うた <菊舎尼>
摘草(つみくさ) (三春)[草摘む]
のどかな春の一日、野に出て蓬(よもぎ)、芹(せり)、嫁菜(よめな)、土筆(つくし)など食用の野草、あるいは蒲公英(たんぽぽ)、菫(すみれ)、桜草などの草花を摘み集めて遊ぶこと。
つみ草や背(せな)に負ふ子も手まさぐり <太祇>
野焼(のやき) (初春)[野焼く・野火・草焼く・焼野(やけの)]
春の初め、風のない日に野の枯草に火をつけて焼き払う。それによって害虫が駆除され、草の芽生えが促進され、またその灰が草の成長を促すという。
古き世の火の色うごく野焼かな <飯田蛇笏>
野火ゆきて萱(かや)倒れゆくあはれかな <星野立子>
畑打(はたうち) (三春)[畑打つ・畑返(はたけかえ)す・田打(たうち)・耕(たがえ)し]
春の彼岸を過ぎると、農作物の種をまく季節だから、畑を打ち返さなければならない。
動くとも見えで畑打つ男かな <去来>
生きかはり死にかはりして打つ田かな <村上鬼城>
花衣(はなごろも) (晩春)[花見衣・花見小袖(こそで)]
女性が花見に着て行く晴れ着。また一般に桜の花の咲くころに着る女の華やいだ衣服のこともいう。和服をさすのが普通である。
花衣ぬぐやまつはる紐(ひも)いろいろ <杉田久女>
花見(はなみ) (晩春)[花の酒・花人(はなびと)]
桜の花が咲くと、花の名所に出かけ、花の下に花莚(はなむしろ)を広げ、持参の料理や酒を出して楽しむ。ときには酔った人が、歌をうたったり、踊りをおどったりする。
何事ぞ花見る人の長刀(なががたな) <去来>
みな袖(そで)を胸にかさねし花見かな <中村草田男>
ぶらんこ (三春)[鞦韆(しゅうせん)・ふらここ]
現在のぶらんこはとくに春のものと限るわけではないが、中国で昔「鞦韆」といって寒食(かんしょく)の節(冬至から105日目にあたる日、火気を断ち、冷たいものを食べた)の宮廷の女たちの遊戯とされたことによって、春季と定められている。
ふらここの会釈(ゑしゃく)こぼるるや高みより <太祇>
鞦韆は漕(こ)ぐべし愛は奪ふべし <三橋鷹女>
行事
御水取(おみずとり) (仲春)[水取]
奈良東大寺二月堂の行事。修二会(しゅにえ)の行の一つ。3月13日の午前2時ごろ行われる。堂の南階段下の良弁杉(ろうべんすぎ)のもとにある閼伽井屋(あかいや)で、遠く若狭(わかさ)から地中を伝ってきているというお香水を汲(く)み取って堂に運び、仏前に供える。この夜、童子(どうじ)が回廊で振り回す大松明(たいまつ)の火の粉を浴び、お香水をいただけば厄除(やくよ)けになるというので、人々が多く集まる。
水とりや氷の僧の沓(くつ)の音 <芭蕉>
西行忌(さいぎょうき) (仲春)
「願はくは花の下(もと)にて春死なむそのきさらぎの望月(もちづき)のころ」と詠んで釈迦入滅(しゃかにゅうめつ)の日(旧暦2月15日)に死ぬことを望んでいた西行は、文治(ぶんじ)6年(1190)2月16日に河内(かわち)の弘川(ひろかわ)寺に入寂(にゅうじゃく)した。芭蕉が敬慕した歌人だから、俳人にとっても忘れがたい日である。
きさらぎの雲は白しや西行忌 <五十崎古郷>
涅槃会(ねはんえ) (仲春)[涅槃像・寝釈迦(ねじゃか)・仏の別れ・餅花煎(もちばないり)]
旧暦2月15日が釈迦入滅(しゃかにゅうめつ)の日とされていて、その日寺院では涅槃像を掲げ、香華(こうげ)を供えて涅槃会を営む。一般の家では餅花煎や団子などを供物とする。
涅槃会やさながら赤き日の光 <言水>
初午(はつうま) (初春)
二月初午の日に稲荷(いなり)神社や稲荷の祠(ほこら)で行われる祭礼。いまの暦の2月に行われることが多いが、もともとは旧暦の2月なので、いまも旧暦によっている地方がある。
初午や煮しめてうまき焼豆腐 <久保田万太郎>
花祭(はなまつり) (晩春)[仏生会(ぶっしょうえ)・灌仏会(かんぶつえ)・花御堂(はなみどう)・甘茶]
4月8日が釈迦(しゃか)降誕の日とされていて、その日の祝賀の行事。花御堂に祀(まつ)られた誕生仏に甘茶の湯を灌(そそ)ぎかける。
花まつり母の背ぬくし風甘し <楠本憲吉>
針供養(はりくよう) (初春)[針祭・針納(おさめ)]
縫い針を使うのを忌みつつしみ、一年中の折れ針を各地にある淡島(あわしま)神社(淡島堂)に納めて供養する日。関東では2月8日だが、関西以西では12月8日がその日とされる。東京では浅草寺(せんそうじ)境内の淡島社が針供養で知られている。
昼月の淡島さまや針供養 <赤星水竹居>
雛祭(ひなまつり) (仲春)[雛・ひいな・雛人形・桃の酒]
3月3日の桃の節供。もともと三月上巳(じょうし)の節供。女の子のための節供とされている。いまの暦の3月3日に行われることが多いが、桃の花の季節にはまだ早いことから、地方によっては、旧暦に従ったり、4月3日に行ったりしている。
花咲かぬ片山陰も雛祭 <一茶>
遍路(へんろ) (三春)[遍路宿・遍路笠(がさ)・四国巡(めぐ)り]
弘法大師(こうぼうだいし)が巡ったという四国の八十八か所の寺を巡拝する人。白衣を身に着け、笠をかぶり、杖(つえ)を手にする。春の季題と定められたのは大正期の高浜虚子以来のこと。
道のべに阿波(あは)の遍路の墓あはれ <高浜虚子>
動物
鶯(うぐいす) (三春)[初鶯(はつうぐいす)・春告鳥(はるつげどり)]
古来、梅に鶯という取り合わせで、春の先駆けの鳥として親しまれている。俳句でも春を知らせる鳥として詠まれるが、その鳴き声だけでなく、さまざまな姿態が取り上げられる。
鶯や餅(もち)に糞(ふん)する縁の先 <芭蕉>
蚕(かいこ) (晩春)[毛蚕(けご)・透蚕(すきご)・捨蚕(すてご)・蚕飼(こがい)]
絹糸をとるために飼う。晩春に孵化(ふか)し、桑の葉を食べて成長する。孵化したての幼虫を「毛蚕」、4回脱皮して体が透き通っているのを「透蚕」、病気になって捨てられるのを「捨蚕」という。「繭(まゆ)」「蚕蛾(こが)」などは夏季。
宵(よひ)からの雨に蚕の匂(にほ)ひかな <成美>
怠け蚕(ご)といはれ遅れ蚕首振れる <西本一都>
帰る雁(かえるかり) (仲春)[帰雁(きがん)・雁の別れ・行く雁]
秋に北方から渡来した雁は、3月ごろ北に帰る。秋分に来て春分に帰るともいわれる。
帰る雁田ごとの月の曇る夜に <蕪村>
蝌蚪(かと) (晩春)[お玉杓子(たまじゃくし)・蛙(かえる)の子・蛙生(うま)る]
池や水たまりに、ときには真っ黒になるほど群がって泳いでいる蛙の子。
飛び散つて蝌蚪の墨痕淋漓(ぼっこんりんり)たり <野見山朱鳥>
蛙(かわず) (三春)[かえる・初蛙(はつかわず)・遠蛙(とおかわず)・夕蛙]
冬眠していた蛙は、春から夏にかけて田んぼなどでうるさいほどに鳴き立てる。蛙の出始める時期をとって春の季題とする。
古池や蛙とび込む水の音 <芭蕉>
雉(きじ) (三春)[きぎす・きぎし・雉子(きじ)]
草原、雑木林などにすむ日本特有の鳥。雄の羽色は複雑で、尾は長く美しい。雄はケンケンと勇ましく鳴き、雌はチョンチョンと可憐(かれん)に鳴く。鳴き声のあわれさから春の季題とされる。親子の情愛の深い鳥とされており、野を焼いても親鳥は子を思って飛び立たずに焼け死んでしまうという。
父母のしきりに恋し雉子(きじ)の声 <芭蕉>
囀(さえずり) (三春)[囀る]
春、さまざまな鳥が楽しくさえずるのをいう。春の季節の喜びの声である。
囀の高まり終り静まりぬ <高浜虚子>
白魚(しらうお) (初春)[白魚舟(しらおぶね)・白魚汲(しらおく)む・白魚汁]
6、7センチメートルの半透明の細い魚。2月から4月にかけて川や湖にさかのぼり、そのころが美味。素魚(しろうお)は別種。
白魚やさながら動く水の色 <来山>
蝶(ちょう) (三春)[初蝶・紋白蝶(もんしろちょう)・鳳蝶(あげはちょう)・黒あげは]
日本の昆虫のなかでもっとも美しい。春から夏にかけて山野や、ときには都会地でもみかけるが、俳句では春のものとされている。
蝶一つ現(あ)れて華やぐ道となる <八木絵馬>
燕(つばめ) (仲春)[つばくろ・つばくらめ・初燕(はつつばめ)]
3、4月ごろ南方から渡来し、10月ごろ帰って行く鳥。二つに割れた長い尾をもち、すばやい飛び方に特色がある。
春すでに高嶺(たかね)未婚のつばくらめ <飯田龍太>
猫の恋(ねこのこい) (初春)[猫の妻・浮かれ猫・孕(はら)み猫]
猫は早春のころに異性を求めることが多いという。一匹の牝(めす)を数匹の牡(おす)が争って、異様な声をあげたりする。
うらやまし思ひ切る時猫の恋 <越人>
蛤(はまぐり) (三春)[蛤鍋(はまなべ)・焼蛤・蒸蛤]
浅海の砂の中にいる貝。美味で、婚礼や雛祭(ひなまつり)などの料理によく用いる。貝殻はしっかりしているので、薬の容器や玩具(がんぐ)にされる。
蛤の荷よりこぼるるうしほかな <正岡子規>
雲雀(ひばり) (三春)[揚雲雀(あげひばり)・初雲雀・告天子(こくてんし)・叫天子(きょうてんし)]
空高く舞い上がり、しばらくさえずったあと、一直線に落下するように地上に降りる。春、もっとも人々に親しまれている小鳥。
雲雀聞き聞き牛に眠れる男かな <言水>
若駒(わかごま) (晩春)[春駒・春の馬]
子馬が生まれるのは3月から7月にかけてだが、とくに春の子馬が目につくところから春季とされる。駒は馬の子、また若馬のことだが、馬と同じ意味にも用いる。
若駒の親にすがれる大き眼(め)よ <原石鼎>
植物
梅(うめ) (初春)[白梅(はくばい)・紅梅(こうばい)・梅林・夜の梅・探梅(たんばい)]
早春、他の花に先駆けて咲き、香が高く、清楚(せいそ)であるため、古来詩歌によく詠まれる。
梅一輪(いちりん)一輪ほどの暖かさ <嵐雪>
白梅のあと紅梅の深空(みそら)あり <飯田龍太>
紫雲英(げんげ) (仲春)[蓮華草(れんげそう)・げんげん・五形花(げげばな)]
春の田んぼ一面に咲く紅紫色の蝶(ちょう)形の小花。秋の末に田の水を干して種をまき、緑肥とされるが、野生化もしている。
桜島いまし雲ぬぎ紫雲英の上 <山口青邨>
木の芽(このめ) (三春)[木の芽時・芽立(めだち)・芽吹く]
春に芽吹く木々の芽。木によって時期に遅速があり、芽の形もさまざまである。柳の芽、楓(かえで)の芽、蔦(つた)の芽など、とくに美しい。
大原や木の芽すり行く牛の頬(ほほ) <召波>
桜(さくら) (晩春)[朝桜・夕桜・夜桜]
日本の花の代表とされる。一斉に花開き、数日咲き誇ると潔く散ってしまうところが、とくに愛される。
木(こ)のもとに汁も膾(なます)も桜かな <芭蕉>
見かへればうしろを覆(おほ)ふ桜かな <樗良>
桜濃くジンタかするる夜空あり <石橋秀野>
菫(すみれ) (三春)[壺(つぼ)すみれ・姫すみれ・菫草(すみれぐさ)・相撲取草(すもうとりぐさ)・一夜草(ひとよぐさ)]
山野に自生する草花。鋸歯(のこぎりば)の葉の間から柄(え)が出て、紫色の可憐(かれん)な花をつける。子供が二つの花を引っかけ、引っ張って闘わせるので「相撲取草」という。
山路(やまぢ)来て何やらゆかしすみれ草 <芭蕉>
芹(せり) (三春)[芹摘(せりつみ)・田芹(たぜり)・根白草(ねしろぐさ)]
小川のへりや田の畦(あぜ)など、浅い水のきわに生える。葉や根が香り高く、春の七草の一つ。
芹の中小雀(こすずめ)水を浴びにけり <岡本癖三酔>
竹の秋(たけのあき) (晩春)[竹の秋風]
春の終わり近くになると、地中の筍(たけのこ)を育てるために地上の竹の葉は黄ばんで落ちる。それが他の草木の秋のようすに似ているのでいう。
夕方や吹くともなしに竹の秋 <永井荷風>
蒲公英(たんぽぽ) (三春)[鼓草(つづみぐさ)・ふじな・田菜(たな)]
地面に張り付いたように生えた葉の間から、10センチメートルほどの茎が出て花をつける。黄色の花が普通だが、西日本地方には白い花も見られる。
蒲公英がまだ日に染まず草の中 <原子公平>
土筆(つくし) (仲春)[つくしんぼ・つくづくし・筆の花]
杉菜(すぎな)の胞子茎(ほうしけい)で、春の野や畦(あぜ)や堤などの雑草の間に頭を出す。摘み取って和(あ)え物や酢の物にして食べる。
土筆摘む野は照りながら山の雨 <島田青峰>
躑躅(つつじ) (晩春)[山躑躅・岩躑躅・大紫(おおむらさき)]
各地に自生し、また庭に植えられる。花は漏斗(ろうと)状の五つに裂けた形で、紅、淡紅、紫、白などさまざまな品種がある。こんもりとした低木が普通だが、まれには小高木となる。
花びらのうすしと思ふ白つつじ <高野素十>
椿(つばき) (三春)[白(しろ)椿・紅(べに)椿・藪(やぶ)椿・落(おち)椿]
北海道を除く各地に自生し、また多くの園芸種がある。肉の厚い濃艶(のうえん)な花が、つやのある葉の間に咲き、花全体がぽとりと地に落ちる。
赤い椿白い椿と落ちにけり <河東碧梧桐>
濡れてゐし雨の椿をいま憶(おも)ふ <橋本鶏二>
薺の花(なずなのはな) (三春)[ぺんぺん草・三味線草(しゃみせんぐさ)]
単に「薺」といえば、春の七草の一つで新年の季題。春、白い小さな四弁の花を咲かせる。花が咲き、実をつければ、その実が三味線の撥(ばち)のような形をしているところから「ぺんぺん草」「三味線草」という。
よくみれば薺花さく垣ねかな <芭蕉>
菜の花(なのはな) (晩春)[菜種の花・花菜(はなな)]
春の菜の花畑には一面に黄色の花が咲く。菜種をとるために栽培するのだが、食用には花の咲く前のつぼみを用い、花菜という。
菜の花や月は東に日は西に <蕪村>
花(はな) (晩春)[花の香(か)・花の雲・花盛り]
桜の花のこと。「桜」といわずに「花」といえば、いっそう豊かで華やかな感じがある。
これはこれはとばかり花の吉野山 <貞室>
花の雲鐘は上野か浅草か <芭蕉>
蕗の薹(ふきのとう) (初春)[蕗の芽・蕗の花・蕗味噌(ふきみそ)]
山野に自生し、また庭の隅などにある蕗の花芽。土を割って出てきて、薄緑色の卵形をしている。蕗みそや、みそ汁に刻んで入れて食べる。ほろ苦い風味が春の味わいである。
庭土の肌のうるみや蕗の薹 <小宮豊隆>
藤(ふじ) (晩春)[藤棚・藤の花・藤波・山藤]
山野に自生し、また藤棚をつくって栽培する。蔓(つる)性の落葉低木。薄紫また白の花房をつける。
くたびれて宿かる頃(ころ)や藤の花 <芭蕉>
桃の花(もものはな) (晩春)[白桃(しらもも)・緋桃(ひもも)・桃林(とうりん)・桃の村]
淡紅色の花が多いが、濃紅色や白色もある。果実をとるため桃畑に栽培されるが、観賞用として庭園にも植えられる。
船頭の耳の遠さよ桃の花 <支考>
柳(やなぎ) (晩春)[青柳(あおやぎ)・糸柳(いとやなぎ)・門柳(かどやなぎ)・遠柳(とおやなぎ)]
芽吹いてまもなくの薄緑の葉をつけた柳が美しいので、春の季題になっている。
月もややほのかに青き柳かな <青蘿>
山吹(やまぶき) (晩春)[八重山吹・濃(こ)山吹・白山吹]
山野に自生するが、庭園にも栽培する。青い茎が叢生(そうせい)し、黄または白の花が咲く。
ほろほろと山吹散るか滝の音 <芭蕉>
蓬(よもぎ) (三春)[餅草(もちぐさ)・艾草(もぐさ)・さしも草(ぐさ)]
山野に自生し、若葉は柔らかく、香気があり、草餅(くさもち)の材料になる。乾燥して灸(きゅう)の艾(もぐさ)もつくる。
蓬萌(も)ゆ憶良(おくら)旅人(たびと)に亦(また)吾(われ)に <竹下しづの女>
若草(わかくさ) (晩春)[草若し]
春、萌(も)え出したばかりの柔らかく若々しい草。
若草や水を隔てて駒(こま)の声 <麦水>
若布(わかめ) (三春)[若布刈(わかめかり)・めかり・若布汁]
日本沿岸の代表的な食用海藻。春、刈り取って干して製品とする。春のわかめは色も鮮やかで美しい。
みちのくの淋代(さびしろ)の浜若布寄す <山口青邨>
蕨(わらび) (仲春)[初蕨(はつわらび)・早蕨(さわらび)・蕨汁]
山野に自生しているシダ類の一種で、春になると、地下茎から小さなこぶしを握ったような新芽が伸び出してくる。姿も可憐(かれん)であり、食用にしてうまい。
負ふた子に蕨折りては持たせける <暁台>
【夏】
時候
秋近し(あきちかし) (晩夏)[秋隣(あきとなり)・秋迫る・来(こ)ぬ秋]
夏の終わり、さすがの暑さも盛りを越したころ、秋もまもないと感じられることをいう。
秋ちかき心の寄るや四畳半 <芭蕉>
暑し(あつし) (三夏)[暑(しょ)・暑(あつ)さ・暑気(しょき)・暑熱(しょねつ)]
夏の暑さをいう。「暑(しょ)」と読めば、小暑(しょうしょ)・大暑(たいしょ)の時節をも意味する。
大蟻(おほあり)の畳をありく暑さかな <士朗>
夏至(げし) (仲夏)
二十四気の一つ。いまの暦の6月21、22日ごろにあたる。北半球では一年中で太陽がもっとも高くなり、いちばん日が長い。
池水のにほひに夏至の夜風かな <武田鶯塘>
初夏(しょか) (初夏)[夏の初(はじめ)・孟夏(もうか)・首夏(しゅか)]
夏の初めは、暑さもまだそれほどのことはなく、新緑を吹き渡ってくる風のさわやかな季節である。
初夏の卓(たく)朝焼けのして桐(きり)咲けり <飯田蛇笏>
涼し(すずし) (三夏)[涼味(りょうみ)・朝涼(あさすず)・夕涼(ゆうすず)・涼風]
夏の暑さのなかでは、わずかの涼しさでもうれしいものである。
此(この)あたり目に見ゆるものはみなすずし <芭蕉>
夏(なつ) (三夏)
立夏から立秋の前日までが夏。おおよそいまの暦の5月、6月、7月、旧暦の4月、5月、6月にあたる。さわやかな新緑の時期から蒸し暑い梅雨を経て、熱暑の期を迎える。若者にとってはうれしい季節である。
描きて赤き夏の巴里(パリ)をかなしめる <石田波郷>
晩夏(ばんか) (晩夏)[季夏(きか)]
夏の終わりであるが、なお暑い日が続く。しかし日差しのぐあいも盛夏とは違うし、草木のようすもどこか異なっている。
オリオンが出て大いなる晩夏かな <山口誓子>
短夜(みじかよ) (三夏)[明易(あけやす)し・明急ぐ・明早し]
春分の日を過ぎて、夜が昼よりも短くなり、夏至(げし)の日がもっとも短い。夏の夜は暮れが遅く、夜明けが早いので、いかにも短い感じがする。
短夜や蘆間(あしま)流るる蟹(かに)の泡 <蕪村>
明易き腕(かひな)ふと潮(しほ)匂(にほひ)ある <中塚一碧楼>
麦の秋(むぎのあき) (初夏)[麦秋(むぎあき)・麦秋(ばくしゅう)]
「あき」はもともと果実や穀物が成熟し、収穫されるときのことをいうから、「麦の秋」とは麦の収穫期のこと。収穫の喜びと安堵(あんど)の気持ちがある。旧暦4月の異名でもある。
麦の秋大利根(おほとね)ゆるく流れたり <小絲源太郎>
夜の秋(よるのあき) (晩夏)[夜(よ)の秋]
夏も終わり近くなると、夜はぐっと涼しくなり、早くも秋がきたかと感じることがある。
西鶴(さいかく)の女みな死ぬ夜の秋 <長谷川かな女>
立夏(りっか) (初夏)[夏立つ・夏来(く)る]
二十四気の一つの四月節。穀雨(こくう)ののち15日。いまの暦では5月5、6日ごろ。この日から夏になるわけだが、まだ春の気分も残っている。
夏立つや衣桁(いかう)にかはる風の色 <也有>
天文
青嵐(あおあらし) (三夏)[青嵐(せいらん)・夏嵐(なつあらし)]
青葉のころに吹き渡る強い風。「南風」よりやや強い風である。「南風」は生活語だが、これは文学的な用語。
野を庭にして青嵐十万家(か) <蓼太>
夏嵐机上の白紙飛び尽くす <正岡子規>
炎天(えんてん) (晩夏)[炎日(えんじつ)・日盛(ひざかり)・炎天下]
晴れ上がった夏の日の、燃え上がるような空。「エンテン」という強い語感が、灼(や)け付くような暑さにふさわしい。
炎天を来て燦然(さんぜん)と美人たり <久米三汀>
雲の峰(くものみね) (三夏)[入道雲・積乱雲・夕立雲(ゆうだちぐも)]
夏の強い日差しによって生ずる上昇気流にのって、むくむくとわき上がる雲。それが崩れて雷雲が生じ、夕立を降らせる。
しづかさや湖水の底の雲の峰 <一茶>
薫風(くんぷう) (三夏)[風薫(かお)る・風の香(か)]
木々の緑のなかを吹いてきて、かぐわしく匂(にお)うように感じられる風。「青嵐(あおあらし)」よりも穏やかな風である。
薫風や下戸(げこ)に戻りし老(おい)が宿 <太祇>
風と風ぶつかりあへり薫るため <鷹羽狩行>
五月雨(さみだれ) (仲夏)[五月雨(さつきあめ)]
もともと梅雨期の雨のことだが、「五月」の語に引かれて、いまの暦の感覚で、梅雨よりすこし前の雨をいうこともある。
五月雨に鳰(にほ)の浮巣を見に行(ゆか)む <芭蕉>
五月雨や大河を前に家二軒 <蕪村>
梅雨(つゆ) (仲夏)[梅雨(ばいう)・ついり・梅(うめ)の雨]
暦のうえでは立春から135日目、いまの暦の6月11、12日ごろの入梅の日から30日間をいい、またそのころの長雨そのものが梅雨である。
梅雨(つゆ)見つめをればうしろに妻の立つ <大野林火>
夏の月(なつのつき) (三夏)[月涼し]
夏の夜空の月は涼しげだが、月の下の街なかはむし暑いこともある。短夜の月だから、どこかはかなげでもある。
市中(いちなか)はものの匂(にほ)ひや夏の月 <凡兆>
虹(にじ) (三夏)[虹の輪・虹の橋・朝虹・夕虹]
夏、夕立のあとなどに現れる半円形の色帯。普通の虹の色は、内側から、菫(すみれ)色・藍(あい)色・青・緑・黄・橙(だいだい)色・赤の順。俗に朝虹が立てば雨、夕虹が立てば晴という。季語となったのは大正時代以降。
虹立ちて忽(たちま)ち君の在(あ)る如(ごと)し <高浜虚子>
旱(ひでり) (晩夏)[旱魃(かんばつ)・旱天(かんてん)・旱畑(ひでりばた)・大旱(たいかん)]
夏の盛りに雨が少なく、晴天が続くと、田や池や小川の水が干上がり、田の面はひび割れして、作物も枯れてしまう。都会も水不足になり、水道も断水したりする。近代以降の季語。
汽罐車(きかんしゃ)の車輪からからと地の旱 <山口誓子>
南風(みなみ) (三夏)[南風(みなみかぜ)・南風(なんぷう)・大南風(おおみなみ)・南風(はえ)]
夏の季節風。主として関東以北で「みなみ」といい、近畿以西で「はえ」という。「大南風」はとくに強い南風。
日もすがら日輪(にちりん)くらし大南風 <高浜虚子>
夕立(ゆうだち) (三夏)[ゆだち・白雨(はくう)]
夏の午後の激しい驟雨(しゅうう)。多く雷を伴い、1時間くらいで晴れ上がる。
夕立に走り下(くだ)るや竹の蟻(あり) <丈草>
夕焼(ゆうやけ) (晩夏)[ゆやけ・大夕焼(おおゆやけ)・夕焼雲(ゆうやけぐも)]
太陽が西に没してからも、しばらく空が赤黄色に染まっていることがある。夏に限ったものではないが、夏の終わりの日照り続きのころに多く見られ、いかにも夏にふさわしい景色だから夏の季語とされている。近代以降の季語。
夕焼や思ひかへして貝拾ふ <山口誓子>
雷(らい) (三夏)[雷(かみなり)・いかずち・はたたがみ・迅雷(じんらい)]
ほかの季節にもあるが、夏にもっとも多い。多くは雨を伴う。江戸時代にも季語として用いられているが、近代になってから好んで俳句につくられるようになった。
雷近く林相翳(かげ)を深うしぬ <臼田亜浪>
地理
青田(あおた) (晩夏)[青田風(あおたかぜ)・青田面(あおたのも)・青田売]
青々と葉の伸びた稲田。穂が出るのもまもなくである。
傘さしてふかれに出(い)でし青田かな <白雄>
清水(しみず) (三夏)[苔清水(こけしみず)・岩清水・泉(いずみ)]
見るからに冷たそうな、清らかな水である。もともとは夏と限るものではないが、その冷たい心地よさによって、夏の季語とされている。
落ち合うて音なくなれる清水かな <蕪村>
滝(たき) (三夏)[滝壺(たきつぼ)・滝見・瀑布(ばくふ)]
滝は一年中かかっているが、水量も多く、いかにも涼しげであるところから、夏の季語とされる。近代になってからの季語。
滝の上に水現れて落ちにけり <後藤夜半>
夏野(なつの) (三夏)[青野(あおの)・卯月野(うづきの)・五月野(さつきの)]
強い日差しの下で、草いきれのたつ夏の野原。「卯月野」「五月野」はいずれも旧暦により、新緑の野、また梅雨のころの野のことをいう。
馬ぼくぼく我を絵に見る夏野かな <芭蕉>
夏山(なつやま) (三夏)[夏の山・夏嶺(なつね)・青嶺(あおね)]
夏になると山々は緑に覆われる。地域により、また山の高さにより、その緑にもさまざまの濃淡がある。
夏山や吊橋(つりばし)かけて飛騨(ひだ)に入る <前田普羅>
生活
青簾(あおすだれ) (三夏)[玉(たま)簾・簾・絵簾]
細く削った青竹でつくった簾。縁先の軒端にかけて、夏の強い日差しを防いだり、開け放った部屋が見透かされるのを遮ったりするのに用いる。玉簾は美称。
うら表おもてはわきて青簾 <白雄>
汗(あせ) (三夏)[汗ばむ・汗みどろ]
夏の暑いさなか、じっとりと汗ばむこともあれば、玉のような汗が吹き出すこともある。ときには自分の汗臭さが嫌になったりもする。
汗の香に衣ふるはな行者堂 <曽良>
汗臭き鈍(のろ)の男の群に伍(ご)す <竹下しづの女>
袷(あわせ) (初夏)
春の間に着ていた綿入れを、綿の入っていない袷にかえるのは、実にすがすがしいものであった。現在は綿入れを着ることも少なくなったので、袷の清涼感は忘れられてきている。
行く女袷着なすや憎きまで <太祇>
鵜飼(うかい) (三夏)[鵜舟(うぶね)・鵜川(うかわ)・鵜篝(うかがり)・鵜匠(うしょう)]
舟の上から鵜を使って鮎(あゆ)をとる漁法。岐阜市の長良(ながら)川の鵜飼がとくに有名。毎年5月11日から10月12日まで、満月の前後数日を除いて行われるが、俳句では夏季のものとされる。鵜舟には篝火をたき、鵜匠が鵜縄をさばいて鵜を操る。謡曲『鵜飼』以来、悲しく、あわれなものとされている。
おもしろうてやがて悲しき鵜舟かな <芭蕉>
鵜飼の火川底見えて淋(さび)しけれ <村上鬼城>
扇(おうぎ) (三夏)[扇子(せんす)・白扇(はくせん)・扇売(おうぎうり)・末広(すえひろ)]
竹や木を骨にして紙や絹を張り、折り畳み式で、絵や文字を描くことが多い。舞や儀式にも用いるが、俳句では涼を入れるためのものとして、夏季とする。
目に嬉(うれ)し恋君の扇真白(ましろ)なる <蕪村>
泳(およぎ) (三夏)[水泳(すいえい)・水練(すいれん)・海水浴・浮袋]
古く水練は武術の一種とされたが、いまは海や川あるいはプールにおける水泳が、夏のスポーツとして親しまれている。近代になって季題として確立した。
満潮に身を横たへて泳ぎけり <篠原温亭>
蚊帳(かや) (三夏)[蚊屋(かや)・古蚊帳(ふるがや)・初蚊帳(はつがや)]
蚊を防ぐために部屋に吊(つ)る。夜、寝るときに用いるのが普通だが、雷を防ぐともいわれて、夕立のおりに吊ったりもした。萌黄(もえぎ)色に染めた麻でつくられたものが多い。近江(おうみ)(滋賀)、丹波(たんば)(京都)、大和(やまと)(奈良)などが主産地。
蚊帳くぐる女は髪に罪深し <太祇>
行水(ぎょうずい) (晩夏)
盥(たらい)に湯を入れ、そこに腰を下ろして汗を流す。庭先や土間などで手軽に行われた。江戸時代になってよくみられたが、季題として確立するのは近代になってから。
行水も日まぜになりぬ虫の声 <来山>
行水の女にほれる烏(からす)かな <高浜虚子>
草刈(くさかり) (三夏)[草刈る・草刈女(くさかりめ)・草刈籠(かご)]
家畜の飼料や肥料の原料とするために雑草を刈ること。涼しい朝のうちに作業をすることが多い。近代になって確立した季題。
草刈女行き過ぎしかば紺(こん)匂(にほ)ふ <軽部烏頭子>
更衣(ころもがえ) (初夏)
昔は旧暦4月朔日(ついたち)、綿入れを脱いで袷(あわせ)になることをいったが、厳密にその日と限らなくとも、一般に、春の衣から夏の衣にかえることをいう。夏の衣から秋の衣にかえることは「秋の更衣」という。
御手討(おてうち)の夫婦(めをと)なりしを更衣 <蕪村>
新茶(しんちゃ) (初夏)[走り茶]
その年初めて摘んで製造した茶。初夏のころ売り出され、香りが高くて喜ばれる。「茶摘」は八十八夜(立春から88日目)のころだから晩春、「新茶」は初夏とされる。
宇治に似て山なつかしき新茶かな <支考>
鮓(すし) (三夏)[鮨(すし)・鮓漬ける・鮓桶(すしおけ)・鮒鮓(ふなずし)]
鮓はもともと魚類の保存食で、魚を飯にまぶして漬け込むことによって、発酵して酸味を生ずるようにしたもの。江戸時代後期になって、江戸では握り鮨が行われるようになった。発酵させてつくるなれ鮨が、夏の保存食になるところと、その味わいの清涼感から、夏の季語とされた。
寂寞(じゃくまく)と昼間を鮓のなれ加減 <蕪村>
納涼(すずみ) (晩夏)[涼(すず)む・夕涼み・涼み台]
夏の夕方から夜にかけて、暑さを避けるために、縁側に出たり、戸外の水辺や風通しのいい所をそぞろ歩いたりする。
立ありく人にまぎれて涼みかな <去来>
田植(たうえ) (仲夏)[田植唄(うた)・苗取(なえとり)・早乙女(さおとめ)]
稲の苗を田に植え付ける作業。もともと村の共同作業で、そのとき皆で歌うのが田植唄。苗代(なわしろ)から苗をとる苗取は普通男性の仕事で、苗を田に植えるのは女性の仕事とされた。田植をする女性を早乙女という。
湖の水かたぶけて田植かな <几董>
簟(たかむしろ) (三夏)[籐筵(とうむしろ)・蒲莚(がまむしろ)・花茣蓙(はなござ)]
竹を細く削って莚のように編んだ敷物。夏季、涼をよぶために用いる。籐を編んだのが籐筵、蒲を編んだのが蒲莚。
細脛(ほそはぎ)に夕風さはる簟 <蕪村>
心太(ところてん) (三夏)[心天(ところてん)・石花菜(ところてん)・こころぶと]
天草(てんぐさ)を原料とした半透明の涼しげな食べ物。冷たい水に冷やしておき、心太突きで突き出して、酢じょうゆや蜜(みつ)などをかけて食べる。
心太逆(さか)しまに銀河三千尺 <蕪村>
花火(はなび) (晩夏)[仕掛花火・遠花火・手花火]
古く花火は盂蘭盆(うらぼん)に行われるものであったから、秋のものとされていたが、近代になって東京などでは盆が新暦で行われ、また夏の川開きなどでも欠かせぬものとなったことから、夏の季題としての感じが強くなった。子供の遊びの手花火はもともと夏のものである。
花火尽きて美人は酒に身投げけん <几董>
手花火は面輪(おもわ)面輪を廻り消ゆ <石原八束>
冷麦(ひやむぎ) (三夏)[冷(ひや)し麦(むぎ)・切麦(きりむぎ)]
小麦粉を原料とした細い麺(めん)を、冷水または氷で冷やして食するもの。うどんよりも細い。
冷麦の箸(はし)をすべりてとどまらず <篠原温亭>
虫干(むしぼし) (晩夏)[土用干(どようぼし)・曝書(ばくしょ)・虫払い]
土用の晴れ上がった日、衣類や書籍などを陰干しにし、カビや虫の害を防ぐ。古くは寺や神社の宝物の虫払いをする行事であった。書物の虫干をとくに曝書という。
虫干や甥(をひ)の僧訪ふ東大寺 <蕪村>
浴衣(ゆかた) (三夏)[湯帷子(ゆかたびら)・初(はつ)浴衣・藍(あい)浴衣]
入浴のあとなど素肌に着るもので、木綿の白地に型染めをしたものが多い。江戸時代でも季語であったが、近代になってからの作例が多い。
老が身の着かへて白き浴衣かな <村上鬼城>
行事
端午(たんご) (初夏)[菖蒲(しょうぶ)の節供・菖蒲(あやめ)の日]
5月5日を端午節供といい、男子の節供とする。邪気を払うため菖蒲を軒に挿し、男子のある家では鯉幟(こいのぼり)を上げ、武者人形を飾る。もともと宮中の節会(せちえ)であったが、江戸時代になって武家から民間に定着した。地方によっては旧暦、またひと月遅れで行われる。
黒松の暮色のなかの端午かな <中山純子>
夏越(なごし) (晩夏)[名越(なごし)の祓(はらえ)・御祓(みそぎ)・茅(ち)の輪(わ)・形代(かたしろ)]
旧暦6月晦日(みそか)は、一年の半分が終わり、夏が終わる日なので、忌みの日として神社で祓(はらえ)が行われる。地方によっては人や牛馬が海や川に入って御祓(みそぎ)をし、また神社に浅茅(あさじ)で茅の輪をつくって人がこれをくぐり祓をする。また白紙を人の形に切り、自分の名を書いて川に流し、穢(けがれ)をはらったりもする。
吹く風の中を魚(うを)飛ぶ御祓かな <芭蕉>
竹さやぎ夏越の星の流れたる <久米三汀>
祭(まつり) (三夏)[神輿(みこし)・山車(だし)・祭笛(まつりぶえ)]
平安時代にはただ祭といって賀茂祭(かもまつり)(葵祭(あおいまつり))をさしたが、俳句では祭というと夏祭を意味する。祭は夏に行われることが多いからである。
草の雨祭の車過ぎてのち <蕪村>
神田川(かんだがは)祭の中をながれけり <久保田万太郎>
動物
鮎(あゆ) (三夏)[年魚(ねんぎょ)・香魚(こうぎょ)・鮎鮨(あゆずし)・鮎狩・鮎釣]
美しい姿の川魚で、塩焼きにして美味。風味が高いので香魚という。川で孵化(ふか)していったん海に入った稚魚は、春、川をさかのぼり、十数センチメートルから20センチメートルほどに成長し、秋にはまた流れを下り下流域で産卵し、衰弱してやがて死ぬ。
鮎くれてよらで過ぎ行く夜半(よは)の門 <蕪村>
鮎釣の腰を真白に水たぎつ <木津柳芽>
蟻(あり) (三夏)[山蟻・蟻の道・黒蟻]
夏の間、勤勉に餌(えさ)を探して、仲間で協力して運ぶ。家の中にも入ってきて、蟻の行列をつくったりする。大きな黒蟻は単独で畳の上を歩き回ることもある。
蟻の道雲の峰よりつづきけん <一茶>
蟻台上に餓(う)ゑて月高し <横光利一>
蚊(か) (三夏)[藪(やぶ)蚊・縞(しま)蚊・蚊柱(かばしら)]
薄暗くなってくると出てきて、人の血を吸う。藪蚊や縞蚊は昼間でも出てくる。夕方、軒先のあたりに柱状に群がっているのを「蚊柱」という。
古井戸や蚊に飛ぶ魚の音闇(くら)し <蕪村>
この家の蚊の多かりし思ひ出(い)で <高野素十>
蛾(が) (三夏)[火取虫(ひとりむし)・燈蛾(とうが)]
形は蝶(ちょう)に似ているが、蝶と違って夜に飛ぶ種類が多い。翅(はね)は蝶より地味で、灯火を慕って室内に入ってくる。
蛾打ち合ふ音にはなれて眠りたる <臼田亜浪>
河鹿(かじか) (三夏)[初(はつ)河鹿・河鹿笛(ぶえ)・河鹿宿(やど)]
渓流にすむ小さな灰色の蛙(かえる)で、夏に雄が玉を転がすような美しい声で鳴く。古くは秋季とされていたが、大正時代以後はその実際の生態によって夏季とされている。
夕まけて河鹿の声ののぼりくる <清崎敏郎>
蝸牛(かたつむり) (三夏)[かたつぶり・ででむし・まいまい]
小さな渦巻の殻を背負い、頭に角(つの)状の触角をもつ蝸牛は、その姿に愛敬(あいきょう)があるので、童謡などにもよく歌われる。
かたつぶり角(つの)ふりわけよ須磨(すま)明石(あかし) <芭蕉>
でで虫の渦かたむきて動き出す <鷹羽狩行>
鹿の子(かのこ) (三夏)[子鹿(こじか)・親鹿(おやじか)・鹿(しか)の子(こ)]
4月中旬から6月中旬にかけて鹿の子が生まれる。茶褐色の体に白い鹿の子斑(まだら)があって美しい。1年目はまだ角(つの)が生えていない。
人を見るこころもとなき鹿の子かな <後藤夜半>
金魚(きんぎょ) (三夏)[金魚玉(だま)・金魚売・金魚鉢(ばち)]
あでやかな姿の金魚はもともとは鮒(ふな)の変種で、室町時代に中国から渡来し、日本で発達した。「金魚玉」は金魚を飼って観賞するための球状のガラスの容器。
いつ死ぬる金魚と知らず美しき <高浜虚子>
金魚玉とり落しなば鋪道(ほだう)の花 <波多野爽波>
蜘蛛(くも) (三夏)[蜘(くも)・蜘蛛の囲(い)・蜘蛛の巣(す)]
多くの種類があるが、網状の巣を張る種類が多く、昆虫類がかかるのを待って捕食する。集団で生まれた蜘蛛の子は、ちりぢりになって独立生活に入る。
小さく赤い蜘蛛手を這(は)えり糸曳(ひ)きて <金子兜太>
蝉(せみ) (晩夏)[蝉時雨(しぐれ)・油蝉(あぶらぜみ)・にいにい蝉]
夏の日にうるさいほどに鳴く。たくさんの蝉が一斉に鳴くのを「蝉時雨」という。蝉取りは夏休みの子供たちの楽しみである。
閑(しづ)かさや岩にしみ入る蝉の声 <芭蕉>
蝉とんで木蔭(こかげ)に入りし光かな <高浜虚子>
蝉時雨蝉の鼓膜は青からむ <磯貝碧蹄館>
蚤(のみ) (三夏)[蚤の跡]
赤褐色の2、3ミリメートルの虫。跳躍力が強い。衣服やふとんの中に入って人の血を吸う。蚤にくわれた跡はたいへんかゆい。
切られたる夢はまことか蚤の跡 <其角>
蠅(はえ) (三夏)[家蠅(いえばえ)・蒼蠅(あおばえ)・五月蠅(さばえ)]
腐敗物や汚物にたかり、また食物に集まり、うるさく飛び回って人に嫌われる。
やれ打つな蠅が手をすり足をする <一茶>
蠅生れ天使の翼ひろげたり <西東三鬼>
初鰹(はつがつお) (初夏)[鰹・松魚(かつお)・鰹売]
江戸では初夏のころ、その年初めての鰹を珍重し、高価であったが無理をしても買い求めた。鎌倉や小田原のあたりで釣られたものが、その日のうちに早飛脚で江戸に運ばれたり、江戸湾外でとれたものが直接舟で江戸に運ばれたりした。
鎌倉を生きて出(い)でけむ初鰹 <芭蕉>
目には青葉山ほととぎす初鰹 <素堂>
鱧(はも) (三夏)[生(いせ)鱧・水(みず)鱧・干(ひ)鱧]
穴子(あなご)に似た形の海の魚で、1メートル以上の大きなものもある。小骨が多いので、骨切りをして料理する。白身の高級魚。瀬戸内海で多くとれ、関西で好んで賞味される。「水鱧」は出始めのころの小さいもの。
丹念に刻み了(をは)んぬ鱧の皮 <青木月斗>
蛇(へび) (三夏)[くちなわ・青大将(あおだいしょう)・山棟蛇(やまかがし)]
夏の山野でよくみかける。たまには庭に出てくることもある。形や動作が不気味なところから人に嫌われるが、日本に生息する多くの種類は無毒であり、鼠(ねずみ)を食べたりするから人にとって有益である。
草むらにうごかぬ蛇の眼(め)と遭ひぬ <長谷川素逝>
蛍(ほたる) (仲夏)[蛍籠(かご)・草蛍(くさぼたる)・蛍売]
夏の夜の水辺を光りながら飛び交う蛍は美しい。古くは腐った草が蛍になるとも思われていた。
草の葉を落つるより飛ぶ蛍かな <芭蕉>
門前に蛍追ふ子や旅の宿 <高浜虚子>
時鳥(ほととぎす) (三夏)[初(はつ)時鳥・山(やま)時鳥]
古来、詩歌によく詠まれている鳥。春に南から渡ってきて、晩秋に南へ帰る。「テッペンカケタカ」とか「ホゾンカケタカ」と鳴くというが、「特許許可局(とっきょきょかきょく)」とも聞きなしている。杜鵑、杜宇、子規、蜀魂、不如帰など多くの書き方があり、俳句にもよく取り上げられる。
ほととぎす大竹藪(やぶ)をもる月夜 <芭蕉>
谺(こだま)して山ほととぎすほしいまま <杉田久女>
植物
青梅(あおうめ) (仲夏)[梅の実・実梅(みうめ)・小梅(こうめ)]
梅の青い実。梅雨(つゆ)に入るころ、梅の木の若葉の陰に太っている。非常に酸味が強い。熟すると黄色くなるが、青いうちにとって梅酒をつくったり、梅干しにしたりする。
青梅に眉(まゆ)あつめたる美人かな <蕪村>
青葉(あおば) (三夏)[青葉若葉]
若葉が生い茂り、さらに青々となったようす。古く青葉は春、あるいは雑(ぞう)とされたが、「青葉若葉」と続けて夏季に用いられるようになった。季題として確立したのは大正時代以降。
青葉揺れうごく光りと影に覚(さ)む <大野林火>
紫陽花(あじさい) (仲夏)[手毬花(てまりばな)・七変化(しちへんげ)]
梅雨(つゆ)どきに咲く毬(まり)状の花。野生の額(がく)紫陽花の園芸種。花が開いてからその色が変化することから、「七変化」「八仙花(はっせんか)」ともいう。
あぢさゐやよれば蚊の鳴く花のうら <暁台>
花二つ紫陽花青き月夜かな <泉鏡花>
あやめ (仲夏)[花あやめ・白あやめ]
剣状の葉の間に、40~50センチメートルの花茎が伸び、紫色の花が咲く。昔のあやめは菖蒲(しょうぶ)(サトイモ科)のことで、いまのあやめ(アヤメ科)や花菖蒲(アヤメ科)とは異なる。
きのふ見し妹(いも)が垣根の花あやめ <暁台>
旅ゆけば古き野の道あやめ咲く <富安風生>
萍(うきくさ) (三夏)[浮草・根無草・かがみぐさ・萍の花]
池・沼・水田などの水面に広がる水草。一面に絨毯(じゅうたん)を敷き詰めたようになることもある。盛夏のころ、淡緑色の小さな花を開く。
うき草や今朝はあちらの岸に咲く <乙由>
卯の花(うのはな) (初夏)[空木(うつぎ)の花・花うつぎ]
空木は枝の多く分岐した1メートル数十センチメートルの落葉低木で、野山や道のほとりに生え、また庭園にも植える。房をなして咲く白色五弁の花は、雅趣があって、古歌に多く詠まれている。
卯の花や彳(たたず)む人の透き通り <麦水>
瓜(うり) (晩夏)
種々の瓜類の総称だが、瓜といえば甜瓜(まくわうり)をさすことが多い。甜瓜は果物がわりとして賞味され、蔬菜(そさい)としても用いられ、漬物にもされる。
朝露によごれて涼し瓜の泥 <芭蕉>
杜若(かきつばた) (仲夏)[燕子花(かきつばた)]
とがった剣状の葉の間に、濃紫の花が咲く。花の姿が燕(つばめ)の飛ぶ姿に似ているから「燕子花」とも書く。古歌にも多く詠まれている。
潮(しほ)ささぬ沢水甘し杜若 <言水>
黴(かび) (仲夏)[青(あお)黴・黴の宿]
夏の高温と湿気で、食物や住居、衣類などに黴が生える。陰気くさくて嫌われる。
黴の宿頭上に橋の音すなり <久米三汀>
百日紅(さるすべり) (仲夏)[百日紅(ひゃくじつこう)]
桃色の花が多いが、黄色や白もある。盛夏のころ咲くが、花期が長く、百日も咲いているように思われる。樹肌がつるりとして、猿でも滑りそうにみえるので「さるすべり」という。古く天竺(てんじく)(インド)から中国を経て渡来したものだという。
女来(く)と帯纏(ま)き出(い)づる百日紅(さるすべり) <石田波郷>
竹落葉(たけおちば) (初夏)[竹の葉散る・笹(ささ)散る]
竹や笹の類は、竹の子が育ち、新葉が生じた初夏のころ古い葉を落とす。
一ひらの竹の落葉のまひしこと <富安風生>
筍(たけのこ) (初夏)[竹の子・たこうな・たかんな]
種々の竹はそれぞれに竹の子を生ずる。とくに孟宗竹(もうそうちく)の子は食用として喜ばれる。煮たり、ゆでたり、筍飯(たけのこめし)に炊いたりする。
竹の子や児(ちご)の歯ぐきの美しき <嵐雪>
常磐木落葉(ときわぎおちば) (初夏)[松葉散る・杉落葉]
松、杉、樫(かし)、椎(しい)、樟(くす)などの常緑樹は、初夏のころ古い葉を落とす。
清滝(きよたき)や波にちり込む青松葉 <芭蕉>
しづかなる音のただ降る椎落葉 <長谷川素逝>
茄子(なす) (晩夏)[初茄子(はつなすび)・茄子漬(なすづけ)]
紫紺色の茄子は色も形も美しく、煮たり、焼いたり、漬物にしたりして、食べ方にも変化が多く、美味である。
珍らしや山を出羽(いでは)の初茄子 <芭蕉>
茄子もぐ手また夕闇(ゆふやみ)に現れし <吉岡禅寺洞>
夏草(なつくさ) (三夏)[青草・夏の草]
夏に生い茂るさまざまの草。『万葉集』の時代には「しげく」「ふかく」「しなえ」「かる」などの枕詞(まくらことば)としても用いた。
夏草や兵(つはもの)どもがゆめの跡 <芭蕉>
夏木立(なつこだち) (三夏)[夏木(なつき)]
幾本も立ち並んでいる夏の樹木。青葉若葉が盛んに茂り、木の下は薄暗いほどである。「夏木」は1本の木。
木啄(きつつき)も庵(いほ)は破らず夏木立 <芭蕉>
撫子(なでしこ) (仲夏)[大和(やまと)撫子・河原撫子・姫撫子]
山野に自生する多年草。秋の七草の一つだが、夏のうちから花を咲かせるので、俳句では夏季とされている。淡紅色または白色の優美な花である。
酔うて寝むなでしこ咲ける石の上 <芭蕉>
合歓の花(ねむのはな) (晩夏)[ねぶの花・花合歓]
合歓は山野に自生し、また庭に植える落葉高木。枝は斜めに張り出し、羽状に分かれた複葉が夜になると閉じるのでこの名がある。ピンク色の刷毛(はけ)状の花が咲く。
象潟(きさかた)や雨に西施(せいし)がねぶの花 <芭蕉>
真(まっ)すぐに合歓の花落つ池の上 <星野立子>
葉桜(はざくら) (初夏)
花が終わり、みずみずしい若葉の茂った桜のこと。江戸時代の中期以後に季題として確立した。
葉ざくらや南良(なら)に二日の泊り客 <蕪村>
葉ざくらに消ゆべき天とうちあふぐ <石橋秀野>
蓮(はす) (晩夏)[蓮の花・蓮華(れんげ)・はちす]
アジア南部の原産というが、池、沼、蓮田などに広く栽培される。水底の泥中から長柄を伸ばして水面に広葉を浮かべ、紅色や白色の美しい花を水の上に開く。
蓮の香や水をはなるる茎二寸 <蕪村>
花茨(はないばら) (初夏)[茨の花・花うばら・野いばらの花]
茨は山野に自生する落葉低木。つる性の枝には多くの刺(とげ)があり、香りの高い白い五弁の花が咲く。
花茨故郷の道に似たるかな <蕪村>
花橘(はなたちばな) (仲夏)[橘の花]
暖地の海に近い山地に自生する。6月ごろ白い花をつけ、古くは実よりも花の香りが賞美された。古歌では昔の恋人の思い出を誘う香りとされている。
駿河路(するがぢ)や花橘も茶の匂(にほ)ひ <芭蕉>
薔薇(ばら) (初夏)[薔薇(そうび)・花薔薇(はなそうび)]
古く渡来した植物で、古歌にも詠まれているが、いまは種々の新種が生み出されている西洋薔薇をさすのが普通である。
薔薇(ばら)剪(き)つて短き詩をぞ作りける <高浜虚子>
向日葵(ひまわり) (晩夏)
北アメリカ原産で、夏の暑い太陽の下、鮮やかな黄色の大形の花を開く。太陽に向かって回るといわれる。
向日葵や炎夏死おもふいさぎよし <飯田蛇笏>
牡丹(ぼたん) (初夏)[ぼうたん・白(はく)牡丹]
豪華な花で、昔から花の王といわれた。その豊麗な感じから富貴草(ふうきそう)といい、また花期がほぼ20日であることから廿日草(はつかぐさ)ともいう。
方百里雨雲寄せぬ牡丹かな <蕪村>
白牡丹といふといへども紅(こう)ほのか <高浜虚子>
麦(むぎ) (初夏)[麦の穂・大麦・小麦]
春の終わりごろ青い穂を出した麦は、初夏のころ黄褐色に成熟して刈り取られる。俳句で麦といえば、初夏の黄熟したもののことである。
つかみ合ふ子供のたけや麦畠(むぎばたけ) <游刀>
子は母と麦の月夜のねむい道 <長谷川素逝>
夕顔(ゆうがお) (晩夏)[夕顔棚]
垣根や夕顔棚につるを伸ばし、夕暮どき、五つに裂けた白い大きな合弁花を開く。翌日の昼間は、しぼんでしまう。はかない感じのなかに趣(おもむき)がある。
夕顔や酔(よう)てかほ出す壁の穴 <芭蕉>
夕顔のひらきかかりて襞(ひだ)ふかし <杉田久女>
百合(ゆり) (初夏)[白百合・鬼百合・山百合]
種々の種類のものが、山野に自生し、また庭に植えられ、切り花にもされる。直立した一つの茎に、一花または数花の美しい花が咲く。
起(た)ち上る風の百合あり草の中 <松本たかし>
若葉(わかば) (初夏)[若葉風・若葉雨・柿(かき)若葉]
初夏の木々のみずみずしい葉。木によって色や輝きが異なっている。椎(しい)若葉、樫(かし)若葉などと木の名につけていうこともある。
絶頂の城たのもしき若葉かな <蕪村>
病葉(わくらば) (晩夏)
夏の青葉のなかで、病変のために茶色や黄白色になった葉。秋の落葉期を待たずに、ほかの葉より先に落ちて朽ちる。
病葉のいささか青み残りけり <野村喜舟>
【秋】
時候
秋(あき) (三秋)
8月8日ごろの立秋から、11月8日ごろの立冬の前日までが秋。木々は紅葉し、秋草の花が咲き、秋風は寂しげである。
くろがねの秋の風鈴鳴りにけり <飯田蛇笏>
秋の暮(あきのくれ) (三秋)[秋夕(あきゆうべ)・秋の夕暮]
古くは秋という季節の終わりを意味したが、芭蕉(ばしょう)のころから、秋の夕暮を意味するようになった。夏に比べると目にみえて日の暮れが早くなり、肌寒く、わびしげである。
此(こ)の道や行く人なしに秋の暮 <芭蕉>
秋の日(あきのひ) (三秋)[秋日(あきび)・秋日向(ひなた)]
秋の一日のこと。また秋の太陽のこともいう。そのどちらとも決められないような使い方もする。日差しは案外強く、日の暮れは早い。
白壁にかくも淋(さび)しき秋日かな <前田普羅>
秋深し(あきふかし) (晩秋)[秋更(ふ)くる・秋闌(あきたけなわ)]
秋がすっかり深まったことをいう。秋のあわれが極まる。
秋深き隣は何をする人ぞ <芭蕉>
朝寒(あささむ) (晩秋)[朝寒し]
秋も深くなると、朝のうちはまるで冬のような寒さを感じることがある。
朝寒や関の扉(とびら)の開く音 <蝶夢>
九月尽(くがつじん) (晩秋)
旧暦9月の末日、つまり秋の終わりである。いまの暦では11月の初めごろにあたるが、現在は9月の終わりのことをいう場合が多い。「尽」に名残(なごり)を惜しむ気持ちがある。
九月尽遙(はる)かに能登(のと)の岬(みさき)かな <暁台>
爽か(さわやか) (三秋)[秋爽(しゅうそう)・爽気(そうき)・爽(さわ)やぐ]
夏から秋になると、温度が下がり、空気も澄んで乾いてきて、いかにもさわやかな感じがする。そのため秋の季題とされている。
爽かに日のさしそむる山路かな <飯田蛇笏>
残暑(ざんしょ) (初秋)[秋暑(しゅうしょ)・秋暑し]
秋になっても、彼岸のころまでは暑さが残っている。いったん涼しくなってからぶり返す暑さは、耐えがたいものがある。
牛部屋に蚊の声闇(くら)き残暑かな <芭蕉>
秋あつし鏡の奥にある素顔 <桂信子>
冷まじ(すさまじ) (晩秋)
秋の終わりごろの、寒々として、わびしげなようすをいう。
冷まじや胸先走る濁り川 <角川源義>
二百十日(にひゃくとおか) (仲秋)[厄日(やくび)・二百二十日(にひゃくはつか)]
立春から数えて210日目は、季節の変わり目にあたって、暴風雨がやってくることが多い。いまの暦の9月1日か2日ごろにあたる。農家では厄日として恐れている。その10日後の二百二十日も暴風雨がくることの多い厄日とされている。
眉(まゆ)に飛ぶ天竜しぶき厄日過ぐ <秋元不死男>
肌寒(はださむ) (晩秋)
秋もなかばを過ぎて、冷気が肌に寒々と感じられるようになったこと。
肌寒や霧雨暮るる馬の上 <素丸>
初秋(はつあき) (初秋)[初秋(しょしゅう)・新秋・孟秋(もうしゅう)]
秋の初めのころ。残暑のなかにも、吹いてくる風には澄んだ秋の気配が感じられる。
初秋や小雨ふりこむ膳(ぜん)の上 <成美>
冷やか(ひややか) (仲秋)[ひやひや・冷ゆる]
秋になって、冷気を覚えること。直接肌に触れる感じでもあり、なんとなくそのように感じられることもいう。
ひやひやと壁をふまえて昼寝かな <芭蕉>
冷やかや人寝静まり水の音 <夏目漱石>
身に入む(みにしむ) (三秋)
秋の気配が身にしみるように感じられること。あわれな感じを伴う。
身にしむや亡妻(なきつま)の櫛(くし)を閨(ねや)に踏む <蕪村>
漸寒(ややさむ) (晩秋)[ようやく寒し・うそ寒]
秋もなかばを過ぎて、ようやく寒さを覚えるようになったこと。
漸寒や一万石の城下町 <高浜虚子>
行く秋(ゆくあき) (晩秋)[秋の名残(なごり)・秋の果(はて)]
秋という美しい季節の終わりである。名残を惜しむ気持ちが強い。
行秋や抱(だ)けば身に添ふ膝頭(ひざがしら) <太祇>
夜寒(よさむ) (晩秋)[夜寒さ]
秋もなかばを過ぎると、日中はそうでもないが、夜になると寒さを感じることがある。
あはれ子の夜寒の床の引けば寄る <中村汀女>
夜長(よなが) (三秋)[長き夜・長夜(ちょうや)]
一年中でもっとも夜の時間の長いのは12月の冬至のころだが、それよりも9月、10月の秋のころが、めっきり夜が長くなったように感じる。
よそに鳴る夜長の時計数へけり <杉田久女>
立秋(りっしゅう) (初秋)[今朝の秋・秋立つ]
二十四気の一つ。旧暦7月の節。いまの暦の8月8日ごろ。まだ暑さは厳しいが、風の音に秋がきたことが知られる。
立秋の眼(め)に浮(うか)みけり湖(うみ)の雲 <士朗>
秋たつと耳掻(か)いてゐておぼえけり <清水基吉>
天文
秋風(あきかぜ) (三秋)[秋の風・秋風(しゅうふう)]
秋に吹く風。秋の初めのさわやかな風にもいい、秋の終わりの寂しげな寒々とした風にもいう。
秋風や白木の弓に弦(つる)張らん <去来>
草の中ひたすすみゆく秋の風 <橋本多佳子>
秋高し(あきたかし) (三秋)[秋高(しゅうこう)・天高(てんたか)し]
秋を「天高く馬肥ゆる候」というが、もともとこれは中国の杜審言(としんげん)の「秋高くして塞馬(さいば)肥ゆ」によるもの。秋空が澄んで高く感じられること。
痩馬(やせうま)のあはれ機嫌や秋高し <村上鬼城>
秋の雨(あきのあめ) (三秋)[秋雨(あきさめ)・秋霖(しゅうりん)]
秋の初めから中ごろにかけて、曇りがちで小雨が降り続くことがある。寒々としてわびしい。
馬の子の故郷はなるる秋の雨 <一茶>
秋雨に水漬(みづ)きて登呂(とろ)の森の跡 <水原秋桜子>
秋の空(あきのそら) (三秋)[秋天(しゅうてん)・秋空(あきぞら)]
秋の空はさわやかに澄み渡り、色も濃く、深い。しかし、天気は案外変わりやすく、「男心と秋の空」などともいう。
秋の空昨日や鶴(つる)を放ちたる <蕪村>
秋晴(あきばれ) (三秋)[秋日和(びより)]
晴れ上がった秋の日は、空が澄んでいて、遠くまでくっきり見える。空の色も青くて深く、空が高くなったような感じがする。
秋晴の妻と会ひたる路上かな <雛津夢里>
天の川(あまのがわ) (初秋)[銀河(ぎんが)・銀漢(ぎんかん)]
夜空に川のように見える小さな星の群。恒星の集合よりなるが、古くから夜空の川と見られた。夏から秋にかけてが、とくに目だって美しいので秋季とされ、七夕(たなばた)の伝説と関連して、棚機津女(たなばたつめ)と彦星(ひこぼし)が、年に一度この川を渡って逢(あ)うと考えられた。
荒海や佐渡に横たふ天の川 <芭蕉>
虚子一人銀河と共に西へ行く <高浜虚子>
十六夜(いざよい) (仲秋)[二八夜(にはちや)・既望(きぼう)]
旧暦8月16日の夜、またその夜の月のこと。十五夜の月より月の出がやや遅いので、ためらいながら出る月の意味である。
十六夜もまだ更科(さらしな)の郡(こほり)かな <芭蕉>
稲妻(いなずま) (三秋)
暗い夜、雷鳴はあまり聞こえないが、電光だけが走ることがある。それを稲妻という。秋に多く、それが稲を実らせると信じられていたので、秋季とされている。
稲妻のかきまぜて行く闇夜(やみよ)かな <去来>
鰯雲(いわしぐも) (三秋)[鱗雲(うろこぐも)]
空にまだら状に広がった小さな白雲。小さな波のように美しく整うこともある。イワシが群がっているようにみえるので鰯雲といい、魚の鱗のようでもあるので鱗雲ともいう。
鰯雲ひとに告ぐべきことならず <加藤楸邨>
霧(きり) (三秋)[朝霧・霧時雨(しぐれ)]
地面に近い空気が冷やされると、水蒸気が細かな水滴となって、煙のように立ちこめる。秋に多く、冷ややかな感じが秋にふさわしいので、秋季とされている。霧が細かな雨のように降るのを「霧時雨」という。
霧時雨富士を見ぬ日ぞ面白(おもしろ)き <芭蕉>
白樺(しらかば)を幽(かす)かに霧のゆく音か <水原秋桜子>
秋色(しゅうしょく) (三秋)[秋光(しゅうこう)・秋の光]
秋らしいようす、秋らしい気配をいう。「秋光」といえば、そこに秋の明るい日差しが加わる感じである。
憩ふ人秋色すすむ中にあり <橋本鶏二>
月(つき) (三秋)[月光(げっこう)・弦月(げんげつ)・有明月(ありあけづき)]
空気が澄んでいるので、月は秋がとくに美しい。そのため、「月」といえば秋の月をさすものとされている。
月天心貧しき町を通りけり <蕪村>
月光の走れる杖(つゑ)をはこびけり <松本たかし>
露(つゆ) (三秋)[白露(しらつゆ)・夕露(ゆうづゆ)]
地面や草木などが冷えると、空中の水蒸気が水滴となってその上に付着する。秋に多いので秋季とする。
捨舟に白露みちし朝(あした)かな <闌更>
金剛の露ひとつぶや石の上 <川端茅舎>
流れ星(ながれぼし) (三秋)[流星(りゅうせい)・夜這星(よばいぼし)]
小さな星が地球に落ちてきた際、大気に触れて光を放ち、星が流れるように見える。四季を通じたものだが、とくに秋の夜空によく見られるところから、秋季とされている。
流星の使ひきれざる空の丈(たけ) <鷹羽狩行>
後の月(のちのつき) (晩秋)[十三夜(じゅうさんや)・二夜(ふたよ)の月]
旧暦9月13日の月。八月十五夜の月と九月十三夜の月を二夜の月といって、月見をする。豆名月、栗(くり)名月ともいい、名残(なごり)の月ともいう。
後の月葡萄(ぶだう)に核(さね)のくもりかな <成美>
遠ざかりゆく下駄(げた)の音十三夜 <久保田万太郎>
野分(のわき) (仲秋)[野分(のわけ)・野分(のわき)だつ]
野の草木を分けるように吹く秋の暴風。主としていまの台風をそういった。
吹き飛ばす石は浅間の野分(のわき)かな <芭蕉>
名月(めいげつ) (仲秋)[明月(めいげつ)・十五夜・今日の月]
旧暦8月15日の月。いわゆる十五夜の月。仲秋の満月のこと。芋、団子、枝豆、薄(すすき)の穂などを供えて月見をする。芋名月という。
名月や池をめぐりて夜もすがら <芭蕉>
今日の月馬も夜道を好みけり <村上鬼城>
明月の空の大きくありしかな <高野素十>
地理
秋の水(あきのみず) (三秋)[秋水(しゅうすい)]
秋の、ひんやりと澄みきった水。池や川や、そのほかどんな水でもよい。
秋の水竹の根がらみ流るなり <暁台>
秋の山(あきのやま) (三秋)[秋山(しゅうざん)・秋澄む]
秋の山は澄みきった空気のなかで紅葉に彩られて、まことに美しい。
秋山(しゅうざん)はめぐり幾瀬(いくせ)のこもり鳴る <水原秋桜子>
刈田(かりた) (晩秋)[刈小田(かりおだ)・刈田道]
稲を刈り取り、刈株だけが並んでいる田。明るく広々としているが、寂しい眺めである。
木曽(きそ)谷の刈田をわたるひざしかな <加藤楸邨>
初潮(はつしお) (仲秋)[望(もち)の潮(しお)]
旧暦8月15日の大潮のこと。2月と8月の満月の日はもっとも潮が高い。春の大潮は昼に高くなるが、秋の大潮は夜に高くなる。
初潮や鳴門(なると)の浪(なみ)の飛脚舟 <凡兆>
花野(はなの) (三秋)
秋の草花の咲き乱れた野をいう。華やかだが、秋のわびしさもある。
新妻の靴ずれ花野来しのみに <鷹羽狩行>
生活
秋の燈(あきのひ) (三秋)[燈火親(とうかした)しむ]
秋の夜の燈火は、落着いて澄んだ感じである。読書するのにふさわしいので「燈火親しむ」といわれる。
秋の燈やゆかしき奈良の道具市 <蕪村>
燈火親しむ汝(なんぢ)はフランス刺繍(ししゅう) <鷹羽狩行>
稲刈(いねかり) (晩秋)[刈稲(かりいね)・田刈(たかり)・稲車(いねぐるま)]
実った稲を刈り取ること。普通、10月である。早稲(わせ)は9月中に刈り取られる。
稲刈れば小草に秋の日のあたる <蕪村>
稲車押すこと厭(あ)きてぶらさがる <福田蓼汀>
案山子(かかし) (三秋)[鳥威(おど)し・おどし]
農作物に対する鳥獣の害を避けるため、田畑に立てる一本足の人形。竹や藁(わら)で骨組みをつくり、古い野良着を着せて頬(ほお)かむりをさせ、蓑(みの)や笠(かさ)をつけさせたりする。
物の音ひとりたふるる案山子かな <凡兆>
砧(きぬた) (三秋)[衣打(ころもう)つ・擣衣(とうい)・小夜砧(さよぎぬた)]
もともと、木の槌(つち)で布や衣類を打ち柔らげるときの石や木の台のことだが、俳句では、それを打つこと、とくにその音をいうことが多い。
憂(う)き我にきぬた打て今は又止みね <蕪村>
新蕎麦(しんそば) (晩秋)[初蕎麦・走り蕎麦]
蕎麦には、春にまいて夏に収穫する夏蕎麦と、夏にまいて秋に収穫する秋蕎麦がある。その秋蕎麦のまだ熟しきれないやや青みを帯びた蕎麦粉で打ったものをいう。
新蕎麦や熊野へつづく吉野山 <許六>
新米(しんまい) (晩秋)[今年米(ことしまい)・早稲(わせ)の飯(めし)]
その年収穫された新しい米。10月ごろになると早稲の米が出回ってくる。新米は神前にも供え、飯に炊くとなかなかうまい。
一つまみ新米あげし祠(ほこら)かな <池内たけし>
相撲(すもう) (初秋)[宮相撲(みやずもう)・土俵(どひょう)・相撲(すまい)]
現在の大相撲は季節を特定することはできないが、もともとは宮廷の初秋の行事として相撲節会(すまいのせちえ)があり、また神社の宮相撲も、秋祭の際に行われることが多いので、秋季とされている。
やはらかに人分け行くや勝相撲(かちずまふ) <几董>
燈籠(とうろう) (初秋)[盆燈籠(ぼんとうろう)・切子(きりこ)]
お盆の魂(たま)迎えの燈籠。燈籠の枠の角を落とした切子形で下に長い白紙を下げたものを切子燈籠といい、略して切子という。
初恋や燈籠に寄する顔と顔 <太祇>
まつくらな海がうしろに切子かな <草間時彦>
行事
踊(おどり) (初秋)[盆踊・踊子・踊唄(おどりうた)]
「踊」というだけで盆踊を意味する。7月13日から16日にかけての盆の時期に、寺の境内や町の広場などで大ぜいの人が集まって踊る。
四五人に月落ちかかる踊かな <蕪村>
七夕(たなばた) (初秋)[星祭・星合(ほしあい)]
旧暦7月7日の行事。東京地方ではいまの暦の7月7日に行うが、地方によっては8月7日に行う。中国の牽牛(けんぎゅう)・織女(しょくじょ)の伝説に乞巧奠(きこうでん)の行事が加わり、それに日本の棚機津女(たなばたつめ)の信仰が加わったもの。笹(ささ)竹に詩歌や願い事を書いた短冊や色紙をつるし、6日の宵から軒先に立てる。
七夕や賀茂川わたる牛車(うしぐるま) <嵐雪>
七夕や髪ぬれしまま人に逢(あ)ふ <橋本多佳子>
重陽(ちょうよう) (晩秋)[重九(ちょうきゅう)・菊の節供(せっく)・今日(きょう)の菊]
旧暦9月9日の節供。9は陽数にあたるので、それを重ねるところから、重陽という。その日に茱萸(しゅゆ)を袋に入れて山に登り、菊酒を飲んで災厄を逃れたとされており、菊の節供といわれる。宮廷では重陽の宴が行われる。農村で9月の9日、19日、29日の3回、農作物の収穫を祝う催しを行う地方があるが、それもこの重陽の影響であろうといわれる。
人心(ひとごころ)しづかに菊の節句かな <召波>
盆(ぼん) (初秋)[盂蘭盆(うらぼん)・魂祭(たままつり)・霊棚(たまだな)]
もともと旧暦の7月13日から15日、または16日までの行事。現在、主として都会地ではいまの暦のその日に行うので、夏の行事になっているが、地方では旧暦、またはひと月遅れで行う所が多く、秋の行事である。仏壇の前に霊棚(たまだな)をつくり、初物の野菜などを供え、祖先の霊を弔う。
霊棚の奥なつかしや親の顔 <去来>
盆ごころ夕がほ汁に定まれり <暁台>
盆のもの買ひととのへし夜の雨 <大野林火>
動物
鰯(いわし) (三秋)[鰮(いわし)・真鰯・鰯網]
暖流にのって日本近海に回遊する魚。漁獲が多いので値は安いが、塩焼きや鱠(なます)、あるいは干物にして好まれる。秋に多くとれる。
暮色濃く鰯焼く香の豊かなる <山口誓子>
鶉(うずら) (三秋)[鶉野(の)・鶉籠(かご)]
尾が短く、丸々とした鳥で、茶色に黒の斑(まだら)がある。草むらなどを走り、グッグックルルと鳴く。
桐(きり)の木に鶉鳴くなる塀の内 <芭蕉>
落鮎(おちあゆ) (三秋)[錆(さび)鮎・渋(しぶ)鮎]
鮎は秋になって卵をもつと、川を下って下流で産卵し、やがて死ぬ。産卵のために下流に下る鮎、また産卵を終えて流されてゆく鮎のことを「落鮎」という。産卵期の鮎は背が黒くなり、鉄が錆びたような色になるので「錆鮎」「渋鮎」という。
落鮎や日に日に水の恐ろしき <千代女>
雁(かり) (晩秋)[がん・かりがね・菱喰(ひしくい)・初雁]
北方から渡ってきて越冬する。頸(くび)が長く、尾は短くて、その鳴き声は趣(おもむき)深いものとされている。「菱喰」はとくに大形の種類で、「沼太郎」ともいう。
幾行(いくつら)も雁過る夜となりにけり <青蘿>
ただ一羽来る夜ありけり月の雁 <夏目漱石>
鮭(さけ) (三秋)[しゃけ・秋味(あきあじ)・初鮭(はつざけ)]
鮭は秋の産卵期に大挙して川をさかのぼる。北方に多く、とくに秋、川をさかのぼる直前のものが美味とされ、北海道地方では「秋味」という。
鮭取りのししむら濡(ぬ)れて走りけり <沢木欣一>
秋刀魚(さんま) (晩秋)
晩秋のころ、寒流にのって日本近海にきて、大量にとれる。そのころちょうど脂がのっているので、塩焼きにして大根おろしを添えて食べるとうまい。
ひとりたのしげ夕焼秋刀魚二つ切り <加藤楸邨>
鹿(しか) (三秋)[鹿の妻(つま)・小牡鹿(さおしか)・鹿狩(しかがり)]
鹿は秋が交尾期で、牡鹿(おじか)が牝(め)鹿を呼んで高く強い声で鳴く。また紅葉の景に配されることからも、秋季とされている。
ぴいと啼(な)く尻(しり)声かなし夜の鹿 <芭蕉>
鴫(しぎ) (三秋)[草鴫・田鴫・百羽掻(ももはがき)]
北方から渡来する鳥だが、種類が多く、日本を通過していくものと、日本で越冬するものがある。いったいに湿潤な土地を好み、ひっそりと身を潜めているようすがあるので、それを「鴫の看経(かんきん)」(経を読むこと)という。またくちばしで羽をしごく「羽づくろい」というしぐさをするが、それを「百羽掻」という。
鴫たつや行き尽したる野末より <蕪村>
つくつく法師(つくつくぼうし) (初秋)[法師蝉(ほうしぜみ)]
夏の終わりから初秋のころ、ツクツクボーシと鳴く蝉。「おしいつくつく」とも「筑紫(つくし)恋(こい)し」とも聞かれる。
つくつくぼうしつくつくぼうし斗(ばか)りなり <正岡子規>
法師蝉しみじみ耳のうしろかな <川端茅舎>
蜻蛉(とんぼ) (三秋)[とんぼう・やんま・あきつ]
夏、秋を通じてみられるが、とくに秋に多くみられる「赤蜻蛉」のような種類もあり、秋空にふさわしいので秋季とされている。「やんま」「あきつ」は古名だが、とくに「やんま」は比較的大形の種類をさす言い方でもある。
行く水におのが影追ふ蜻蛉かな <千代女>
蜻蛉(とんぼう)の夢や幾度杭(くひ)の先 <夏目漱石>
鯊(はぜ) (三秋)[沙魚(はぜ)・真鯊(まはぜ)]
河口や内湾の比較的浅い所に多い小形の魚。秋の彼岸ごろによく釣れるので、秋季とされている。種類が多く、てんぷらや佃煮(つくだに)にされる。
鯊の潮芥(あくた)たたへて満ちにけり <高浜虚子>
蜩(ひぐらし) (初秋)[かなかな]
夏の終わりから初秋のころの、夕方や明け方に鳴く蝉(せみ)。その鳴き声から「かなかな」という。
かなかなに母子のかやのすきとほり <石田波郷>
蓑虫(みのむし) (三秋)[鬼の子]
蓑蛾(みのが)の幼虫。木の葉や木の屑(くず)を体から分泌した糸でつづって巣をつくり、木の枝からぶら下がって越冬する。「鬼の子」といわれ、また「父よ父よ」と鳴くともいい伝えられている。
蓑虫の音(ね)を聞きに来よ草の庵(いほ) <芭蕉>
虫(むし) (三秋)[虫の音(ね)・虫籠(かご)]
俳句でただ「虫」といえば、秋鳴く虫のこと。蟋蟀(こおろぎ)、鈴虫、松虫、きりぎりすをはじめ、種類が多い。
行水(ぎゃうずい)の捨て処(どころ)なき虫の声 <鬼貫>
其(その)中に金鈴(きんれい)をふる虫一つ <高浜虚子>
鵙(もず) (三秋)[鵙高音(たかね)・鵙日和(びより)・百舌鳥(もず)]
秋には人家近くにもきて、樹木の上のほうに止まり、尾を上下に動かしながら、鋭い声で鳴く。その引き締まった鳴き声は、秋の澄みきった空気に、いかにもふさわしい。
かなしめば鵙金色(こんじき)の日を負ひ来(く) <加藤楸邨>
渡り鳥(わたりどり) (三秋)[候鳥(こうちょう)・漂鳥(ひょうちょう)]
秋になると、北方から渡ってくる雁(がん)、鴨(かも)、鴫(しぎ)、千鳥、鶫(つぐみ)、鶸(ひわ)など、また、秋、南方へ渡ってゆく燕(つばめ)や時鳥(ほととぎす)などの総称。
京近き山にかかるや渡り鳥 <暁台>
植物
赤のまんま(あかのまんま) (初秋)[犬蓼(いぬたで)の花・赤のまま]
道ばたや野に自生する犬蓼の花。紅紫色の小さな粒状の花が咲く。赤い米粒のようで、子供がままごと遊びの赤飯にする。
此辺(このへん)の道はよく知り赤のまま <高浜虚子>
朝顔(あさがお) (初秋)[牽牛花(けんぎゅうか)]
垣根や窓に絡み、毎朝次々に花を咲かせる。もともと薬用植物として中国から渡来したものだが、江戸時代にさまざまな変種がつくられるようになった。
朝顔に釣瓶(つるべ)とられてもらひ水 <千代女>
稲(いね) (三秋)[稲田(いなだ)・稲穂(いなほ)・陸稲(おかぼ)・稲の花]
日本における稲作の歴史は古く、種類も多い。秋の早い時期に実る早稲(わせ)もあれば、中ごろの中稲(なかて)、秋が深まって実る晩稲(おくて)もある。水田につくるのが普通だが、畑につくる「陸稲」もある。稲の花は二百十日のころが花盛りである。
稲つけて馬が行くなり稲の中 <正岡子規>
芋(いも) (三秋)[里芋・衣被(きぬかつぎ)・芋畑(いもばたけ)]
里芋のこと。東北地方の一部では「芋」が山芋(やまのいも)をさし、また近年では「芋」が薩摩(さつま)芋をさす傾向もあるが、俳句では「里芋」のことをいう。「衣被」は子芋を皮のままゆでたもの。
星空へひしめく闇(やみ)の芋畑 <長谷川素逝>
末枯(うらがれ) (晩秋)[末枯(うらが)るる]
野山の草が葉の先のほうから枯れてくること。草の葉の一枚一枚というより、そのあたりのようす全体にいうことが多い。
末枯や国によこたふ最上川 <蓼太>
イエス立つ野はことごとく末枯るる <有馬朗人>
女郎花(おみなえし) (初秋)[おみなめし・粟花(あわばな)]
1メートルほどの茎の上に、傘状に群がった淡黄色の小花をつける。その姿の優しく繊細な感じが女性的である。秋の七草の一つ。
ひよろひよろとなほ露けしや女郎花 <芭蕉>
柿(かき) (晩秋)[富有柿(ふゆうがき)・渋柿(しぶがき)・柿日和(びより)]
日本の秋を代表する果物。秋空に実っている柿は美しい。富有柿はとくに美味である。渋柿は吊(つる)し柿や熟柿(じゅくし)にして食べる。
柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺 <正岡子規>
桔梗(ききょう) (初秋)[きちこう・沢(さわ)桔梗]
山野に自生するが、庭にも植えられる。上品な紫色、いわゆる桔梗色、または白色の清楚(せいそ)な花が咲く。秋の七草の一つ。沢や湿地など水辺を好む種類のものが「沢桔梗」。
莟(つぼみ)より花の桔梗はさびしけり <三橋鷹女>
菊(きく) (初秋)[菊・白菊・菊人形]
中国でつくられたといわれ、日本でも古くからその気品の高さと香気が愛され、皇室の紋章にもなっている。江戸時代以来、多くの園芸品種がつくりだされ、秋にはほうぼうで菊花展が行われ、「菊人形」などもつくられる。
菊の香や奈良には古き仏達 <芭蕉>
黄菊白菊その外の名はなくもがな <嵐雪>
茸(きのこ) (晩秋)[菌(きのこ)・茸(たけ)・茸飯(きのこめし)]
山林の中の朽ち木や落ち葉の積もった地に生ずる茸類の総称。松茸(まつたけ)、椎茸(しいたけ)、しめじ、栗茸(くりたけ)など、うまいものがあり、「茸飯」を炊いたりするが、一方、天狗茸(てんぐたけ)、紅茸(べにたけ)、笑い茸など、有毒のものも多い。
食へぬ茸(たけ)光り獣(けもの)の道せまし <西東三鬼>
桐一葉(きりひとは) (初秋)[一葉・一葉落つ]
桐の落葉。他の樹に先駆けて、一葉ずつばさりと落ちる。中国の古典『淮南子(えなんじ)』に「一葉落ちて天下の秋を知る」とあるところからきたもの。
桐一葉日当りながら落ちにけり <高浜虚子>
草の花(くさのはな) (三秋)[千草(ちぐさ)の花]
秋の野に咲くさまざまな草の花。淋(さび)しげで、可憐(かれん)な花が多い。
草いろいろおのおの花の手柄かな <芭蕉>
草の実(くさのみ) (三秋)[草の穂]
秋のさまざまな草の実。穂をなすものもあり、莢(さや)がはじけて飛び出すものや、人の衣服や動物に付着するもの、風にのって空中を飛ぶものなどもある。
草の実の袖(そで)にとりつく別れかな <凉菟>
葛の花(くずのはな) (初秋)[葛(くず)]
紅紫色の小さな蝶(ちょう)形花が、十数センチメートルの房状をなして下から咲き上る。秋の七草の一つ。「葛」といえば風になびく葉の印象が強く、秋季全般にわたるが、「葛の花」は初秋。
葛の花水に引きずる嵐(あらし)かな <一茶>
栗(くり) (晩秋)[毬栗(いがぐり)・柴(しば)栗・丹波(たんば)栗]
山地に自生し、また畑や庭にも植えられる。刺(とげ)のある毬がはじけて地に落ちる。「柴栗」は小粒だがうまい。「丹波栗」は大粒でよく知られている。
栗のつや落ちしばかりの光なる <室生犀星>
鶏頭(けいとう) (三秋)[鶏頭花(か)・扇(おうぎ)鶏頭・からあい]
古く中国から渡来したという。染料に用いられたので、古名を「韓藍(からあい)」といった。高さ1メートルほどで、深紅の細花の固まった鶏冠(とさか)状の花序をつける。
鶏頭の十四五本もありぬべし <正岡子規>
木の実(このみ) (晩秋)[木の実落つ・木の実雨]
秋にはさまざまの木の実が熟する。「木の実」といった場合、林檎(りんご)や柿(かき)などの果物は除き、その他の樫(かし)、椎(しい)、栃(とち)、榧(かや)、椋(むく)など、すべてをいう。風が吹いたりして一斉にばらばら落ちるのを「木の実雨」という。
よろこべばしきりに落つる木の実かな <富安風生>
新松子(しんちぢり) (晩秋)[青松笠(あおまつかさ)]
今年できた青い松笠。円錐(えんすい)形で堅い。枯れて笠が開き、種をこぼしてしまったものを「松ぼっくり」「松ふぐり」という。
新松子にあたり爽(さはや)ぐ艸(くさ)の庵(いほ) <松瀬青々>
松笠の青さよ蝶(てふ)の光り去る <北原白秋>
西瓜(すいか) (初秋)
球形の大きな実とその赤い果肉は、だれにも懐かしいものである。夏のころから出始め、冷たい西瓜の一切れは夏の風物詩でもあるのだが、俳句では秋季とされている。
こけさまにほうと抱(かか)ゆる西瓜かな <去来>
薄(すすき) (三秋)[芒(すすき)・尾花(おばな)・花芒(はなすすき)・枯尾花(かれおばな)]
ひとむらに生い茂り、秋になると穂の形の花を出し、つやつやと光る「尾花」「花芒」となり、それが白い絮(わた)となって飛び、あとは「枯尾花」となる。秋の七草の一つ。
君が手もまじるなるべし花芒 <去来>
山は暮て野は黄昏(たそがれ)の芒かな <蕪村>
竹の春(たけのはる) (仲秋)[竹春(ちくしゅん)]
その年に竹の子として生えた竹は、秋になって緑が美しくなる。「竹春」といえば旧暦8月の異称でもある。
一むらの竹の春ある山家(やまが)かな <高浜虚子>
蔦(つた) (三秋)[蔦かづら・蔦紅葉(もみじ)]
山野に自生して木や崖(がけ)に絡み、また人に植えられて塀や建物を覆う。落葉樹のいわゆる夏蔦のことをいう。その紅葉の美しさから「蔦」というだけで秋季とする。冬も青々としているいわゆる冬蔦はこの場合、含まない。
つたの葉の水に引かるる山辺かな <暁台>
唐辛子(とうがらし) (三秋)[蕃椒(とうがらし)・天井守(てんじょうもり)・鷹の爪(たかのつめ)]
青いとがった実が、秋に色づいて真っ赤になる。つるして乾燥させたり、実を摘み取って莚(むしろ)に干し並べたりして香辛料にする。天井につるして保存するのを「天井守」といい、実の一つ一つの形から「鷹の爪」という。
青くてもあるべきものを唐辛子 <芭蕉>
梨(なし) (三秋)[有(あり)の実(み)・長十郎(ちょうじゅうろう)・二十世紀(にじっせいき)]
歴史の古い果物だが、江戸時代から盛んに栽培されるようになった。「なし」が「無し」に通じることを嫌って「有の実」ともいう。
梨むくや甘き雫(しづく)の刃(は)を垂るる <正岡子規>
萩(はぎ) (初秋)[山萩・鹿鳴草(しかなきぐさ)・もとあらの萩]
山萩や野萩は山野に自生するが、庭に植えられる種類のものもある。低木なのだが、茎が枝状に叢生(そうせい)するところから、草と考えられ、秋の七草の一つにも数えられている。古くから詩歌に詠まれ、鹿(しか)と取り合わされることが多く、「鹿鳴草」「鹿妻草(しかつまぐさ)」のような雅名もある。花期の終わりごろになると、枝の元のほうには花も葉もなくなって荒れたようすになるので「もとあらの萩」という。
しら露もこぼさぬ萩のうねりかな <芭蕉>
芭蕉(ばしょう) (三秋)[芭蕉葉(ば)・芭蕉林(りん)]
広く破れやすい葉が美しい。その風に鳴る音が秋を感じさせるので秋季とする。中国原産だが、古く渡来し、「はせを」と書かれた。俳人の芭蕉の名も、その庵(いおり)にこれが植えられていたことに由来している。
芭蕉野分(のわき)して盥(たらひ)に雨を聞く夜かな <芭蕉>
藤袴(ふじばかま) (初秋)[蘭草(らんそう)・香草(こうそう)]
1メートルほどの高さで、茎の上に淡紅紫色の気品ある花を咲かせる。庭にも植えられるが、関東中部以西の、比較的湿気の多い土地に自生する。秋の七草の一つ。
うつろへるほど似た色や藤袴 <北枝>
葡萄(ぶどう) (仲秋)[甲州葡萄・黒葡萄・マスカット]
葡萄棚に垂れ下がって実り、店頭にもさまざまな種類のものが並べられる。在来種を改良したものという「甲州葡萄」や、外来の「マスカット」がよく知られている。江戸時代初期から詠まれているが例句は多くない。
亀甲(きっかふ)の粒ぎつしりと黒葡萄 <川端茅舎>
芙蓉(ふよう) (初秋)[木(もく)芙蓉・酔(すい)芙蓉]
中国原産というが、九州や沖縄にも自生する落葉低木。庭に植えられ、淡紅色の五弁の花を開く。よく、美人に例えられる。蓮(はす)のことも芙蓉ということから、それと区別して、「木芙蓉」という。また、朝、白い花が咲き、午後に淡紅色となる種類があり、それを「酔芙蓉」という。
月満ちて夜の芙蓉のすわりけり <暁台>
鬼灯(ほおずき) (三秋)[酸漿(ほおずき)・かがち]
ナス科の多年草で、秋に、実と、それを包む萼(がく)が赤くなって美しいので秋季とする。女の子が、球形の実から種を抜き、口に入れて鳴らして遊ぶ。古名を「かがち」という。
少年に鬼灯くるる少女かな <高野素十>
曼珠沙華(まんじゅしゃげ) (仲秋)[彼岸花(ひがんばな)・死人花(しびとばな)]
秋の彼岸のころ、田の畦(あぜ)や川の堤や墓地の間などに、30センチメートルほどの茎を伸ばして、真紅の花を咲かせる。『法華経(ほけきょう)』の「摩訶曼陀羅華曼珠沙華(まかまんだらげまんじゅしゃげ)」からきた呼び名。「天上界の花」「赤い花」の意の梵語(ぼんご)である。仏の花として墓地に植えられたので、「死人花」というような不吉な名もある。「火事花(かじばな)」「野松明(のたいまつ)」「ちんちろ花」など方言が多い。
つきぬけて天上の紺曼珠沙華 <山口誓子>
木槿(むくげ) (初秋)[木槿垣(むくげがき)・きはちす]
高さ3メートルほどの落葉低木。よく枝分れするので、生け垣にも用いられる。朝早く花が開き、夕方にはしぼむ。「槿花一日の栄(きんかいちじつのえい)」といわれ、人の栄華のはかなさに例えられる。古く「きはちす」とよばれ、略して「はちす」ともいう。また古く「あさがほ」はこの花をさすことがあるという。
道のべの木槿は馬に喰(く)はれけり <芭蕉>
木犀(もくせい) (晩秋)[金(きん)木犀・銀(ぎん)木犀・木犀の花]
中国原産の常緑樹。薄褐色の樹皮が犀(さい)の皮に似ていることからいう。橙黄(とうこう)色の小花をつけるのが「金木犀」。白い小花をつけるのが「銀木犀」。香りが高く、庭木として好まれる。
金木犀風の行手に石の塀 <沢木欣一>
紅葉(もみじ) (晩秋)[黄葉(もみじ)・色葉(いろは)・濃紅葉(こもみじ)]
落葉樹の葉が寒気にあって赤や黄色に変わったもの。また変わることを「もみづる」という。とくに楓(かえで)の紅葉が美しく、「紅葉」といえば、楓紅葉をさすことも多い。
一枝の濃紫(こむらさき)せる紅葉あり <竹下しづの女>
桃の実(もものみ) (初秋)[白桃(はくとう)・水蜜桃(すいみつとう)]
豊かに熟した桃の実は、美しく、美味である。早い種類は夏のころにもみられるが、主として岡山県に産する「白桃」は、初秋から仲秋に近く現れる。
中年や遠くみのれる夜の桃 <西東三鬼>
柳散る(やなぎちる) (仲秋)
柳の葉が黄ばんで散ること。田舎(いなか)の川べりの柳などは秋のなかばに散るが、都会の街路樹のしだれ柳などは、散るのが遅い。
船寄せて見れば柳の散る日かな <太祇>
蘭(らん) (仲秋)[蘭の香・蘭の花]
香り高い花を咲かせ、古くから秋季とされている。実際は日本では春に花を咲かせる「春蘭」しかなく、秋に咲く中国産の「秋蘭」は香りが高いが、日本には自生しない。古く漢字で「蘭」と書けば、蘭草(らんそう)のことで、キク科の藤袴(ふじばかま)をさし、江戸時代の芭蕉(ばしょう)のころまではそうであった。その後、いまいう蘭の類が栽培されるようになり、その気品の高さが秋にふさわしく、ごく少ないが香りの高い「秋蘭」があるということと、また藤袴とのかかわりもあって、多くの蘭の開花の実際とは別に、秋季とされてきている。次の、芭蕉の句は藤袴、蕪村(ぶそん)の句は蘭であると思われる。
蘭の香(か)や蝶(てふ)の翅(つばさ)にたきものす <芭蕉>
蘭の香や菊より暗きほとりより <蕪村>
林檎(りんご) (晩秋)[苹果(りんご)・林檎もぐ]
林檎園に実っている林檎は美しく、店頭に積まれている林檎は秋も深まったことを感じさせる。江戸時代の元禄(げんろく)以後の俳句にみられるが、明治時代までは夏季とされた。現在は、早生(わせ)種の「青林檎」は夏、「林檎」は秋とされている。
林檎噛(か)む歯に青春をかがやかす <西島麦南>
【冬】
時候
寒の内(かんのうち) (晩冬)
いまの暦の1月5日ごろにあたる寒の入(かんのいり)から、2月3日ごろの節分(立春の前日)まで。前半が小寒、後半が大寒である。
鎌倉のなかの往来(ゆきき)も寒の内 <清水基吉>
小春(こはる) (初冬)[小春日和(こはるびより)・小春日・小六月(ころくがつ)]
旧暦10月のことをいう。いまの暦の11月のころだが、そのころ、ぽかぽかと暖かな春のような日和が続くことがあるので、そのように称する。
海の音一日遠き小春かな <暁台>
寒し(さむし) (三冬)[寒気(かんき)・寒夜(かんや)・寒苦(かんく)]
冬の寒さのこと。
塩鯛の歯ぐきも寒し魚(うを)の店(たな) <芭蕉>
まのあたりみちくる汐(しほ)の寒さかな <久保田万太郎>
師走(しわす) (初冬)[極月(ごくげつ)・臘月(ろうげつ)]
もともと旧暦12月の別称であるが、現在は新暦の12月にもいう。この月になると、師(僧)があわただしく走り回るところからいうのだとされているが、確かではない。「極月」「臘月」も12月の異称。
何(なん)にこの師走の市(いち)に行く烏(からす) <芭蕉>
節分(せつぶん) (晩冬)[節替(せつがわ)り]
立春の前日のこと。いまの暦の2月2、3、4日のころにあたる。いよいよ明日から春だという喜びがある。
節分の何げなき雪ふりにけり <久保田万太郎>
大寒(だいかん) (晩冬)
二十四気の一つ。いまの暦の1月20日ごろから15日間。一年中でもっとも寒いときである。なお、その前の15日が小寒。
大寒の埃(ほこり)の如(ごと)く人死ぬる <高浜虚子>
短日(たんじつ) (三冬)[日短(ひみじ)か・暮早(くれはや)し]
冬は日が短く、とくに冬至のころは短い。朝はなかなか明けず、夕方はすぐ暗くなる。
短日や杉山透る竹の笛 <青柳志解樹>
年の暮(としのくれ) (仲冬)[歳暮(さいぼ)・歳晩(さいばん)・年末(ねんまつ)]
年末が押し詰まったころをいう。12月の中旬以後をいうのが普通だが、12月の初めごろからをいうこともある。
米くるる友どち持ちて年の暮 <蝶夢>
初冬(はつふゆ) (初冬)[初冬(しょとう)・上冬(じょうとう)・孟冬(もうとう)]
冬の初めのころ。ぽかぽかと暖かい日もあれば、冷たい風に震え上がる日もある。
はつ冬の山々同じ高さかな <鳳朗>
春近し(はるちかし) (晩冬)[春隣(はるとなり)・春を待つ・春めく]
冬の寒さも和らいできて、春ももう遠くはないと思うのである。
春近し石段下りて薺(なづな)あり <高野素十>
冬(ふゆ) (三冬)
11月7、8日ごろの立冬から、2月4日ごろの立春の前日である節分までが冬。寒風吹きすさび、雪が降り、ときにはほっとするような暖かい日がある。
山河はや冬かがやきて位(ゐ)に即(つ)けり <飯田龍太>
冬ざれ(ふゆざれ) (三冬)[冬され・冬ざるる]
冬の寒々としてわびしいようすをいう。もともと「冬されば」(冬になったので)の語が誤用されたもの。
冬ざれや雨にぬれたる枯葉竹 <永井荷風>
冬の日(ふゆのひ) (三冬)[冬日(ふゆび)・冬日向(ひなた)]
冬の一日の意味にも、冬の太陽の意味にも用いる。「冬日」といえば冬の太陽、「冬日向」はその太陽のさす暖かいところ。
冬の日や馬上に氷る影法師 <芭蕉>
行く年(ゆくとし) (仲冬)[年逝(ゆ)く・年歩む]
年の暮に、一年が去ってゆくこと。「年の暮」というよりも、年を惜しむ気持ちが強い。
ゆく年の一夜明らむ水の音 <川崎展宏>
立冬(りっとう) (初冬)[冬立つ・冬に入る]
二十四気の一つ。旧暦10月の節。いまの暦の11月7日か8日ごろ。朝晩は急に寒くなったような気がするが、天気のよい昼間などはまだぽかぽかと暖かい。
立冬のことに草木のかがやける <沢木欣一>
堂塔の影を正して冬に入る <中川宋淵>
天文
霰(あられ) (三冬)[初(はつ)霰・玉(たま)霰]
大気中の水蒸気が冷えて氷粒になったもの。気温が零度に近いときに多い。短時間にやむのが普通。「初霰」はその冬初めての霰。「玉霰」は美称。
呼びかへす鮒売(ふなうり)見えぬ霰かな <凡兆>
玉霰幽(かす)かに御空(みそら)奏(かな)でけり <川端茅舎>
凩(こがらし) (初冬)[木枯(こがらし)]
冬の初めに吹く強い寒風。木の葉を吹き落とし、枯れ木にしてしまう。
凩の果(はて)はありけり海の音 <言水>
海に出て木枯帰るところなし <山口誓子>
時雨(しぐれ) (初冬)[時雨(しぐ)る・山めぐり・横しぐれ]
冬の初めのころ、晴れていたと思うとはらはらと降り、かと思うとまた晴れて日が差してくる。そのように降る雨。「山めぐり」は周囲の山をめぐるように降るという意味の、時雨の異称。「横しぐれ」は風があって横から吹き付ける時雨。
笹(ささ)の葉に西日のめぐる時雨かな <才麿>
しぐるるや駅に西口東口 <安住敦>
霜(しも) (三冬)[霜夜(しもよ)・はだれ霜]
風がなく晴れた寒い夜、大気中の水蒸気が、物体や地表に触れて、氷の結晶となり、白く付着する。
霜百里舟中(しうちゅう)に我月を領す <蕪村>
霜の墓抱き起こされしとき見たり <石田波郷>
冬の月(ふゆのつき) (三冬)[月冴(さ)ゆる・寒月]
寒々と冴え返った冬の月。「寒月」というほうがもっと寒さが厳しい。
この木戸や鎖(ぢゃう)のさされて冬の月 <其角>
寒月や我ひとり行く橋の音 <太祇>
霙(みぞれ) (三冬)[霙(みぞ)る]
雪と雨が入り交じって降るもの。霙がやがて雪に変わったりする。
淋(さび)しさの底ぬけてふるみぞれかな <丈草>
雪(ゆき) (晩冬)[初(はつ)雪・深(み)雪・六花(むつのはな)]
雪の深い地方では、雪は苦しみであろうが、伝統的な文化の中心地であった京都や江戸の地方では、雪は珍しく、美しいものであるとされ、雪見なども行われた。雪の結晶が六角状であることから「六花」という。
下京(しもぎゃう)や雪つむ上の夜の雨 <凡兆>
雪はげし抱かれて息のつまりしこと <橋本多佳子>
地理
枯野(かれの) (三冬)[枯原・冬野]
草木が枯れ果てた寒々とした野。「冬野」というよりもわびしい感じが強い。
旅に病んで夢は枯野をかけ廻(めぐ)る <芭蕉>
犬らしくせよと枯野に犬放つ <山田みづえ>
氷(こおり) (晩冬)[氷(こお)る・凍(こお)る・氷上(ひょうじょう)・結氷(けっぴょう)]
寒い朝、水たまりや手水鉢(ちょうずばち)に氷が張る。寒さの厳しい地方では池や川や海までも氷る。
捨舟の内そと氷る入江かな <凡兆>
氷上にかくも照る星あひふれず <渡辺水巴>
冬の山(ふゆのやま) (三冬)[枯山(かれやま)・山眠(やまねむ)る]
落葉樹は葉を落とし、常緑樹も眠ったようなわびしい山。春の山を「山笑う」というのに対して「山眠る」という。
めぐり来る雨に音なし冬の山 <蕪村>
枯山にはるか一つの葬を見る <飯田蛇笏>
山眠り椎の実あまた降らせたり <楠本憲吉>
水涸る(みずかる) (三冬)[渇水期(かっすいき)・涸川(かれかわ)]
冬になると降雨量が減り、また水源地が雪に埋もれて、川の水が涸(か)れ、池や沼の水が少なくなる。
昼の月でてゐて水の涸れにけり <久保田万太郎>
涸川や波を曳(ひ)きゐる杭(くひ)ひとつ <水原秋桜子>
生活
風邪(かぜ) (三冬)[風邪(ふうじゃ)・感冒(かんぼう)・流感(りゅうかん)]
風邪は冬に限るものではないが、やはり寒い冬に風邪をひく人が多い。
風邪の子や眉(まゆ)にのび来(き)しひたひ髪 <杉田久女>
炬燵(こたつ) (三冬)[切炬燵(きりごたつ)・掘(ほり)炬燵・置(おき)炬燵]
「切炬燵」はいろりを切った上に炬燵櫓(やぐら)をのせたもので、「掘炬燵」はそれを掘り下げたもの。「置炬燵」は畳の上に櫓を置き、中に小火鉢を入れたもの。昔は燃料に木炭や豆炭を用いたが、現在は電気が普通である。
住みつかぬ旅の心や置炬燵 <芭蕉>
盃(さかづき)に怒濤(どたう)のひびく炬燵かな <佐藤南山寺>
炭(すみ) (三冬)[木炭(もくたん)・白炭(しろずみ)・備長(びんちょう)]
暖房用の木炭。火鉢や炬燵に用いるもので、昔は欠かせぬものであったが、現在はほとんど使われなくなった。「白炭」は特別の製法による堅炭(かたずみ)。「備長」はその高級なもの。
更(ふ)くる夜や炭もて炭をくだく音 <蓼太>
炭つげばまことひととせながれゐし <長谷川素逝>
咳(せき) (三冬)[しわぶき]
冬は寒さのため、呼吸器や気管を悪くして、咳をすることが多い。
咳の子のなぞなぞあそびきりもなや <中村汀女>
雑炊(ぞうすい) (三冬)[おじや・鶏(とり)雑炊・河豚(ふぐ)雑炊]
一般の家庭では冷や飯や残った汁物を利用してつくる経済的なものだが、料亭などでは、河豚やすっぽんなどの鍋(なべ)物のあとでつくる高級な料理である。近代になって冬の季語とされるようになった。
雑炊もみちのくぶりにあはれなり <山口青邨>
焚火(たきび) (三冬)[落葉焚(おちばたき)]
暖をとるために焚く火。また庭の落ち葉をかき集めて焼くのが「落葉焚」。
とつぷりと後ろ暮れゐし焚火かな <松本たかし>
天の階(かい)あるとき近し落葉焚 <古賀まり子>
竹馬(たけうま) (三冬)[高足(たかあし)・鷺足(さぎあし)]
2本の竹の棒に足をかけて歩く子供の遊び道具、またはその遊び。一年を通じてみられるものだが、とくに雪の中での遊びに用いられるところから、明治時代になって冬の季語とされた。「高足」「鷺足」ともいう。
竹馬やいろはにほへとちりぢりに <久保田万太郎>
年忘(としわすれ) (仲冬)[忘年会・忘年]
年末にその一年の苦労を忘れるため、人が集まって宴会をすること。また、単にその一年の苦労を忘れることにもいう。
人に家を買はせて我は年忘 <芭蕉>
紙ひとり燃ゆ忘年の山平(やまたひら) <飯田龍太>
蒲団(ふとん) (三冬)[布団(ふとん)・掛蒲団・敷蒲団]
蒲団は一年中用いるのだが、その暖かな感じをたいせつにして、俳句では冬季とする。
蒲団着て寝たる姿や東山 <嵐雪>
布団肩まで故郷(こきゃう)へ戻ること思ふ <鈴木真砂女>
冬籠(ふゆごもり) (三冬)
冬の寒い間、外出を控えて、家の中に引きこもって過ごすこと。
金屏(きんびゃう)の松の古さよ冬籠 <芭蕉>
行事
一茶忌(いっさき) (仲冬)
旧暦11月19日。1827年(文政10)のこの日、小林一茶は65歳で故郷の信州柏原(かしわばら)に没した。個性的な境涯俳句に特色があった。
一茶忌や父を限りの小百姓 <石田波郷>
クリスマス (仲冬)[降誕祭・聖夜]
キリストが生まれたのを祝う祭。その前夜をクリスマスイブ(聖夜)といってミサを行う。外来の行事だが、家庭でパーティーを行うというような形で、日本の風俗になってきている。クリスマスツリーを「聖樹」、クリスマスケーキを「聖菓」などという。
一人来てストーブ焚(た)くやクリスマス <前田普羅>
聖夜ミサ首筋やはらかく祷(いの)る <鷹羽狩行>
除夜の鐘(じょやのかね) (仲冬)[百八(ひゃくはち)の鐘(かね)]
大晦日(おおみそか)の夜12時をはさんで、寺では除夜の鐘を撞(つ)く。百八の煩悩を打ち消すために108回撞くのを習わしとする。
除夜の鐘襷(たすき)かけたる背後(うしろ)より <竹下しづの女>
年の市(としのいち) (仲冬)[歳の市・暮の市・師走(しわす)の市]
年の暮に正月の飾り物などの新年用品を売るために立つ市。
不二(ふじ)を見て通る人あり年の市 <蕪村>
酉の市(とりのいち) (初冬)[お酉さま・一(いち)の酉・熊手市(くまでいち)]
11月の酉の日に各地の鷲(おおとり)(大鳥)神社で行われる祭礼、またその際に立つ市。福を掻(か)き込むという熊手をはじめ、宝舟、千両箱、おかめの面などを売る。東京浅草の鷲神社の酉の市が有名。
ぬかるみに下駄(げた)とられけり酉の市 <高橋淡路女>
芭蕉忌(ばしょうき) (初冬)[桃青(とうせい)忌・時雨(しぐれ)忌・翁(おきな)忌]
旧暦10月12日。1694年(元禄7)のこの日、松尾芭蕉は51歳で旅先の大坂に没した。その前号により「桃青忌」といい、おりから時雨月で、また芭蕉が時雨を愛していたところから「時雨忌」といい、生前、人々から翁とよばれていたところから「翁忌」ともいう。
芭蕉忌や香もなつかしきくぬぎ炭 <成美>
時雨忌や心にのこる一作者 <河野静雲>
山国のまことうす日や翁の忌 <長谷川素逝>
蕪村忌(ぶそんき) (晩冬)[春星(しゅんせい)忌]
旧暦12月25日。1783年(天明3)のこの日、与謝(よさ)蕪村は68歳で京都の自宅に没した。その画号によって「春星忌」ともいう。
蕪村忌や残照亭に灯の用意 <名和三幹竹>
瓶(かめ)にさす梅まだかたし春星忌 <大橋越央子>
動物
牡蠣(かき) (三冬)[石花(かき)・牡蠣田(かきだ)]
岩などに付着する貝で、美味であるため大掛りに養殖されている。松島、広島、志摩半島などが主産地。太平洋側では冬に採るので冬季とする。「牡蠣田」は牡蠣の養殖場。
松島の松に雪降り牡蠣育つ <山口青邨>
鴨(かも) (三冬)[真鴨(まがも)・青頸(あおくび)・葭鴨(よしがも)・緋鳥鴨(ひどりがも)]
秋の終わりごろ北方から渡ってきて、冬の間を日本の湖や川や海で過ごし、春の初めに北へ帰ってゆく。「真鴨」は「青頸」ともいい、もっとも多くみられる。ほかに「葭鴨」「緋鳥鴨」など種類が多い。
海くれて鴨の声ほのかに白し <芭蕉>
鴨渡る鍵(かぎ)も小さき旅カバン <中村草田男>
寒鴉(かんがらす) (晩冬)[寒鴉(かんあ)]
寒さが厳しくなると、餌(えさ)を求める鴉が人家近くに現れ、ときには傍若無人に台所のごみをあさったりする。
寒鴉羽うちておのれ醒(さ)ましけり <鷲谷七菜子>
寒鯉(かんごい) (晩冬)
寒中の鯉。川や池の底に潜っていてあまり動かないが、釣りの対象としておもしろく、また食用として美味である。
生きてをる寒鯉の眼(め)とあひにけり <富安風生>
寒雀(かんすずめ) (晩冬)[ふくら雀]
寒くなると、雀は餌(えさ)を求めて、人家近くにやってくる。寒さのために毛並のふくらんだ雀を「ふくら雀」という。
寒雀身を細うして闘へり <前田普羅>
狐(きつね) (三冬)
各地の山野に生息していて、利口な動物とされており、昔から人をだまし、また人に取り憑(つ)くといわれてきた。冬、人里近くにきて、鶏を襲ったりするので冬季とされている。
母と子のトランプ狐啼(な)く夜なり <橋本多佳子>
鯨(くじら) (三冬)[勇魚(いさな)]
鯨は冬、日本の近海に回遊してきて、古くから漁の対象とされ、「勇魚」とよばれた。
暁や鯨の吼(ほ)ゆる霜の海 <暁台>
雪の上に鯨を売りて生きのこる <加藤楸邨>
熊(くま) (三冬)[羆(ひぐま)・月輪熊(つきのわぐま)・黒熊]
「羆」は北海道、「月輪熊」は東北地方以西にいる。この二種を総称して「黒熊」という。冬の初め、冬眠に入る前の熊が人里近くに現れることがある。厳寒期の熊は冬眠中なので人の目に触れることは少ないが、北方の動物というイメージもあって、冬季とされている。
熊の子が飼はれて鉄の鎖舐(な)む <山口誓子>
鷹(たか) (三冬)[大鷹(おおたか)・蒼鷹(もろがえり)・刺羽(さしば)・隼(はやぶさ)]
日本では鷲(わし)に次ぐ猛禽(もうきん)。「大鷹」は「蒼鷹」ともいい、鷹狩に用い、日本にいる留鳥である。「刺羽」は日本で生まれて南方へ渡り、「隼」は北方から渡ってくるものと、日本で繁殖するものがある。鷹は冬によく目にし、鷹狩のシーズンも冬なので、冬季とされる。
鷹一つ見付けてうれし伊良古崎(いらござき) <芭蕉>
千鳥(ちどり) (三冬)[磯(いそ)千鳥・遠(とお)千鳥]
一般に水鳥として冬季としているが、種類によっては、夏に日本にいて冬は南方へ行くものや、春と秋に日本を通過するだけのものもある。海浜にいることが多く、よく海上を飛び交う。そのようすについて「磯千鳥」「遠千鳥」などさまざまな言い方がある。
立つ浪(なみ)に足見せて行く千鳥かな <太祇>
遠千鳥ちりぢり高し多摩川原(たまがはら) <高野素十>
海鼠(なまこ) (三冬)[海参(いりこ)]
海にいる棘皮(きょくひ)動物。形はグロテスクだが、美味。冬がいちばんうまいので冬季とされる。「海参」は煮て干したもので、中華料理の材料にされる。
生きながら一つに氷る海鼠かな <芭蕉>
河豚(ふぐ) (三冬)[真(ま)河豚・虎(とら)河豚・ふくと]
驚いたときなど、腹を膨らませユーモラスな姿になる。とくに肝臓と卵巣が有毒だが、身がたいへん美味で、刺身や鍋(なべ)料理にされる。古く「ふくと」といった。
あら何ともなやきのふは過てふくと汁 <芭蕉>
河豚食ふや小鼻動かす癖ありて <内藤吐天>
鰤(ぶり) (三冬)[寒(かん)鰤・初(はつ)鰤]
冬、日本の沿岸に回遊してくる鰤を「寒鰤」と称し、脂がのって美味である。「初鰤」はその冬初めての鰤。
鰤の海沖津白波加へけり <水原秋桜子>
塩打ちし寒鰤の肌くもりけり <草間時彦>
水鳥(みずとり) (三冬)[水禽(すいきん)・浮寝鳥(うきねどり)]
水に浮かぶ鳥の総称。鴨(かも)、雁(がん)、鳰(にお)、鴛鴦(おしどり)など。秋に北方から渡ってきて、冬の間を日本で過ごし、春にまた北へ帰ってゆくものが多いところから、冬季とする。水の上で寝る姿を「浮寝鳥」という。
水鳥や舟に菜を洗ふ女あり <蕪村>
さしのぞく木(こ)の間月夜や浮寝鳥 <松本たかし>
植物
落葉(おちば) (三冬)[落葉山(おちばやま)・落葉籠(かご)]
落葉樹は、秋の終わりごろから冬にかけて葉を落とし、冬の間、地に散り敷いている。「落葉山」に入り、「落葉籠」にかき集めて、堆肥(たいひ)をつくったりする。
西吹けば東にたまる落葉かな <蕪村>
わが歩む落葉の音のあるばかり <杉田久女>
蕪(かぶ) (三冬)[かぶら・かぶらな]
大根とともに親しまれている冬の根菜(こんさい)。煮て食べることもあるが、種々の漬物にすることが多い。各地に名産の蕪がある。「すずな」といえば春の七草の一つ。
大鍋(なべ)に煮くづれ甘きかぶらかな<河東碧梧桐>
濁り江に出荷のための蕪洗ふ <森田峠>
枯蘆(かれあし) (三冬)
冬になって枯れた水辺の蘆。一面の枯れた蘆は、寒々としているが、美しい情景でもある。
枯蘆の日に日に折れて流れけり <闌更>
枯草(かれくさ) (三冬)[草枯(くさか)る]
冬の枯れた草。「枯草」は個々の草が枯れたのをいうことが多いが、「草枯る」はある程度の広さの草が枯れたことをいうのが普通である。
枯草と一つ色なる小家かな <一茶>
草枯れて石のてらつく夕日かな <村上鬼城>
寒菊(かんぎく) (三冬)[冬菊(ふゆぎく)]
冬に咲く種類の菊。花も葉もやや小さい。黄色の花が多いが、白い花もある。
寒菊や粉糠(こぬか)のかかる臼(うす)の端(はた) <芭蕉>
冬菊のまとふはおのがひかりのみ <水原秋桜子>
寒椿(かんつばき) (晩冬)[冬椿]
寒中に咲く種類の椿。また伊豆や房総地方、あるいは紀州、四国、九州などの暖かい地方では、普通の椿も冬の間に花をつける。
赤き実と見てよる鳥や冬椿 <太祇>
寒椿つひに一日(ひとひ)の懐手(ふところで) <石田波郷>
寒梅(かんばい) (晩冬)[冬(ふゆ)の梅(うめ)・早梅(そうばい)・寒紅梅(かんこうばい)]
梅は種類によっては冬のうちに咲き始める。「寒紅梅」は12月に咲くが、香りが少ない。
寒梅や雪ひるがへる花のうへ <蓼太>
冬の梅あたり払つて咲きにけり <一茶>
早梅や日はありながら風の中 <原石鼎>
木の葉(このは) (三冬)[木の葉雨・木の葉散る]
「木の葉」というだけで、枯れて散る葉、いま散ろうとしている葉などを思い、冬季とする。「木の葉雨」は、木の葉が雨のようにぱらぱらと落ちること。
水底(みなそこ)の岩に落ちつく木の葉かな <丈草>
山茶花(さざんか) (初冬)
冬の初めに、白色や淡紅色の五弁の花をつける。椿(つばき)に似ているが、花も葉も小ぶりである。
山茶花に月夜いみじき二三日 <細見綾子>
水仙(すいせん) (晩冬)[水仙花(すいせんか)]
水仙は冬の終わりから早春にかけて咲くが、俳句では冬季とされている。「水仙」というだけで水仙の花を意味する。
水仙や夜はかくるる月の中 <二柳>
水仙や古鏡(こきゃう)の如(ごと)く花をかかぐ <松本たかし>
大根(だいこん) (三冬)[だいこ]
もっとも親しまれている冬の根菜。種類が多く、生でも、煮ても、漬物にしても食べられる。「すずしろ」といえば春の七草の一つになる。
大根に実の入る旅の寒さかな <園女>
流れ行く大根の葉の早さかな <高浜虚子>
茶の花(ちゃのはな) (初冬)
白い小さな花が、茶畑や垣根などにみられる。つつましく、静かな感じである。
茶の花に兎(うさぎ)の耳のさはるかな <暁台>
石蕗の花(つわのはな) (初冬)[つわぶきの花]
暖かい地方に自生するが、庭にも植えられる。全体が蕗(ふき)に似ているが、葉は蕗よりも緑が濃く、光沢がある。初冬のころ、長い茎を出して黄色い花をつける。
日が射して蜂(はち)を待つかの石蕗の花 <阿部みどり女>
南天の実(なんてんのみ) (三冬)[実(み)南天・白(しろ)南天]
南天は庭の隅などによく植えられ、固まった小さな実が冬の間、赤くつややかに熟して美しい。実の白い「白南天」もある。正月の床飾りにも用いられる。
南天の早くもつけし実のあまた <中川宋淵>
実南天二段に垂れて真赤かな <富安風生>
葱(ねぎ) (三冬)[根深(ねぶか)・葉葱(はねぎ)・一文字(ひともじ)]
古くから栽培され、野菜として食べられ、また薬味としても用いられている。昔の女房詞(にょうぼうことば)で「一文字」というのは、古く「葱(き)」と称し、それが1文字(1音)であることによるとか、茎が1本長く育つので、その形によるとかいわれている。
葱の香や傾城町(けいせいまち)の夕あらし <蝶夢>
冬草(ふゆくさ) (三冬)[寒草(かんそう)]
冬も青く枯れ残っている草。枯れた草は「枯草」といい、「冬草」とは別である。
冬草やはしごかけ置く岡の家 <乙二>
冬木立(ふゆこだち) (三冬)[枯木立(かれこだち)・冬木(ふゆき)・寒林(かんりん)]
立ち並んだいかにも冬らしいようすの木立。落葉樹が葉を落とし尽くしたものもあれば、常緑樹でも、勢いがなく寒さを堪えしのんでいるようなものがある。
斧(をの)入れて香におどろくや冬木立 <蕪村>
蜜柑(みかん) (三冬)[蜜柑山・温州(うんしゅう)蜜柑・紀州蜜柑]
現在は種のない「温州蜜柑」が好まれている。昔からあった「紀州蜜柑」は種が多く、小形である。炬燵(こたつ)の中や暖炉のそばで食べる蜜柑はうまい。冬の生活と蜜柑は分かちがたいものである。
をとめ今たべし蜜柑の香をまとひ <日野草城>
【新年】
時候
元日(がんじつ) [三始(さんし)・元三(がんさん)]
新年の第一日。年の始め、月の始め、日の始めであるから「三始」といい、「元三」という。「元」は始めを意味する。
元日や手を洗ひをる夕ごころ <芥川龍之介>
小正月(こしょうがつ) [望正月(もちしょうがつ)]
元日を大正月とし、それに対して正月15日、あるいは正月14日から15日までを「小正月」といって祝う。望(もち)の日(15日)を月の始めと考える古代の暦法に由来し、とくに農民の間でその習慣が受け継がれている。
松とりて世ごころ楽し小正月 <几董>
新年(しんねん) [年の始・年明く・年立つ]
一年の始めのこと。旧暦では同じころに立春となり、春がくるわけだが、いまの新年はまだ冬のさなかである。
新年の山見てあれど雪ばかり <室生犀星>
初春(はつはる) [新春・明(あけ)の春・花の春・老の春]
旧暦の新年は春の初めでもあるので、初春という。いまの暦では春ではないが、やはり「初春」は新年の意味で用いられる。「花の春」「老の春」のような「――の春」という言い方の「春」も、新年を意味する。
初春や思ふ事なき懐手(ふところで) <尾崎紅葉>
たのしさとやや淋(さび)しさと老の春 <富安風生>
松の内(まつのうち) [松七日(まつなのか)・注連(しめ)の内(うち)]
正月の門松を立てておく期間。古くは15日まで。現在も関西では15日までだが、関東では7日までとされている。
子を持たぬ身のつれづれや松の内 <永井荷風>
天文
御降(おさがり) [富正月(とみしょうがつ)]
元日に降る雨または雪。三が日の間に降るものにいうこともある。「御降」があるとその年は豊年であるといわれているので、「富正月」という。
お降りや暮れて静かに濡(ぬ)るる松 <島田青峰>
初空(はつぞら) [初御空(はつみそら)]
元日の空。晴れ渡った空と考えるのが普通だが、すこし雲があってもよい。
初空の雲静かなり東山 <高浜虚子>
初日(はつひ) [初日(はつひ)の出(で)・初日影(はつひかげ)]
元日の日の出。海辺や山上へ出かけていって初日を拝む風習がある。
大空のせましと匂(にほ)ふ初日かな <鳳朗>
地理
初富士(はつふじ)
元日に見る富士。昔、江戸の町から遠く見る富士を賞した。いまも元日は工場などが休んでいるので、大気の汚染が少なく、晴れていれば東京のビルの屋上などから富士が見える。
初富士のかなしきまでに遠きかな <山口青邨>
若菜野(わかなの)
春の七草を摘む野。「若菜」は春の七草のこと。
若菜野に昔男ぞなつかしき <伊藤松宇>
生活
鏡餅(かがみもち) [お鏡・具足餅(ぐそくもち)・餅鏡(もちいかがみ)]
正月の供え餅。大小の中高の丸餅を2個一重ねにしたもの。伊勢海老(いせえび)、橙(だいだい)、串柿(くしがき)、昆布、楪(ゆずりは)など、めでたいものを添えて飾る。武家では床の間に具足を飾り、その前に紅白の餅を飾り、「具足餅」という。
一村(いっそん)を鼓でよぶや具足餅 <史邦>
鏡餅母在(ま)して猶(なほ)父恋し <暁台>
書初(かきぞめ) [試筆(しひつ)・筆始(ふではじめ)・吉書(きっしょ)]
新年になって初めて書や画(え)をかくことをいう。めでたい文句や詩歌を書くことが多く、「吉書」ともいう。宮中では2日に「吉書始(きっしょはじめ)」が行われ、一般でも2日に行われることが多い。
大津絵の筆のはじめは何仏(なにぼとけ) <芭蕉>
大和仮名(やまとがな)いの字を児(ちご)の筆始 <蕪村>
書初やうるしの如(ごと)き大硯(すずり) <杉田久女>
門松(かどまつ) [松飾(まつかざり)・門木(かどき)]
正月、家の戸口や門の前に立てる一対(いっつい)の松の飾り。松に竹を組み合わせたのが多いが、地方によっては、楢(なら)、榊(さかき)、樒(しきみ)、椿(つばき)その他さまざまな木が用いられ、「門木」という。
門松や本町筋の夜の雨 <一茶>
一人子と閑(しづ)かに住めり松飾 <日野草城>
歌留多(かるた) [歌がるた・いろはがるた]
正月の室内の遊び。藤原定家が選んだものといわれる小倉(おぐら)百人一首が用いられ、それを「歌がるた」というのに対して、子供向きのやさしい「いろはがるた」がある。
座を挙げて恋ほのめくや歌かるた <高浜虚子>
獅子舞(ししまい) [獅子頭(ししがしら)・獅子の笛]
正月に家々を訪れて、祝意を表す芸能。越後(えちご)月潟出身の越後獅子・角兵衛獅子が名高い。
獅子舞は入日の富士に手をかざす <水原秋桜子>
顔(かんば)せにあてて吹くなり獅子の笛 <橋本鶏二>
注連飾(しめかざり) [年縄(としなわ)・飾縄(かざりなわ)・飾藁(かざりわら)・輪飾(わかざ)り]
魔除(まよ)けのために正月の門口に張る注連縄(しめなわ)。左縒(よ)りの縄で、白幣(はくへい)を垂らし、藁の尻(しり)は切らない。地方によっては昆布や串柿(くしがき)、橙(だいだい)、あるいは伊勢海老(いせえび)などを取り付けて飾る。大小さまざまあって、門口以外のあちらこちらや、仕事の道具などにも飾る。
洗はれて櫓櫂(ろかい)細身や注連飾 <大野林火>
雑煮(ぞうに) [羹(かん)・羹を祝う]
普通、正月三が日雑煮を祝う。神仏に供え、一家そろって膳(ぜん)につく。正月6日まで食べて七日粥(なぬかがゆ)以後は食べないという所もある。調理の仕方は地方によってさまざまである。古くは「羹」といった。餅を羹(あつもの)にするのである。
三椀(さんわん)の雑煮かゆるや長者ぶり <蕪村>
年玉(としだま) [お年玉]
正月の贈り物。とくに子供に対するものにいうことが多い。もともとは正月の神への供物であり、それは同時に神からの賜り物であるという意味をもっていた。
年玉の蕪菜(かぶな)かろげや黒木うり <蝶夢>
かへらうといふ子にお年玉何を <上村占魚>
屠蘇(とそ)
新年に飲む長寿息災の薬酒。山椒(さんしょ)、細辛(さいしん)、防風(ぼうふう)、桔梗(ききょう)、乾薑(かんきょう)、白朮(びゃくじゅつ)、肉桂(にっけい)などを調合した屠蘇延命散を味醂(みりん)に入れてつくる。
指につく屠蘇も一日匂(にほ)ひけり <梅室>
年始(ねんし) [年賀(ねんが)・年礼(ねんれい)・礼者(れいしゃ)・御慶(ぎょけい)]
新年、親戚(しんせき)や知人の間で正式の訪問をして賀辞を述べること。正月三が日の間のこととされていたが、近年はかならずしもそれにこだわらず、4日以後も、松の内くらいには行われている。
長松(ちゃうまつ)が親の名で来る御慶かな <野坡>
年賀やや羞(は)ぢらひて子の髪厚し <石田波郷>
羽子板(はごいた) [羽子(はね)・羽子(はね)つく]
むくろじの実に鳥の羽をつけた「羽子」を突いて遊ぶための柄(え)のついた板。板に簡単な絵をかいた素朴なものから、役者絵の押し絵細工を施した豪華なものまである。
東山静かに羽子の舞ひ落ちぬ <高浜虚子>
羽子板の重きが嬉(うれ)し突かで立つ <長谷川かな女>
初夢(はつゆめ) [夢はじめ]
新年、最初にみる夢。古くは節分の夜から立春の明け方までの夢をいったが、元禄(げんろく)のころからは除夜の夢、やがて、正月2日の朝の夢をいうようになった。明治以後は2日の夜みる夢をいう。「一富士、二鷹(たか)、三茄子(なすび)」が吉夢の代表とされている。
初夢に古郷(ふるさと)を見て涙かな <一茶>
黒髪の初夢の端踏まれけり <鷹羽狩行>
春著(はるぎ) [春着(はるぎ)]
正月に着る新調の晴れ着。普通は女性の和服についていう。
春著きるや裾(すそ)ふみおさへ腰細く <杉田久女>
松納(まつおさめ) [松取る・松送り]
門松を取り払うこと。地方によって日は違う。東京は6日の夕方、京都・大阪地方では14日の夕方である。また7日の所も多く、ほかに4日、11日などがある。
松とりて二日になりしやなぎかな <大江丸>
月白うして鳰(にほ)啼(な)くや松納 <渡辺水巴>
万歳(まんざい) [三河(みかわ)万歳・大和(やまと)万歳・尾張(おわり)万歳]
正月に家々を訪れ、祝言を述べる一種の門付(かどづけ)。出身地によって「三河万歳」「大和万歳」「尾張万歳」などとよばれる。
万歳の烏帽子(えぼし)さげ行く夕日かな <闌更>
行事
七草(ななくさ) [七種(ななくさ)・七草粥(がゆ)・七草打(うち)・薺打(なずなうち)]
正月7日、粥に7種の菜を入れて食べる。万病を除くとされる。その7種は時代によってやや異なるが、現在は、芹(せり)、薺(なずな)、五行(ごぎょう)、はこべら、仏の座、菘(すずな)(蕪菜(かぶらな))、蘿蔔(すずしろ)(大根)とされる。菜は6日の夜、まな板の上で、「七種なずな、唐土の鳥と日本の鳥と、渡らぬさきに七種なずな……」とはやしながらたたく。それを「七草打」「薺打」という。
七種やあまれどたらぬものもあり <千代女>
俎板(まないた)の染むまで薺打はやす <長谷川かな女>
初詣(はつもうで) [初参(はつまいり)・初社(はつやしろ)]
元日の早朝に鎮守の社に参詣(さんけい)すること。また、元日に限らず、新年のうちに、神社や寺にその年初めて参詣することにもいう。大都会の近くでは人気のある神社や寺に初詣が集中する。
鳩の翔(た)つ塵(ちり)もめでたし初詣 <富安風生>
藪入(やぶいり) [宿下(やどさが)り・十六日遊(じゅうろくにちあそ)び]
1月16日、奉公人が休みをもらって自宅に帰ること。「宿下り」「十六日遊び」ともいう。
やぶ入の寝るやひとりの親の側 <太祇>
若菜摘(わかなつみ) [若菜・若菜野(の)]
正月6日に、7日の七草のための若菜を摘むこと。若菜は「七草」の総称。
朝の間に摘みてさびしき若菜かな <白雄>
草の戸に住むうれしさよ若菜摘 <杉田久女>
若水(わかみず) [初水(はつみず)・福水(ふくみず)・若水汲(く)み]
元日の朝一番に汲む水。「若水汲み」はその家の主人が勤めるが、年男の役目ともされる。汲む時刻が決められていたり、その際、種々の儀式めいたことが行われたりする。
わかみづや流るるうちに去年(こぞ)ことし <千代女>
若水や一つの桶(をけ)へ二釣瓶(ふたつるべ) <小杉余子>
動物
初鴉(はつがらす)
元日にみかけたり、声を聞いたりする鴉。普段はその黒い姿としわがれ声から、不吉だとして嫌われる鴉も、元日には改まった感じがして悪いものではない。
ばらばらに飛んで向うへ初鴉 <高野素十>
嫁が君(よめがきみ)
正月三が日にみかけたり、物音を聞いたりする鼠(ねずみ)のこと。鼠は大黒様の使いともされており、正月にこれをもてなす地方もある。
明る夜のほのかにうれし嫁が君 <其角>
植物
歯朶(しだ) [裏白(うらじろ)]
新年の飾りに用いる裏白のこと。2枚の葉が相対し、常緑で、かつ裏が白いところからめでたいものとされた。
誰(た)が聟(むこ)ぞ歯朶に餅(もち)負ふ丑(うし)の年 <芭蕉>
福寿草(ふくじゅそう)
もともと野生の宿根草だが、江戸時代に鉢植えにして観賞されるようになった。晩冬のころ、地中から短い茎を出し、黄色のふくよかな感じの単弁花を開く。新年を祝う植物とされ、浅い鉢に梅や南天などと寄せ植えにされて新年の床飾りに用いられる。
福寿草家族のごとくかたまれり <福田蓼汀>
楪(ゆずりは) [譲葉(ゆずりは)・杠(ゆずりは)]
宮城県以西に自生する常緑高木。高さは10メートルほどになり、庭木にもする。新しい葉が出ると、古い葉が垂れ下がって場所を譲るようにみえるところから「譲葉」という。めでたい木として、その葉を新年の飾りに用いる。
ゆずり葉の茎も紅(べに)さすあしたかな <園女>
季語
きご
俳句、俳諧(はいかい)、連歌のなかの季節を表すことば。「春風」(春)、「夕立」(夏)、「紅葉(もみじ)」(秋)、「雪」(冬)などの類。古くは単に季、あるいは季の詞(ことば)、四季の詞といった。「季題」と同じ意味に用いられるが、とくに俳句の場合に限って「季題」といい、俳諧、連歌の付句(つけく)の場合に「季語」といって、区別することもある。近年の俳句では「季語」といわれることが多い。季語は日本文学の長い歴史のなかで、しだいに成熟し、増加してきた。季語はこの国における風土と感情の特徴をよく表しており、ただ俳句のためだけのものでなく、広く日本文化を考えるうえでの鍵(かぎ)ともなるような語群を形成している。季語の総体が大きな文化的産物であるともいえる。
あることばが一定の季節を表すという考えは、すでに平安時代の歌人の間にもみられ、『能因歌枕(うたまくら)』には12か月に分けて約150の季節を表すことばが収められている。南北朝時代から室町時代にかけての連歌の発句(ほっく)において、季語はなくてはならないものと考えられるようになり、付句においても季語の働きが注目された。里村紹巴(じょうは)の連歌論書『連歌至宝抄』(1627)には約270の季語がみられる。江戸時代になって、俳諧が成立すると、季語はますます重要視され、庶民的な生活感覚を反映して、新しい季語も増え、季語を集めた「季寄せ」「歳時記」の類も多く出版されるようになった。江戸初期の北村季吟の『山之井』(1648)は約1300の季語を収めるが、同後期の曲亭馬琴(ばきん)著・藍亭青藍(らんていせいらん)増訂『俳諧歳時記栞草(しおりぐさ)』(1851)では約3300の季語を集めている。現代の歳時記は4000数百の季語を収めているのが普通である。近代俳句の革新者正岡子規(まさおかしき)は、季語の実感を重んじ、季語のもつ連想内容の豊富さが俳句にとって有益であると考えた。それを受け継ぐ高浜虚子(きょし)は、日本の風土的・民族的性格をよく表すものとして季語を重んじた。
[山下一海]
『飴山実他著『季題入門』(有斐閣新書)』
改訂新版 世界大百科事典 「季語」の意味・わかりやすい解説
季語 (きご)
一定の季節と結びつけられて,連歌,俳諧,俳句で用いられる語を季語(または季題)という。少数の語の季語化は,《古今和歌集》以下の勅撰和歌集でなされていたが,季語化の意識が強くなったのは,四季の句をちりばめて成立する連歌においてである。連歌の季語化は,和歌によって培われた情趣にもとづき,季語としての内容(本意(ほい))を確定するものであった。〈春の日も事によりて短き事も御入候へども如何にも永々しきやうに〉(紹巴《至宝抄》)受けとることにより,〈春の日〉という季語の本意が決まったのである。連歌の一体として発生しながらも,江戸時代に独自の展開をした俳諧では,季語がいちじるしく増大する。1641年刊の《誹諧初学抄》では約600語だった季語が,幕末の《俳諧歳時記栞草》(1851)では3000を軽く超えている。和歌,連歌の季語は,貴族の自然観や人生観に根ざしていたが,俳諧においては,〈売初(うりぞめ)〉〈麦蒔(むぎまく)〉(《誹諧初学抄》)のように町人,農民などのことばが数多く季語化されたのである。短詩である俳句の流行した明治以降は,季語は作品と読者をつなぐ紐帯として重んじられ,さらに増加を続けている。たとえば〈春一番〉は1960年代に定着した新しい季語である。季語は,季節(四季)による世界の分節化・秩序化であり,各季語の来歴は,日本人の感覚と思考の軌跡だといってよいだろう。コラム参照
→歳時記
執筆者:坪内 稔典
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の季語の言及
【挨拶】より
…その上で,状況に応じて称賛・卑下などの寓意を託することもある。俳句に季語をよみこむのは,その名ごりであるが,近代の独詠は脇を予想しない。それに対して,連句時代の発句のもつ対詠的性格を広く挨拶とよぶこともある。…
【季題】より
…連歌,俳諧や近代俳句で,句に詠みこむ季節感をもつ特定の語を,古くは〈四季の詞〉〈季の詞〉などといったが,明治末年以後,俳句に用いる四季の詞について,季題という語が用いられて一般化した。季語が広く連歌,俳諧の付句に用いる四季の詞までを含んで用いられるのに対して,俳句(発句)の季語を意味することが多い。早く和歌では勅撰集などで四季の部立が行われ,題詠の風も一般化し,季節の景物を詠むことが行われて,季節の詞が諷詠の題となった。…
【詩語】より
…また〈歌枕〉は名所として人々の憧憬を刺激する地名だが,地名をいうだけで人々の共同的想像力をかきたてえた点で,重要な詩的装置であり,古典的なpoetic dictionの好例といえるものであった。さらに重要なものとして,《万葉集》《古今和歌集》以後,連歌・俳諧の長い歴史的経過を通じ,きわめて精緻に体系化され,現代の俳句歳時記に集大成されている〈季題〉〈季語〉の一大宝庫がある。季題とは四季それぞれの歌を詠むに当たって,その季節を一語よく象徴しうるごとき題を詠題として立てた万葉や古今以来の分類法にもとづく用語である。…
※「季語」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...