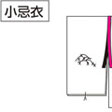関連語
精選版 日本国語大辞典 「小忌衣」の意味・読み・例文・類語
おみ‐ごろもをみ‥【小忌衣】
日本大百科全書(ニッポニカ) 「小忌衣」の意味・わかりやすい解説
小忌衣
おみごろも
日本古代以来の祭服の一種。小忌とは不浄を忌み嫌う、すなわち清浄という意味で、大嘗会(だいじょうえ)や新嘗祭(にいなめさい)などの宮中の神事に、小忌人(おみびと)とよばれる祭官や、舞姫が着用する上着。束帯(そくたい)の袍(ほう)の上、または女房装束の唐衣(からぎぬ)の上に着装する白の麻布製で、身頃(みごろ)には春草、梅、柳、鳥、領(えり)に蝶(ちょう)、鳥などを山藍摺(やまあいずり)(青摺)で表す。右の肩に、赤紐(あかひも)という赤、黒二筋の組紐をつけて垂らす。舞楽の「東遊(あずまあそび)」を神社の庭上で奉奏するときに、舞人や歌方が着用する小忌衣は袍の形で、前者が桐竹(きりたけ)文、後者が棕梠(しゅろ)文を山藍摺で表し、赤紐は左肩につけられている。
[高田倭男]
[参照項目] | | |
関連語をあわせて調べる
2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...