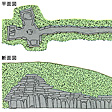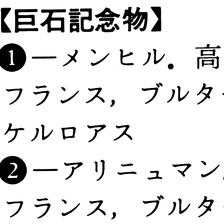日本大百科全書(ニッポニカ) 「巨石記念物」の意味・わかりやすい解説
巨石記念物
きょせききねんぶつ
面取りや化粧仕上げなどの加工が比較的少ない大きな石を用いてつくられた建造物で、一般に新石器時代から初期金属器時代に建造されたものをいう。その研究は19世紀後半に西ヨーロッパで始まった。巨石ということばはギリシア語のメガスmegas(巨大な)とリトスlithos(石)に由来し、英語ではmegalithic monumentという。
中世には、巨石記念物を「巨人の墓」とする考えが主流であった。これは各地にみられる古文書などによって知られ、中世のヨーロッパ人は「巨人の墓」の被葬者の身長を3~5メートルと考えていた。その後、文献による巨石記念物の建造者の究明が試みられ、ローマ人などさまざまな民族が建造者とみなされた。また、ローマ時代の歴史家や旅行家の著述に、イギリスの巨石記念物の記載がないことから、これをローマ時代以降のものとする説も主張された。
巨石記念物と一口にいってもその内容は多岐にわたる。G・ダニエルはヨーロッパの巨石記念物を次の4種に分けた。
[寺島孝一]
立石
第一は単一の立石(りっせき)(メンヒルmenhir)で、フランスのブルターニュ地方に多く分布している。高さは1~6メートルほどのものが多いが、とくに巨大なロックマリアケルのメンヒルは長さ20メートルを超えている。また南フランスからイタリアにかけては、彫刻のある立石がみられる。
[寺島孝一]
立石群
第二は立石群で、これはさらに二つに分けられる。一つは環状列石で、グレート・ブリテン島西部には、コーンウォールやカンバーランドで単一の輪を形成するものがある。同じ環状列石でも、エーブベリーやストーンヘンジでは、幾重にも列石を巡らせたり、堤や溝をつくっている。これらを総称してストーン・サークルstone circleとしているが、その多くが正円ではなく、楕円(だえん)形を呈しているところから、近年はストーン・リングstone ringとよばれることが多い。立石群の第二は列石(アリニュマンalignement)で、フランスのブルターニュ地方カルナックの列石が著名である。この列石は大きく3群に分かれるが、東西にほぼ4キロメートルにわたり続くものである。この3群のうち用いられた石材のもっとも多いものはメネック群で、幅100メートル、長さ100メートルの中に、1099本の立石が11列に並べられている。アリニュマンの分布は、フランス、イギリスにとくに多い。
[寺島孝一]
巨石墓
第三は巨石墓で、これがヨーロッパの巨石記念物のなかではもっとも多く、中心的な存在である。分布はスカンジナビア半島からイベリア半島まで普遍的にみられ、現在も5万基ほどが残っているとされている。巨石墓のなかで支石墓(ドルメンdolmen)は、3枚以上の支石の上に天井石をのせた比較的単純な構造をもっている。羨道墓(せんどうぼ)(ギャラリー・グレーブgallery grave)で最大のものはアイルランドのニューグレンジにあるもので、長さ19メートルの墓道と、高さ6メートルの十字形をなす玄室からなっている。この天井は持送り式にしているが、この形態はイギリスのオークニー諸島に数多くみられる。
[寺島孝一]
巨石神殿
第四は巨石神殿であるが、これは地中海のマルタ島、ゴゾ島周辺に限られている。この遺跡は墓所と考えられたこともあったが、埋葬の痕跡(こんせき)がなく、現在では神殿と考えられている。
巨石墓の上や周囲に立石が配されたり、立石群が巨石墓に連なるなど、立石や立石群と巨石墓はそれぞれ独立したものではなく、互いに関連したものであるといえる。
巨石を用いた建造物はヨーロッパに限らず世界中に認められる。ピラミッドなどは巨石記念物からは除外されることが多いが、小形の箱式石棺なども含むこともあり、巨石の範囲をどこまでとするかはさまざまである。またG・E・スミスの太陽崇拝を伴う巨石文化の移動説は、現在受け入れられていないものの、巨石記念物を考えるうえで、学界に大きな波紋を投げかけた。
[寺島孝一]
『G・ダニエル著、近藤義郎他訳『メガリス』(1976・学生社)』
改訂新版 世界大百科事典 「巨石記念物」の意味・わかりやすい解説
巨石記念物 (きょせききねんぶつ)
megalithic monuments
自然石または一部加工しただけの石で築いた建造物。メガリスは〈巨大な石〉を意味するギリシア語に由来し,最大の石には20tを超えるものがある。1本の柱状の石を立てたものはメンヒル(立石),柱状石を1ないし数列立て並べたものはアリニュマン(列石),環状に並べたものはストーン・サークル(環状列石,ウェールズ語ではクロムレック),また巨大な平石を数個の石で支えたものはドルメン(支石墓)と呼ばれ,新石器時代後半から青銅器時代初期にかけてのヨーロッパ,特に大西洋岸に色濃く分布する。同じ頃,同地には多くの石室墓が築造された。巨大な平石を立てて壁体とし,上を蓋石で覆う。形状によってギャラリー(通廊)墓とかパッセージ(羨道(せんどう))墓などと呼び分けられる。もとは墳丘で覆われ,地上に石が露出していたわけではないが,広義にはこれらも巨石記念物に含められている。
これら巨石記念物は,単独の場合もあるが,多くは各種の組合せとして存在する。たとえばフランスのブルターニュ地方のカルナック列石は,3群に分かれて東西3kmにわたって続くが,各群の端部にはストーン・サークルあるいはドルメンが付属する。またストーンヘンジ遺跡は二つのストーン・サークルからなるが,それぞれ中央にドルメンおよびメンヒルが立っている。
クレーンとか滑車などの道具がない時代に,このような巨石を動かしたり立てたりすることは極めて困難であったろう。一番重い石を動かすには,木の〈ころ〉を用い綱で引くとすると,1100人の力を要したと推定される。石を立てるにはまず穴を掘り,石の一端を穴に落としこんだ。また石を持ちあげるには〈てこ〉を用い,つぎつぎと材木をさしこんでいったと考えられている。いずれにしろ多人数の協同作業が必要であった。これら巨石記念物は広範に分散した初期農業共同体の中心に位置しており,農耕儀礼の中枢と見る考えがある一方,巨石記念物を構成する石列が,夏至に太陽が昇る方向を指すなどの理由から,太陽崇拝と結びつける解釈もある。
ところで,かつてこれら巨石記念物は,ミュケナイ文明の影響がドナウ川流域を経由して,あるいは地中海沿いに大西洋岸に達したもので,前1500年前後が最盛期であったと考えられてきた。しかし,巨石記念物はドナウ川流域には分布しておらず,かえって西ヨーロッパにおける炭素14法による年代がミュケナイ文明の発生前である前4000年頃まで遡ることを重視する学者は,大西洋岸の巨石記念物を地方的な独自の進化と見る。
ヨーロッパ以外でも類似の石造物は広く知られ,中近東からインド,およびシベリア,北日本にはストーン・サークルが,北アフリカ,インド,中国東北,朝鮮半島から北九州にはドルメン(支石墓)が分布する。オセアニア,新大陸にもメンヒルの存在が認められている。縄文時代の後・晩期,北海道および東北地方ではストーン・サークルが作られた。直径2~3mのものと10m以上の2種があり,秋田県大湯環状列石が著名である。
執筆者:山本 忠尚
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「巨石記念物」の意味・わかりやすい解説
巨石記念物【きょせききねんぶつ】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
山川 世界史小辞典 改訂新版 「巨石記念物」の解説
巨石記念物(きょせききねんぶつ)
megalithic monuments
巨石遺構ともいう。巨大な石を中心とする墳墓,または原始信仰に関係のある遺跡をいい,メンヒル(立石),アリニュマン(列石),ストーン・サークル(環状列石),ドルメン,羨道墳(せんどうふん)などがあげられる。インドシナ半島ラオスの石甕(いしがめ)や,イースター島の石人は特殊なものである。メンヒルはことにフランスのブルターニュ地方,アリニュマンも同地方,ストーン・サークルは南イギリス,フランス,スペイン,ドルメンは北フランス,スカンディナヴィア南部,北ドイツ,あるいは中国東北部の石棚,または朝鮮半島の碁盤(ごばん)式支石墓,日本の北九州の支石墓などというように分布し,ものによっては分布範囲が広い。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「巨石記念物」の意味・わかりやすい解説
巨石記念物
きょせききねんぶつ
megalithic monument
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「巨石記念物」の解説
巨石記念物
きょせききねんぶつ
megalithic monumentsの訳語。自然の,あるいはわずかに手を加えた,大きな石を使用した構造物。メンヒル(立石),アリニュマン(列石),ストーンサークル(環状列石),ドルメン(支石墓),チャンバー・トゥーム(石室墳)などを含む。新石器時代の末期以後,旧大陸の各地で,さまざまな時期に構築された。ドルメンは東南アジア各地では最近まで営造され,「生きた巨石記念物」といわれる。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
旺文社世界史事典 三訂版 「巨石記念物」の解説
巨石記念物
きょせききねんぶつ
megalithic monuments
ドルメン(石テーブル),メンヒル(立石),ストーン−サークル(環状列石),アリニュマン(並立石)などと名づけられ,墳墓や太陽崇拝の祭壇に用いられた。類似の巨石記念物は世界各地で発見されている。
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の巨石記念物の言及
【ケルト人】より
… ケルト文化は初期ヨーロッパにおいて,指導的な地位を占めた。ストーンヘンジやメンヒル,ドルメンなどの巨石記念物を,ケルト人とりわけドルイド神官の創設に帰する憶測は,現在では否定されたが,それらの祭祀的使用,装飾造形技術には見るべきものがあった。のち7,8世紀に,ケルト世界で制作された彩色装飾写本(たとえば《ケルズの書》)のように,ヨーロッパが誇る文化遺産が生まれた。…
【祭祀遺跡】より
… 農耕祭祀にかかわるものとしては,西アジアの初期新石器時代の集落に,独立した建物(パレスティナのイェリコ遺跡),あるいは建物の一部(トルコのチャタル・ヒュユク遺跡)が祠堂として使われたものがある。北西ヨーロッパの新石器時代から青銅器時代にかけては,巨大な石で構築した各種の遺構の存在が目だっており,巨石記念物と総称されている。その代表例とされるイギリスのストーンヘンジや3000本近い立石を列に並べたフランスのカルナック列石(クロムレクcromlech)は,ともに太陽崇拝との関連が論じられている。…
【先史美術】より
…
【ヨーロッパの巨石文化】
地中海の島々から大西洋の沿岸地域,グレート・ブリテン島にかけて,巨大な石で構築された建造物が多く残っている。詳細は〈巨石記念物〉の項目にゆずり,ここでは美術的に重要なもののみをとりあげる。 巨石文化を残した人々は絵画や彫刻をあまりつくらなかったが,特定の地方では,土製または石製の偶像がつくられたり,メンヒルに人物の姿を浮彫したり,巨石や土器に特殊な装飾が施された。…
【ドルメン】より
…巨石記念物の一種。ブルトン語でdolはテーブル,menは石を意味し,大きく扁平な1枚の天井石を数個の塊石で支えた形がテーブルのように見えることからこのように呼ばれた。…
※「巨石記念物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...