こしらえこしらへ【拵】
- 〘 名詞 〙 ( 動詞「こしらえる(拵)」の連用形の名詞化 )
- ① いろいろはかりめぐらすこと。いろいろと工夫すること。
- [初出の実例]「龍女が仏に成ることは、文殊のこしらへとこそ聞け」(出典:梁塵秘抄(1179頃)二)
- ② きたるべき事態にそなえて、いろいろと準備すること。
- (イ) 準備。用意。したく。
- [初出の実例]「我等討たれぬと聞き給はば、此所に転び入りて伏し沈み給ふべし。いざやこしらへせん」(出典:寛永版曾我物語(南北朝頃)七)
- (ロ) 特に嫁入りじたくのこと。
- [初出の実例]「あの身体(しんだい)の敷銀は弐百枚も過ものこしらへなしに五貫目」(出典:浮世草子・世間胸算用(1692)二)
- (ハ) 遊郭などで、座敷の準備。
- [初出の実例]「店の男来たり。〈略〉おこしらへでござります」(出典:洒落本・箱まくら(1822)下)
- ③ 飾ること。装飾すること。また、そのもの。
- (イ) 刀身相応の金具や塗り、柄巻(つかまき)などの装備。こしらえかたによって、合口拵(あいくちこしらえ)、太刀拵(たちごしらえ)、脇指拵、また、打刀(うちがたな)の好みにより肥後拵、水戸拵などがある。つくり。→こしらえつき。
- [初出の実例]「刀、脇差を、かねたくさんに付て、いかにも結構なるこしらへにて進ぜらるる」(出典:咄本・昨日は今日の物語(1614‐24頃)上)
- (ロ) 化粧、服装などをととのえること。身じたく。身なり。
- [初出の実例]「拵(コシラヘ)も貧家の娘、公界勒(くがいづとめ)さすべき衣類なけれど」(出典:浮世草子・傾城禁短気(1711)三)
- (ハ) 俳優が、いろいろと役づくりをすること。扮装(ふんそう)。
- [初出の実例]「わきをよび出すあひならは、只今いつると案内云べし。若こしらへならぬをしらず、よび出しては越度なり」(出典:わらんべ草(1660)一)
- ④ もののやりかた。しかた。方法。
- [初出の実例]「一日一日物のたらぬこしらへ、おのれも合点ながら俄かに分別も成がたし」(出典:浮世草子・世間胸算用(1692)二)
- ⑤ 構築すること。物をつくること。また、そのもの。作り。
- [初出の実例]「陵のこしらえをいそいでせらるるぞ」(出典:四河入海(17C前)三)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
Sponserd by 
拵
こしらえ
一般には外観、装飾のことなどをいうが、日本刀では外装のことで、刀装ともいう。刀剣を保護し、使用しやすくするために不可欠のものであるが、佩用(はいよう)者の威容を整え、その身分や家柄を表示するものでもあった。
時代によって変遷があるが、長寸のものは大きく分けて太刀拵(たちごしらえ)と打刀(うちがたな)拵になる。寸法の短いものには腰刀拵、小サ刀(ちいさがたな)拵、合口(あいくち)拵などと呼称されるものがある。平安時代から鎌倉時代にかけては、太刀拵が盛行し、南北朝から室町時代にかけては、戦乱の多かったことから、太刀にかわって打刀が用いられるようになった。これが戦国時代になると、戦闘方式の変化に伴い、従来腰に佩(は)いていた太刀拵の儀仗(ぎじょう)的性格が強くなり、一般には具足(ぐそく)の締帯(しめおび)に差す打刀の形式が流行するようになった。打刀拵では、太刀拵のような帯執足金物(おびとりあしかなもの)がなく、鞘(さや)は塗鞘(ぬりざや)で、それまでとは異なった自由な意匠が施されるに至った。江戸時代の武家においては、裃(かみしも)着用の際の大小拵(打刀と脇差)は、鞘は黒蝋(ろう)色塗、柄糸(つかいと)・下緒(さげお)も黒組糸を用い、鐔(つば)・小柄(こづか)・笄(こうがい)などには後藤家作の鳥銅地金色絵のものをつけるのが制となる。また尾張(おわり)拵とか薩摩(さつま)拵とかいう、各藩ごとに特色のある形式を生じた。
[小笠原信夫]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
拵【こしらえ】
刀装ともいう。日本刀の外装,すなわち刀身を入れる鞘(さや),茎(なかご)(握る部分)を入れる柄(つか)および鐔(つば)の総称。なお鐔のないものを合口(あいくち)拵という。儀仗(ぎじょう)(儀式用)と兵仗(武用)とがある。平安時代には公卿(くぎょう)の飾太刀があり,武家には毛抜形太刀,錦包籐巻(とうまき)太刀,銀・銅蛭巻(ひるまき)太刀,黒漆太刀,兵庫鎖太刀などがあった。鎌倉〜室町期には革包(かわづつみ)太刀が盛行。室町中期には戦闘様式の変化に伴い打刀拵が生まれた。桃山時代には打刀と腰刀を共造(ともづくり),すなわち1対とする大小拵が生まれ,江戸時代には裃(かみしも)着用の際に大小拵を用いたが,鞘は黒蝋塗で,柄糸(つかいと),下緒(さげお)も黒の組糸を用い,小柄(こづか),笄(こうがい)は後藤家の作をつけることなどが規定された。富裕な町人の拵にも趣向がこらされた。
→関連項目日本刀|三所物
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
拵 (こしらえ)
日本で刀剣の外装をいい,〈つくり〉などともいう。起源は古墳時代にさかのぼるが,用語としては,江戸時代に入ってから使われたものであろう。柄(つか),鞘(さや),鐔(つば)の3部から成る。本来は身の危険を防ぎ,刀身を保護するためのものであるが,やがて身分の標識,着用者の嗜好,戦闘方法の変移などのさまざまな要素が加わって,その様式も変化し,単なる実用品ではない,金工,漆工などの高度の技術を駆使したものも現れる。しかし装飾は無制限ではなく,公家社会では金,銀,銅などの材質や,蒔絵,螺鈿(らでん)などの加飾方法も位階によって異なっていた。武家社会でも華美,豪奢になることを禁止する法が各時代にしばしば公布されている。
→刀装
執筆者:原田 一敏
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
普及版 字通
「拵」の読み・字形・画数・意味
拵
9画
[字音] ソン
[字訓] よる・こしらえる
[字形] 形声
声符は存(そん)。〔集韻〕に「据る」「插む」の訓がみえるが、用例はほとんどない。〔左伝、哀八年〕「 (こ)れを樓臺に囚へ、之れを拵(かこ)ふに棘(きよく)を以てす」の〔注〕に、「拵は擁なり」とみえる。
(こ)れを樓臺に囚へ、之れを拵(かこ)ふに棘(きよく)を以てす」の〔注〕に、「拵は擁なり」とみえる。
[訓義]
1. よる。
2. 国語で、「こしらえる」「かこう」とよむ。
[古辞書の訓]
〔名義抄〕拵 カコフ
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内の拵の言及
【刀装】より
…刀剣の外装のことで,[拵](こしらえ)ともいう。刀剣を身につけるのに,また保護するのに不可欠のものであるが,佩用(はいよう)者の身分や好尚,時代の式制によっていろいろな様式,種類がみられる。…
※「拵」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by 


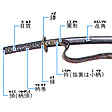
 (こ)れを樓臺に囚へ、之れを拵(かこ)ふに棘(きよく)を以てす」の〔注〕に、「拵は擁なり」とみえる。
(こ)れを樓臺に囚へ、之れを拵(かこ)ふに棘(きよく)を以てす」の〔注〕に、「拵は擁なり」とみえる。