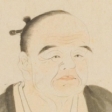関連語
精選版 日本国語大辞典 「松下見林」の意味・読み・例文・類語
まつした‐けんりん【松下見林】
日本大百科全書(ニッポニカ) 「松下見林」の意味・わかりやすい解説
デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「松下見林」の解説
旺文社日本史事典 三訂版 「松下見林」の解説
松下見林
まつしたけんりん
江戸前期の儒医・歴史学者
大坂の人。古林見宜 (けんき) に医学を学び,算数・経学にも通じた。21歳で京都にのぼり国史の研究に没頭,『日本三代実録』の校訂や『異称日本伝』を編纂した。和漢の古典にくわしく,蔵書は10万巻余といわれる。晩年讃岐(香川県)高松藩に仕えた。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
367日誕生日大事典 「松下見林」の解説
松下見林 (まつしたけんりん)
江戸時代前期;中期の歴史家
1704年没
出典 日外アソシエーツ「367日誕生日大事典」367日誕生日大事典について 情報
関連語をあわせて調べる
[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...