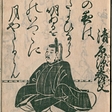関連語
精選版 日本国語大辞典 「清原深養父」の意味・読み・例文・類語
きよはら‐の‐ふかやぶ【清原深養父】
改訂新版 世界大百科事典 「清原深養父」の意味・わかりやすい解説
清原深養父 (きよはらのふかやぶ)
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「清原深養父」の意味・わかりやすい解説
清原深養父
きよはらのふかやぶ
生没年未詳。平安中期の歌人。908年(延喜8)内匠允(たくみのじょう)、923年(延長1)内蔵(くら)大允、930年従(じゅ)五位下(『古今集(こきんしゅう)目録』)の官位のみ知られる『古今集』時代の歌人。房則の息で、孫に歌人元輔(もとすけ)、曽孫(そうそん)に清少納言(せいしょうなごん)がある。補陀落寺(ふだらくじ)を建立したと伝えられる(『拾芥抄(しゅうがいしょう)』、『井蛙抄(せいあしょう)』)。『深養父集』があり、『古今集』以下の勅撰(ちょくせん)集に41首入集(にっしゅう)。中古三十六歌仙の一人。藤原清輔(きよすけ)は『袋草紙(ふくろぞうし)』で、深養父が『三十六人撰』に入らなかったのを不審としている。
夏の夜はまだ宵(よひ)ながら明けぬるを雲のいづこに月やどるらむ
[杉谷寿郎]
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「清原深養父」の意味・わかりやすい解説
清原深養父
きよはらのふかやぶ
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「清原深養父」の解説
清原深養父 きよはらの-ふかやぶ
清原元輔(もとすけ)の祖父。中古三十六歌仙のひとり。延長元年(923)内蔵大允(くらのだいじょう)。紀貫之(きの-つらゆき)らと交流があり,琴をよくした。「古今和歌集」以下の勅撰(ちょくせん)集に41首はいる。家集に「深養父集」。
【格言など】夏の夜はまだ宵ながら明けぬるを雲のいづこに月宿るらむ(「小倉百人一首」)
関連語をあわせて調べる
2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...