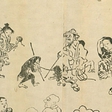日本大百科全書(ニッポニカ) 「猿回し」の意味・わかりやすい解説
猿回し
さるまわし
猿に芸をさせて金銭を得る大道芸。猿舞(さるまわ)し、猿曳(さるひき)、猿引き、猿飼(さるかい)、猿太夫(さるだゆう)などさまざまな呼称がある。猿が馬の病気を治すという信仰は中国伝来のもので、近世まで厩(うまや)で猿を舞わせるということが行われていた。そのために城下に猿回しを置いたという。猿回しが芸能として確立するのは鎌倉時代で、『吾妻鑑(あづまかがみ)』の寛元3年(1245)の条や、1300年(正安2)ごろに成立したといわれる絵巻『融通念仏縁起(ゆうずうねんぶつえんぎ)』などによって確かめられる。中世、猿飼は猿楽(さるがく)、アルキ白拍子(しらびょうし)、鉢叩(はちたたき)などとともに七道者(しちどうもの)の一つにあげられている。いわゆるアルキ渡世の芸人であり、非人として賤民(せんみん)視されていた。近世に入って猿回しはいっそう芸人化し、全国にその数を増しているが、下級神人として大名家や貴人の屋敷に参入し、厩の祈祷(きとう)や疫病退散の呪術(じゅじゅつ)を職能として保持しつつ、一方では猿と馬、猿と犬といった組合せで芝居を仕組んで、掛け小屋で興行されることも近世初頭から行われていた。狂言の『靭猿(うつぼざる)』や、人形浄瑠璃(じょうるり)の『近頃河原達引(ちかごろかわらのたてひき)』などにも取り入れられているのでもわかるように、大道芸の花形であったが、明治以後急速に姿を消した。
[織田紘二]
改訂新版 世界大百科事典 「猿回し」の意味・わかりやすい解説
猿回し (さるまわし)
大道芸の一種。猿引き,猿飼,猿舞,猿太夫,まし遣いなどともいう。猿を飼いならして芸をさせるもので,その歴史は古く,《吾妻鏡》にも左馬頭入道正義が猿を舞わせた記事が見える。古くは厩祭(うまやまつり)や厄病除けの祈禱をし,祝言を述べて猿を舞わせる祝言職であった。初春の祝福芸として万歳とともに禁裏や高家への出入りも許されている。江戸時代には各地に猿屋町・猿屋垣内が置かれ,組織化された集団があった。のちには季節を問わず大道芸,門付(かどづけ)芸として人気を集め,猿芝居に転じたりした。猿回しを題材にした狂言,常磐津に《靱猿(うつぼざる)》,長唄に《外記猿》などがある。近年,山口県に周防猿回しの会が誕生し,再興の動きもある。
執筆者:織田 紘二
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「猿回し」の意味・わかりやすい解説
猿回し
さるまわし
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「猿回し」の意味・わかりやすい解説
猿回し【さるまわし】
→関連項目猿芝居
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「猿回し」の解説
猿回し
さるまわし
猿曳(さるひき)・猿飼・猿舞・猿太夫・マシ使いとも。日吉山王(ひえさんのう)の神使い,馬の厄病除けなど,猿に対する信仰を背景として,新春をことほぐ祝福芸・祈祷芸の一つ。中世初頭すでに大衆に受容されていたことは「石山寺縁起」「融通念仏縁起」からも知られる。のち大道芸・門付(かどづけ)芸ともなった。近世には各地に猿回しの集団があったが,江戸では穢多頭弾左衛門の支配に属し,猿飼とよばれていた。江戸の猿飼たちは近世後期以降は見世物興行にも進出。明治期以後は衰退したが,最近では山口県周防の猿回しや,日光で保存集団が結成された。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
日本文化いろは事典 「猿回し」の解説
猿回し
出典 シナジーマーティング(株)日本文化いろは事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の猿回しの言及
【厩神】より
…馬の子が生まれると祝いを催すことが多く,3日目にぼた餅を配ったり近所の人を招いて蒼前祭をする地域もある。また正月あるいは毎年定期的に厩祭をすることも一般的で,近世には猿回しを専業とする者が厩の悪魔払いに回っていた。【宮本 袈裟雄】。…
【サル(猿)】より
…ことに西日本でこの風が著しい。 猿を飼いならして芸を教え,舞わせて銭を乞う猿曳(さるひき),猿回しなどの職は12世紀ころから知られ,《三十二番職人尽歌合》にも載せられている。狂言には《靱猿》があり,また近世には大名その他の厩祈禱(うまやのきとう)に猿曳を業とする者が訪れて猿を舞わせ,そのついでに町家を訪れて祝言を述べた。…
※「猿回し」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...