デジタル大辞泉 「さる」の意味・読み・例文・類語
さる[助動]
「出さらにゃ、ここへ引きずり出す」〈浄・千両幟〉
翻訳|monkey
室町期より近世にわたって用いられた四段活用型の尊敬の助動詞であるが、この命令形「され」から転じたと見られる「さい」について「ロドリゲス日本大文典」(一六〇八)では、少し目下の者に対して用いる旨の記述があり、敬意は低い。→さい(助動詞「さる」の命令形)
哺乳(ほにゅう)綱霊長目中ヒトを除いた部分non-human primatesに対する一般呼称。狭義には、類人猿、原猿類をも除き、オマキザル、オナガザル2上科に属する種を総称することもあるが、一般名であるから厳密な限定はない。英名のモンキーmonkeyは尾の長いサルをさし、尾がないか極端に短いものつまりtailless monkeyをエープapeとよぶ。
[伊谷純一郎]
原猿類と真猿類の2亜目に大別される。前者は、メガネザル、ロリス、キツネザルの3下目5科からなり、後者は、オマキザル、オナガザル、およびヒトニザルの3上科中ヒト科を除いた4科からなる。これらはさらに、55属、約180種に分けられる。
[伊谷純一郎]
サルは、第三紀暁新世中期に食虫目のような下等な哺乳類から分岐したと考えられている。最初の化石群は、この時期の北アメリカ・ロッキー山脈沿いから出土するが、始新世にはユーラシアに広く分布を広げ、原猿類の繁栄期を迎える。次の漸新世の地層から出土するサル類の化石はきわめて少ないが、エジプトのファイユームの化石群のなかには現生のショウジョウ科の祖型が知られている。中新世には、ショウジョウ科、オナガザル科、オマキザル科がそれぞれ独自の進化を遂げ、鮮新世の初頭にはヒト科の祖型が現れる。
[伊谷純一郎]
他の哺乳類と異なり、樹上に適応することによって独自の生活空間を獲得し、その進化の過程で大きな成功を収めたグループであるといってよい。したがって、霊長類がもつ基本的な特徴は、樹上への適応に関係のある諸形質である。すなわち、これらの諸特徴は、樹上での目測を誤らないための目と、樹上での活動を保証する手足の発達に集約されているといえる。まず、両眼は顔の両側から前面に移行し、両眼の視野の交差部分が広くなり立体視が可能になる。暁新世の原猿には、眼輪の閉じていないものがあるが、始新世の原猿、そしてそれ以降のサル類はすべて閉じた眼輪をもつ。ただメガネザルを除く原猿類は、側頭窩(そくとうか)と眼窩が通じているが、メガネザル類と真猿類のすべては完成された眼窩をもっている。このような目の構造の変化に伴って、鼻口部の短縮がおこり、機能的にも嗅覚(きゅうかく)依存型から視覚依存型へと移行し、大脳皮質部の相対的な発達の基盤をなしている。鼻口部の短縮は歯式によく現れており、原始的な哺乳類の歯式の基本型は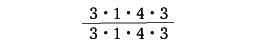
の44本であるが、すべてのサル類はこれより少なく、オナガザル科とショウジョウ科では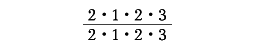
の32本となっている。
ショウジョウ科とオナガザル科では、手足の指のつめはすべて平づめになっている。それ以外のものも、幾対かの平づめをもっている。手足の母指と他の指との対向が可能となり、把握や食物などの保持ができるようになっている点も重要な特色である。また、前肢はしだいに単なる歩行器官から解放され、手として完成されてゆく。手のひらは裸出し、指掌紋が発達する。鎖骨が発達し、腕の回転が自由になる。
このほか、産子数の減少、妊娠期間の長期化、寿命の延長、表情そしてコミュニケーションの発達、社会構造の複雑化などをあげることができる。サル類は、動物界でもっとも進化を遂げた種と、きわめて原始的な種を同時に含む。このこと自体もこのグループの大きな特色であるといわなければならない。
[伊谷純一郎]
サルは、新旧両大陸の赤道を中心に分布を広げている。メガネザルは、フィリピン、ボルネオ島、スマトラ島に分布する。ロリス類は、アジアではインドとインドシナ半島、スマトラ島、ジャワ島、ボルネオ島に、またアフリカではサハラ砂漠以南の森林、疎開林、サバナに広範な分布をみせる。キツネザル類は、マダガスカル島とコモロ諸島の特産である。原猿類は、第三紀暁新世と始新世には北アメリカ大陸やヨーロッパで適応放散し多くの化石が知られているが、両大陸は現在ではサル類とは無縁の地になっている。オマキザル類は、アマゾン川・オリノコ川流域を中心とする南アメリカ大陸と、北はメキシコ南部までの中央アメリカに分布し、そのために新世界ザルの名でもよばれる。オナガザル類の分布は、サハラ砂漠以南のアフリカ大陸、アラビア半島の一部、およびインド半島以東、チベット、中国の中南部、東南アジアの島々、そして日本の本州北端にまで達する。モルッカ諸島以東、ニューギニア、オーストラリア、朝鮮半島、琉球(りゅうきゅう)列島、そして北海道には分布しないし、サル類の化石も知られていない。ショウジョウ科のオランウータンはボルネオ島とスマトラ島に、テナガザル類はインドシナ半島を中心に、西はアッサム、北は中国南部、そしてスマトラ、ジャワ、ボルネオの各島に分布する。アフリカの類人猿であるゴリラ、チンパンジー、ボノボは、いずれもアフリカの熱帯林に分布している。サル類の分布の北限を占めるのはニホンザルで、青森県下北(しもきた)半島の北緯41度30分、南限を占めるのはチャクマヒヒで、アフリカ南端の南緯34度30分である。
[伊谷純一郎]
サル類の故郷が熱帯の多雨林であることは、その分布によく示されている。原始的なものほど熱帯多雨林の中に閉じこもっているが、オナガザル類になると森林から脱出する種も目だつようになる。アフリカやアラビア半島ではサバナ、草原、半砂漠にさえすむようになった種がいるし、アジアではヤセザル類がヒマラヤの森林限界に達し、またニホンザルのように多雪地帯にすむようになった種もいる。このような熱帯森林からの脱出と分布の拡大は、地上性の獲得と無関係ではない。原猿類と新世界ザルはすべて樹上生活を営むが、旧世界のオナガザル類では、コロブスとアフリカのオナガザル属(グエノン)が主として樹上生活者であるのに対して、パタスモンキー、マカック、ヒヒなどは地上性の傾向が強い。類人猿では、テナガザルとオランウータンが純粋な樹上生活者、アフリカの3種は半地上・半樹上性といってよい。サル類のなかには、樹上生活への適応のために形態的な特殊化を示すものが知られている。新世界ザルのオマキザル、クモザル、ホエザルの3亜科は、把握力をもつ尾が第五の足としての機能を果たし、尾を枝に絡めてぶら下がることができる。また、クモザルやアフリカ産のコロブスは、手を鉤(かぎ)状にして枝から懸垂するが、手の母指は退化して痕跡(こんせき)だけになってしまっている。フクロテナガザルとクロステナガザルの足の第3・第4指は、皮膜によって癒着したようになっている。テナガザルとオランウータンの極端に長い腕も、樹上での枝渡りに適した特殊化であるといえる。
原猿類のうち、メガネザル、ロリス、コビトキツネザル、アイアイは夜行性であり、マングースキツネザルは朝夕に活動する薄暮性、その他の大型のキツネザル、インドリ、シファカは昼行性である。真猿類では、中央・南アメリカのヨザルを唯一の例外として、他はすべてが昼行性である。
夜行性の原猿類には、単独生活者で雑食性のものが多い。果実や樹脂などの植物食のほかに、昆虫やクモ、トカゲなどの小動物を捕食する。それに対して、昼行性の原猿類は植物食に偏している。サル類の食性の原型は、偏りのない雑食性が基本であり、偏食はそれから派生した食性と考えられるが、雑食と偏食は、原猿類のみならず真猿類の各系統群にも並行してみられる。新世界ザルでは、マーモセット類とフサオマキザルが雑食であるのに対して、クモザルは果実食、ホエザルは葉食と偏食化している。オナガザル類では、マカック、ヒヒなどが雑食であるのに対して、コロブスやヤセザルはリーフ・イーターleaf eaterともよばれる偏食主義者である。ショウジョウ科でも、オランウータンは果実食に偏し、ゴリラは葉、茎などの植物食に偏しているのに対して、テナガザル、ボノボ、チンパンジーは雑食である。近年の野外研究によって、チンパンジーは、あらゆる種類のサル、小形のレイヨウやノブタの子などを捕食していることが明らかにされた。アリ、シロアリなどの昆虫類にも強い嗜好(しこう)を示す。アリやシロアリの捕食には、木の枝などの道具を用いることも知られている。
夜行性の原猿類のうち、ガラゴ、アイアイなど単独行動をする種のなかに、巣をつくるものが知られている。コビトキツネザルやロリスなどは、木の洞穴などをねぐらにする。真猿類中唯一の夜行性の種ヨザルも、集団でまとまって木のうろに潜り込んで日中を過ごす。これらの種にとって巣はねぐらであり、生活の中心になっている。彼らは日中は巣の中に潜んで眠り、夜間は巣を抜け出して自分の縄張りをパトロールして採食に専念し、朝になるとまた巣に戻ってくる。巣づくりの習性をもっているのは、それらのもっとも下等なサルたちと、もっとも高等な大形類人猿だけである。オランウータン、チンパンジー、ボノボ、ゴリラは、毎夕その夜を過ごすための新たな巣をつくる。これは巣というよりもベッドとよんだほうがよいであろう。チンパンジーのベッドは、樹上で枝を折り曲げてつくられる杯状のもので、その上に体を横たえて夜を過ごすが、わずか3、4分で完成する。ゴリラは、樹上よりも地上で草本を束ねるようにしてベッドをつくることが多い。その他の昼行性のサル類は巣づくりの習性をもたない。彼らは集団のまとまりを保って縄張りの中を遊動し、毎夕たどり着いた所で巣をつくることなしに夜を過ごす。ただ、縄張りの中に幾か所かの決まった泊まり場をもつものもある。テナガザルは1、2本の特定の巨木を、ニホンザルは険しい斜面や尾根を、マントヒヒやゲラダヒヒは断崖(だんがい)を泊まり場としている。遊動生活に巣づくりを兼ね合わせているのは大形類人猿だけである。
[伊谷純一郎]
もっとも原始的なサルは、集団をつくらない。このような種社会は、単独行動をする雌雄の各要素からなっており、多くは短い交尾期間中にそういった雌雄が出会って交尾をし、また単独の生活に戻る。雌は子を哺育するが、その期間も短く、やがて子は雌親から離れて単独の生活に入る。このような社会をもつ種では、性差がほとんどみられないのが特色である。コビトキツネザル、アイアイ、ロリスの仲間がこのような社会をもっている。
夜行性の原猿類のなかにも集団をつくるものがある。セレベスメガネザルは、雌雄各1頭とその子からなるペアの集団をつくっている。この型の集団は、サル類の単位集団のなかでもっとも原初的なものであり、真猿類においても同型の集団は各系統群にみることができる。昼行性の原猿類では、インドリとシファカがこれと同じペアの単位集団をもっている。この構造が維持されるためには、ペアの間で生まれた子は、雌雄ともに、性的成長に達するまでに生まれ育った出自集団を離脱しなければならない。こうして集団を離れた若い雌雄が新しいペアを形成すると考えられる。
昼行性の原猿類のうち、キツネザル属に含まれる種は、複雄複雌のよりサイズの大きい集団をつくっている。この型の集団の維持機構は、おそらくオナガザル類にみられる母系の社会に近いものであろう。この型の集団と、前記のペア型の集団との関係は明らかにされていないが、これら2型は、サル類の社会集団の基本をなすものであり、真猿類の各種も、これらいずれかの社会形態をもち、あるいはより高度な発達を遂げたものも、そのいずれかの系譜を引いていると考えることができる。
原猿類の社会行動にみられる顕著な特色の一つは、マーキング行動である。原猿類の多くは、上腕、耳下、腋下(えきか)、鼠径(そけい)部などに皮脂腺(せん)をもっており、それを木の幹などに塗り付ける。このような皮脂腺をもたないものは、自分の尿や糞(ふん)でマーキングを行う。自分よりも劣位の個体や雌にマーキングをするといった例も知られている。この行動は一種の縄張り行動で、原猿類が嗅覚に依存した生活を営んでいることを知ることができる。真猿類になると、オマキザル類に若干同様の行動を認めることができるが、オナガザル類ではほとんどこの行動はみられなくなる。
新世界ザルのゲルディモンキー、ヨザル、ティティ、サキ、ヒゲサキなどはいずれも小型の多夫一妻、単婚などの集団をもっており、それに対して、リスザル、ウアカリ、オマキザル、クモザル、ウーリークモザル、ウーリーモンキー、ホエザルは複雄複雌のより大型の集団をもっている。オマキザル科の社会は単婚かあるいは雌雄とも集団を出入りする双系の社会をもつものが多いが、フサオマキザルは母系の社会を、またクモザル類は父系の社会をもつことが近年の研究で明らかになった。クモザルの単位集団は、チンパンジーの社会にみられるような離合集散を繰り返すことが知られている。ホエザルはのどに音声を共鳴させる袋をもっており、群れ間で相互に大声をあげて接触を避け、縄張りを防衛する。
オナガザル類は、メンタウェールトンとブラザモンキーがペアの集団をもつことが知られている。また、アカコロブスは双系の集団をもつ。それ以外のすべての種は、単雄複雌あるいは複雄複雌の母系的な単位集団をもつ。このことから、これら母系的な単位集団はペアに由来すると考えられるが、その機序は明らかにされてはいない。単雄複雌の集団は、アフリカのオナガザル属、コロブス属、東南アジアのラングール属などの樹上性の種に多くみられ、それに対して複雄複雌の集団は、マカック属、ヒヒ属など、地上性または半地上・半樹上性の種に認められる。しかし、ハイイロヤセザルなどでは地域によって両型が認められ、また雄の子は性的成熟までに出自集団を離脱し、単位集団は母系によって継承されるという点では、両型の基本構造は共通しているといわなければならない。集団を離れた雄は単独行動者として、あるいは雄グループを形成してより広範囲を行動し、やがて他の集団に接近してその成員になる。
単雄複雌の集団は普通20頭未満とそのサイズが小さいのに対し、複雄複雌の集団は30~60頭といったより大きなサイズをもち、ときには数百頭に達する例も知られている。後者においては、雄間、そして雌間に、直線的な安定した順位が認められる。また、血縁集団間にも安定した順位があり、同年に生まれた子の間では、血縁集団間の順位が踏襲される。雄間の直線的な順位にはいくつかの分節が認められ、最高位の1~数頭をリーダーとよぶ。リーダー・クラスの雄は雌たちとともに群れの中心部に位置して群れの統制にあたり、より若い雄たちはそれを取り囲んで群れの周辺部を形成するという空間的配置をとる。帯状になって移動するときにも、行列の先頭と後尾にはこれらの若い雄たちが位置する。
ニホンザルについての長期にわたる研究によって、集団内では血縁間の交配が避けられていることが明らかにされてきた。とくに1親等、つまり母と息子、2親等、つまり兄妹、弟姉、祖母と孫息子などの間柄には交尾が認められない。これまでに少数の例外的な記録がありはするが、統計的にみても近親婚は避けられているといってよい。さらにそれに加えて、ほとんどすべての雄は出自集団を離脱し、近親の雌とは社会的な距離を置くことになるから、近親婚はさらに確実に避けられているわけである。
一方、単雄複雌の集団では、雄が1頭だけであるために父と娘の間に近親婚がおこる可能性があるが、実は雄が一つの集団に雌たちとともに生活する期間は4、5年であるために、結果的に避けられているわけである。ハイイロヤセザルでは、単雄複雌の集団のほかに、雄だけからなる集団がみられ、ときおり後者は前者に攻撃を加え、雄のすげ替えがおこる。このあと新しい雄は、雌たちが抱いている子を殺し、やがて雌たちは発情を開始して新しい雄と雌たちとのつながりができるという過程をたどるのであるが、この社会変動を機に若い雄たちの離脱と子殺しによる消失などで集団のサイズはもとの約半数に減って新たな出発を迎えることになる。この現象は、単雄複雌の構成をもついくつかの種でみられている。
オナガザルの母系的な社会の一部に、重層の構造をもつものが知られている。ゲラダヒヒの単位集団は、単雄複雌の普通数頭からなる集団であるが、これがいくつも集まって、200~400頭といったハードherd、つまり地域集団を形成して遊動する。またマントヒヒは、一つの単位集団のなかに、いくつかの単雄複雌の構成をもつ下位集団をもち、さらにこのような構造をもつ単位集団がいくつも集まって休眠集団をつくる。
類人猿の社会は、種ごとに多様な構造をもっているが、そのいずれもがオナガザル類のような母系的な社会をもっていないという点で共通している。テナガザルの単位集団は典型的なペアの集団であり、子は雄も雌も性的成熟までに出自集団を離れる。オランウータンは、真猿類中唯一の単独行動者で単位集団をもたない。ゴリラは、平均10頭ばかりの単雄複雌の集団をもつが、雌が集団間を移籍することが認められている。ゴリラの単位集団は家父長的な雄が死亡すると、雌たちは単独行動をする雄や近隣の集団の雄に奪われるから、結局継承されることのない集団であるといえる。チンパンジーとボノボの単位集団はともに複雄複雌で、前者は平均40頭程度、後者は80頭程度のサイズをもつ。集団は縄張りをもち、集団間は互いに接触を避け合っているが、雌は性的成熟に達すると隣接する集団に移籍する。両種とも雄の移籍は認められていない。チンパンジーでは、集団内の雄間に強い結合がみられる。ボノボの隣りあった遊動域をもつ二つの集団は、ときに一時的に融合し、異なる集団に属する個体間で平和裏に社会的交渉が交わされる。チンパンジーには、これまでに十数例の子殺しと共食いがみられ、犠牲者の大半が雄の子であることが知られているが、この理由は明らかにされていない。
[伊谷純一郎]
サルの研究は、20世紀後半に入って急速に盛んになったが、現生のサルを対象にして人間性の究明を目ざすという目的と、医学、薬学、神経生理学、心理学などの実験動物としての必要性が高まったためである。1960年以降は、各国に霊長類研究所がつくられ、日本においても、1956年(昭和31)に財団法人日本モンキーセンターが、また1967年には京都大学霊長類研究所(現、京都大学ヒト行動進化研究センター)がともに愛知県犬山市に設立された。前者は、90種を越える生きたサルを収集、飼育、展示し、世界一の規模を誇っているし、後者では、サル類を対象とした実験的研究を行っている。また、日本モンキーセンターは国際学術雑誌『Primates』と、一般誌『モンキー』を刊行している。また、日本霊長類学会は、1985年に発足した。
[伊谷純一郎]
サルの飼育は、種によって難易の度は異なるが、多くが熱帯産であり、なかには特殊化した食性をもつものがいるので、一般的に困難であるといってよい。また、幼児期には扱いやすくても、成長後は行動の制御が困難になるなどの点も留意しておく必要があろう。ニホンザルは保護動物であるから、自由に飼育することは許されていない。サルは人間と共通の病気をもち、またとくに熱帯から輸入されたものは、ウイルス、細菌、寄生虫など、まだ十分に解明されていない病原をもつものがあるので注意を要する。一般の家庭では飼育しないほうがよい。
[伊谷純一郎]
人間との類似性から、サルはすべての動物のなかでも特殊な位置を与えられてきた。すなわち、サルは動物と人間あるいは自然と文化の中間に置かれ、このことは、世界中の神話や儀礼のなかに登場するサルのさまざまな性格を説明している。
多くの民族がサルに関しては一種の逆進化論を語っており、サルはいわば退化した人間と考えられている。たとえばメキシコのアステカの創世神話では、原初に激しい嵐(あらし)がおこって人々を吹き飛ばすが、風に運ばれた人々も生き残った者もサルになったといい、これは人間が変身したものと考えられている。マヤ系インディオのキチェの神話集『ポポル・ブフ』のなかでも、サルは創造主が最初に木でつくった人間の末裔(まつえい)であると語られている。彼らは顔をつぶされ破壊されてしまったが、その子孫はいまもなお森の中に住んでいると信じられている。またチアパス高原では、サルは悪と混沌(こんとん)の象徴とされ、女たちが男の誘惑に負けたりすると、それはサルのせいだとされる。この否定的な性格は、同地のカーニバルに現れて、いたずらの限りを尽くす道化のサルにも受け継がれている。ボルネオ島先住民のダヤクでも、創造主が人間をつくろうとした際の失敗作が、オランウータンやサルの祖先だと語られている。
しかし、サルはつねに否定的な性格を負わされているわけではない。バビロニアやエジプトではサル(ヒヒ)は月の神と同一視され、とくにエジプトでは太陽神を出迎える従者としてのサルの像が多数残されている。このサルは太陽神の仲間であるとともに、知恵の神や書記、学者の守護神ともされている。東アフリカの王権神話では、王となる人物がしばしばサル(コロブス属)に結び付けられ、ケニアの農耕民メルでは白黒2色のコロブスモンキーが神聖視されている。インドでも神聖な動物とされ、アッサム地方の山地農耕民ガロでは共同体の供犠にサルを用いる。またインドネシア、スマトラ島北部の民族集団バタックでは、人間とサルの祖先が同じであると考え、食べることを禁じている。このほかマダガスカル島でも、サルを殺したり捕らえたりすることをタブーとし、死んだサルは埋葬するという。
[加藤 泰]
日吉神社(ひえじんじゃ)(山王権現(さんのうごんげん))の神使(しんし)とされるサルは、山の神としても尊ばれた。猿神信仰もみられ、また庚申信仰(こうしんしんこう)に基づく「見ざる、聞かざる、言わざる」を表した三猿塔(さんえんとう)(庚申塔)を立てることも広く行われている。群馬県利根(とね)郡片品(かたしな)村では、旧暦9月の申(さる)の日に猿追祭が行われ、サルに扮(ふん)した人が幣帛(へいはく)(神への奉納物)を担いで武尊様(ほだかさま)というお宮の周りを三度逃げ回る。これを櫃元(ひつもと)、酒元(さかもと)という祭役が追うが、サルが追い詰められるとその年は豊作という。また、サルは子供の無事を祈る願掛けとしても信仰されるため、妊婦の安産を守るという子安地蔵にくくり猿を奉納したり、子供の背守りにサルをつける風習もある。
サルを厩(うまや)に飼う風習は海外にもその例がみられ、わが国では鎌倉時代に厩にサルを置いたことが、橘成季(たちばなのなりすえ)編『古今著聞集(ここんちょもんじゅう)』(1254)巻20にみられる。蒼前神(そうぜんしん)はウマを保護する神として信仰されているが、厩の祭りには、猿曳(さるひ)きがこの神を祀(まつ)って『勝善経(そうぜんきょう)』を誦(しょう)し、サルを舞わせたという(猿屋伝書)。
狩猟者は、サル(去る)ということばを使うのを嫌い、ヤマノヒト、エテモン、キムラなどの山ことばを用いるが、岩手県遠野地方では、年を経たサルは毛に松脂(まつやに)を塗り込んでいるため、鉄砲の弾も通らないといって恐れる。サルは昔話の主人公として登場することも多く、『猿蟹合戦(さるかにがっせん)』『猿婿入り』『猿の生肝(いきぎも)』などがよく知られている。
[大藤時彦]
上代の文献から数多くみえ、『日本書紀』皇極天皇(こうぎょくてんのう)の巻にも登場する。『万葉集』巻3には大伴旅人(おおとものたびと)の酒を讃(ほ)むる歌のなかに、「あな醜賢(みにくさか)しらをすと酒飲まぬ人をよく見ば猿にかも似む」の一例がある。『懐風藻(かいふうそう)』など漢詩に用例が多く、『和漢朗詠集(ろうえいしゅう)』下「猿」に「猿の叫び三声暁峡(みこゑけうかふ)深し」(紀長谷雄(きのはせお))とあるように、暁方(あけがた)の峡谷で悲しげに三声鳴き旅情をかき立てる、というのが類型化していたようである。和歌の用例はあまり多くはないが、「ましら」「まし」などの形で詠まれ、『古今集』雑躰(ざってい)に「わびしらにましらな鳴きそあしひきの山のかひある今日にやはあらぬ」(凡河内躬恒(おおしこうちのみつね))の歌があり、『古今六帖(ろくじょう)』や『紫式部集』などにもみえる。『枕草子(まくらのそうし)』には人間の比喩(ひゆ)として2例用いられている。御伽草子(おとぎぞうし)や草双紙(くさぞうし)などにも昔話に取材した猿の話がいくつかある。俳諧(はいかい)では芭蕉(ばしょう)の「初しぐれ猿も小蓑(こみの)をほしげ也(なり)」(猿蓑)が有名。
[小町谷照彦]
『伊谷純一郎編『人類学講座2 霊長類』(1977・雄山閣)』▽『杉山幸丸著『サルの百科』(1996・データハウス)』▽『西田利貞・上原重男著『霊長類学を学ぶ人のために』(1999・世界思想社)』

サルのおもな種類(原猿類)〔標本画〕

サルのおもな種類(オマキザル類)〔標本…

サルのおもな種類(オナガザル類)〔標本…

サルのおもな種類(ヒトニザル類)〔標本…

サルの表情とコミュニケーション

アフリカにおける植生と霊長類の分布

霊長類の基本的単位集団の6型
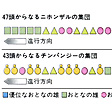
サルの移動時の行列

アカゲザル

オランウータン

クロホエザル

コビトガラゴ

シロガオサキ

チンパンジー

テイチゴリラ(ローランドゴリラ)

ニホンザル

パタスモンキー

ピグミーマーモセット

フクロテナガザル

ボリビアリスザル

ワオキツネザル

ワタボウシタマリン
ヒトにもっとも近縁な動物で,ヒトとともに哺乳綱霊長目をなす。もともとニホンザルを指すことばであったが,現在ではヒト以外の霊長類の総称として用いられ,狭義には,真猿類のオマキザル科とオナガザル科の種を指す。英語では,尾の長いサルをmonkey,尾のないサルをape,原猿類をlemur,またはprosimianといっている。
いわゆるサルということばから連想するイメージは,賢そうな顔つきや目つきをもち,木登りがうまく,手先が器用で,果実や木の実を好み,群れをなして森の中でくらしている動物といったものであろう。もちろん,後述のように,これからはずれる種も少なくないのだが,このようなイメージは,顔の前面に並んだ両眼,あまり突出していないあご,大きな頭,物を握ることのできる手,人のような平づめ,雑食に適した歯などという形態上の特徴に基づいている。分類学のうえでも,このような特徴を総合してサル類の位置づけが行われ,その特異な進化史的背景の検討が行われている(分類と分布については〈霊長類〉の項目を参照)。
サル類のおもな生息環境は熱帯の森林であるが,ニホンザル,アカゲザル,ラングールなどのように,その一部が冷温帯に進出しているものや,パタスモンキーやヒヒ類のように乾燥した草原に生息するものもいる。活動の時間帯は,原猿類では夜行性のものが多いが,真猿類では南アメリカ産のヨザルを除いてすべてが昼行性である。サルの祖先は原始的な夜行性の哺乳類から派生し,それがしだいに樹上の生活に適応していく過程でサルらしさを獲得したと考えられる。原猿類の多くと新世界ザルのすべては完全な樹上生活者である。旧世界ザルのコロブス亜科も樹上生活者であるが,オナガザル亜科の種は地上をも利用するものが多い。類人猿はどの種も上肢が下肢に比べて長く,樹上生活への適応を示すが,テナガザルとオランウータンは完全な樹上生活者であるのに対して,ゴリラとチンパンジーは地上で活動する割合が大きい。つまり,サルは樹上に生活の場を得てサルとして完成されたのち,あるものは再び地上に向かったのである。とくにヒトの祖先は,この地上生活への再適応を直立二足歩行という新たな移動様式の獲得によって成し遂げたと考えることができ,このような視点からサル類の移動様式(ロコモーション)の進化とヒトの直立二足歩行の起源が検討されている。
サルの主要な食物は植物であるが,多くのものが雑食の傾向をもつ。原猿類では,夜行性のものは昆虫,小動物を好む雑食性,昼行性のものは植物食である。新世界ザルの多くも雑食性であるが,マーモセット科は昆虫,小動物を好み,オマキザル科のホエザルは葉食,クモザルは果実食に偏る。旧世界ザルのコロブス亜科は葉食性で,オナガザル亜科は雑食性である。採食される植物の種類は多様で,葉,芽,茎,花,果実,樹皮などさまざまな部位が利用され,昆虫や小動物もアリ,バッタ,セミ,甲虫類,カニ,貝,鳥の卵など,またヒヒはレイヨウなどの幼獣を捕食する。類人猿の中で,テナガザルとチンパンジーは雑食,オランウータンは果実食に偏り,ゴリラは植物食である。チンパンジーは,アリ,シロアリなどの昆虫,アカコロブス,ブッシュバックや野ブタの幼獣などをとらえてその生肉を食べる。
夜行性の原猿類は,巣をつくりそれをねぐらとし,睡眠や育児のために用いるが,真猿類で巣をつくるのは大型類人猿だけで,それもただ一夜を過ごすための,あるいは昼寝のためのものにすぎない。サル類のほとんどは定まった泊り場(ねぐら)をもつことなく,日々,集団のなわばりの中を遊動してくらしているのである。草原にすむゲラダヒヒやマントヒヒでは,集団のなわばりは完全に重複し,特定の岩山や崖を共同の泊り場として用いることがある。
原猿類やマーモセット科には,皮脂腺の分泌物や排泄物を木の枝などにぬりつけて印づけ,つまりマーキングをするものがあるが,真猿類にはこのような行動はほとんど見られない。ホエザルやテナガザルは,朝,大声を発してそれぞれの集団の居場所を示しあい,また,ニホンザルなどの行動域には,林床によく踏まれた移動経路(サル道)ができているが,このように高等なサルでは音声や地形などによってなわばりを区別し,集団間の配置の調和を保っている。
原猿類と旧世界ザルは決まった繁殖期をもつものが多いが,類人猿ではそのような繁殖の季節性は消失している。新世界ザルの繁殖行動についてはまだ十分に明らかにされていない。真猿類の多くには雌の月経周期が見られ,発情に伴う雌の性皮の腫張は,ヒヒやマカックの多くおよびチンパンジー,ピグミーチンパンジーに見られる。ピグミーチンパンジーの雌の性皮の腫張はとくに顕著でかつ長期に及ぶ。原猿類には2~3対の乳頭をもつものがあり,出産子数も1~3頭であるが,真猿類の乳頭は1対で,1回の産子数はマーモセット科が2子であるのを除いて,ほとんどは1子である。マーモセット科を除く新・旧世界ザルは,雌は生後4~5年で性的成熟に達し子を生み始める。雄の性的成熟は雌より1~2年遅れる。類人猿の性成熟年齢は7~10歳で,初産年齢はそれよりさらに数年遅れ,出産間隔は3~4年,8年という例も知られている。飼育下での寿命は,ニホンザルが27年,チンパンジーが37年,ゴリラが35年とされ,オランウータンでは56年という記録がある。
大型類人猿を除いたサル類の社会的単位には,その構成から見て,単独生活型,1組の雌雄とその子どもからなるペア型,異なった性,年齢のより多くの個体からなる群れ型の3型がある。原猿類にはこれら三つの型が見られる。
新世界ザルでは,マーモセット科とオマキザル科の一部はペア型で,クモザル,ホエザルなど残りのオマキザル科は複雄複雌群をもつ。旧世界ザルのすべては群れ型の社会単位をもつが,集団構成には複雄群と単雄群の2型が見られる。また,いくつもの単雄群が集合した複合的な社会も見られる。
類人猿のうちでテナガザルは典型的なペア型であるが,大型類人猿各種の社会組織は種ごとに異なっており,それぞれ上述の三つの社会単位のいずれでもない。オランウータンはこれまで単独生活者とみなされてきた。しかし,一時的な10頭以上もの集りが観察されたり,近隣の個体どうしは互いに見知り合っていると思われる行動が知られるようになり,個体間の交渉の頻度は少ないながらも,顔ぶれの定まったどうしがある地域と結びついて生活している可能性もある。ゴリラの集団は1頭の大きな雄(シルバーバック)と複数の雌とその子どもからなり,ときには,数頭の若い雄(ブラックバック)を含む。チンパンジーの単位集団は,複数の雄,雌,子どもからなるが,その全員がつねに集まってくらしているわけではなく,集団の遊動域内でときに集合しときには分散するというきわめて柔軟な結びつきを保っている。ゴリラとチンパンジーの社会単位は,構成だけを見るとそれぞれオナガザル類の単雄および複雄の集団と区別できないが,若い雌が出自(しゆつじ)集団(生まれ育った集団)を離れて他集団に移籍するという点で,雄が集団間を移籍する母系的なオナガザル類の単位集団とはその維持機構が根本的に異なっている。チンパンジーの雄は雌とは対照的に出自集団の遊動域を離れることはなく,また他集団に加入したという例は知られていない(ただし母親についていった子どもの例は少数ある)。サル類は,その形態,生態,社会生活などの諸側面を通じて,原始的な段階からヒトに連なる高等な段階まで,さまざまな進化の段階を示す。このこと自体が,サル類の大きな特徴といってよいであろう。
サルは,医学,薬学,神経生理学,心理学などにとってかけがえのない実験動物であり,小児麻痺ワクチン製造にサルが用いられたことはまだ記憶の新たなところであろう。近年,各国に,人類の進化を探るための研究や医学などの研究のために,サル類の研究所が建てられたが,日本の京都大学霊長類研究所もその一つである。また,愛知県犬山市の財団法人日本モンキーセンターは,博物館機能を備えた同様の民間施設で,80種以上のサルを保有,一般に公開し,世界一を誇っている。
執筆者:増井 憲一
ヨーロッパにはヒト以外の霊長類は産しないので,ギリシア・ローマの人々は,アフリカから輸入した猿を餌育,愛玩しつつも神格化することはほとんどなかった。キリスト教が支配的になると,猿は邪悪なもの,悪魔的なものとして忌みきらわれた。しかし,ジブラルタルに移されたバーバリーエイプは,18世紀初めにここを占領したイギリス軍によって幸運のシンボルとされ,今日に至るまで手厚く保護されている。一方,多くの猿を産するアフリカでは,猿を神格化するのがふつうで,古代エジプト人はマントヒヒを聖獣とみなし,死後はミイラにさえした。知恵の神トートも,マントヒヒの頭をもった姿に描かれることがある。またミイラ製造の過程で死者の内臓をはかるはかりの上に座すハピ神も,マントヒヒを原型とする猿である。今日でも中央アフリカのコンゴ民主共和国のバクバ族が語る創造神話では,猿のフームーを原初の人間としている。
とはいえ,古代から現代に至るまで一貫して猿を神聖視しているのはインドであろう。なかでもハヌマンラングールは,古代叙事詩《ラーマーヤナ》に登場する神通力の持主ハヌマット猿将のモデルとして神聖視されている。《ラーマーヤナ》が伝わった東南アジア各地でも同様である。仏典にも聖なる猿の話は多く,例えば猿が如来の鉢をもち釈尊にみつを奉ったという,いわゆる獼猴献蜜の故事などは,いくつもの石窟寺に彫られているほか,中央アジア経由で中国にもたらされた。中国でも古代から猿に関する伝説は多い。
しかし,古代から唐代ころまでは,猿(えん)(猨,蝯など)と呼ばれるテナガザルの系統がとくに神秘化され,猴(こう)と呼ばれるマカック属の系統は卑しいとされた。とくに白猿は,神仙にもたとえられるほどで,人間の女をかたって妻にすることさえ許された。宋代ころからは猿の神秘性はうすれ,代わって猴をめぐる話が優勢となる。小説《西遊記》に登場するサル孫悟空は,宋代以降にわかに優勢になった猴の代表者であるが,そのイメージには,猿をめぐる伝承も,また遠くインドのハヌマットの要素も,ともに揺曳(ようえい)している。中国の奥地の山中にすむシシバナザル(金糸猴,仰鼻猴)も,その美しい金毛や特異な容貌(青い顔とあおむきの鼻孔)のゆえに多くの伝説をもっているし,野人,野女と呼ばれる猿も,今日まで話題を提供し続けている。
執筆者:中野 美代子
日本の猿は尾が短く体も小さくて猴と書くべき種類に属する。縄文時代から食用にされ,貝塚から骨が出るほか,古くから人に飼養されて愛玩用ともされ,銅鐸(どうたく)の絵画や埴輪(はにわ)の像の中にも猿をかたどったものがある。古くはマシ,マスなどと呼び,現代でも青森県,岩手県北部,秋田県鹿角郡,山形県庄内地方,和歌山県日高郡などの方言となって残り,一部では忌詞(いみことば)として用いられる。またエテという名称も忌詞として用いられるが,猿が巧みに物をつかむところから得手と称したといわれる。
猿の毛皮は敷物や矢を収納する靱(うつぼ)を覆うのに用いられ,第2次世界大戦には防寒帽にも使用された。肉は食用で軟らかく,塩漬として薬用にも供せられた。身体を温め下痢を止めるという。頭部は壺にいれて蒸焼きにして脳の薬とされる。サンコウ焼と呼ぶ黒焼きである。しかしながら,狩人は猿を撃つことをきらい産子(うぶご)にたたるとか,火事になるなどと信じていた。ことに西日本でこの風が著しい。
猿を飼いならして芸を教え,舞わせて銭を乞う猿曳(さるひき),猿回しなどの職は12世紀ころから知られ,《三十二番職人尽歌合》にも載せられている。狂言には《靱猿》があり,また近世には大名その他の厩祈禱(うまやのきとう)に猿曳を業とする者が訪れて猿を舞わせ,そのついでに町家を訪れて祝言を述べた。その機会は多く正月であって俳諧の季題ともなっている。猿を厩に飼って馬を守らせ病災を除くまじないとすることは中国やインドから伝えられたもので,日本の猿使いは陰陽師が民間に降って職となったものと考えられ,主として大都市に近い土地に集団で居住することが多かった。
庚申(こうしん)は中国から伝えられた信仰で,この日の夜に身体にすむ三尸(さんし)虫が天に登って天帝にその人の悪事を告げるといわれ,それを防ぐために集まって語りあかす庚申講が中世以来盛んになった。この際に庚申の猿にちなんで青面金剛の神像下に3頭の猿(三猿(さんえん))を描き,これを俗に〈言わざる,見ざる,聞かざる〉と称し,このような行為をつつしむことで人生を安全幸福におくることができるとする教えが尊ばれた。庚申信仰はもと日吉神社の神使が猿であるとされたように,山の神の使わしめを猿と考える民間信仰を基礎とし,中国伝来の教義をもって形をととのえたために,貴賤をとわず全国的に信仰されるに至ったものではなかろうかと考えられている。3年ごとに庚申供養の儀礼を行い,庚申塔を建立する風習は江戸時代に盛行し,神道でも庚申を猨田彦大神(さるたひこのおおかみ)(猿田彦命)と説くようになったが,これも庚申と猿との関連を無視しえなかったためであろう。
猿は動作,姿が人に似るため昔話や伝説の主人公としても人気があり,猿神譚,猿聟入(さるむこいり),猿地蔵,猿蟹合戦などの口承伝承の主人公としても活躍している。
執筆者:千葉 徳爾
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
漢字表記地名「沙流」のもとになったアイヌ語に由来する地名。本来は「サルベツ」(現沙流川)流域をさし、場所名としても用いられた。表記は古くは平仮名で「さる」(「津軽一統志」「狄蜂起集書」・元禄郷帳・享保十二年所附)とみえ、のちには片仮名で書かれ、異表記はみない。漢字表記は「佐留」(「東行漫筆」など)がみられる。語義について秦「地名考」は「サルベツ シヤラベツなり。尾の名なり。名義詳ならす」とし、「地名考并里程記」は「夷語シヤルなり。則、湿沢といふ事。此辺湿沢なる故、地名になすといふ」とする。「東行漫筆」もまた「夷人シヤリと云。沢多く葭生る所を云よし」(文化六年四月一一日条)と記している。なお「蝦夷日誌」(一編)に「扨此処をサル場所と云は、則サルベツの左右の地なればなり。然れども其勝手不宜して会所を今此地にうつすなり」とあるように、当初運上屋(のち会所)はサルベツ河口のサルフトに置かれていたが、一八世紀半ば頃東方のモンベツ(サルモンベツ)に移されたため、モンベツをサルとよぶ場合もあった。たとえば「サルノ岬ヲ廻レハ則チサルノ会所元ナリ」(「観国録」安政三年九月一八日条)という記述は「モンベツ」一帯をさしている。
気候や地形について「東蝦夷地場所大概書」に「佐留場所」の会所近辺は「高山なく用水も自由、薪となす雑木も多し」「寒気もゆるやかに四季とも凌能き方也」とある。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…フタバガキ科の落葉高木で,マメ科のムユウジュ(無憂樹)およびクワ科のボダイジュ(菩提樹,インドボダイジュ)とともに仏教の三大聖木とされる。原産地のインドではサルsal,その漢名を沙羅といい,釈迦がクシナガラで涅槃(ねはん)に入ったとき,その四方にこの木が2本ずつ生えていたという伝説から,沙羅双樹という。沙羅は娑羅とも書き,サンスクリット語シャーラśalaの音写で,堅固樹の意である。…
…馬を飼っておく独立した建物や家屋内の馬(ときには牛)を飼う部屋で,〈まや〉とも呼ぶ。農耕馬を飼う農家の馬屋と乗馬用の馬を飼う武家屋敷や神社・寺院の馬屋とでは構造が異なる。農家の馬屋は,主屋内にある内馬屋と独立して建つ外馬屋に分かれるが,南部の曲屋は外馬屋を主屋に接続させて成立した形式である。また日本海側の多雪地方に多い中門造はもともとは主屋内にあった馬屋を中門に移すことによって成立しており,両者の中間的な存在である。…
…また月経中は,精神的にも不安定であることが多いので,つとめて平静心を保つようにし,強い刺激を避ける。
[動物の月経]
ヒト以外の各種霊長類(サル)での月経は,旧世界ザル以上の高等霊長類(ニホンザル,カニクイザル,アカゲザル,ヒヒ,テナガザル,オランウータン,チンパンジー,ゴリラ)の雌でみられ,月経周期日数や血中ホルモンの分泌動態が,ヒトのそれとほぼ同じであることは興味深い。新世界ザルでは月経はみられないが,血中ホルモンの周期的変動がみられる。…
…繁華な大道や街頭,また仮設の掛け小屋などで行われるさまざまな芸能の総称。〈辻芸〉とも呼ばれる。
[日本]
ほとんどすべての芸能は,その発生期においては屋外の大地の上で行われており,むしろ芸能にあっては,長く〈屋外の芸〉もしくは〈大道の芸〉という芸態が当然のことであった。しかし,特に近世以降に人形浄瑠璃,歌舞伎といった舞台芸能が発展すると,〈門付(かどづけ)芸〉〈見世物〉〈物売り(香具師(やし))の芸〉なども広く含めたもろもろの大道の雑芸(ざつげい)は,舞台芸能とははっきり区分けされて意識されるようになった。…
※「さる」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...