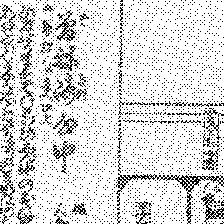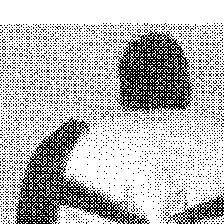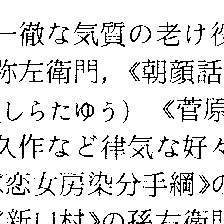共同通信ニュース用語解説 「人形浄瑠璃」の解説
人形浄瑠璃
太夫の語りと三味線の伴奏に合わせ、主に3人がかりで1体の人形を操る人形芝居。徳島では人形芝居の先進地だった兵庫県・淡路島から訪れた興行で広がり、明治時代に最盛期を迎えた。人形芝居向けの農村舞台は県内に80棟近くあり全国の9割以上を占めるとされる。1999年には阿波人形浄瑠璃として国の重要無形民俗文化財に指定され、現在もアマチュアを中心に約20の人形座が活動する。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
精選版 日本国語大辞典 「人形浄瑠璃」の意味・読み・例文・類語
にんぎょう‐じょうるりニンギャウジャウルリ【人形浄瑠璃】
- 〘 名詞 〙 日本の古典芸能の一つ。三味線と浄瑠璃に合わせて、俳優の代わりに、人形遣いが人形をあやつって演じさせる劇。文祿・慶長(一五九二‐一六一五)の頃発生し、古浄瑠璃の時代、近松と竹本義太夫の提携時代、竹本・豊竹の二座対立時代を経て、文楽座に継承された。人形あやつり。
- [初出の実例]「人形浄瑠璃ものまねなど、古風なあそびしたまへるはあらず」(出典:随筆・癇癖談(1791か)上)
改訂新版 世界大百科事典 「人形浄瑠璃」の意味・わかりやすい解説
人形浄瑠璃 (にんぎょうじょうるり)
劇と語り物の接点に立つ舞台芸術。その最も円熟した形態が,現在文楽と呼ばれる,義太夫節浄瑠璃に合わせて,三人遣いの人形が操られるものである。なお,音楽史の側面は〈義太夫節〉の項目を,また歌舞伎への影響については〈歌舞伎〉の項目のうち[人形浄瑠璃との交流]を参照されたい。
人形浄瑠璃の歴史
成立
浄瑠璃は,三河国矢矧(やはぎ)の長者の娘浄瑠璃姫と牛若丸の恋物語で,《十二段草子》とも呼ばれ,中世後期から近世初期に多くの絵巻や草子に書き留められたが,本来は三河の巫女たちによって語られた女主人公をめぐる鳳来寺峰の薬師の霊験譚であったといわれる。その成立については,少なくとも1474年(文明6)ころには,薬師如来の申し子である姫の誕生,牛若との悲恋,死と成仏を語る現在の《しゃうるり御前物語》(山崎美成旧蔵)のごとき長編が都で行われていたと考えられ,1世紀余りのちの〈文禄から慶長への交〉には,外来の三味線を伴奏楽器として,傀儡子(くぐつ)の人形戯と結んで,人形浄瑠璃が成立する(《絵巻“上瑠璃”》および《しゃうるり十六段本》所収の信多純一説)。そのころには,すでに浄瑠璃姫物語以外の新作や幸若(こうわか)の曲目が浄瑠璃の節で語られ,〈浄瑠璃〉は一作品名から一語り物ジャンルの名称に転じていた。
→傀儡 →語り物
古浄瑠璃--1590年代~1680年代
《東海道名所記》は,人形浄瑠璃成立当初,京で幸若物の《鎌田》や浄瑠璃の新作《牛王(ごおう)の姫》《あみだのむねわり》が演じられたと伝え,《三壺聞書》は,1614年(慶長19)金沢でも《浄瑠璃姫の十二段》とともに《あみだのむねわり》《牛王の姫》が演じられたという。以後,三都で多くの古浄瑠璃太夫が一流を編み出したが,17世紀前期までの曲には中世的作風が色濃く残存していた。
古浄瑠璃に,近世演劇的方法を最初に打ち出したのは,江戸の和泉太夫(丹波少掾)らによる金平(きんぴら)浄瑠璃である。中世以来の鬼退治で名高い源頼光主従の武勇譚,いわゆる四天王物を母体としながら,坂田金時の子金平という超人的勇力の持主を新たに主人公に設定し,彼を中心に源家一統とその対立者との抗争を描く金平浄瑠璃は,稚気と行動力に満ちた金平のめざましい活躍,和泉太夫の豪快な語り口が江戸の庶民を引きつけ,爆発的人気を呼んだ。和泉太夫の正本(しようほん)に岡清兵衛という作者署名の存することも画期的である。浄瑠璃史では金平物と同傾向の四天王物も含め,58年(万治1)和泉太夫・岡清兵衛の《宇治の姫切》以後,江戸,上方を通じ約170種の正本を金平浄瑠璃に数えている(室木弥太郎《語り物--舞・説経・古浄瑠璃--の研究》参照)。
金平浄瑠璃の主人公が明確な意志をもって源氏を脅かす謀叛人や妖怪と闘い世を泰平に復せしめる構想は,運命にもてあそばれる主人公の悲哀を詠嘆する中世的語り物とは異質で,単純ながらドラマの基本線が認められる。大坂で《頼光跡目論(あとめろん)》など金平物を得意とした井上播磨掾の門下から,竹本義太夫が生まれたのも故なしとしない。しかし中世色の濃い説経風の古浄瑠璃,角(かく)太夫節なども民衆の根強い支持を保ち,他方,古典的な優雅な題材を扱いつつ現代風俗をも摂取して浄瑠璃の地位を高めた宇治加賀掾は,近松初期の作品《世継曾我》(1683・天和3)などを演じ,古浄瑠璃と義太夫節の橋渡し的存在となった。
近松・義太夫時代--1680年代~1720年代
宇治加賀掾のワキをつとめていた竹本義太夫(筑後掾)は1684年(貞享1)大坂道頓堀,現在の浪花座の位置に竹本座を創立,歌舞伎と肩を並べる現代劇としての義太夫節を創始した。義太夫節は,古浄瑠璃に比べ,詞が写実的に語られ,地の文も一字一句詞章に即し綿密に節付けされ,単に優美・哀調・豪快等の情趣を漂わせる以上に,劇的緊張感の醸成に最も注意が払われる。それは語り物とはいえ,ドラマの本質を備えた戯曲を得てはじめて真の達成をみるべきものである。
85年近松門左衛門が義太夫の門出を祝って執筆した《出世景清》は,孤独の勇者景清と彼を愛するゆえに裏切りを犯す阿古屋との深刻な葛藤を扱い,義太夫節の出発点にふさわしい,近世悲劇(広末保《近松序説》参照)の本質を備えた作品であった。1703年(元禄16)近松・義太夫コンビによる最初の世話浄瑠璃《曾根崎心中》が上演され,人形浄瑠璃の現代劇化はいっそう推し進められた。貧しい手代と下級遊女の真摯な恋が封建社会の種々の規範と対立し,主人公たちが死をもって恋を貫こうとする構想には,近世悲劇の典型が認められ,以後近松は《堀川波鼓》《冥途の飛脚》《心中天の網島》《女殺油地獄》《心中宵庚申》など24の世話浄瑠璃を著した。18世紀初期に,無名の庶民を主人公としながら悲劇の風格を備え,イプセンの近代劇と相通ずる,時・所・筋の三一致的扱いが認められるなど,近松世話浄瑠璃は世界演劇史的観点からも高く評価されている。同時に近松は,雄大,華麗に時代物にも健筆をふるい,《酒呑童子枕言葉》《傾城反魂香》《平家女護島》など100作近くを著したが,特に15年(正徳5)《国性爺合戦》は,17ヵ月続演の画期的大当りをとり,初代義太夫没後の竹本座の基礎を固め,この成功を契機として,18世紀前半の上方演劇界で,浄瑠璃は歌舞伎を圧し,現代劇の首座を占めるに至る。
浄瑠璃全盛期--1720年代~1751年
1703年初代義太夫の門弟豊竹若太夫(越前少掾)は,竹本座から独立し豊竹座を創立,持ち前の美声と経営的手腕で地歩を固め,初代義太夫,近松没後の浄瑠璃界は竹豊両座対抗の時代を迎えた。両座の競争により浄瑠璃界はいっそう活気を帯び,享保後半~寛延期(1726-51)25年間に,現在の文楽や歌舞伎の主要演目となる名作が次々と初演されるが,近松・紀海音(1723年(享保8)以前の豊竹座作者)時代と異なり,これらの作品の多くは合作制により生み出された。34年人形に三人遣いが考案され,人形浄瑠璃の写実的傾向はいっそう強まり,特に竹本座の人形遣い吉田文三郎は人形が〈生きて働く〉と絶賛され,彼の考案した演出,衣装などは,現在まで文楽,歌舞伎の舞台に生き続けている。文三郎が立役(男性)を得意としたのに対し,豊竹座の藤井小三郎,小八郎は名女形遣いと謳われた。この人形の芸風の違いは,太夫の曲風とも関係する。竹本座の座頭2世義太夫(竹本政太夫,播磨少掾)は質実剛健な語り口(西風と呼ぶ。音階的には陰旋法)で男性を語るに適し,初世豊竹若太夫は花やかな語り口(東風,陽旋法)で女性の表現に適していた(近石泰秋《操浄瑠璃の研究》参照)。
この期を代表する作者は並木宗輔(千柳)である。享保後期から豊竹座にあって,《苅萱桑門筑紫𨏍(かるかやどうしんつくしのいえづと)》《和田合戦女舞鶴》《奥州秀衡有鬙壻(うはつのはなむこ)》など,女性が活躍する作品を書いたが,社会の矛盾や人間の罪業を鋭く見据え,特に封建社会で人格を認められない女性の苦悩をえぐり出し,悲痛な作品が多かった。若太夫はこの暗い戯曲に派手な東風の節付けを巧みに施し,興行的にも成功を収めた。一方,竹本座では近松門下の文耕堂,初世竹田出雲(竹本座経営者兼作者)らが,2世義太夫の質実剛健な語り口にふさわしい,英雄的な男性主人公の活躍を力強く描いた(《ひらかな盛衰記》など)。45年(延享2)両座の太夫の世代交替を機に,並木宗輔は竹本座に移り,2世竹田出雲,三好松洛らと合作《菅原伝授手習鑑》《義経千本桜》《仮名手本忠臣蔵》など,時代物の最高傑作を次々に著し,文三郎の人気と相まって人形浄瑠璃は隆盛の極に達し,〈歌舞伎はなきが如し〉とまでいわれた。これらの合作では出雲,松洛らが親子の情愛の描出に力を注ぐ一方,並木宗輔の作風もかつての暗さが薄れ,歴史と宿命の前に微弱な存在にすぎぬ人間の営みを,無常観をもって淡々と描くようになった。
古典化時代--18世紀後期以後
人形浄瑠璃は劇と語り物の接点に立つ舞台芸術で,中世的語り物の域を脱し,近世興行界で歌舞伎と鎬(しのぎ)を削っていくには,演劇性,写実性の大幅な摂取が必要であったが,その面に徹すれば語り物の本質が失われる。人形操法,太夫の語り口が,演劇的,写実的に発達し切った1740年代に,並木宗輔の戯曲は,叙事詩的時間処理に留意し,無常観を根底に置くことで,劇と語り物の最後の均衡を保ち得たが,近代への胎動が兆す18世紀後期の作者近松半二は,語り物の思想である無常観を排し,主人公の主体的行為を追求する劇の方向を推し進め,《奥州安達原》《本朝廿四孝》《妹背山婦女庭訓(おんなていきん)》《伊賀越道中双六》など,ダイナミックで絢爛たる舞台を繰りひろげた。しかし1765年(明和2)に豊竹座,67年には竹本座が退転し,半二没後,特に19世紀以後は新作にみるべきものはなく,人形浄瑠璃の現代劇の時代は終わった。
このころより,人形浄瑠璃は三味線音楽の発達(朱と呼ばれる譜を発明)と相まって,芸の練磨・伝承に重点が置かれ,古典化の途をたどる。ただし人形浄瑠璃の観客数は必ずしも減少したわけではなく,大坂市中には群小座が分立し,その中から19世紀初頭に,高津橋南詰(現在の国立文楽劇場付近)に植村文楽軒が建てた小劇場が,後に難波神社境内に移り,文楽の芝居と呼ばれ,幕末・明治期人形浄瑠璃界の中心勢力となり,1909年(当時,御霊(ごりよう)文楽座)に経営が植村家から松竹合名会社に移って以後も,文楽座の名称は残り,大正・昭和ころから〈文楽〉は人形浄瑠璃の代名詞となった(祐田善雄《浄瑠璃史論考》参照)。
→文楽
執筆者:内山 美樹子
明治期の人形浄瑠璃
1872年(明治5),文楽軒の小屋は文楽座と名乗るが,当時,すでに文楽座は他座に抜きん出た大一座であった。しかし,84年,群小の人形芝居小屋が合同して,前年の内紛によって文楽座から脱退した三世竹本大隅太夫,二世豊沢団平らを擁し,大阪の中心地船場博労町に彦六座を開場した。一方,文楽座も,同年,小屋を彦六座の近くの船場平野町御霊神社境内に移し,御霊文楽座と名乗って,二世竹本越路大夫(のちの竹本摂津大掾)を中心に七世竹本津太夫,五世豊沢広助,初世吉田玉造,初世桐竹紋十郎らの陣容を整え,これに対抗した。こうして,両座が競合する明治期の大阪人形浄瑠璃の黄金時代が現出する。中江兆民は,この時期に輩出した名人たちの芸を評して神技・三絶といっている(《一年有半》)。しかし,93年,彦六座は消滅,あとを継いだ稲荷座も,98年,名人団平の急死によって閉場し,活動写真などの他の大衆娯楽に押されながら,大正期以降,人形浄瑠璃の芸の伝承は文楽座で行われることになる。
→文楽
執筆者:斎藤 武
人形の操法と仕掛の変遷
大江匡房(1041-1111)の《傀儡子記(くぐつき)》によると,日本の人形芝居は中国から輸入された傀儡子(くぐつ)まわしが起源とされる。福岡県の古表神社,大分県の古要神社に残る相撲人形に古形を見ることができる。世界の人形劇の操法には(1)手遣い,(2)指遣い(ギニョル),(3)糸操り(マリオネット),(4)棒遣い,(5)幻灯人形,(6)からくり人形,(7)写し絵の七つがあるが,人形浄瑠璃に用いられるものは手遣いで,日本独特の操法といわれる。人形の下から手を突っ込んで遣ういわゆる一人遣いから二人遣い,三人遣いの3方法がある。1703年(元禄16)に《曾根崎心中》のお初を遣った辰松八郎兵衛は突込み人形の名人といわれるが,彼はこのほか,片手人形や手妻(てづま)人形を遣ったという。片手人形は,人形の胴の背後から手を入れて片手で遣ったところから名付けられたが,ときには両手で2体,3体,5体,7体の人形を遣った。また体内に細工した糸を引いて男人形,鬼神,観世音と手品のように変化させる手妻人形もあり,元禄期(1688-1704)にはその名手に山本飛驒掾がいた。一人遣いの形式は,文楽のつめ人形や東京八王子の車人形,乙女文楽に残っているが,手妻人形の背後から手を差し込み引き糸で首を動かす方法は,やがて三人遣いに発展した。
今日の文楽のような三人遣いは元禄期の江戸孫四郎座にもあったが,本格的に活用されたのは1734年(享保19)の《蘆屋道満大内鑑(あしやどうまんおおうちかがみ)》の与勘平・野干平の人形からである。近松門左衛門の浄瑠璃はすべて一人遣いの突込み操法であった。人形操法の工夫・改良は,竹本座の名手吉田文三郎,近本九八郎,豊竹座の若竹東工郎,豊松藤五郎の力に負うところが大きい。立役の人形に足を付け始めたのは《源氏烏帽子折》の金王丸のときとも,《世継曾我》の朝日奈のときともいわれるが,享保(1716-36)から延享年間(1744-48)にかけて,人形の写実性を高めるさまざまな発明工夫がなされ,人形浄瑠璃は全盛期を迎えることになる。
以下その発明工夫の過程を年代順にあげる。(1)人形の口開き,目ふさぎ,五指動く工夫が,1727年(享保12)豊竹座の《摂津国長柄人柱》の入鹿から。(2)人形の目の動く仕掛が,30年豊竹座の《楠正成軍法実録》の和田七の人形から。(3)人形の指先の動く仕掛が,33年竹本座の《車還合戦桜》の大森彦七の人形から。(4)三人遣いが,34年竹本座の《蘆屋道満大内鑑》の与勘平・野干平の人形から。(5)眉の動く仕掛が,36年(元文1)竹本座の《赤松円心緑陣幕》の本間入道の人形から。(6)2倍の大きさの人形が,36年豊竹座の《和田合戦女舞鶴》の板額の人形から。(7)立役人形の屛風手(〈数の子手〉ともいい,5本の指を革でつなぎ蝶番(ちようつがい)のように動かす)が,47年(延享4)豊竹座の《悪源太平治合戦》から。(8)耳の動く仕掛が,47年《義経千本桜》の狐忠信から。
人形の首
人物の性別,老幼,性格,境遇などに応じて,男の首(かしら)には,老年に〈鬼一(きいち)〉をはじめ9種,中年には〈文七(ぶんしち)〉をはじめ20種,若者には〈源太(げんだ)〉をはじめ5種,あわせて34種がある。女の首は,老年に〈婆(ばば)〉をはじめ3種,中年に〈老女形(ふけおやま)〉をはじめ4種,若い女性には〈娘〉をはじめ7種,あわせて14種がある。このほか,〈景清〉〈丞相(しようじよう)〉などの,一役一首で他に流用されることがほとんどない特殊な首が6種,これに新作ものの首を加えると24種になる。
立役首には,悲劇の主役に使われる〈文七〉,悪公家の〈口開文七(くちあきぶんしち)〉をはじめ時代物の荒物に使われる〈大団七(おおだんしち)〉,ならず者の〈小団七〉,武将から町人まで広く使われる〈検非違使(けんびし)〉,二枚目の〈源太〉などがある。立役首の名称は,初演の役名からとられたものが多いが,これに対して女形の首は,役名が付けられたものは少なく,種類も少ない。〈娘〉は丸顔と細面と表情にやや違いがあるが,時代物と世話物の区別なく使われる。《曾根崎心中》のお初などには,目を閉じる仕掛の〈ねむり娘〉が使われる。また,天保(1830-44)のころの名人笹屋芳兵衛作と推定される〈笹屋〉は普通の〈娘〉にくらべると細面で目が細く,三姫に使われる。
特殊な首としては,盲目の〈景清〉,〈丞相〉,美しい娘の形相が変わる〈がぶ〉,〈玉藻前(たまものまえ)〉などがある。〈文七〉にもいろいろのものが用意されていて,現在,文楽協会に約300個の首がある(図参照)。 首の塗りは,年齢,性格によって区別され,白,薄卵,卵,濃卵,猩臙脂(しようえんじ)が塗られる。たとえば,〈文七〉は白塗りが定法(《菅原》の松王丸,《太功記》の光秀)だが,役によって薄卵塗り(《一谷》の熊谷など),卵塗り(《八陣》の朝清など)の場合もある。
首の仕掛には,眉の上下する仕掛,目の開閉する仕掛,寄り目,引き目,寄せ目の仕掛などがあり,ごくまれに,鼻や耳の動くもの,口の開閉する仕掛のものもある。眉には描き眉と付け眉があるが,描き眉には,美しい弧を描いた〈源太〉や〈若男(わかおとこ)〉の眉,太く猛々しい〈小団七〉の眉,どっしりした知謀をあらわした〈べらぼう眉〉,きりっとした武士眉,細く優美な娘の眉,老女形の青眉がある。付け眉は黒毛のほかに,白と胡麻があり,眉尻の毛を揃えたものと伸び放題のじぞろにしたものがある。いずれも役柄に応じたものである。
人形の鬘と衣装
髪型も,性別,年齢,職業,地位によってそれぞれきまった型がある。初期の人形芝居は鬘(かつら)/(あたま)に毛を直接うえていたが,安永(1772-81)のころから随時つけ替える便法が考案された。立役鬘は髷油付き(まげあぶらつき)のものと髷結い上げものに大別され,時代物と世話物の双方にさまざまな種類がある。また,前髪にも数種あり,鬢(びん)の種類も直鬢(じきびん),中鬢,低鬢をはじめ多種あり役柄によって異なる。前髪の左右に短い毛のさがっているものを〈しけ〉というが,女形の首にもこれがつくものもある。女形鬘には,下げ髪,切髪,馬の尻尾があり,ほかに,〈型もの〉〈島田もの〉〈丸髷もの〉〈笄(こうがい)もの〉などがある。子役の鬘は男の子の〈がっそう〉,女の子の〈三方下り蝶々髷(ちようちようまげ)〉など数種ある。
人形の衣装は専門の衣装担当者が付帳を各段について書き入れる。たとえば,《一谷嫩軍記(ふたばぐんき)》の熊谷直実なら文七首,黒鵞絨半腰,向い鳩紋付,赤地金襴雲丸竜裃,向い鳩紋付,白衿,浅葱(あさぎ)中衿となる。原則として公家は衣冠・束帯,大名は大紋,勇者には黒天の着付に赤地金の裃,若武者には華美な熨斗目(のしめ)の織紋,町人の老人は茶無地の着付,町人の若者は浅黄立縞の着付,百姓は木綿縞,女は片はずしの政岡なら緋緞子(ひどんす)の着付に紺金の帯,黒綸子(くろりんず)竹刺繡の裲襠(うちかけ),立兵庫(たてひようご)の傾城なら赤縮緬平金散し胴ぬき着付,黒綸子鯉滝などの刺繡裲襠,鮟鱇(あんこう)帯,赤帯揚鴇(とき)しごき,白綸子衿,赤返し衿,赤湯具,お七髷の娘なら段鹿子振袖の着付,島田髷の女房は鳶石持(とびこくもち)と大体きまっている。舞台における人形の衣装の色の配合はまことによく考えられていて,《仮名手本忠臣蔵》の山科閑居の段は,お石は黒,戸無瀬は赤,小浪は白の着付と,同じ女性でも区別されている。また《義経千本桜》の佐藤忠信の源氏車の紋や,《仮名手本忠臣蔵》の大星由良助の二つの巴の文,《夏祭浪花鑑》の団七九郎兵衛の白木綿茶弁慶染の浴衣,《菅原伝授手習鑑》の梅王・松王・桜丸の三つ子の白繻子(しろじゆす)柴童子格子着付(梅王は赤縮緬梅の台付ぬいかけ,松王は白繻子松繡(しようじゆ)ぬいかけ,桜丸は赤縮緬桜台付ぬいかけ)と初演のときからきまっているものが多い。
胴,手,足
魂をもつ人間以上に美しい姿や勇ましい動作をする人形も,衣装を脱がすと単純な構造である。人形の胴は肩板と腰輪とそれをつなぐ布切れからなり,肩板の両端に,衣装をつけたとき肩のふくらみを作るへちまがつけられている。また立役の肩板は真ん中が切り抜かれていて別に吊肩があり,手足は両肩から紐でぶら下がっている。人形遣いは腰輪の下から左手を差し込み,人形の胴串を握る。腰輪の右側に突上げの棒と呼んでいる約30cmの短い竹の棒があり,突き上げて巧みに強さを表したり,人形の重みを支えたりする。女の人形は肩板も腰輪も小さく,原則として足はつけない。また初世吉田栄三は腰輪に帛魂(きぬたま)という綿入れの袋をつけて女のふくよかな色気をつけていたが,今日では衣装の裾に綿入れの腰蒲団を縫いつける。
人形の手は首と同じように檜でつくり,塗色は首に合わせて塗る。大別して手首の動くものと動かぬもの,指の動くものと動かぬものがある。手の種類は〈かきつばた〉〈チャリ手〉〈摑(つか)み手〉〈たこ摑み〉〈かせ手〉〈蠅叩き手〉〈さぶた手〉〈女手〉〈婆手〉〈子役手〉の10種類のほか,〈三曲手〉(琴手,撥(ばち)手,三味線手),〈狐手〉など24種の特殊手がある。人形の手は物を持つことができないので,右手首にU字型の指革に人差指を差し込んで人形遣いが自分の五指で持つ。また左手には差金(さしがね)という棒がついていて,この差金にある小猿の左右を引くと手首や指が動き,左手が物を持つときには左遣いが左手で持って左手指のそばに持っていく。
人形の足は原則として男だけにつけ,女は裾さばきで歩く姿を見せる。ただし〈草履打〉の岩藤や〈奥庭〉のお初,《曾根崎心中》のお初には足がつく。足には〈文七〉〈丸め〉〈源太〉〈きれもも〉〈もも長〉〈中足〉〈女足〉〈子役足〉〈藁足〉の9種と,特殊足として〈狐足〉〈景清足〉〈熊足〉があり,人形を軽くするためこれらは桐でつくられている。
人形の操法
文楽は主(おも)遣い,左遣い,足遣いの3人が一つの人形を遣う,いわゆる三人遣いを原則とする,世界でも類例のない人形劇である。文楽の番付には主遣いの名しか書かれていないが,人形頭取(とうどり)の持つ〈小割帳〉には3人の名が記載されている。主遣いが人形の胴の後ろの帯の下から左手を突っ込んで人形の首の胴串を掌で支え,小指と薬指で握る。中指は引栓を引いて首をうなずかせ,親指と人差指で小猿を引いて人形の眉,目,口を動かす。また親指で肩板を上下させて人形の息づかいを見せる。左手で人形を支えるときは,淡路人形が肘(ひじ)を曲げずに人形を持ついわゆる鉄砲差しとは違って,二の腕を水平にして肘を垂直に曲げて人形を直立させる。重い立役の人形を長時間支えるために胴に付いた突上げを使い,胸か二の腕に当てる。主遣いは足遣いが遣いやすいように大(1尺2寸,36cm),中(8寸,24cm),小(5寸,16cm)の高下駄(たかげた)をはいて人形を高く支える。
左遣いは人形の左手の差金を右手で持ち,空いた左手で人形の胴を支えて主遣いを助けたり,刀などを持ち添えたりする。足遣いは足の後ろに付いた鍵型の足金を握って足を動かし,女の人形は衣装の裾の裏を持って裾さばきをして歩かせる。また女の人形の立膝するときには,足遣いが衣装の下で右腕を立て握りこぶしをして膝があるように見せる。足遣いは主遣いの腰に右腕を軽くつけてその腰のひねりを感じとり,人形の首を見上げて人形の動きを知り,足拍子を踏むなどで,人形の舞台の独特の雰囲気をつくりだす。
一人前の人形遣いとなるために足遣い10年,左遣い10年の修業を経たのち主遣いとなり,さらに10年の努力が必要であるとされている。なかには,一生足遣いや左遣いや〈つめ〉遣いで終わる人もある。
人形の型
人形の操法には泣いたり,笑ったり,怒ったりする動作のほかに,さまざまな型がある。たとえば,女の人形の〈くりず〉は,頭(ず)を刳(く)ることで,主として娘や老女形の首に遣われ,右へ〈くりず〉をしようと思えばいったん左に首をやり,顎(あご)をおとして右へ首を回して女の切ない,やるせない思いを表す型である。また,〈うしろぶり〉は,女の恨みごとや悲しみが頂点に達したときにする女形独特の美しい後ろ姿である。
立役の代表的な型としては,〈団七走り〉〈ギバ〉〈六方〉〈打込(うちこみ)〉〈石投げ〉などがある。〈団七走り〉は,武将が押し寄せる敵軍を偵察するため,松の大木に登ろうとして駆け行く型で,左右の手を大きく交互にふって走りだす。いったん前の手を胸に引き付けてから後ろにふるのが人形独特の豪快さを発揮する。〈ギバ〉は,尻をついて両足を開き出す型で,両足を前に投げ出し肩で大きく息をつく。〈打込〉は,刀で渡り合う型で,戦闘の場に用いられ,足拍子が入るのが特色である。
こうした典型的な動作のほかに,歌舞伎と同様に,〈大玉造〉と呼ばれた初世吉田玉造の〈いがみの権太〉の型,〈沢市〉の型,初世桐竹紋十郎の〈重の井〉の型,初世吉田栄三の〈弁慶〉〈治兵衛〉の型,また名人といわれた吉田文五郎の〈お園〉の型など,特定のすぐれた人形遣いの演出が伝えられている。
舞台の様式
古浄瑠璃の舞台には次の5種の様式が存在した。(1)人形を高くあげ,人形遣いは見物に姿を見せない。杉山丹後掾,山本土佐掾,井上播磨掾の芝居に見られる。今日も佐渡の野呂間人形に残っている。(2)人形遣いが上半身を上幕と勾欄(こうらん)(手摺)の間に出している一種の出遣い形式で,土佐少掾,和泉太夫,江戸半太夫,伊勢大掾の舞台に見られる。(3)舞台が3段になり,本手が幕で,二の手,三の手は手摺(てすり)になっている。井上播磨掾の舞台に見られる。(4)二の手,三の手の手摺が平面になっていて糸操りを併用し,付舞台もある。井上播磨掾の芝居に見られる。さらに花道もあり,付舞台や花道で出遣いをする様式もある。宇治加賀掾の芝居に見られる。(5)初期の特殊な三人遣いの舞台で手摺に平面の台がついている。江戸孫四郎の舞台に見られる。
こうした古浄瑠璃時代の様式から,近松時代,完成期にかけて,舞台の様式は洗練され機構も確立をみる。すなわち1694年(元禄7)の《本海道虎石》で捩子手摺(もじてすり)が工夫され,人形の遣いようを見せ,つくり舞台をつけることになるが,1705年(宝永2)の《用明天王職人鑑》で後世の人形芝居の舞台形式の基本が確立する。やがて17年(享保2)の《国性爺合戦》で大幕の上に小幕を引きはじめ,20年の《信州川中島合戦》で張抜きの本山をつくり,28年の《加賀国篠原合戦》では正面の太夫の床を横にした形式が確立する。さらに宝暦期(1751-64)には,水からくり,セリ,大道具などにさまざまな工夫が凝らされ,人形浄瑠璃は黄金時代を迎えるのである。その完成された舞台は《戯場楽屋図絵拾遺》(1802)に集成されている。明治期に入ると,吉田玉造らによる何段返しや宙づりなどの工夫が加わり,今日の舞台に引き継がれるのである。
現代の舞台
文楽の舞台は歌舞伎や他の演劇の舞台とはまったく異なり,庭もなければ座敷や廊下もない。ただ背景のほかには舞台横から見ると3枚の長い手摺が真っ直ぐに走っているだけで,背景に近い板の間の本舞台(二重という)とその前の手摺(本手。二重の手摺という)を境に一段低い板の間(舟底)があるだけである。
主遣いは高い舞台下駄をはき,足遣いは始終中腰になって足を遣うため,普通の役者の舞台と同じであれば人形は宙に浮き,人形遣いたちの姿は3人とも観客に丸見えになってしまう。そこで,人形が庭や畳の上や廊下を歩くように見せるために,主遣いと左遣いは上半身だけを見せ,足遣いは姿を見せないよう低い姿勢で手摺の下で動き,人形の足が二の手摺(舟底の手摺の上端)にくるように遣う。このため舟底の手摺に道路や廊下や畳を描くと,観客席からは人形が街道や座敷を歩いているように見えることになる。また一段高い本手(二重の手摺)に敷居が描いてあると二重が座敷や御殿となる。そこから段を下りて庭(舟底)へ出る場合には引割りといって黒衣の手伝いが引くと,一時空間ができたりまた階段が左右に別れて,人形遣いは段を下りるように遣いながら左遣い,足遣いもろとも舟底へ出る。これは手摺を人形もろとも3人の人形遣いが乗り越えることができないところから工夫されたものである。
なお,1984年3月に開場した国立文楽劇場は,中劇場が全席753席で,花道をつくると677席,出語り席を設けると731席となり,小ホールは159席という規模である。中ホールの舞台設備は,間口17.5m,高さ6m,奥行き18.5m,緞帳(どんちよう)3本,回り舞台,花道,出語り床,舟底,迫り,大セリ1台。
執筆者:吉永 孝
地方の人形浄瑠璃
文楽の源流ともいうべき淡路の人形浄瑠璃をはじめ,日本の各地にはさまざまな人形芝居が伝承されてきた。特に,義太夫節を用いる淡路と阿波の人形浄瑠璃はその代表的なもので,歴史も古く,広範囲に影響を及ぼした。淡路人形浄瑠璃における職能的な操り座の成立は寛文年間(1661-73)といわれるが,遅くとも古浄瑠璃時代には活躍していたことが明らかである。その行動圏は早くから島内にとどまらず,享保ころには,全盛期を迎えた竹豊両座に参加するものも出ていたと考えられる。さらに19世紀には,江戸,上州,北陸,紀州,九州などの諸国に回国行脚(あんぎや)が行われ,各地の人形芝居に多大な影響を与えた。三人遣いの操法や義太夫節がいつからとり入れられたかは確定しがたいが,現存する淡路人形浄瑠璃の演目には,文楽に残っていない作品も存在する。阿波人形浄瑠璃は,淡路の流れを汲み江戸末期に形成されたが,一時は淡路の人形浄瑠璃を圧倒するほどの勢いをみせた。淡路,阿波ともに,現在の人形は文楽の人形よりも大きいが,いずれも明治以降の変化で,古くは文楽人形よりもやや小さなものであった。
一方,古浄瑠璃を地とした文弥節の曲節による一人遣いの人形芝居が富山県(加賀文弥人形),鹿児島県(薩摩文弥人形),宮崎県(日向文弥人形),佐渡などに遺存した。加賀と薩摩は元禄期に上方から伝えられたといわれ,また日向は江戸後期に薩摩から伝来したとされている。佐渡の文弥人形は,明治初期に説経人形を改良してつくられたものだが,佐渡には金平浄瑠璃や説経節の流れも古くから伝わり,幕末の記録には,〈近松なにがしのつくれる浄瑠璃を説経とか云ふふしにて語る,いと鄙びたり〉とあるように,重層的で多様な人形浄瑠璃史が存在する。また,説経人形の間(あい)狂言として演じられた野呂間人形も残っている。
ほかに,一人遣いで,車のついた木箱に腰をかけて人形を遣う東京都八王子の車人形(説経節),二人遣いの埼玉県白久の串人形(義太夫節),指遣いの岩手県南部の軽石人形(義太夫節),一人遣いの千葉県袖ヶ浦の袱紗(ふくさ)人形(説経節)など,特色ある人形芝居が存在し,民衆芸能のありさまを連綿と伝えてきたが,その多くが保存と伝承を危ぶまれている。
執筆者:斎藤 武
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「人形浄瑠璃」の意味・わかりやすい解説
人形浄瑠璃
にんぎょうじょうるり
人形浄瑠璃は、一般に浄瑠璃の語りにあわせて演じる人形劇全般の称であるが、狭義には義太夫(ぎだゆう)節を使い、三人遣い形式によるものをさし、現在では唯一の専門劇団である「文楽(ぶんらく)」のことを意味する。江戸時代には操(あやつり)浄瑠璃または操芝居とよんだ。文楽は世界の数ある人形劇のなかでも、もっとも洗練された完成度の高い舞台芸術の一つといえよう。なお、人形浄瑠璃と歌舞伎(かぶき)とは約400年に及ぶ歴史のなかで、相互に影響、競合しながら歩んできた。
[山田庄一]
歴史
源流から古浄瑠璃時代
日本における人形劇の源流を探ると、宗教的・呪術(じゅじゅつ)的な古来の神人形と、大陸から渡来したと考えられる芸能的人形の二つの流れが想定されるが、少なくともすでに奈良時代には人形回しの芸能が存在したことが文献によって知られる。平安後期の11世紀中ごろになると、人形回しは逃散(ちょうさん)民によって形成された漂泊集団の職能の一つになり、その集団を「傀儡子(くぐつ)」とよんだ。鎌倉時代に入ると、傀儡集団は神社や仏閣の周辺あるいは街道の宿駅に定住するようになり、さらに室町時代になると、猿楽(さるがく)や幸若(こうわか)の舞を演ずるものも現れ、このうち西宮戎(にしのみやえびす)神社(兵庫県)の末社、百太夫(ひゃくだゆう)社を本拠とする一団はとくに勢力をもち、「夷舁(えびすかき)」(えびすまわし)と称して各地を回った。この夷舁は近年まで残って、春になると御影(みえい)などを配って家々を祝福して夷の人形を舞わせた。
一方、日本には古来「語物(かたりもの)」と称して筋のある物語を口で語る芸能の伝統があり、「平曲(へいきょく)」を始まりとしている。平曲は琵琶(びわ)の伴奏にあわせて『平家物語』を語るもので琵琶法師の専業であったが、謡曲や幸若あるいは説経節(せっきょうぶし)などの音曲の出現で流行に遅れたため平曲にいろいろの改革が加えられ、物語の種類も拡大されていった。それらのなかで『十二段草子』(浄瑠璃姫物語)が人気を博し、その曲節を浄瑠璃節とよんで他の詞章にも流用されるようになった。初期の浄瑠璃は相変わらず琵琶を伴奏とし、あるいは扇拍子の素語りであったが、永禄(えいろく)(1558~1570)ごろ琉球(りゅうきゅう)から三弦楽器が渡来し、これを改良した三味線を伴奏に用いるようになって曲節が大きく飛躍、浄瑠璃は新しい時代の音曲としての位置を確立した。文禄(ぶんろく)・慶長(けいちょう)(1592~1615)のころ浄瑠璃と夷舁が結び付いて人形浄瑠璃が発生したが、その始まりは、浄瑠璃に初めて三味線を使ったと伝えられる沢住検校(さわずみけんぎょう)の弟子、目貫屋長三郎(めぬきやちょうざぶろう)と、西宮の夷舁、引田淡路掾(ひきたあわじのじょう)と伝えられ、あるいは浄瑠璃語りは滝野勾当(こうとう)の弟子の監物(けんもつ)、次郎兵衛だともいい、明らかでない。人形浄瑠璃は時流にのって大いにもてはやされ、慶長の終わりから元和(げんな)(1615~1624)ごろには京都はもとより江戸をはじめ全国各地で興行されるようになった。しかし舞台は小屋掛けの粗末なもので、人形も一人遣いの簡単な動きしかできず、浄瑠璃もまだまだ単調な曲節で、物語も神仏の霊験(れいげん)記などの素朴な内容であった。
浄瑠璃が流行すると演者の数も増え、それぞれにくふうを凝らして一派をたてる者が続出し、技芸を競うようになった。杉山丹後掾(たんごのじょう)は慶長の末ごろ京都から江戸に下り、1615年(元和1)に江戸で最初の浄瑠璃興行を行った。杉山一門の柔らかな芸風に対して、沢住検校門下の薩摩浄雲(さつまじょううん)は硬派の代表で、寛永(かんえい)(1624~1644)のころ江戸に下り、豪快勇壮な語り口が江戸の人々の好みにあったため大いに繁盛し、金平(きんぴら)節の元祖桜井和泉太夫(いずみたゆう)(丹波少掾(たんばのしょうじょう))、虎屋(とらや)源太夫などの名手が門下から現れた。一方、上方(かみがた)では、明暦(めいれき)の大火(1657)のあと虎屋源太夫は弟子の喜太夫とともに上京して四条河原で興行して好評を博し、源太夫門下から名手井上播磨掾(はりまのじょう)が出た。播磨掾は師匠譲りの武勇物を得意としたが、浄瑠璃にくふうを凝らして「うれい(愁い)」(情緒的なもの)にも長じ播磨節をたて、大坂道頓堀(どうとんぼり)で操芝居を興行して人気を集めた。当時の大坂では「うれい」を強調した角太夫(かくだゆう)節の山本角太夫(土佐掾(とさのじょう))が、南京(なんきん)糸操り、水からくり、手妻(てづま)人形など、からくりをくふうした人形と組んで興行して対抗していた。
同じころ京都では、紀州の人、宇治嘉太夫(かだゆう)が謡曲を基本とした一派を編み出し(嘉太夫節、加賀節)人気があったが、1677年(延宝5)大坂から播磨掾の孫弟子にあたる清水理太夫をワキに迎えて一座を固め、同年暮れに受領(ずりょう)(掾号を受けること――宮家や公家(くげ)の収入源でもあった)して宇治加賀掾(かがのじょう)を名のった。まもなく不和を生じて加賀掾のもとを去った理太夫は西国(さいごく)に下って修行を積み、1684年(貞享1)名を竹本義太夫(ぎだゆう)と改め大坂道頓堀に竹本座の櫓(やぐら)をあげた。義太夫はそれまでの各派浄瑠璃の長所を集大成して、さらに自らのくふうを加えたうえ、作者に近松門左衛門(ちかまつもんざえもん)、三味線に竹沢権右衛門(ごんえもん)、人形遣いに辰松(たつまつ)八郎兵衛らの名手を得て大坂中の人気を独占し、やがて他派の浄瑠璃はしだいに衰微して「浄瑠璃」といえば「義太夫節」を意味するまでになった。そこで竹本座旗揚げまでの各派浄瑠璃を総称して「古浄瑠璃」とよんでいる。
[山田庄一]
義太夫による完成と竹豊(ちくほう)時代
竹本義太夫は自分の創始した浄瑠璃を「当流」あるいは「新浄瑠璃」と名づけたが、それは従前の各派浄瑠璃と芸術的に大きな開きがあり、明らかに一線を画するものであった。基本的には井上播磨掾の剛健な音(おん)遣いと宇治加賀掾の繊細な節回しを統合しているが、諸派浄瑠璃の曲節のほか、謡曲、狂言小歌、平曲、説経節なども取り入れ、当時の音曲を集大成したものであった。しかも近松門左衛門という不世出の名作者を得て、戯曲の内容は文学として飛躍的に高度になったばかりでなく、従来のような神仏霊験譚(れいげんたん)や武勇伝の単調な物語から、人情の機微をうがった華麗なロマンへ発展し、さらに『曽根崎(そねざき)心中』に始まる「世話物(せわもの)」の創造によってよりいっそう観客と密着したものとなった。戯曲の構成もこのころに時代物の五段組織が定着した。その理由については能楽の五番立(だて)を模したというが、世話物の場合は物語が短く単純なため、通常、上・中・下の3巻あるいは上・下2巻にまとめられている。
一方、人形については傀儡子の芸からあまり進歩がなく、片手遣いの小さなもので、舞台も簡単に幕を張った陰から人形を上に差し出して演じていたが、やがて場面に応じて道具を飾るようになり、張り抜きの山やからくりを利用して本水(ほんみず)を用いる舞台なども現れた。人形も山本飛騨掾(ひだのじょう)が手妻(てづま)人形を考案して、背中から手を入れて引き栓(せん)でからくりを扱う「差し込み式」をつくり、後世の人形の仕掛けの源流を創始したが、辰松八郎兵衛などは裾(すそ)から手を入れて遣う「突っ込み式」で、いずれにしても一人遣いから脱しきれなかった。
竹本義太夫は1701年(元禄14)受領して筑後掾(ちくごのじょう)藤原博教(ふじわらのひろのり)と名のり、名声、技芸とも高まっていったが、2年後の1703年に門弟の筆頭で美声の誉れ高かった竹本采女(うねめ)が独立して豊竹(とよたけ)若太夫と名のり、竹本座と同じ道頓堀に豊竹座を創立した。作者には狂歌師鯛屋貞柳(たいやていりゅう)の弟で学者・俳諧(はいかい)師として著名であった紀海音(きのかいおん)を招いて近松に対抗させ、『冥途の飛脚(めいどのひきゃく)』に対する『傾城三度笠(けいせいさんどがさ)』、『心中宵庚申(よいごうしん)』に対する『心中二つ腹帯』など同じ題材の作品をはじめ数多くの名作を上演して成功、ここに竹本、豊竹両座が競い合ってますます人形浄瑠璃の人気を盛り上げ、技芸面でも急速な充実を示した。これより1765年(明和2)に豊竹座、その翌々年の1767年に竹本座が相次いで退転するまでの約60年間は操浄瑠璃の黄金時代で、「歌舞伎はあって無きがごとし」とまでいわれ、一般に「竹豊時代」とよんでいる。竹本座では義太夫没(1714)後、その遺言により門弟の政太夫(まさたゆう)を後継者とすることに不満を抱く者たちが相次いで豊竹座に移る。この苦境に、近松は『国性爺合戦(こくせんやかっせん)』を書き、17か月続演という空前の大入りを収めた。さらに、近松没(1724)後も、初世竹田出雲(いずも)、文耕堂(ぶんこうどう)、長谷川千四(はせがわせんし)らの合作を次々に発表、政太夫は1734年(享保19)2世義太夫を襲名、翌年上総少掾(かずさのしょうじょう)を受領し、さらに1737年(元文2)には播磨少掾(はりまのしょうじょう)を再受領するなど、語り口に新境地を開いた。また、初世吉田文三郎(ぶんざぶろう)らが人形の改良に力を尽くし、手妻の技術を取り入れて、人形の首(かしら)の目や口、眉(まゆ)あるいは手足などの動くくふうを行い、ついに1734年の『芦屋道満大内鑑(あしやどうまんおおうちかがみ)』の野干平(やかんべい)の役で三人遣いを考案し、ここに現在の人形浄瑠璃の形式がいちおうできあがったわけである。義太夫節も、両座に優れた太夫が輩出し、それぞれ元祖の語り風を守って座風が明確になり、特色を発揮した。両座の位置から、じみで堅実な竹本座の語りを「西風(にしふう)」、華麗でつややかな豊竹座のものを「東風」とよんでいる。
続いて延享(えんきょう)年間(1744~1748)に入ると、播磨少掾が死去、越前少掾(えちぜんのしょうじょう)を受領した豊竹座の祖、若太夫も引退して、竹豊両座とも新しい活躍期を迎えた。とくに竹本座では、座本の2世竹田出雲が豊竹座から立(たて)作者の並木宗輔(そうすけ)(千柳(せんりゅう))を迎え三好松洛(みよししょうらく)らとの合作で『夏祭浪花鑑(なつまつりなにわかがみ)』『菅原伝授手習鑑(すがわらでんじゅてならいかがみ)』『義経千本桜(よしつねせんぼんざくら)』『仮名手本忠臣蔵(かなでほんちゅうしんぐら)』など浄瑠璃の代表的名作を次々に上演して操り史上の最盛期を現出した。しかし人形の発達によって自由な動きが可能になるにしたがって浄瑠璃の内容も見た目本位の作品が多くなり、かつ、操りに圧倒された歌舞伎がいち早く浄瑠璃の当り狂言を取り入れて上演することによって衰運挽回(ばんかい)の機運をつかんだことなどが重なり合って、人形浄瑠璃の人気はしだいに下降線をたどることとなった。すなわち、竹本座では近松半二を作者の中心として『奥州安達原(おうしゅうあだちがはら)』『本朝廿四孝(ほんちょうにじゅうしこう)』などの名作を上演したが興行的には苦しく、豊竹座も1764年(明和1)に座本であり創始者であった越前少掾が84歳の高齢で没するとたちまち座運が傾いて、両座は相次いで退転、ここに竹豊時代は幕を閉じた。このあと豊竹座は1767年に豊竹此吉(このきち)が北堀江市(きたほりえいち)の側(かわ)に再興、竹本座も道頓堀で再興を図り、『妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)』(1771)で一時的な大当りをとったこともあったが、長続きはしなかった。
[山田庄一]
文楽座創立から国立文楽劇場開場まで
竹豊両座の退転後は演技者には数多くの名手が出たが、作者には優秀な人材なく、新作の行われることはあっても傑作は生まれず、むしろ過去の名作の再演が多くなり、浄瑠璃も人形も先人の遺産のうえにさらに磨きをかけてゆく洗練の時代に入っていった。浄瑠璃の流行は全国に広がって、天明(てんめい)期(1781~1789)には江戸で新作が行われ『伽羅先代萩(めいぼくせんだいはぎ)』『加賀見山旧錦絵(かがみやまこきょうのにしきえ)』などは今日に残っている。大坂では社寺の境内や寄席(よせ)など小さな操芝居の数が増えていったが、寛政(かんせい)年間(1789~1801)に淡路出身の植村文楽軒が浄瑠璃の小屋の経営に手を染めた。1811年(文化8)2世文楽軒のとき大坂博労(ばくろう)町稲荷(いなり)の境内に操芝居を開き、さらに4代目の文楽翁は1872年(明治5)に松島に移転、文楽座と名づけた。これに対し1884年に稲荷境内に彦六座ができたので、文楽座も平野町の御霊(ごりょう)神社境内に移転した。文楽・彦六両座の対抗はかつての竹豊時代の再現を思わせ、しかも太夫には2世竹本越路(こしじ)太夫(摂津大掾(せっつのだいじょう))、2世竹本津太夫、3世竹本大隅(おおすみ)太夫ら、三味線に2世豊沢団平、5世と6世の豊沢広助(ひろすけ)ら、人形に初世吉田玉造、吉田玉助、初世桐竹紋十郎(きりたけもんじゅうろう)らの名手が輩出して技芸を競い合い、明治期の人形浄瑠璃は黄金時代を築き上げた。しかし、経営は双方とも苦しく、まず1893年に彦六座がつぶれ、1909年(明治42)には文楽座も植村家の手から松竹に譲渡された。彦六系の芸人たちはその後も稲荷座、明楽(めいらく)座、堀江座と続いて文楽座に対抗していたが、1914年(大正3)佐野屋橋南詰(みなみづめ)の近松座の休座を機に文楽座に併合され、ここに人形浄瑠璃の専門劇場としては文楽座が唯一の存在となり、「文楽」の名称が人形浄瑠璃の代名詞となった。
大正期も、太夫に3世越路太夫、3世津太夫、6世竹本土佐太夫、2世豊竹古靭(こうつぼ)太夫(山城少掾(やましろのしょうじょう))ら、三味線に3世鶴沢清六(せいろく)、6世豊沢広助(ひろすけ)、7世野沢吉兵衛(きちべえ)、初世鶴沢道八(どうはち)、6世鶴沢友次郎(ともじろう)ら、人形に初世吉田栄三(えいざ)、吉田文五郎らが数多くの名舞台を展開した。しかし、1926年(大正15)に御霊文楽座が火災にあい、まもなく四つ橋に移転新築されたが、世相は昭和初期の不況から第二次世界大戦へ突入、四つ橋文楽座も戦災を受けた。
終戦後、文楽座は松竹の手でまもなく四つ橋に再建されたが、当時急速に高まった労働組合運動の影響を受けて、1948年(昭和23)5月ついに組合派と非組合派に分裂、組合派は2世桐竹紋十郎を中心に3世豊竹呂太夫(ろだゆう)(10世豊竹若大夫)、2世野沢喜左衛門らが集まって三和(みつわ)会を結成して松竹を離れ自主公演を行い、非組合派は豊竹山城少掾、4世鶴沢清六、吉田文五郎(難波掾(なにわのじょう))らを中心に因(ちなみ)会派と称し、従来どおり四つ橋文楽座を本拠とし松竹資本のもとに興行を続けていった。この2派分裂によって演技陣が甚だしく手薄となり、両派とも興行成績は思わしくなく、松竹は挽回を期して1956年、文楽座を四つ橋から発生の地道頓堀に移転新築し、また『お蝶(ちょう)夫人』『ハムレット』『椿姫(つばきひめ)』など過去にはなかったジャンルの新作を試みたりした。この間、1955年2月には6世竹本住大夫(すみたゆう)、豊竹山城少掾、8世竹本綱大夫(つなたゆう)、4世鶴沢清六の4人が第一次重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定され、同年5月には文楽両派がそろって「人形浄瑠璃文楽」として重要無形文化財の総合指定を受け、伝承者の養成や公開に関する経費の国庫負担への道が開かれた。しかし、1962年に松竹は文楽(因会派)の経営放棄を決断した。その結果、国、大阪府、大阪市、放送文化基金(当初はNHK)の四者が補助金を出して設立した財団法人文楽協会が1963年1月に発足、同時に因会と三和会の両派合同が実現し、同年4月、道頓堀文楽座で第1回公演が行われた。しかし、文楽座の建物は従前どおり松竹の所有であったため、まもなく朝日座と改称され、文楽は専用の劇場を失ってしまった。
1966年、東京都千代田区隼(はやぶさ)町に国立劇場が開場し、その小劇場(客席数630)は文楽上演を主目的とした理想的設計であり、年4回の文楽の定期公演が定着して若い観客層の開拓にも成功するとともに、後継者の養成も始められた。また相次いで行われた欧米などの海外公演が予想以上の好評を博して、文楽は世界最高の人形劇という声価を高めつつある。それだけに本拠の大阪に専用の劇場建設を望む声が関係者の間に高まり、悲願は実って1984年3月、大阪市中央区日本橋(にっぽんばし)に国立劇場文楽劇場(通称国立文楽劇場、客席数753)が開場した。後継者養成の本拠もこちらに移され、往時の隆盛をふたたび取り戻すべく文楽は新時代に突入したわけである。
なお、1955年に認定された4人以降の人間国宝は、大夫では10世豊竹若大夫(わかたゆう)、4世竹本越路大夫、4世竹本津大夫、7世竹本住大夫、三味線では6世鶴沢寛治(かんじ)、野沢松之輔(まつのすけ)、2世野沢喜左衛門(きざえもん)、10世竹沢弥七(やしち)、5世鶴沢燕三(えんざ)、4世野沢錦糸(きんし)、8世竹沢団六(だんろく)(のち7世鶴沢寛治)である。
[山田庄一]
文楽の太夫と三味線
人形浄瑠璃はその発生の初めから太夫が主導権を握ってきた。それは、いかなる人形遣いの名人がいても、太夫が作品の意味を完全に語り生かしてくれなければ、どうにもならないからであった。したがって一座の座長はかならず太夫の第一人者がこれにあたり、絶対の権威をもっていた。その名前を劇場の櫓(やぐら)の下に記したので「櫓下(やぐらした)」とよび、また番付面で小屋の紋章の下に名を書くため「紋下(もんした)」ともいう(種々の事情により豊竹山城少掾を最後に櫓下はなくなっている)。
太夫は本来1人で一段を受け持っていたが、のちには一段を2、3人で分担するようになった。この場合、初めの部分を口(くち)、次を中(なか)あるいは次(つぎ)、最終部分を切(きり)とよび、切が最重要の部分でとくに切場(きりば)と称し、これに対して口、中、次を端場(はば)という。端場でも切場と場面が異なり独立しているものを立端場(たてはば)とよぶ。また端場のうちで短いものは太夫、三味線が観客に姿を見せず御簾(みす)の中で演奏することがあり、これを「御簾内(みすうち)」というが、普通は肩衣(かたぎぬ)を着けた「出語り」が原則になっている。太夫は1人で一段を語るから、登場人物の性格はもとより舞台の情景描写まで的確に表現することがたいせつで、音楽的な美しさに優先する。浄瑠璃の演奏を「歌う」といわず「語る」という意味もここにある。ただし道行(みちゆき)などの景事(けいごと)(舞踊的要素の多い場面)では、太夫、三味線弾きがそれぞれ複数で床(ゆか)に並んで合奏して音楽的効果を高めることもあり、また複数の太夫が各役を分担して語る「掛合い」も行われている。義太夫節の音階が他の邦楽に比べて低いのも「語る」目的のためであり、さらに、力強い発声の要求から、太夫は厚い腹帯を巻き下腹部に砂袋を当てて肚(はら)の底から声を出す。しかし戯曲の内容を語るのが第一義だといっても、演者によって解釈も異なれば、肉体的な天分も各人違うのは当然で、そこから太夫固有の語り口が生まれてくる。
竹本義太夫は大音であったが文章を語るうちに歌い、歌ううちに語る絶妙の域に達していたといわれ、どちらかといえば渋くじみであった。これに対し豊竹若太夫は天性の美声で、華麗な節回しに豊かな表現をする華やかではでな芸風で、まったく対照的であった。この西風と東風が義太夫節の両面を示すものであったが、のちには個人の芸風が尊重されるようになった。これが「風(ふう)」であり、原則的には初演の太夫の名をかぶせてよぶが、とくに後世の太夫が優れたくふうを残した場合にはその風が伝えられているものもあり、またある一部分だけを違った風で語ることもある。現在、太夫の風をもっとも顕著に示している作品は『妹背山』の三段目「山の段」で、背山のほうを渋く荘重な西の染太夫風、妹山のほうを明るく華やかな東の春太夫風とまったく対照的な語り口で演じるのが演出的にも優れた効果をあげている。義太夫節には他の邦楽のように家元制度が存在しないにもかかわらず、芸脈が乱れることなく伝承されてきたのは、一にかかって風の尊重によるところが大きい。太夫が床にあがった際、演奏の前後に床本を恭しく頂く習慣も、先人の風を尊ぶ心の一つの表れとみていい。とはいっても義太夫節の曲節が時代とともに変化したことも事実で、近年では豊竹山城少掾の出現によって語り口が合理化されたといえよう。このように、先人の風をあくまでも守りつつ、演者が個性を生かして新しい芸風を開拓してゆくところに、義太夫節の時代とともに歩む正しい姿勢があるわけである。
義太夫節の三味線には太棹(ふとざお)が用いられ、撥(ばち)も大きくて荘重な響きを出す。これは、義太夫の語りの内容がほとんど悲劇ばかりであることにも起因するが、いずれにしても単なる伴奏とは意味が異なり、あくまでも太夫の語りを助けて戯曲の内容をより的確に表現することに重点が置かれる。したがって同じ音階の一音にも場合によって大きな差異が生ずるわけで、この点がほかの伴奏と違い、とくに「浄瑠璃を弾く」とか「模様を弾く」というような言い方がされる。太夫と同様、三味線にも「風(ふう)」があり、大別すれば竹本座系の鶴沢と豊竹座系の野沢が中心であるが、そもそも初世義太夫の三味線であった初世竹沢権右衛門が豊竹座に移って豊竹上野少掾(こうずけのしょうじょう)を弾いたように、太夫の風ほど厳格でなかった。三味線の各派を概略説明すれば、権右衛門のあと竹本座の筆頭三味線になったのが鶴沢の祖初世友次郎で、同じく豊竹座で権右衛門の跡を継いだのが野沢の祖初世喜八郎であり、文化(ぶんか)年間(1804~1818)に3世竹沢弥七(やしち)が豊沢広助と改名して豊沢系が生まれた。現在の三味線の曲風の違いは明治期の文楽系と彦六系によるものが多く、同一の曲でも手が異なっている。なお曲の伝承については、安永(あんえい)年間(1772~1781)に3世鶴沢友次郎(俗に松屋清七)が記譜法を発明してから大きく進歩した。これは弦の勘どころ(ツボ)をいろは四十八文字で示したもので、朱墨で記入したので「朱(しゅ)」とよんでいる。
[山田庄一]
人形と人形遣い
人形の構造
人形は首(かしら)、胴、手、足、衣装からなっている。首の大きさは約15~20センチメートルで、男女、老若、性格などに応じて約70種類もあり、すべて木彫りに塗料で彩色を施し、鬘(かつら)をかぶせて使う。首の下に咽木(のどき)、胴串(どうぐし)があり、糸で操作すると目、眉、口が動く仕掛けになっている。ただし女の首は動きが少ない。仕掛けのばねには鯨のひげを用いる。胴は肩板と腰輪とそれをつなぐ前後2枚の布からなり、肩板の中央の穴に首の胴串を差し込んで遣う。手足は胴の両肩から紐(ひも)でぶら下げるが、原則として女役には足がなく、衣装の裾をさばくことで足があるように見せている。また手、足には役柄によって十数種類あり、左の手には差金(さしがね)がついている。衣装は役柄によって共通したものを用いる場合が多く、人形遣いが胴串を握るための切れ目が背中にあるのが特徴である。衣装を着けた人形は立役(たちやく)の荒い役柄の物がもっとも大きく、身長は約140~150センチメートル、重量20キログラムに及ぶものがある。
[山田庄一]
人形の遣い方
一体の人形を3人で遣うが、中心になる人形遣いが左手で胴串を握って人形全体を支え、右手で人形の右手を遣う。これを主遣(おもづか)いとよぶ。人形の左手を左遣いが、人形の両足を足遣いがそれぞれ遣うが、足遣いが楽に作業できるように、主遣いは高さ17~35センチメートルの特殊な下駄(げた)を履く。これを舞台下駄とよんでいるが、高さは遣う人形の大きさによって変える。馬に乗る人形のときにはさらに高いものも用いる。舞台下駄は底に草鞋(わらじ)をつけて滑り止めにする。人形遣いは3人とも黒衣(くろご)とよぶ黒い着物に黒い頭巾(ずきん)をかぶって観客に顔を見せないのが原則であるが、景事や切場では主遣いだけが紋付に袴(はかま)、あるいは肩衣を着けて遣う。これを「出遣い」とよび、一人遣いの当時すでに辰松八郎兵衛が出遣いを見せた記録がある。なお登場人物のうちであまり重要でない役(たとえば腰元や捕手(とりて)など)は一人遣いの人形を用い、これを「つめ」とよんでいる。人形遣いの修行は足遣いから始めて、左、主と進むのが決まりで、俗に「足十年、左十年」といわれ、主遣いまでには長期間の訓練が要求される。
[山田庄一]
舞台
文楽の舞台はほかの演劇と違って、三人遣いのために特殊な構造になっている。いわゆる平舞台の部分は船底(ふなぞこ)と称して約2メートルの幅で床面より37センチメートルほど低くなっており、この前後に手摺(てすり)と称する板が立てられる。その高さは前面(二の手)が約48センチメートル、後方(一の手)が約85センチメートルで、これより奥、すなわち二重にあたる部分を本手(ほんて)とよぶ。手摺は足遣いを隠すためのもので、つまり人形の足の高さはつねに約85センチメートルに支えられ、客席から見ると人形が手摺の上端に立っているように見えるわけである。さらに二の手の前に三の手とよぶ高さ24センチメートルほどの黒い手摺が置かれる。船底の左右(上手、下手)にはそれぞれ人形の出入りする揚幕があり、下手の揚幕の上が鳴物(なりもの)部屋になっている。舞台の間口はせいぜい12~15メートル程度が適当である。舞台の上手には客席に斜めに突き出した太夫の語る「床(ゆか)」があり、回り舞台のように回転できるようになっていて、太夫、三味線の交代を行う。
[山田庄一]
文楽以外の人形浄瑠璃
文楽のように三人遣いで義太夫節にあわせて演じる人形劇は全国各地に残っており、東は栃木県の奈佐原(なさはら)(鹿沼(かぬま)市)から西は九州まで広く分布して、なかには江戸時代の名作の首(かしら)を伝承している所も少なくない。しかしなんといっても淡路(兵庫県)と阿波(あわ)(徳島県)のものが目だっている。人形浄瑠璃の歴史でも触れたように、人形の一座は西宮戎(にしのみやえびす)神社と密接な関係をもっていたから、海を隔ててすぐ向かい側の淡路島からさらに鳴門(なると)を越えて阿波へ伝えられ、村々に多くの人形座が生まれた。そして、本流の大坂とは別に独自の発達を遂げ、とくに幕末から明治にかけて、鳴州(めいしゅう)、人形常(にんぎょうつね)、人形富(とみ)、大江順、天狗久(てんぐひさ)らの人形彫りの名手が阿波に出現したのと、観客数が増えて小屋の規模が大きくなったことから人形の大形化が現れ、首の種類や表情も文楽系とは違ったものとなった。阿波の人形の最盛期は明治30年(1897)ごろまでであるが、大正から昭和にかけてしだいに凋落(ちょうらく)の道をたどり、とくに戦後は急速に衰退して絶滅の危機に瀕(ひん)していたが、伝統文化見直しで保存への気運が生まれ、地元の高校生がクラブ活動の一つに取り上げるなど、若い世代にも伝統の火を守り続けるための動きが現れている。
[山田庄一]
無形文化遺産の登録
2008年(平成20)「人形浄瑠璃文楽」としてユネスコ(国連教育科学文化機関)の無形文化遺産に登録された。
[編集部]
『『日本古典文学大系49・50 近松浄瑠璃集』(1958、1959・岩波書店)』▽『『日本古典文学大系51・52 浄瑠璃集』(1959、1960・岩波書店)』▽『角田一郎著『人形劇の成立に関する研究』(1963・旭屋書店)』▽『斎藤清二郎著『かしら』(1964・岩崎美術社)』▽『『日本古典文学大系99 文楽浄瑠璃集』(1965・岩波書店)』▽『宮尾しげを著『図説文楽人形』(1967・中林出版)』▽『吉永孝雄著『文楽』(1967・淡交新社)』▽『『伝統と現代5 人形芝居』(1969・学芸書林)』▽『『日本古典文学全集45 浄瑠璃集』(1971・小学館)』▽『『日本古典文学全集43・44 近松門左衛門集』(1972、1973・小学館)』▽『高木浩志著『文楽のすべて』(1982・淡交社)』▽『権藤芳一著『文楽の世界』(1985・講談社)』
百科事典マイペディア 「人形浄瑠璃」の意味・わかりやすい解説
人形浄瑠璃【にんぎょうじょうるり】
→関連項目演劇|歌舞伎|戯曲|義太夫節|竹田出雲|人形劇|無形文化遺産保護条約|櫓|櫓下
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「人形浄瑠璃」の意味・わかりやすい解説
人形浄瑠璃
にんぎょうじょうるり
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「人形浄瑠璃」の解説
人形浄瑠璃
にんぎょうじょうるり
江戸時代に成立した人形劇。浄瑠璃の語り手,三味線弾き,人形遣いの3者が一体となって上演する形式で,操り浄瑠璃,操り芝居ともよばれた。室町末期に,夷舁き(えびすかき)とよばれた人形回しと,当時流行の浄瑠璃という語り物と,最新の楽器であった三味線の提携が成立して上方で発生したというが,その経緯は明らかではない。成立期には人形で猿楽能の演目を上演する能操りや,説経節という語り物による説経操りなどの類似する芸能も存在した。人形劇の内容を語る浄瑠璃は,竹本義太夫による当流(新)浄瑠璃の成立以前の古浄瑠璃と,それ以降の義太夫節に大別される。長編の語り物で,「仮名手本忠臣蔵」など多くの作品が歌舞伎化され,人形浄瑠璃自体も歌舞伎の表現手法をとりいれて発達した。人形操法は,近松門左衛門作品初演の頃には1人遣いで,18世紀前期から3人遣いが発達し現代に及んでいる。主要な劇団・劇場に,竹本座・豊竹座・文楽座などがあった。現在では文楽(ぶんらく)とよばれ,東京の国立劇場小劇場,大阪市の国立文楽劇場などで上演されている。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「人形浄瑠璃」の解説
人形浄瑠璃
にんぎょうじょうるり
傀儡子 (くぐつ) と浄瑠璃が結合して成立。元禄時代(1688〜1704),竹本義太夫・近松門左衛門らが出て舞台芸術として完成,全盛期をむかえたが,明和(1764〜72)ころより衰微し歌舞伎に圧倒された。明治時代以後,文楽座を中心にして興行したが,現在は重要無形文化財として保存されている。人形が3人遣 (つか) いになったのは享保(1716〜36)末ころからのこと。また各地に義太夫節以外の曲によって残存している。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の人形浄瑠璃の言及
【歌舞伎】より
…歌舞伎は,舞楽,能,狂言,人形浄瑠璃などとともに日本の代表的な古典演劇であり,人形浄瑠璃と同じく江戸時代に庶民の芸能として誕生し,育てられて,現代もなお興行素材としての価値を持っている。明治以後,江戸時代に作られた作品は古典となり,演技・演出が〈型(かた)〉として固定したものも多いが,一方に新しい様式を生み出し,その様式にもとづいた作品群を作りつづけてきた。…
【興行】より
…女歌舞伎は,遊女の抱え主が主催者となって,掛小屋で木戸銭(入場料)をとって歌舞伎踊をみせた。 江戸時代に入ると歌舞伎や人形浄瑠璃の興行は,江戸でも上方でも共通に幕府から興行権を与えられたもののみが行うことができるというきびしい仕組であった。江戸を例にすると宮地芝居を別として,歌舞伎では1714年(正徳4)9月以降幕末まで中村座の中村勘三郎,市村座の市村羽左衛門,森田座の森田勘弥の3人の座元に限って,歌舞伎を興行する権利が官許され,興行権の象徴である〈櫓(やぐら)〉をあげることができた。…
※「人形浄瑠璃」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...