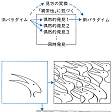精選版 日本国語大辞典 「発見」の意味・読み・例文・類語
はっ‐けん【発見】
- 〘 名詞 〙
- ① それまで人に知られていなかったもの、現象などをあらたに見つけること。初めて見出すこと。
- ② ⇒はつげん(発現)
発見の語誌
( 1 )①の用法は明治以降に見えるもので、森鴎外は「発見」を「発見とか発明とかいふ詞を今のやうに用ゐるのは、翻訳から出てゐるのだが〈略〉今までありながら目に見えなかったものを見えるやうにする」〔大発見〕としている。
( 2 )福沢諭吉は挙例「西洋事情」のように「発見」を用いる一方で、「古論武子が亜米利加を発明せし以前」〔世界国尽‐四〕と、「発明」を「発見」と同意に使っており、明治初期においては、「発見」がいまだ一般化していなかったと推定される。
日本大百科全書(ニッポニカ) 「発見」の意味・わかりやすい解説
発見
はっけん
発見には、通常用いられている「初めてみつけだす」という意味を特化したものとして、「地理上の発見」や「技術的発明」と並び科学・技術上重要な「科学上の発見」がある。ここでは、とくに1960年代以降、科学論、科学史上で活発な議論が行われてきた、いわゆる「科学的発見」scientific discoveryを扱う。
[宮下晋吉]
クーン、ハンソンの発見論
アメリカの科学史家T・S・クーンは、1962年の『科学革命の構造』でいわゆるパラダイム論を展開した。それは、パラダイム変換としての科学革命の「核心」をX線の発見や酸素の発見のような科学史上の大発見とみなす、一種の「科学的発見論」であった。ところで、クーンの「パラダイム」Paradigmとは、「一般に認められた科学業績で、一時期の間、専門家に対して問い方や答えのモデルを与えるもの」、つまり、ある種の知的枠組み(コイレ流の)であるが、一方、同じパラダイムを共有する科学者集団、「科学共同体」でもあり、その点で彼の発見論は社会学的発見論でもあった。
クーンによれば、たとえばレントゲンによるX線の発見のような科学的発見は、「特定の時間と空間で個人に起こる」もの、すなわち「単一なできごと」ではない。つまりX線発見史上周知のように、写真乾板に生じた原因不明のかぶりなどから、後年、実は自分もX線を発見していたと称する科学者が続出したが、それゆえに彼によれば「レントゲンの設備がX線を生んだのなら、多数の他の実験家たちも気づかずにX線をつくっていたに違いない」、したがって発見は、そのような多数の偶然的な発見の、いわば同時多発的できごとにほかならない(「同時発見」説、「偶然的発見」説)。では、多数の発見のなかでどれが真の発見であり、当時の科学者集団(旧パラダイムに属する)のなかでだれが発見者の栄誉に輝くかについて、彼は、レントゲンの場合「スクリーンが予想に反して光りだした異常性anomalyに気づいたこと」が「革新性に導く本質的な役割を果たした」とみなし、一般的に科学的発見の構図を、社会学的にはアノミー論的に、旧パラダイムから新パラダイムへの「パラダイム転換」としてのように描き出した。
また、アメリカの科学哲学者ハンソンNorwood Russel Hanson(1924―1967)は『科学的発見のパターン』(1958)で、「観察」とその結果である「事実」は科学上の一定の知識や理論の存在を前提とすると考え(「理論負荷性」)、「科学的発見」をそのような知識や理論の枠組みの変換――一種の「理論変換」としてとらえる発見論を展開したが、その場合の「変換」は本質上、関連させるものによって、異なるものに見えるというような(ゲシュタルト)心理学的なものであった()。
[宮下晋吉]
科学的認識と発見
これらのいわゆる「新科学哲学派」の発見論に対し、「同時発見」説、「偶然的発見」説は俗説であるばかりか、全体として科学的発見論における不可知論であり、非合理主義的・反科学的主張であるという批判がある。前述の発見論のその後の極端な展開、たとえば「発見の時間と場所の単一性」や「理由づけの理論的な本性」を「神話」として全面否定するような議論などは、その批判が当を得ていることを裏づけているように思われる。ジュール、マイヤー、およびヘルムホルツらによるエネルギー保存則の発見の例のように、科学史上、同時発見的状況は一般的に存在するが、それは、当時の科学(理論)の発展段階と技術水準(とくに実験)との関連で理解されるべきである。また発見には、とくにその出発点では、経験としての発見の段階で偶然的要素が含まれうるが、真の科学的発見とは、科学的認識のプロセスにおいて偶然を必然に転化させる過程と解する必要がある。さもなくば、たとえばX線発見の場合、あとになって実は自分はレントゲン以前にX線に起因する現象(写真乾板に生じた原因不明のかぶりなど)をみいだしていたとして、発見の「先取権」を主張した多数の「えせ発見」や、あるいは当時の世紀末的世情の下で流行していた「心霊科学」における「黒色光線」などオカルト的・空想的な未知の新放射線の予想と、真のX線発見を区別する客観的な基準はなにひとつ存在しなくなるからである。
さらにまた、科学的認識の理論として「理論的発見」と「実験・観察的発見」を区別したうえで、後者に関し「探検」的発見の存在に注意し、それと「偶発」的発見の間の区別の相対性を指摘する議論もあるが、科学的発見における偶然と必然の間の関係は、本質上「発見の諸タイプ」の分類の問題ではなく、認識のプロセス、すなわち「経験としての発見」から法則性の確立へ、という科学的発見の歴史過程にかかわる問題であるのは、すでに述べたとおりである。なお「発見と逸機」の差に注目する最近の議論(アレクサンダー・コーンAlexander Kohn)もあるが、これも、多数の発見例の比較的リアルな取扱いにもかかわらず、俗説としての「偶然的発見説」の一形態にすぎず、科学的発見は本質上「科学の運」、不運の問題ではないことも前述のとおりである。
[宮下晋吉]
『T・S・クーン著、中山茂訳『科学革命の構造』(1971・みすず書房)』▽『岩崎允胤・宮原将平著『科学的認識の理論』(1976・大月書店)』▽『宮下晋吉著「X線の発見と実験・技術・社会(1)――T. Kuhnらの科学的発見論の検討」(『科学史研究』第Ⅱ期第21巻・1982)』▽『N・R・ハンソン著、村上陽一郎訳『科学的発見のパターン』(1986・講談社)』▽『アレクサンダー・コーン著、田中靖夫訳『科学の運――発見と逸機の科学史』(1990・工作舎)』▽『トーマス・S・クーン著、安孫子誠也・佐野正博訳『科学革命における本質的緊張――トーマス・クーン論文集』(1998・みすず書房)』▽『村上陽一郎著『近代科学を超えて』(講談社学術文庫)』
改訂新版 世界大百科事典 「発見」の意味・わかりやすい解説
発見 (はっけん)
discovery
一般には,これまで知られていなかったものが,初めて知られるようになることで,英語のdiscover,フランス語のdécouvre,ドイツ語のentdeckenなどがすべてそうであるように,〈覆いを取り除く〉という行為がかかわる,という了解がある。これは,自然にある事実や法則は本来〈客観的〉に実在し,それがこれまで知られていなかったのは,単にそれを人の目から覆い隠していた覆いをだれも取り除かなかったからだ,という考え方に基づいているといえる。その点で,これまでに存在しなかった(知られていなかった,のではなく)ものを新しく生み出す〈発明〉とは区別されることになる。
常識的には,前述の意味が発見として通用しているが,多少とも詳しく吟味してみると,事態はそう簡単ではない。第1に,認識論的・心理学的な問題がある。極端な場合,茎を折った水藻の折れ口から,水中で立ちのぼる気泡を見たネアンデルタール人は,〈酸素を発見した〉といえるであろうか。何ごとか(事実にせよ,理論にせよ)を〈見いだす〉ということは,決して,単に〈見る〉ことではない。ハンソンN.R.Hanson(1924-67)は《科学理論はいかにして生まれるかPatterns of Discovery》(1958)において,事実の〈理論負荷性theory-ladeness〉を提案し,この点を強力に主張した。ある理論を前提にしてものを見るとき,初めて,ある事実が〈見える〉のであり,したがって,理論的前提が変化したとき(ハンソンはそれを心理学のゲシュタルト変換に模した),同じものを〈見て〉いても,〈見え方〉が変わって新しい事実が〈発見〉される,という側面が強調されたのである。
こうした論点は,発見についての素朴な考え方の欠陥を補うものではあったが,ブラニガンA.Brannigan(1949- )が《科学的発見の現象学》(1981)で指摘するとおり,こうした認識論的・心理学的アプローチだけでは,発見と学習との区別がつかない。一人の個人が,新しいことを学ぶ際に起こっていることと,いわゆる発見とはいかにして区別されるか。さらに,例えばコロンブスのアメリカ大陸の発見といわれるものは,ヨーロッパ人の視点から見ても,それよりもはるか以前に北方系のバイキングが,現在のカナダやアメリカの東海岸に基地を置いていたことがわかっている以上,〈それまでに知られなかったことが初めて知られるようになること〉という定義には当てはまらない。こうした点は,素朴な発見論はもとより,認識論的・心理学的議論だけでも,発見を論ずるためには不十分であることを物語っている。ある事がらが発見であるか否かは,それが発見として社会的に認知されるかどうか,という問題と不可分であり,こうした社会的側面の考慮が必要になる。
科学的発見には,〈多重発見multiple discovery〉とか〈同時発見simultaneous discovery〉とか呼ばれる現象がある。熱力学の第1法則におけるジュール,マイヤー,ヘルムホルツら,進化の動因としての自然淘汰説におけるC.ダーウィンとウォーレスの場合に典型的なように,一つの事実や仮説や理論が,複数の人々の手で,独立に(あるいはほとんど独立に)同時に(あるいはほとんど同時に)発見される現象をさす。多重発見は,しばしば時代の成熟readinessとして考えられてきたが,むしろその〈成熟〉の内容もまた,結局は,後代の人々が歴史に対してどのような〈認知〉を与えるか,という点に依拠しているのであって,発見が社会的認知に支えられた概念であることを暗示している。発見のもつこの社会的側面には,一方で,発見に対して,学問的優先権を与えるという社会的制度が絡んでいることは確かであり,学会における〈登録〉や学会誌への発表など,発見を発見として社会的に認知せしめるための制度が,逆に発見を発見たらしめているともいえる。
→発見法 →発明
執筆者:村上 陽一郎
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
普及版 字通 「発見」の読み・字形・画数・意味
【発見】はつけん
字通「発」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「発見」の意味・わかりやすい解説
発見
はっけん
「発明と発見」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の発見の言及
【発見法】より
…ヒューリスティックスheuristicsの訳語で,〈発見〉に資する思考法ないし技法をいう。発見には,〈事実の発見〉と〈概念の発見〉と〈法則の発見〉と〈理論の発見〉の四つの層が区別される。…
【発明】より
…現在の用法では一般に,まだ知られていない物事,原理・法則などを初めて明らかにすること,また,特に機械・器具類あるいはそれらに関する技術を初めて案出することをいう。漢語の〈発明〉には,古代中国の五方神鳥のうち,東方に位置する鳥の名で,転じて鳳凰の朝鳴くことの意もあるが,《史記》《漢書》などでは開き明らかにする,すなわち〈発見〉の意で用いられた。そこから日本では考え,悟る心の働きがめざましいこと,すなわち賢いことをも指すようになった。…
※「発見」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...