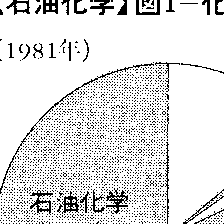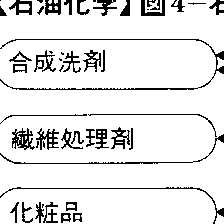精選版 日本国語大辞典 「石油化学」の意味・読み・例文・類語
せきゆ‐かがく‥クヮガク【石油化学】
- 〘 名詞 〙 石油および天然ガスを原料とした、化学製品の合成、分離、製造に関する化学。
- [初出の実例]「石油化学コンビナートの公害問題は」(出典:失われた男(1966)〈田村泰次郎〉)
改訂新版 世界大百科事典 「石油化学」の意味・わかりやすい解説
石油化学 (せきゆかがく)
petrochemistry
石油や石油随伴天然ガスを原料として化学製品を生産する化学技術の体系をいう。
第2次大戦後,中東地域で世界最大規模の油田が開発され,その石油が世界各国に豊富かつ安価に供給されるようになり,石炭から石油へというエネルギーの流体化革命が進むなかで,化学工業の原料もまた石炭から石油へと大きな転換を遂げた。国内資源に乏しい日本はいち早く石油化学技術の導入と石油化学産業の育成を目指し,おりから合成繊維,合成樹脂などの高分子化学工業の急成長もあり,これに対する原料供給態勢の確立をはかった。その結果,1950年代末ころから石油精製企業,総合化学企業がこぞって石油化学産業に進出し,国の産業政策上の援助も加わって,四半世紀にも満たない短期間に基幹産業である鉄鋼業をもしのぐほどの急成長を遂げた。すなわち1980年において,日本の化学工業における石油化学工業のシェアは出荷額基準で53%と過半を占め(図1),またその規模を81年末のエチレン生産能力でみれば624万t/年であり,アメリカの1814万t/年に次いで第2位,自由世界全体の約15%を占めている。しかしながら,1973年の石油危機を契機として石油価格が急騰しただけでなく,石油供給の短期的な不安定性あるいは長期的な資源制約の懸念も加わり,日本の石油化学の原料基盤に疑問が投げかけられるに至った。他方,石油化学製品市場においては国内外の経済の停滞から需要が伸び悩み,そのうえ海外からの割安な石油化学製品の輸入が急増している。
石油化学製品のおもな用途は合成樹脂,合成繊維,合成ゴムなどの高分子化学分野であって,合計80%をこえている(図2)。これらの高分子化学製品がわれわれの日常生活の必需品である衣料,住宅資材,食品包装などはもちろん,産業用資材としても,数えきれないほどの多種多様な最終製品となり,われわれの生活を便利で豊かなものとし,また産業を支えている。
→石油化学工業
石油化学の体系
石油化学工業の原料から中間製品を経て製品に至る流れを図3に示した。同図の中で原料消費量,製品生産量などの数値は1981年の日本の実績である。石油化学工業の原料は時代と国情とによって変化するが,現在の日本ではいわゆるナフサが主原料である。この事情はヨーロッパに似ており,工業燃料として重油が大量に用いられる反面,自動車ガソリンの需要がそう大きくはないために,原油の中の軽質ナフサ留分が相対的に過剰気味になるためである。しかし,最近は石油化学工業の発展もあり,国内の製油所から供給されるナフサだけでは量的にも不足し,また海外から割安なナフサが輸入できることもあって,81年にはナフサ供給量全体の約1/3は輸入によってまかなわれている。なおアメリカやカナダでは天然ガスや製油所ガスがおもな石油化学原料となっている。
さて,ナフサを化学原料として利用する第一歩はナフサ分解と接触改質である。ナフサ分解は石油会社からナフサの供給を受けた石油化学会社(いわゆる石油化学コンビナートのセンター企業)によって行われる。このプロセスはナフサを高温度で分解し,主としてエチレン,プロピレンその他のオレフィン類(アルケン)を生産する。生産されたオレフィン類は傘下の石油化学企業に配給され,化学的加工が行われる。
他方,ナフサの接触改質は石油会社自身の手で行われる例が多い。これは高オクタン価ガソリンの生産プロセスと本質的に同一のプロセスであり,比較的重質のナフサを原料としてベンゼン,トルエン,キシレンなどの芳香族炭化水素を生産する。この方法はガソリンと石油化学製品の市況をにらみ合わせながら,生産を調整できる強みがある。なお石油芳香族を先に述べたナフサ分解の副生分解油から回収することも行われている。
以上のオレフィン類や芳香族類は,重合,酸化,水和,塩素化,水素化,アルキル化,脱水素その他,いろいろな化学反応プロセスを経て図4に示したような石油化学製品となり,いわゆる中間財として多くの関連産業へ供給され,最終的には各種の工業製品のかたちでわれわれの日常生活に使用されている。金額基準でみると,石油化学製品の第1位は繊維・身の回り品,第2位は住宅・建築・土木,第3位は自動車,第4位は電気機械である。
身の回りの石油化学製品
合成繊維はすなわち石油化学製品であるといって過言ではないが,繊維製品のうち合成繊維が占める割合は1978年には約50%に達している。石油化学工業が日本で始まった1960年ころにはナイロン,ポリエステルなどが靴下やワイシャツなどとして珍重された。やがてアクリル系合成繊維が加わり,加工糸やジャージー織物がつくられ,合成繊維はセーター,洋服などの外衣にも用いられるようになった。
合成ゴムの本格的国産化は60年ころから始まったが,合成ゴムは耐摩耗性,均質性などの物性面で優れているだけでなく,天然ゴムにくらべて供給条件が安定していることもあって自動車用タイヤへの使用量が急増し,現在は合成ゴムが大半を占めている。
自動車へのプラスチックの使用量は,エネルギー節約のための自動車の軽量化の動向によって加速され,日本の乗用車の場合,66年の1台当り18.7kgから,77年には45kgへと急増している。その用途の内訳は内装品やランプなどにとどまらず,バンパーその他の大型部品から構造部品にも及んでいる。
情報化社会のTVカメラ,マイク,スピーカー,ビデオテープ,電話機,コンピューター,通信用ケーブル,その他の器材にプラスチックや合成繊維が不可欠の材料部品であることはいうまでもない。未来技術の一つとして注目される光通信用ファイバーには石英だけでなくメタクリル樹脂がその優れた加工性や低価格を理由に,比較的短距離の用途に使われようとしている。
レジャーやスポーツの分野での石油化学製品の進出も目覚ましい。冬のスキー,夏のサーフボードやボート,夏冬を問わないテニスやゴルフの用具にグラスファイバーや炭素繊維(これも石油化学製品)で強化されたプラスチックがふんだんに使われる。スポーツ用衣料もまた合成繊維製品が少なくないし,運動靴にもまた合成ゴムやプラスチックが使われている。
石油化学プロセスの概要
石油化学工業の原料から製品に至るまでの化学反応についての概要は,〈ナフサ分解〉〈接触改質〉〈エチレン〉〈プロピレン〉〈ブチレン〉〈ブタジエン〉〈ベンゼン〉〈トルエン〉〈キシレン〉等の項目を参照されたい。これらの各項目にはプロセスの内容や各オレフィン,芳香族からの誘導品の合成反応について述べられている。
執筆者:冨永 博夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「石油化学」の意味・わかりやすい解説
石油化学【せきゆかがく】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「石油化学」の意味・わかりやすい解説
石油化学
せきゆかがく
petrochemistry
石油または天然ガスを出発原料とし、燃料油など本来の石油製品を除く化学製品の合成を目的とする工業化学をいう。とくに現代有機工業化学の中心をなす分野で、第二次世界大戦後、旧来の石炭化学にかわって発展した。石油化学のもっとも主要な基礎原料としては、ナフサなど石油留分の熱分解、接触改質などで得られるエチレン・プロピレン・ブチレン・ブタジエンなどの低級オレフィン類、ベンゼン・トルエン・キシレン(BTX)などの芳香族類で、このほか天然ガスや石油留分の水蒸気変成による合成ガス(水素、一酸化炭素)、接触分解ガソリン製造時に副生するプロピレン・ブチレンや、エタンの熱分解で得られるエチレンなども石油化学工業の原料として使用される。
石油化学反応を応用した化学工業が現代基幹産業の一つである石油化学工業で、その製品が石油化学製品(ペトロケミカルスpetrochemicals)である。その目標とする最終製品は、プラスチック、合成繊維、合成ゴムなどの高分子化学製品をはじめ、合成洗剤(界面活性剤)、有機溶剤、染料、農薬、医薬など多岐にわたるが、石油化学の中心は、むしろこれら石油化学製品の製造に必要な単量体、中間体を能率的、経済的に合成するプロセスの研究開発にあり、触媒化学、有機合成化学、高分子化学との関連が深い。
なお石油化学は工業的背景が強いため、石油化学工業と同義に扱われることも多い。
[原 伸宜]
化学辞典 第2版 「石油化学」の解説
石油化学
セキユカガク
petrochemistry, petroleum chemistry
本来は,石油工業の基礎となる石油化学(petroleum chemistry)と,石油化学工業の基礎となる石油化学(petrochemistry)とがあり,日本語では共通であるが,最近では後者の意義に解釈されることが多い.石油および天然ガスを原料とする化学工業が石油化学工業であり,これに関連する工業化学が石油化学である.また,場合により石油化学工業と同義にも扱われ,たとえば“石油化学原料”などの用語には,石油化学工業の意味を含んでいる.
出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「石油化学」の意味・わかりやすい解説
石油化学
せきゆかがく
petroleum chemistry
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
関連語をあわせて調べる
1 花の咲くのを知らせる風。初春から初夏にかけて吹く風をいう。2 ⇒二十四番花信風...