デジタル大辞泉 「筏」の意味・読み・例文・類語
いかだ【×筏/×桴】
2
3 《串にさした形が1に似ているところから》
[補説]書名別項。→筏
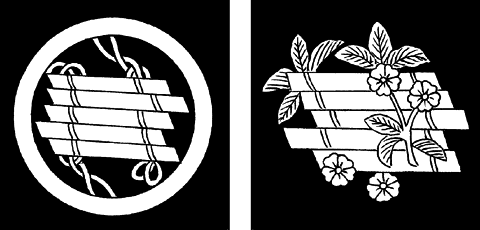
( 1 )挙例の「書紀‐白雉四年七月」の記述、および「十巻本和名抄‐三」に「桴・筏 編二竹木一大曰レ筏、小曰レ桴〈以賀多〉」とあるところから、主に竹あるいは木で作り、その大小によってそれぞれ「筏」「桴」字を当てたことがうかがわれる。
( 2 )「常陸風土記‐行方」の「厳しく海渚に餝ひ、舟を連ね、![]() を編み」の例は、多くの舟を横につなぎ並べて船橋としたものであろう。
を編み」の例は、多くの舟を横につなぎ並べて船橋としたものであろう。
木材,竹,アシ,皮袋を並べてつなぎ合わせ,それらの浮力を利用するいかだは,沿岸,礁湖,河川,湖などでの漁労活動や運搬の用具として世界の各地に分布する。木製のいかだは,韓国の南海島や済州島ではパルソンとよばれ,漁労や海藻採取に使用されている。7本の丸太の4ヵ所に穴をあけ,そこに細木を通して固定した長さ6m,幅1.5mのいかだで,手すりや座席までついている。南アメリカの大西洋岸でも木製いかだが広く用いられているが,とくにブラジル沿岸ではバルサ材が使われ,速力を増すためにいかだの先端をそり上げて三角形にしたジャンガダとよばれるいかだがつくられている。これは5本あるいは7本の奇数の丸太をつなぎ,中央の丸太を太くしていかだの安定をよくすると同時に,リーボードを使用して帆走可能な構造に発達させている。竹製のいかだはオセアニアや,ミャンマー,ベトナムなどの東南アジアから中国にかけてみられる。ヤップ島やパラオ島では8mにもおよぶ6~7本の竹を並べ,数本の竹を直交させて固定しただけのいかだが,浅瀬の多い礁湖内での漁労や運搬に多用されている。台湾のテッパイとよばれるいかだは,10本以上の麻竹(まちく)を並べて籐で固縛し,その両端を焼き曲げ,櫂や帆で推進する。この長さ5m,幅2mのいかだは船首の幅が船尾よりも狭く,両舷側は中央部より高くなっている。そのため,中国のジャンクの起源はこのいかだに由来すると主張する学者もいる。イネ科の大型多年草であるアシ(葦)を束ねて浮力をつけたいわゆる葦舟はナイル川やティグリス,ユーフラテス川の流域では古代から使用されていた。今日でもアフリカのビクトリア湖やチャド湖,南アメリカのチチカカ湖ではさまざまな型の葦舟がつくられ,湖上の交通手段として重要な役割をはたしている。また獣皮を縫い合わせ,中に空気を入れて浮袋としたものをつなぎ合わせたいかだは,黄河流域では皮筏子(ヒハイシ)とよばれ,ティグリス川上流ではケレークとよばれて使われている。
執筆者:須藤 健一
日本では木材や竹を,山の奥地から河川を利用して下流の木材集散地まで搬出するため結束していかだとする。山地で切り倒し,枝を払った丸太を,谷川の頭に下ろし,柴や草苔などで堰を作って水を溜め,そこに浮かべる。伐木をこのような堰につぎつぎに送流し,適当な水量のところから1本ずつ流す。これまでの過程は,カワガリ(川狩)人夫である運材稼業者の手で行われ,その運材法をセキ(堰)ナガシ,クダ(管)ナガシという。水量豊かな本流の適地をアバ(網場)といい,網を張って集材する。ここからいかだ師の手にゆだねられる。伐木をいかだに組み,これに乗って流送するいかだ流しには,特殊な技術が必要で,長年の訓練を経て一人前になる。いかだの組み方は,伐木の大小,河況に応じ,構造を異にするが,一般的には,丸太材7~8本を並べ,藤蔓で結束する(のちには,マンリキなどとよぶ環のついた楔形鉄片を打ち込む方法も用いた)。いかだ1枚を1床とか1房といい,2~4枚ほどを1列縦隊に並べる。いかだの大きさにもよるが,およそ2~3人乗りで,それぞれ前からサキノリ(あるいはヘノリ,ハナノリともいう),ナカノリ,アトノリ(トモノリともいう)といい,サキノリは熟練者が当たった。川幅が広くなる中継地点を境に,上流を上いかだ,下流を下いかだともいい,下いかだは2~4列縦隊にもやう。河流の途中には,瀬や岩壁の難所があるところが多く,そこで命を落とすいかだ師も間々あり,そのいかだ師の名をつけた岩もある。労働歌としていかだ節が各地に伝承されている。いかだ師の服装は,普通,浅黄の股引に盲縞の木綿製はばき(脛巾),足袋にわらじがけで,上衣は筒袖のはんてん(半纒),頭は手ぬぐいで頰かぶりしたり,地域によっては風負けしないようにまんじゅう笠をかぶった。運材といかだ流しは危険をともなう作業なので,きびしい信仰に支えられていた。いかだ流しの日程はあらかじめ留守宅に連絡してあり,難所にかかるころには,留守宅では夜籠りして安全を祈願した。いかだ師も難所にまつられている水神や金毘羅の祠などに祈願しながら,掛声をかけ懸命に乗り切る。この掛声を阿賀野川ではノリトとよぶ。また,いかだ乗り初めには,それぞれの現場から酒樽を流し,これを拾いあげたいかだ師は,中の酒をいただいては,新たに酒を注ぎ足して流す慣行もあった。また,堰流しを始めるときに,節のない選ばれた木の片面を削り,水神,金毘羅権現,伊勢天照大神宮などの神名を書くところがある。中でも,とくに伊勢信仰が各地にみられることが注目される。原木運材としては,道路整備以前,河流を利用するいかだ流しが最良の方法であった。しかし,森林鉄道や貨物自動車などの陸運手段の発達とダム建設のため急速に衰退した。日本のいかだは,原木輸送を主とするものであったが,舟に代用された例が長崎県対馬北西岸にみられた。そこでは丸木組立式で,地元では材木舟とよばれ,最近まで海藻採りに使用されていた。また,江戸時代には,韓国済州島からいかだ舟で日本に漂着した者があり,それを解体して材木として処分したことが知られている。済州島には,対馬杉のいかだ舟を所有している者があり,対馬杉を最良のいかだ材と評価するというが,日韓両いかだ舟の接点を示唆するものとして注目されよう。
→船
執筆者:北見 俊夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
木や竹、草の茎など浮力のある物を紐(ひも)などで結び集めて浮力と安定性を増し、水上に浮かべて運搬などの目的に使用するもの。アシでつくったものはとくに葦舟(あしぶね)とよばれる。道路や鉄道が未発達な時代、あるいは地方によっては陸運より水運のほうが効果的であった時代、水運の初めのものとして筏がつくられた。目的に応じて周囲に手すりをつけたり、航行用に帆をつけたりなどの改良がなされ、多様な形態を示す。移動に際しては、水に浮かべて川を流し下る場合と、棹(さお)(竿)や櫂(かい)、櫓(ろ)、帆などによる場合とがある。用途は二つに大別され、奥地で切り出した木材を輸送するためにそれらを組んで下流の集散地まで河川を流して下っていく場合(筏流しとよばれる)と、簡単な船として使用する場合(筏船とよばれる)とがある。前者の場合、日本では和歌山、岐阜、長野地方でみられ、通常は、こぎ手とかじ取りの2、3人が筏を操る。国外ではヨーロッパや東南アジアにこの形態がみられる。後者の筏船として使用する場合は、単に河川だけでなく海洋上でも利用され、漁労、水上運搬、水上生活の場などが目的となる。
世界のさまざまな筏の例をあげてみると、まずヨーロッパでは、木材運搬として内陸水面を船で引かせる筏や、ロシアの大河川を下る住居付きの大規模な木材運搬の形式がある。アフリカでは森林地帯に簡単な筏が使用されるほか、バルサ材を使用した筏船も発達している。西アジア、中央アジアは木材が乏しいので未発達であるが、インドでは小型の木製筏船がよく発達している。これは木の幹を束ねて竹で固定した長さ1.5メートル程度のもので、使い捨てに近い。東南アジアでは木材を下流に運搬する手段として広く使用され、ボルネオ島やメコン川上流では竹の筏も盛んに利用される。中国では木材の運搬のほかに運河の航行、漁船の目的で使用される。朝鮮にはパルソンとよばれる漁労用の筏、台湾では安平付近で使用される竹製の筏、テッパイがある。テッパイは漁船や渡船として使用される。オセアニアでは広く水上運搬具として利用され、とくにオーストラリア北西部、ビスマーク諸島、アドミラルティ諸島、ソロモン諸島などにみられる。北アメリカでは一部を除いてみられないが、南アメリカではコロンビア、エクアドルなどで農閑期に筏を住居として魚をとるほか、ペルー北部では帆のついた筏が使用されていた記録がある。
葦舟としては、パピルスでつくった古代エジプトの例のほか、アフリカや南アメリカにある。ティティカカ湖の大型の葦舟は漁労や運搬用に用いられている。
[豊田由貴夫]
伐採した木材を谷間に落とし(山落としという)、そこから1本ずつ鉄砲流し(水量が少ない渓流に堰(せき)をつくって貯水し、一度に放流して木材を流す)、管(くだ)流し(木材を連結せずばらばらに流す)などの方法で、水量の豊富な筏場まで流し、網場(あば)と称する所で筏を組み立てる。組み方は、河川の状態などにより異なり、普通、横列に組むときは、材端を藤(ふじ)づるや針金で巻き付けたり、材端に目途(めど)とよばれる穴をあけるか、または鉄環を打ち込んで、これに藤づるや針金を通して連結する。さらにこれを縦列に連結するときは、河川の屈曲状態にあわせ、目途と目途を藤づるで結ぶか、前後の筏が動かないように両側に長材を添えて連結する。また、水量の少ない上流河川では小形の筏をつくり、水量の豊富な下流にきて大形の筏に組み直して流送する。東南アジアの一部では、比重1以上の硬木の筏の上部に竹を組んで浮力をつける方法もとられている。
[山脇三平]
河川中流部の網場で組まれた筏を下流へ流す作業を筏流しといい、1930年代から1940年代ごろまで木曽(きそ)川、熊野(くまの)川、大堰(おおい)川(保津(ほづ)川の上流の一部)、米代(よねしろ)川など各地の河川で行われた。筏には、さきのり、なかのり、あとのりとよばれる筏師が1~3人乗り、櫂(かい)、棹、ときには制動棒などを使って操った。
海上で木材を輸送するために組む筏を海洋筏という。これには縦連式、矢羽根(やばね)式、重積式などの組み方があり、船で曳航(えいこう)する。第二次世界大戦中、北洋材の大量輸送に用いられた。現在でも、港湾内の大貯木場から輸入材を平筏に組み、河川下流沿いの木材工場まで曳航する方法が行われている。
[山脇三平]


 に作り、發(発)(はつ)声。〔説文〕六上に「
に作り、發(発)(はつ)声。〔説文〕六上に「 は
は 中の大
中の大 なり」とあり、小なるものを桴(ふ)という。筏は竹を編んで水を渡るもので、筏舫ともいう。古くは桴といった。
なり」とあり、小なるものを桴(ふ)という。筏は竹を編んで水を渡るもので、筏舫ともいう。古くは桴といった。 オホフネ
オホフネ出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
…伐採した木材をいかだに組んで運ぶ方法はしばしば見られる。ベトナムや台湾では,前方をそり上がらせた竹筏(テッパイ)が漁船として海上で用いられている。また,いくつかの葦の束を舟形に束ね合わせて作るいかだすなわち葦舟は,古代エジプトで用いられていたが,今日でもアフリカや南北アメリカ大陸で幅広く使用されている。…
※「筏」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...