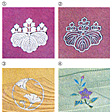精選版 日本国語大辞典 「紋付」の意味・読み・例文・類語
もん‐つけ【紋付】
- 〘 名詞 〙 ( 「もんづけ」とも ) 博打(ばくち)の一種。多くの役者の紋所を印刷した紙に、それぞれ棒形を墨で幾本かずつ描き、描いた棒形一つにつき銭を何文かずつ出させ、くじに当たったものが賞金を得ることにしたもの。紋紙棒引。棒引。棒引紋付。
- [初出の実例]「紋付(もンつケ)にそれしゃの女房割(わり)をいい」(出典:雑俳・川柳評万句合‐宝暦一三(1763)桜一)
日本大百科全書(ニッポニカ) 「紋付」の意味・わかりやすい解説
紋付
もんつき
主として長着や羽織に家紋(定紋(じょうもん))をつけたもの。紋服ともいう。礼装として用いる。かつては、たんす、長持などの油単(ゆたん)や袱紗(ふくさ)などにも家紋をつけることが行われた。古くは公家(くげ)、武家社会に限って着用されたが、江戸時代中期になると、財力を蓄えた富裕な町人、歌舞伎(かぶき)役者などにもしだいに広がった。一般に礼服として定まったのは、明治維新後に裃(かみしも)が廃止されてからである。男子は黒羽二重(くろはぶたえ)染抜き五つ紋付の羽織と対(つい)の長着に、仙台平(せんだいひら)の袴(はかま)が正装である。夏は平絽(ひらろ)で、吉凶とも同じ。女子は黒縮緬(ちりめん)染抜き五つ紋付裾(すそ)模様の二枚襲(かさね)。下着は白羽二重であるが、最近はこれを略し、付け比翼が一般的である。凶事には黒無地とし、夏は平絽を用いる。男児の5歳の祝い着には、黒、褐色(かちいろ)(濃紺)などの羽二重染抜き五つ紋付熨斗目(のしめ)模様の長着と羽織を対で着て、袴をつける。
[岡野和子]
紋服の種類
五つ紋は男女とも第一礼装で、三つ紋はこれに次ぎ、一つ紋は略装となる。背縫いを中心につけた背紋、左右後ろ袖(そで)の袖紋と、両胸の抱き紋をつけたものが五つ紋、背紋と袖紋が三つ紋、背紋だけのものが一つ紋である。五つ紋は染抜きにし、略装となる縫い紋にはしない。男子略礼装としてのお召、紬(つむぎ)、絽などの無地の対や、黒無地の羽織は染抜き三つ紋か、一つ紋の縫い紋にする。女子の場合は、紋綸子(りんず)などの無地の長着に三つ紋、一つ紋の染抜きまたは縫い紋をつける。振袖、訪問着には三つ紋か一つ紋をつけたが、最近はつけないことが多くなっている。黒羽織は三つ紋か一つ紋の染抜きにするか、一つ紋の縫い紋とする。
[岡野和子]
紋の種類
染抜き紋は、あつらえの白生地(きじ)を染めるときに家紋を白く染め抜いて、細い線を墨で描く。これを紋章上絵描きという。既製品の紋服は、黒紋付、色留袖とも石持(こくもち)になっていて、これに紋描きをする。石持は輪のついた紋に限られる。第一礼装は白あげの表紋(日向(ひなた)紋、陽紋)にする。裏紋(陰(かげ)紋)はこれと反対に、細い輪郭線で紋を描くもので、略装として女性や伝統芸能に携わる芸能人が用いる。太陰、中陰、本陰がある。本陰はもっとも細い線で表したもの。細輪の中の下半分に紋を表した糸輪のぞきは芸能人が好んで使う。替え紋(女紋)は、もと武家が略式の忍びの外出に家紋のほかに用いた紋のことで、強い感じの家紋をやさしく変えたり、丸輪の囲みを輪なしにしたり、婚家の紋でなく、生家の紋を用いたりすることもある。伊達(だて)紋は家紋と異なり、絵画風に大柄に刺しゅうや描き絵で表したもので、伊達者、侠客(きょうかく)、役者などが粋(いき)がって用いた。加賀紋は直径5センチメートルぐらいの大きさのものもあり、友禅風に華やかに優雅にかいたり、刺しゅうをしたりしたもので、子供の産着などに用いる。縫い紋は色糸、金糸、銀糸で刺しゅうして紋を表したもので、染抜き紋より略式となる。菅(すが)縫い、けし縫い、蛇腹(じゃばら)縫い、絞り縫い、織り縫いなどがある。織り紋は織りで紋を表したもので、江戸時代の大名、高級武士などが、熨斗目(のしめ)小袖などにつけたものである。特殊なものに比翼紋といって、相愛の男女の家紋を半分ずらして重ねたものがあり、今日では婚礼の披露の招待状、引出物、調度につけたりする。
[岡野和子]
紋の付け方・大きさ
背紋は衿(えり)付け線より5.5~6センチメートル、袖紋は袖山から7.5センチメートル、抱き紋は肩山から15センチメートル下がったところにつける。紋の大きさは時代により変化しているが、現在は男物は3.8センチメートル(鯨尺で一寸)、女物は2.1センチメートル(5分5厘)と小さくなっている。切り付け紋(貼(は)り付け紋)は、染め直しで石持のない場合とか、貸衣装に客の注文で家紋をつけるときに使用する。同地質の布に紋を描き、所定のところに貼り付け、目だたないように細かくかがる。
[岡野和子]
改訂新版 世界大百科事典 「紋付」の意味・わかりやすい解説
紋付 (もんつき)
家紋をつけた着物や羽織を意味し,狭義には五つ紋礼服を指す。紋服ともいう。古くは公家が直垂(ひたたれ)に,武家が大紋(だいもん),素襖(すおう),裃(かみしも)などにつけて家柄や格式をあらわしたほか,胴服に装飾性も兼ねてつけたものもある。江戸時代に家紋の図案化が完成し(紋章),礼装用としてばかりでなく略式や忍びで外出の際の羽織や着物にも替紋,裏紋をつけることが武家から裕福な町人にまで広まった。その技法も多彩な染めや刺繡(ししゆう),絞りなど装飾性に富んだものが生まれた。一般に染め五つ紋付の羽織袴や江戸褄(えどづま)が礼服のきまりとなったのは明治時代からである。男紋は5cm,女紋は3cmと大きかった紋は,しだいに小さくなって現在は男紋3cm,女紋は2cmほど。紋は数によってつける場所がきまっており,一つは背,三つは背と両外袖,五つはそれに加えて胸につける(抱紋(だきもん))。五つ紋付は最高の格式をあらわし,三つ,一つとなるに従い略式となる。あらわし方も陽紋(ひなたもん)(表紋)の染めが正式で陰紋(裏紋)や縫紋は略式である。白黒であらわした染紋と銀糸の縫紋は慶弔両用に用いられるが,慶事や装飾的な場合には金,金銀ぼかし,派手な色目を用いる。紋をつける着物は女物は留袖,喪服,色無地,訪問着,無地羽織などで,男物には黒羽二重の着物と羽織の礼服や,紬,御召(おめし)などの無地につけて準礼装とする。
紋の種類には次のようなものがある。(1)染紋 留袖,喪服,男物羽二重などあらかじめ白く抜いた紋所に陽紋を描き入れる場合と,付下げ訪問着などに色で描く方法がある。染抜紋は白生地から色無地,訪問着などに染める誂(あつらえ)の場合の方法。(2)縫紋 染上がりの訪問着,付下げ,無地の着物や羽織などに金,銀,色糸で刺繡する。おもに一つ紋を陰であらわすが,女物の着物に陽であらわすと装飾的である。(3)張付紋 表地と同質の生地に家紋を描いた丸形を張り付ける。急な場合や染め直したとき役立ち切付紋ともいう。(4)加賀紋 友禅風に彩色した紋で家紋に草花をあしらった多彩で装飾的な紋。(5)伊達紋(だてもん) 絵画風な大型の装飾紋で刺繡や描絵であらわした男性用。(6)比翼紋(ひよくもん) 相愛の男女がそれぞれの家紋を組み合わせて作った紋。
執筆者:山下 悦子
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「紋付」の意味・わかりやすい解説
紋付
もんつき
「紋服」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
関連語をあわせて調べる
[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...