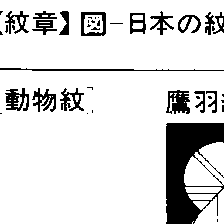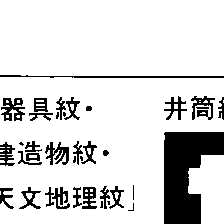精選版 日本国語大辞典 「紋章」の意味・読み・例文・類語
もん‐しょう‥シャウ【紋章】
- [ 1 ] 氏族・家・組・国・団体などが、それを表わすしるしとして定めた、動植物、器物、文字などを図案化したもの。紋。もんどころ。
- [初出の実例]「幼年生徒に〈略〉諸種の物形、紋章等を作らしめ」(出典:教育学(1882)〈伊沢修二〉二)
- [ 2 ] 小説。横光利一作。昭和九年(一九三四)発表。無学ながら勤王の名門という紋章を誇りに、たくましく生きる発明家雁金八郎と、自意識過剰な知識人山下久内を対照させ、巨大な社会機構に支配された不安な時代に喘(あえ)ぐ現代人の姿を描く。
改訂新版 世界大百科事典 「紋章」の意味・わかりやすい解説
紋章 (もんしょう)
ある特定の図案を用いて,個人,一家,一族,団体,結社などを表徴する標識。紋章という呼称は近代になってからのもので,古くは〈家紋〉〈家の紋〉〈定紋(じようもん)〉〈紋じるし〉〈紋所〉などと称していたが,このうち〈家紋〉は厳密にいえば武家の紋のみに用いられた呼称である。団体や結社に用いられるものは記章,バッジと呼ばれることも多く,各種のシンボルマークもこれに近い。
日本
世界で家の紋章を用いるのは,ヨーロッパの貴族社会を除いては日本のみである。日本の紋章の起源は平安時代(11世紀前半),公家の衣服,調度,牛車(ぎつしや)に各自が好みの文様を用いたのがその始まりとされている。旧儀先例を尊重する公家の風から,父祖の好んで用いた文様を慣用するようになり,その家の文様として定着したものである。その大方は無限に連続して広がる複数の文様で,衣服の織紋系統の文様が多く,複雑・繊細である。しかし,この後に発展する武家紋の影響がなければ,現在みるような家紋の形をとるには至らなかっただろう。狭い公家社会では装飾的な意味が強く,武家のように敵味方識別の目印としての紋章は,切実に要求されなかったからである。
武家の家紋の起源は,鎌倉時代初期の旗指物(はたさしもの)の〈しるし〉にある。一族郎党が団結し,外敵に対して戦う際に,団結の象徴ともなり,敵味方を識別するしるしともなるものが必要であった。武家は戦場に信ずる神を守護神として勧請するために,幡(はた)を立てて依代(よりしろ),招代(おぎしろ)とした。神の名以外に依代そのものをも図案として描き加えるようになった。また,狩衣(かりぎぬ),鎧直垂(よろいひたたれ)の好みの文様が単独の図形として用いられ家紋となることもあった。あるいは大将の本陣を囲む五布(横に5段にはいだ布)の幕に,それを示す黒,紺,黄,紫などの染分け模様も目印の役を果たし,これを円で囲むといわゆる引両(ひきりよう)の幕紋となった。これがのちに円形に切りとられて家紋となる。このようにして鎌倉中期には武家の間に家紋の使用が一般化し,モンゴル襲来のときには全国に定着していた。
南北朝時代になると公家も武装することがあり,武家紋の影響を受けて,公家自身が家紋を必要とするようになった。京都に室町幕府が開かれ,公武の交流が親密になると,家紋も相互に影響し合ったことは足利氏への桐紋(〈桐に鳳凰〉は古くから天皇専用の衣服の文様に用いられていた)の下賜の例をみても十分に考えられる。また二つ以上の家紋をもちはじめることも理解できる。南北朝以降,応仁・文明の乱前後にかけて,一族一党が分立し,敵味方に分かれて戦うようになると,今までの単一の同紋では識別できないので,紋は一家単位となり,必要に迫られて伝統の紋に当座のつもりで他の図案を付加したものがそのまま定着した例もあり,戦闘集団の離合につれて紋も分立・派生し,急速に増加する。家の興亡,生死をかける戦いに用いるために,祈願,呪術,縁起をかつぐもの,戦勝の記念などによるものが多い。一般に武家紋は単純・豪放なものが多く,公家紋の複雑・繊細なものとは対照的である。
戦国時代に入ると下剋上による興亡が激しく,戦法は一騎打ちから集団密集戦へと変化し,戦場も広がって一度に各所で戦いが展開され,武功の確認がより切実なものとなる。その結果,各自が旗指物を背負い,自己の姓名や信条,信ずる神仏などを大書し,目だつ武装をして自分を喧伝するようになった。旗指物を含め武装全体がいわば商標となる。その中心が家紋であったが,独自の紋も創作されて個別化し,類似のものがあれば,とがめだてて禁じることもあった。武勇の士を討ちとり,そのしるしを奪い取って自分のものとすることもあった。図案としては,文様からの転用,幕紋の引両,旗の招代から転用した唐団扇(うちわ),目籠(めかご)などのほか,神仏具をかたどった紋もあったが,武家には遠目にも識別しやすく,文字の読めない者にも容易にわかる○,□,×,+,┐, などのような簡単な印が好みに合ったようである。これらを図案化するについては,既成の家紋が目安となったであろうが,家譜などの解説については,もっともらしい説明,故事来歴が捏造(ねつぞう)され,家系の修飾がなされることが多い。
などのような簡単な印が好みに合ったようである。これらを図案化するについては,既成の家紋が目安となったであろうが,家譜などの解説については,もっともらしい説明,故事来歴が捏造(ねつぞう)され,家系の修飾がなされることが多い。
江戸時代,太平の世には戦旗としての旗は無用となって格納され,家紋は挟箱(はさみばこ)に描かれて行列のしるしとなった。服装が制度化され,大紋や肩衣(かたぎぬ),小袖などいわゆる紋付の左右につけられた紋は,幾何学的に図形化され,より対称形に整えられた。また武家社会の形式化,格式化につれて形が硬化し,多くは円形に囲まれるようになった。家格の表徴とされた紋は,四姓(源平藤橘)などの貴種にかたよって偽作された系譜に適合させるために,源氏は笹竜胆(ささりんどう),平家は蝶,藤原氏は藤,橘氏は橘紋などという付会の説にのっとって作られ,さらに賜与や奪取,婚姻などの理由とともに単一の家に2個ないし数個の家紋が作られた。家紋を多くもつことをよしとする風潮のなかで,伝統の家紋の心理的重圧を避けようとする気持ちも手伝って,気軽に自己の紋を作ることが行われた。こうして目印という紋章本来の意義は薄れて定まった位置につける装飾文様の意味が強くなり,優美華麗な伊達(だて)紋が生まれるとともに,本来の家紋の意匠もまた優美繊細なものへと変化する。伝統の家紋は重んじられ,中間(ちゆうげん)や駕籠かきの看板,法被(はつぴ)などには家紋を用いず,単純な合印(あいじるし)を用いた。家紋に代えてその家に関係のない紋を用いることがあるが,これは〈通紋〉〈無駄紋〉〈ただの紋〉などと呼ばれ,蔦,花菱,近代になっては桐などが用いられた。
家紋の源流は神の依代であったので,清浄な白地を主とし,華美な服装ははばかられた。幕紋に由来する三浦氏の黄紫紅の染分け紋,明智氏の水色桔梗(ききよう)紋のほかに色彩紋はなく,その水色桔梗にしてもはたして地色が水色なのかどうか判然としない。
一般の農工商民の間には,商人に商標があるくらいで,紋をつけるべき旗や衣服はもたなかったが,近世になって経済力をつけた町人が苗字帯刀免許の士分になる者もあり,武家風俗を模倣して先祖は名ある武士であったと称し,家紋をもつようになった。その先端をいったのが役者の紋で,好みの衣装の模様や図柄が流行した。役者の紋は芸の血脈,名跡(みようせき)を背景とした商標で,個人紋が家の紋となったものである。役者の紋が一般庶民に紋を普及させた力は大きく,武家紋の優美化に与えた影響も大きい。
家紋は厳密にまた狭義に解釈すれば,武士のみのものであったが,その使用の制限・統制は,菊,桐,葵紋および領主の家紋を除いては,苗字のように使用を禁じられることはなかったので,紋付を着用できるほどの者は,勝手次第に用いていた。明治維新後,庶民にも苗字を名のることが義務づけられ,紋付羽織袴が礼装として一般化するようになると,家紋は苗字に付随してあるべきものとされ,普及をみた。しかし第2次大戦後は,和装が,ことに男の礼装として用いられなくなると紋の使用も廃れ,わずかに墓石などに形をとどめるにすぎなくなった。ただ紋屋の見本帳を集成した〈紋帳〉や〈紋鑑〉は,日本の伝統的なデザインを示すものとして,近年とみに関心を集めている。(図参照。)
執筆者:加藤 秀幸
ヨーロッパ
ヨーロッパにおける紋章の成立は,中世封建制の確立と結びついている。それは12世紀の前半のことであり,おそらく1125年前後と考えられる。その時代には,領主のもとに領地争奪が一般化し,これに備えて,恒常的戦闘集団たる騎士たちが,社会の中核をなすようになっていった。また,11世紀末の開始以来,十字軍による対イスラム教徒戦争と,イベリア半島における国土回復戦争(レコンキスタ)とが本格化して,封建軍隊の組織化が進行した。そこでは,全身を覆う防具をまとい,槍,剣,盾の重装武具をもって騎乗する戦士が,軍隊の主体をなしていた。この戦闘ユニフォームを着用した個人を識別するための標識として,紋章が採用された。盾面をはじめ,兜飾,ヘルメットにその標識が描かれて,個人を表象することになり,さらに戦旗(旗)にも現れて,戦隊帰属をも明示するものとなった。紋章はこのように,戦場における識別という実用上の動機から生まれたが,同時にその標識を通して,個々人のアイデンティティを強調し,また紋章図柄の継承や類比を通して,家統の帰属を表現するという精神的な目的をも果たした。紋章の成立は,封建制が家的集団の再編によって,一つの安定した社会制度となる過程に一致していたことがうかがわれる。
その発祥地は明確ではないが,上述の社会的変化が典型的に進んだ南西フランスかともみなされる。しかしいずれにせよ,紋章の慣習は急速に西ヨーロッパ世界に普及し,共通の理念に従った慣習として受け入れられていった。すでに13世紀には各種紋章の意識的な集成が試みられ,14世紀にはバルトルスの《紋章論》(1356)のような体系的論説が著された。また彩色された紋章図集も作成された。15世紀には,紋章の研究・管理を目的とした専門機関の初歩的なものも設けられた。
紋章はこのような過程で精密に規則化され,膨大な規則に従っている。その成立事情にかんがみて,盾形を標準としているが,その図像については,おおむね次の三つの視点から解説される。第1には,描きこまれる図形は3種類に分類される。(1)平面を複数部分に分割して単一色に塗り分ける〈分割〉,(2)直線,曲線,矩形,円などの抽象的な図形を描きこむ〈幾何学的図形〉,そして(3)具体的な物体を図案化した〈具象的図形〉である。具象的図形としては,皇帝と王をそれぞれ表示するワシとライオンをはじめ,動植物が多用され,また武具,十字架,建造物,楽器なども見られる。これらとは別に象徴的な語句が標語として記入されることもある。
次に,これらの図形の描写法をめぐって,三つのカテゴリーがある。第1は〈金属〉で,金と銀とである。それぞれ黄,白をもっても代えられる。第2は〈色彩〉で,青,赤,黒,緑,紫,橙の原色が許され,中間色は禁じられる。第3は〈羽毛〉であるが,毛皮のようなけばだった小紋様で,これに数種類あり,ことに白テン羽毛を文様・図案化したものが多用される。これらの使用法については厳密な規定があり,例えば〈金属〉どうしや原色どうしを重ねることは禁じられる。
紋章は原理的には,個人にのみ属しており,同じ紋章が二つあってはならない。しかし同一の家統に属するものは,互いに類比した紋章をもつことが求められており,特定のモティーフにバリエーションを加えながら,家統によって共有される。したがって,先祖の紋章祖型に発しながら,種差を設け,同時に類比させる技術手法が必要とされる。細部を変換しつつ類別を加える作業が,紋章学上つねに要請される。また,婚姻などによる複数家統の結合によっては,両家統の紋章モティーフを併合させることがある。このためには,紋章平面を分割し,四分,八分などの複雑な組合せが生ずる。100区分を超えるものまであるが,この組合せについても,厳格な規則が適用される。
上述のほかにも,詳細な規則があるが,それらは,発生後徐々に形成され,ことに絶対王政下において,紋章慣習が公的権威にも支えられて,制度として確立されると,ますます厳密化していった。また図像化された紋章図を言句をもって祖述する方式(ブラゾンblasonという)も開発された。大学における紋章学講座の開設,国家による登録・管理や,使用料の公的徴収などがみられた。ヨーロッパのいくつかの国では,20世紀にまで紋章制度が受け継がれたほどである。本来,紋章は家統の脈絡のもとでの個人に認められるものであるが,擬制的にはさまざまな団体によっても保有されている。都市,ギルド,近代的社団などであり,これらにも紋章学上の規則は準用される。
紋章研究は現在でも個々の紋章創設に際して不可欠であるが,同時に家統継承を遡行的に推定するための確実な資料を提供するものとして,歴史補助学の重要な一環を占めている。紋章がヨーロッパの社会慣習の分析にとって枢要な素材であることを再認識したい。
執筆者:樺山 紘一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「紋章」の意味・わかりやすい解説
紋章
もんしょう
家柄、団体を表すために、動植物や器物などを図案化した印。
[遠藤 武]
日本
公家(くげ)と武家の場合は、その家が属している氏族の系譜上の称号、苗字(みょうじ)と関係のあるもの、庶民の場合は、明治以後につけられた苗字と関係あるものが多く、図紋として用いられている。
[遠藤 武]
歴史
家紋は、保元(ほうげん)・平治(へいじ)(1156~1160)のころ、旗や幕に家の印として用いられたとか、源頼朝(よりとも)に始まるという説があるが、本来は公家が車で宮中に出入りする際に、自分の車と他人の車を識別するために考案されたとみるべきであろう。その成立年代ははっきりとしないが、おそらくは平安時代の中期に、藤原一門などで門地門閥を重んずる風潮が盛んとなり、儀式その他において自家の標識として家紋をつけ、それによって識別の便利さを知ったのであろう。さらに格式ある家紋は、家紋によって他を圧するほどの勢いをもつようになっていった。
公家の家紋は優雅なものが多く、武家の家紋は実用的で、戦いの場において、敵味方の陣地識別のために旗や幕に用いて目印としたのに始まり、簡略で、しかも識別しやすい幾何学模様が多いのが特色といえる。ことに群雄割拠して互いにしのぎを削るような争いが続くにつれて、一軍の将たる者は、地方の群雄の家紋をつねに熟知しなくてはならなくなり、このために『見聞諸家紋』という書籍さえ刊行されるほどであった。
関ヶ原の戦いを契機として、太平の世の基盤ができて、武具、武器、旗、幟、馬印などは無用のものとなり、紋章の用途のうえに一大変革が行われた。つまり家紋は、武士の威儀を正すのに必要なものとなり、儀礼のうえからも、自己の家格門地を表す服装の決まりができて、参勤交代あるいは登城をするときの行列に、家紋を明示する必要に迫られ明暦(めいれき)大火(1657)の翌年に『大名御紋盡(だいみょうごもんづくし)』という後世の「武鑑(ぶかん)」に相当するものが刊行された。弓は袋に刀は鞘(さや)にという太平の世の連続は、おのずから奢侈(しゃし)の風潮を生み、衣服、調度にまで家紋をあしらうようになり、ここに威儀を正すというよりも、装飾としての家紋が普及した。こうして、元禄(げんろく)文化を背景として伊達(だて)紋、加賀紋、鹿子(かのこ)紋、崩し紋、比翼紋などしだいに盛んになっていった。また貨幣経済の発達と商業の隆盛に伴って、富裕な町人の間にも、武家以上の異体異様の紋章を好む風習が流行し、婦女子の間では、自家の紋よりも歌舞伎(かぶき)者の紋を、髪飾りや装身具につけて楽しむことが流行し、江戸時代の末期まで盛行したのである。
明治の新政府となって、服制上にも変化がおこり、和服にかわって洋服を用いることが行われた。嫁入り調度品や花嫁衣装には、江戸時代と同じようにまだ和服全盛の時代であったが、近代資本主義の発達により、産業界では自社製品を製造販売することから、表徴としての記章が生まれた。そして、家紋とは別に重要な役割を演じ、ひいては都市あるいは団体の記章として発展、現在でもこの影響が受け継がれている。
[遠藤 武]
種類
日本の紋章は実に多く、約2800種にも上り、封建社会でのその盛行がしのばれる。しかし今日行われているのは、そのうち100種にも満たず、伊達紋(山水、花鳥などをはでに図案化したもので、芸妓(げいぎ)などが用いる紋)を加えても、300種くらいのものと思われる。
紋章の対象となるものは、日月星辰(せいしん)のほか、植物、動物、調度、文字、自然現象などであるが、そのなかでも公家と武家では、たとえ同一の紋章であっても、武家は尚武を表す意味から、剣が付加される場合がある。たとえば剣酢漿草(けんかたばみ)、丁字、梅鉢、菱(ひし)はその例である。家紋としてもっとも多く用いられたのは植物で、そのなかでも桐(きり)を第一とし、藤(ふじ)、菊、蔦(つた)、笹(ささ)、酢漿草、梅、桔梗(ききょう)の順となる。そのほか巴(ともえ)、唐花(からはな)菱、九曜(くよう)、蝶(ちょう)、木瓜(もっこう)、引両(ひきりょう)、目結(めゆい)などがある。そのほかなじみが深いものに、鷹羽(たかのは)、井桁(げた)、源氏車、鱗(うろこ)、鶴(つる)などがある。
[遠藤 武]
西洋
沿革
西洋で紋章制度が確立されたのは12世紀後期であるが、それ以前の古代諸国にも、紋章類似のものが認められる。たとえばエジプトのツタンカーメン王の墓の壁画にある盾の太陽シンボル、古代ペルシアのペルセポリス宮殿浮彫りの盾にある円の中の4個の円の紋、古代ギリシアの壺(つぼ)に描かれた戦士の盾にみられるメドゥーサの首、獅子(しし)、鷲(わし)、イノシシなど、また、ギリシアの貨幣にあるアテネのフクロウ、コリントのペガサス、クレタのミノタウロスなどである。これらのしるしが個人や団体の標章として永続的に用いられたかどうかについては記録的資料が乏しいが、後世の紋章の前身と考えられる。
紋章制度の確立という意味は、各人(あるいは各団体)が独自の紋をもち、これが継続的であって、社会的に公認されること(国王の認可、紋章院の登録など)である。このような制度が生まれたのは、十字軍の戦いや、騎士の槍(やり)試合などが動機となっている。11世紀末に始まった十字軍に従軍の騎士団は、大規模な集団戦闘で彼我の識別が必要となり、イスラムのアササン騎士団をまねて、マントに目印をつけた。たとえば、聖堂騎士団は赤のマルチーズ十字(先端が二つに分かれた十字)、マルタ騎士団は白で同じ十字、チュートン騎士団はパテ十字(先端が広がった十字)である。これが集団の紋章の始まりで、その後、王、諸侯が各自の紋章を用いるようになり、さらに騎士の槍試合の流行で、各騎士が識別のために紋章を用いた。また、のちには聖職者、都市、大学、商工業者ギルドなども、同じような形式の紋章を用いるようになった。
国王の紋で代表的なものをあげると、イングランドでは、獅子心王リチャード(在位1189~1199)から3匹の獅子を用いているが、獅子はもとノルマン王のもので、イングランドを征服したノルマンディー公ウィリアム(在位1066~1087)が2匹の獅子を用いたのがもととなり今日に至っている(フランス・ノルマンディーの紋は現在でも2匹の獅子)。さらに1837年から、スコットランドの獅子、アイルランドの竪琴(たてごと)が紋章に加えられた。フランス王の紋は青地にユリであるが、これは処女マリアの標章で、ルイ7世(在位1137~1180)のシールに現れたのが最初である。初め散らし模様であったが、シャルル5世(在位1364~1380)から3個と定められた。ドイツでは、ローマ皇帝の継承者としての神聖ローマ皇帝を表すため、1100年ごろから、古代ローマのシンボルである鷲を用いたが、現在のドイツでも国章として用いている。帝政ロシアでも、やはりローマ皇帝の後継者を呼称して、双頭の鷲を紋章とした。
都市の紋章として、ロンドンは聖ジョージの十字と、守護聖人聖ポールの剣、パリは古い河港を表すガレー船と、王室の「青地にユリ」の紋の組合せ、ジュネーブは神聖ローマ皇帝直属の管区を示す鷲と、守護聖人聖ピーターのシンボルである鍵(かぎ)の組合せである。
[高橋正人]
紋章の形式
紋章は英語でコート・オブ・アームズcoat of arms、アームズarms、ヘラルドリーheraldryなどとよばれ、他の国ではアルムarmes(フランス語)、ステンマstemma(イタリア語)、ワッペンwappen(ドイツ語)などとよばれる。また正規の紋章と並行的に、バッジbadgeとよぶ標章が用いられる。コート・オブ・アームズの形式は、初期には盾形(シールドshield、エスカチオンescutcheon)の中に獅子などの形を置くか、盾形を分割して色を施すだけであったが、しだいに周りに付属物が加えられ、イギリス王室などの紋章では、盾形を中心として、上にヘルメット、さらにその上に花環または王冠、その上にクレスト、ヘルメットの両側にマントリング、盾形の両側にサポーターズ(獣あるいは人物など)、下にモットー(標語)という形が用いられ、これが標準的形式となっている。盾形の紋はもと一つであったが、結婚とか、他国を領土に加えるなどによって、盾形の中を分割して、他の紋を加えることが行われている。紋章は家族が同じ形を用いるが、長男は櫛(くし)形、次男は三日月というように、ディファレンスとよぶしるしを付加して区別している。
バッジには紋章の一部、または別の形が用いられる。イギリスでは、イングランドがバラ、スコットランドがアザミ、ウェールズが赤いドラゴン、アイルランドがクローバまたは竪琴をバッジとし、ばら戦争で有名なヨーク家は白バラ、ランカスター家は赤バラである。またポルトガルのエンリケ航海王子は天球儀をバッジとした。近代の軍隊では、連隊ごとにバッジを用いることが一般化されている。
紋章には職種、身分を示すものがある。聖職者の紋には、帽子と房が加えられ、身分によって帽子の色が違い、高級職ほど房の結び目が多い形式である。また近世の高級官吏、軍人には、各自の紋の盾形に、役職を示すシンボルを加えた紋章がある。
[高橋正人]
『沼田頼輔著『日本紋章学』(1928・明治書院)』▽『ヴァルター・レオンハード著、須本由喜子訳『西洋紋章大図鑑』(1979・美術出版社)』▽『高橋正人著『図説シンボルデザイン――意味と歴史』(1981・ダヴィッド社)』
百科事典マイペディア 「紋章」の意味・わかりやすい解説
紋章【もんしょう】
→関連項目巴|紋章学|ワッペン
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「紋章」の意味・わかりやすい解説
紋章
もんしょう
heraldry; arms
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
関連語をあわせて調べる
冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...