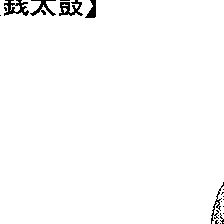関連語
精選版 日本国語大辞典 「銭太鼓」の意味・読み・例文・類語
ぜに‐だいこ【銭太鼓】
改訂新版 世界大百科事典 「銭太鼓」の意味・わかりやすい解説
銭太鼓 (ぜにだいこ)
日本の民俗楽器。(1)硬貨または硬貨状のものを小太鼓の縁につけたり,縁に十文字に針金を渡してそれに通すかして,踊り手が振りながら踊るもの。タンブリンによく似ている。革の張ってないものもある。佐賀県,青森県(えんぶり),宮城県,埼玉県などの民俗芸能に用いられる。〈銭輪(ぜにわ)〉とも呼ばれる。(2)竹筒のなかに硬貨または硬貨状のものを入れたもの。踊り手が振りながら踊る。中国・四国地方の民俗芸能に用いられる。
執筆者:長尾 一雄
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の銭太鼓の言及
【楽器】より
…奏法は,手または桴(ばち)でたたくものがほとんどであるが,なかには振鼓のように回転させて音を出すものもある。なお,太鼓という名称をもっていても,スリット・ドラムのように木製打楽器に属するものや,銭太鼓のように〈がらがら〉に近いものなどもあるので,膜打楽器と太鼓とは必ずしも一致しない。 木製打楽器には拍子木やカスタネットのように打ち合わせる(拍奏)タイプと,木魚や魚板のように桴でたたく(桴奏)タイプとがある。…
※「銭太鼓」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...