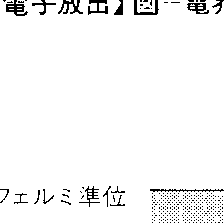改訂新版 世界大百科事典 「電子放出」の意味・わかりやすい解説
電子放出 (でんしほうしゅつ)
electron emission
物質,とくに固体中の電子が真空中に放出される現象。物質内の電子がもつエネルギーは,真空中で静止している電子がもつエネルギー(真空準位のエネルギー)より小さいので,通常,電子は物質中に束縛されており,真空中に飛び出すことはない。しかし外部からの何らかの刺激により,物質内の電子がエネルギーを得て真空準位より高いエネルギーをもつようになると,その電子は真空中に放出される。電子がエネルギーを得て真空中に放出される原因は種々あり,それによって,熱電子放出,二次電子放出,電界放出,エキソ電子放出,光電子放出などと呼ばれる。
熱電子放出
固体が熱せられると,固体を形成している原子の振動が激しくなり,電子は原子振動からエネルギーを得て固体外に飛び出すようになる。このような現象を熱電子放出thermionic emission,その電子を熱電子という。熱電子放出は,1884年にT.A.エジソンにより発見され,O.W.リチャードソンにより研究が進められたので,エジソン効果またはリチャードソン効果とも呼ばれる。熱電子放出はいわば電子の“蒸発”現象としてとらえることができる。熱電子の電流密度Jは,リチャードソンの式,
J=A(1-γ)T2exp(-Φ/kT)
によって求められる。ここでAは定数,γは電子の表面障壁の透過係数,kはボルツマン定数,Tは絶対温度であり,Φは仕事関数で,いわば電子蒸発の潜熱にあたるものである。十分な数の熱電子を放出するには熱電子を放出する物質の温度を上げる必要がある。一般に金属の仕事関数は大きいので動作温度はかなり高くなり,熱電子放出には高融点金属が用いられる。代表的な高融点金属であるタングステンの仕事関数は4.5eVで,動作温度は2700K程度になる。動作温度を下げるには,仕事関数が低くかつ動作温度における蒸気圧の低い物質を用いる必要があるが,この目的にはBaO,SrOなどの酸化物が用いられる。これらの物質の仕事関数は0.9~1.4eVであり,動作温度は1000K程度とかなり低い。熱電子は,真空管やテレビジョンの受像管,X線管などにおいて,電子線源として広く用いられている。
二次電子放出
固体表面にエネルギーをもった粒子が当たり,この粒子からエネルギーを得て固体表面から電子が放出される現象を二次電子放出secondary emissionと呼ぶ。広くはエネルギーをもったイオンや電子の衝撃により,物質表面から電子が飛び出す現象を指すが,狭義には入射電子(これを一次電子という)によってひき起こされる場合をいう。一次電子が固体に当たると一部は反射するが,一部は固体内に入り,その中のいくつかの電子にエネルギーを与え,さらにその電子は別の電子にエネルギーを与えるという過程が繰り返される。このような過程を経てエネルギーを得た電子が固体表面に達し,そのエネルギーが真空準位のエネルギーより高い場合には,その電子は二次電子として真空中に放出される。一次電子エネルギーが低すぎると,固体内の電子に十分エネルギーを与えられないので,一次電子1個当りの二次電子の数(二次電子収率という)は下がる。また一次電子のエネルギーが大きすぎると,一次電子は固体の中のほうにまで入るので固体表面から飛び出る二次電子の数は減り,収率は下がる。二次電子収率が最大になる一次電子のエネルギーは,物質やその物質の表面状態に依存するが,およそ100eVから数百eV程度である。また二次電子収率の最大値は金属では0.5~1.8,帯電防止をした絶縁体では1~20程度になる。二次電子のエネルギーは0から数十eVに分布するが,分布のピークは1~6eV程度と低い値になる。ごく少数の二次電子はオージェ過程(オージェ効果)により生じ,各元素に固有のエネルギーをもつので,固体表面の化学組成を調べるのにも使われている。二次電子収率が1より大きくなることを利用したものに,電子増倍管がある。電子増倍管は,二次電子収率が大きな物質で作った電極(ダイノードという)をいくつか並べた真空管の一種で,この電極に順次高い電圧をかけて使用する。第1段のダイノードに電子が入射すると,複数個の二次電子が放出され,これが第2段のダイノードに当たってさらに多くの二次電子を放出するという過程を次々と繰り返し,電子はねずみ算的に増える。増倍率は最高108倍程度にまで上げられる。電子増倍管の前に光電面を置いた構造にすると,入射光により生じた光電子が,電子増倍管により増倍されるので,きわめて微弱な光にも感ずる光検出器となる。これを光電子増倍管と呼ぶ。二次電子収率は固体の表面状態に敏感に依存するので,走査形電子顕微鏡で,試料表面の差を識別した像(二次電子像)を見るのにも使われている。
電界放出
固体表面に強い電場(電界)をかけたとき,固体表面から電子が放出される現象を電界放出field emissionという。この過程においては,電子は高電界印加により薄くなった表面障壁を量子力学的なトンネル効果によって通り抜け,真空中に飛び出す。電界放出では熱的エネルギーは必要としないので,絶対零度でも可能である。しかし温度が高くなれば,電子のエネルギーが増して表面障壁を通り抜ける確率が上がるので,電界放出が生じやすくなる。常温の金属からの電界放出を観測するには,約3×109V/m程度の高電界を必要とする。このような高電界を生ずるには,試料の先端を針状にして電界を集中させるようにし,数千Vの電圧を印加する。電界放出を最初に観測したのはアメリカのウッドRobert Williams Wood(1868-1955)で,1897年のことであった。量子論的説明は1928年イギリスのファウラーRalf Howard Fowler(1889-1944)とドイツ生れのノルトハイムLothar Wolfgang Nordheimによってなされた。彼らの理論は次のようなモデルに立っている。絶対零度の金属に電界をかけると,図のような状況が実現する。すなわち金属中の伝導電子はフェルミ準位より下の準位をすべて占め,フェルミ準位より上の準位は完全に空いている。いま金属に負,金属の外の陽極に正の電圧を印加すると,金属の外のポテンシャルは,ABの線のようになる。もし電界が十分大きくて,表面障壁の厚みが1nm程度になると,金属内の電子がトンネル効果によって障壁を通り抜け真空外に飛び出る確率が十分な大きさになり,電界放出が観測できるようになる。
電界放出の応用として電界顕微鏡(FEM。field emission microscopeの略)が1936年にE.W.ミュラーによって発明された。電界顕微鏡は鋭い針状試料のまわりに,導電処理をしたガラスに蛍光物質を塗布したスクリーンを置き,超高真空に排気して,試料とスクリーンの間に1~10kVの電圧をかけ,飛び出てくる電界放出電子の像をスクリーン上で観測するものである。倍率は約105倍で,分解能は2nmと高く,金属上に付着したある種の原子を一つ一つ分解してみることも可能となった。電界放出では熱電子に比べより大きな電子電流密度が実現でき,1012A/m2という値もすでに得られている。したがって高輝度高分解能の電子顕微鏡用電子銃として用いてもたいへん有用であり,0.5nm以上の分解能をもち,電子電流が熱電子放出型の場合の100倍という走査形電子顕微鏡も実現している。
エキソ電子放出
金属やある種のセラミックスをこすったり,破砕したりしたときに,その表面から電子が放出される現象をエキソ電子放出exoelectron emissionという。電子は,新たに表面が形成されるときに放出されるエネルギーや表面の原子が再配列するときに出すエネルギーを得て,真空中に飛び出す。エキソ電子放出は,固体の破壊現象などの研究に使われている。
光電子放出
固体に光やX線を照射したときに電子が放出される現象を光電子放出photoemissionという。光電子放出については,〈光電効果〉の項目に詳しく記述されているので参照されたい。
執筆者:小間 篤
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報