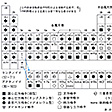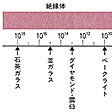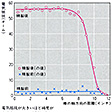翻訳|metal
精選版 日本国語大辞典 「金属」の意味・読み・例文・類語
きん‐ぞく【金属】
- 〘 名詞 〙 ( [オランダ語] Metaal の訳語 ) 非金属に対する語で、一般に、特有の光沢を持ち、熱や電気をよく導き、強度が大きく、延性、展性に富み、常温では固体で、比較的とけにくいものをいう。これは、おおよその区別であって、これらの性質からはずれるものもあり(水銀は常温で液体)、また、金属と非金属との中間の性質をもつ、石墨(せきぼく)、金属ケイ素、ヒ素、アンチモン、ビスマスなどもある。金類。
- [初出の実例]「按に達喜氏の発明に亜爾加里(アルカリ)は咸ち各種の金属(〈注〉メタール)の酸化する者にして」(出典:舎密開宗(1837‐47)内)
- 「岩田は君公の体面上銀より卑しい金属を用ひるのは、異なものであると云ふ」(出典:煙管(1916)〈芥川龍之介〉五)
金属の語誌
( 1 )鉄、銅などの物質は、漢語では「金」という字で表わし、また「金属」という語も存在していたが、それは「かねの類」というほどの意味であり、近代化学の有する概念を持っていない。
( 2 )近代的な意味、あるいは概念は、蘭書によってもたらされた。
日本大百科全書(ニッポニカ) 「金属」の意味・わかりやすい解説
金属
きんぞく
metal
一般に、特有の光沢をもち、電気と熱をよく伝え、展性・延性をもつ常温で固体の物質の総称(ただし水銀は常温で液体)。
元素の4分の3は金属である。2023年の時点で118の元素が知られている。104番以降の元素は信頼性の高いデータはほとんど得られていないが、2014年106番元素のシーボーギウムは第6族元素に特徴的な化学的性質をもつことが高い信頼度で実証された。原子番号93番以上の元素はすべて人工的につくられたものであるが、それ以外でも43番のテクネチウム、61番のプロメチウム、85番のアスタチンと87番のフランシウムの4種は天然には存在しない。これらの元素のうち約3分の2が金属元素であるが、金属的な性質をもつ元素までを含めると4分の3にもなる。
これらの金属元素が形づくる固体は(以下とくに断らないときは、金属とは金属固体を意味する)、塩や砂糖、あるいは岩石などとは異なり、さまざまな際だった性質をもっている。金属は熱や電気をよく伝え、たたいたり伸ばしたりすることによって、線にしたり板にすることができる。光に対して不透明で特有の金属光沢をもっている。アルカリ金属のように酸素と反応しやすい金属もあれば、金や白金のようにほとんど酸化されない金属もある。スズのように室温では金属であるが、冷やすと灰白色の非金属状態に変化するものもある。
一方、黄鉄鉱(硫化第二鉄)のように黄金色の外観をもつ物質ではあるが金属でないものもある。物理的には「金属とは一つのフェルミ面をもつ物質である」と定義づけられるが、これはあまりに専門的な表現である。化学的には、酸と反応して塩(えん)をつくる元素を金属元素というと定義することができるが、これは原子としての性質であり、金属結晶の特性ではない。
[長崎誠三・平林 眞 2015年4月17日]
金属の特質は何によるか
金属の特質の多くは、金属の原子が凝集して結晶になるとき、原子核の周りの最外核を形成する電子(価電子という)が伝導電子となって結晶の中を自由に動き回れる状態になることに起因している。ナトリウムのような1価の金属(価電子が原子当り1個のもの)を例にとると、正イオン当り1個の価電子が結晶格子内の空間に雲のようにたなびいているようすに例えられる。正イオンの格子と負の電荷をもつ電子の雲が静電気的な力(クーロン引力)を及ぼし合って凝集しているのが金属である。電子雲というのは、価電子のそれぞれが波動として結晶全体に広がっているもので、それらを粒子としてみれば、伝導電子が自由に動き回っていることに相当する。
金属に展延性があり、圧延して薄板に成形したり、線引きして針金にしたりできるのは、イオンの格子が外力によってずれても、全体に広がった電子雲との凝集力があまり変化しないからと考えられる。これに反して岩塩やダイヤモンドのような結晶では、外力で変形させることは結合を断ち切ることになる。
金属が容易に変形できるのは、一つは金属結合によっているが、さらには金属結晶の中にある種々の欠陥を仲立ちとして金属原子が外力をかけたとき容易に動けること、結晶の面が互いにずれ合えることによっている。したがって、実在の金属の結晶面を滑らすために必要な力は、理論的に欠陥がないとして計算した値に比べて1桁(けた)も2桁も小さい。もっとも容易に変形させやすい金でいえば、途中なましたりしないで1グラムの金で2000メートル以上に引き伸ばして金糸をつくれる。また、金箔(きんぱく)としては0.07マイクロメートルもの薄さにすることができる。
[長崎誠三 2015年4月17日]
金属の構造敏感性
金属の多くの性質は、特定の処理を行うことによって、しばしば著しく変化する。たとえば、各種の金属元素を添加して合金をつくったり、適当な熱処理を施したり、機械的な変形を加えたり、中性子で照射したりすると、著しく性質が変化することがある。金属が塑性変形を開始するときの機械的応力を降伏点というが、高純鉄では1平方ミリメートル当り約1キログラムなのに対して、炭素を数原子%加え、適当な熱処理を施すと(鋼がこれである)1平方ミリメートル当り200キログラムもの値にまで上昇する。同様なことは、電気伝導度、耐食性などでもおこる。このような金属の性質を構造敏感な性質とよぶが、融点、密度、熱容量などは、前述のような処理によってもあまり変化しない。
[長崎誠三 2015年4月17日]
金属の結晶構造
多くの金属は面心立方格子、最密六方格子、体心立方格子という比較的簡単な結晶格子を形づくっている。通常われわれが見ているのは、細かい結晶が集まったもの(多結晶という)である。
球を密に積み重ねる方法には2通りあるが、一つは面心立方格子になり、一つは最密六方格子になる。まず、平面に球を密に並べる。これは1通りである。次にこの上に球を密に積む方法も1通りである。3層目に球を積む方法には、1層目と同じ位置に積む場合と、2層目のあいたところに積み、4層目はまた1層目と同じになる場合との2通りがある。前者の積み方を六方の積み方といい、最密六方格子がこれにあたる。後者の積み方を立方の積み方といい、面心立方格子はこれである。体心立方格子は、立方体の八つの隅に球があり、立方体の中心に球が1個の形である。これには各隅8個、面の中心にある6個、計14個の球(原子)があるように見えるが、実は4個だけがこの単位胞に属している。隅の8個は隣り合う8個の単位胞により共有され、面の中心の球は隣り合う2個の単位胞により共有されているからである。体心立方構造の場合は2個がこの単位胞に属している。
金、銀、銅、白金、ニッケル、アルミニウム、鉛などが面心立方構造をとり、鉄、タングステン、クロム、ナトリウム、カリウムなどが体心立方構造を、マグネシウム、チタン、ジルコニウムなどが最密六方構造をとる。カドミウムと亜鉛は、ラグビーのボールのように縦に伸ばした球を積んだ形の最密六方構造である。この3通りの結晶構造以外のものは、ウラン、マンガン、スズ、インジウム、ガリウム、水銀など、例外的で少数派のものである。
[長崎誠三 2015年4月17日]
金属の変態現象
鉄は室温では体心立方構造であるが、約910℃で面心立方構造に変わり、さらに約1400℃でふたたび体心立方構造に変わり、1538℃で溶ける。また高圧下では最密六方構造の鉄に変わる。ウランは約1133℃で溶けるが、それまでにα(アルファ)、β(ベータ)、γ(ガンマ)と3回も結晶構造が変わる。マンガンはα、β、γ、δ(デルタ)と4回も変わる。チタンとジルコニウムはそれぞれ880℃と870℃で最密六方構造から体心立方構造へと変態する。このような変態現象は純金属だけではなく合金にもみられ、実用上からは、鉄のようにこれを利用して、さまざまな性質が得られるものもあるが、ウランのように、純金属のままでは使用中に変態により異常に変形したりするので、合金や化合物としてこの変態を阻止し、原子炉燃料に用いる。
スズは低温になると金属的な形から半導体の灰色スズに変わる。この変態は、日常の使用温度では変態の速度が遅いのでおこらないが、1868年1月のロシアのペテルブルグでは零下38℃に達し、多数の美術品やパイプ・オルガンのパイプがこの変態のためぼろぼろになった。この現象をスズペストあるいはスズ病という。
変態現象の機構の理論的解明は、その実用化とともに金属学における重要で興味深いテーマである。
[長崎誠三 2015年4月17日]
金属の輝きと色
金属は、ダイヤモンドのような透明な輝きではなく、光を通さない不透明な輝きを特徴とする。アルミニウムや銀の表面はよく光を反射するので鏡として用いられる。装飾用のめっきはクロムの輝きである。これらは白色光をそのまま反射するので無色の輝きを示すが、その源は金属がよく電気を通す性質による。
光は電磁波であるが、電磁波も周波数が非常に大きくなると表皮効果により、金属のごく表面にしか入らない。この表皮の厚さは10メガヘルツのラジオ波では約0.3ミリメートル、可視光線に対しては数百オングストロームであるので、光は表皮厚さより中へは入れずに反射され、これが金属光沢をもたらす。
多くの金属は無色の金属光沢をもつが、金は黄色く、銅は赤い。一方、銀は白い。銅は入射白色光のうち橙(だいだい)色から短波長側がすべて吸収されるので反射光は赤く、金は緑から短波長側がすべて吸収されるので反射光は黄色く見える。しかし銀の場合は、吸収されるのは約3200オングストロームの紫外線より短波長であるから、可視光線はすべて反射されて色がつかない。
金箔のように厚さが数百オングストロームになると、吸収光の一部は吸収しきれず透過してしまう。金箔を陽(ひ)に透かすと緑色に見えるのは、緑の波長よりも長波長の光は反射され、吸収係数がそれほど大きくない緑付近の光が透過するからである。
[長崎誠三 2015年4月17日]
金属の製錬
白金や金などの貴金属は単体で存在することもあるが、多くは酸化物、硫化物、水酸化物などの形で存在している。これらを適当な方法で還元して金属を取り出す(製錬)技術を冶金(やきん)という。炭素で還元するものには鉄、亜鉛などのほかにマグネシウム、銅、スズ、ニッケル、チタン、コバルト、銀などがある。水素還元により種々の金属が得られるが、実用されているのは酸化物の還元による金属タングステン、モリブデンの製造である。鉄やニッケルも特殊な目的のために水素還元することがある。
より還元力の強い金属で他の金属を還元することができる。テルミット(ゴルトシュミット)法もその一つである。チタンはマグネシウムまたはナトリウムで行う。アルミニウムも現在の溶融塩電解法が行われる前には塩化アルミニウムをナトリウムで還元して製造された。
不安定な金属化合物をつくり、これを熱分解する方法により高純度の金属をつくれるが、工業的に大量にはむずかしい(四ヨウ化チタンまたは四臭化チタンの分解によるチタン、ニッケルカルボニルの分解によるニッケルの製造)。ナトリウム、マグネシウム、カルシウム、アルミニウムなどは、これらの金属の塩類を高温で融解し、これを電気分解して得られる。
また銅は乾式法でも製錬できるが、酸化銅を希硫酸に溶かして硫酸銅水溶液として電解して得られる。同様にニッケル、亜鉛、銀なども製錬可能である。
[長崎誠三 2015年4月17日]
金属の加工性
各種の加工の容易さが、金属の材料としての有用性を物理的・化学的性質に加え、いっそう高めている。金属を溶かして型に流し込み、固めて形状物をつくる鋳造は数千年前の殷(いん)・周の時代から行われているが、近年はきわめて精密かつ機構的にも特殊な性能を備えたものがつくられるようになり、ますます重要な技術になっている。
金属の塊をたたいたり伸ばしたりして板、棒、線、管などをつくる塑性加工技術は、金属の特性をもっともよく生かした加工技術である。人間の髪の毛の数分の1の太さの針金や、細いパイプから径数メートルに及ぶ油送管や、厚さ1メートルの板から1マイクロメートルよりはるかに薄い箔(調理用のアルミニウムフォイルは約20マイクロメートル)までその製品はきわめて多様である。
溶接、ろう付けも金属の使用には欠かせない技術である。
微細な金属の粉末を固め、高温(融点以下)で加熱すると、粉どうしが融着して固形化する(焼結という)。この技術は古くから白金の加工に使われていたものであり、今日ではタングステンやモリブデンなどの高融点金属の素材や、各種精密部品の製造、通常の方法では合金化しない金属どうしを混ぜて複合材料をつくるなど、さまざまに利用されている。
最近では液体状態の金属を毎秒何万℃ともいわれる速さで急冷して結晶化を阻止することにより非晶質(アモルファス)状態が得られる。この状態の金属には耐食性、機械的強さ、物理的性質などにおいて一般の材料ではみられない特性があり、新しい利用の道が開かれつつある。
[長崎誠三 2015年4月17日]
金属の純度
工業用材料のなかで金属ほど純粋なものが使われているものはない。トランジスタが成功したのも、高純度のゲルマニウムやシリコンが得られたからである。金属には原鉱石や製錬の過程で入ってくる不純物がいろいろある。不純物の性状に応じて、蒸留、再電解(アルミニウム)、高真空中での溶融などの方法で精製されている。
半導体材料関係でよく使われるのは帯(たい)精製といわれる方法で、棒状試料を一端からごく狭い幅の溶融領域をつくり、これを順次他端に向かって溶かしていき、ちょうどごみを掃き寄せるように、溶解度の差を使って不純物を掃き寄せていく。こういう操作を繰り返すと不純物は一端に集まる。
シリコンやゲルマニウムなどは抵抗の値で純度を表す。一般にはスリーナインとかフォアナインのアルミニウムといった表現をするが、これはアルミニウムそのものが99.9%とか99.99%あるという意味ではない。アルミニウムの場合、用途のうえから問題になる不純物、銅、鉄、ケイ素を分析してそれを100から引いたものをもってアルミニウムの純度とする。さらに必要があればその他の元素も分析し、これらの合計を100から引く。したがって、このほかにもいろいろな元素がわずかではあるが入っている。正味のアルミニウムは99.9といっても、99.7とか99.8しかないことになる。このように純度というのは、それぞれの目的に応じて約束事として決まっている。各国で規格を決めているが、日本では日本産業規格(JIS(ジス))で何と何とを分析して純度はどう表現するかを決めてある。
非常な高純度になると、化学分析では純度を規定しにくくなるので、シリコンやゲルマニウムのような半導体では電気抵抗の値で規定し、また物理的研究では液体ヘリウム温度(絶対温度4.2K)での電気抵抗は純度にきわめて敏感なので、その値と純度にあまり依存しない室温での値との比を残留抵抗比(RRR)といい、これを目安とする。この値が大きいほど純度が高く、金、銀、銅などでは数万、モリブデンやタングステンでは数十万といった値が得られている。なお、純度という場合は、不純物の量だけでなく、金属格子中の欠陥(格子欠陥)の多少のような物理的純粋さを問題とすることもある。
[長崎誠三 2015年4月17日]
金属の腐食と酸化
自然界では金、白金などの貴金属以外の金属は酸化物、硫化物、あるいは水酸化物、炭酸塩などの形で存在しているが、これはとりもなおさず、これが安定な形であるからである。膨大なエネルギーを使って酸素やイオンから切り離して単体とする操作、つまり製錬をした結果得られた金属は不安定な形であるから、置かれた環境によって、いずれは元の安定な形へ変わっていく。
この腐食といわれる現象は、置かれた環境が大気中であるか、水中であるか、あるいは高温の雰囲気にあったか否かなどにより形態は異なるが、金属材料を使用するうえでもっとも重要な問題である。これを防ぐために、表面にできる酸化皮膜を大きな、亀裂(きれつ)がない一様なものにするなども一方法である。このために純粋化する、あるいは他の金属を加えてステンレス鋼のようにじょうぶな皮膜(酸化クロムの)をつくる。あるいはアルミニウムのように故意にじょうぶな酸化物の皮膜をつくる。めっきはより錆(さ)びにくい、じょうぶな金属の皮膜をつけることである(クロムめっき、金めっき、銀製品の上のロジウムめっきなど)。塗料を塗るのも一方法である。しかし、錆びることは金属の宿命であり、また、それあるがゆえに金属を再生することも可能であり、地球上が使えなくなった金属構造物で覆い尽くされることもないのである。
[長崎誠三 2015年4月17日]
金属の研究と機器
金属や合金は組成、内部構造、表面組織などの微細な変化に応じて性質が著しく変わることがあり、これらを測定する機器が金属の研究、利用に対して果たしている役割は大きい。
金属は可視光に対して不透明であるから、一般の光透過型の光学顕微鏡では組織を見られない。鏡のように平滑に磨いた金属試料の表面を酸などの薬品でわずかに腐食し、組織、相などによるその腐食され方の違いを利用し、反射光によって金属を調べる金属顕微鏡法が開発されたのはいまから約200年前のことである。この方法は現在でも金属の組織、加工のされ方、不純物の存在などを調べるためのもっとも基本的な手段である。ただ、光を使うために倍率は1000倍どまりであることと、表面のみの観察という限界はある。
試料の物性の変化を温度の関数としてとらえる方法である熱分析は19世紀末に開発され、金属、合金の融点、変態などを研究する手段として現在でも重要な技術の一つである。
金属の結晶構造を調べる手段であるX線回折法が確立したのは1910年代のなかばで、以後数多くの金属、合金の構造が明らかにされてきた。最近ではさらに電子回折、中性子線回折によってX線では不明な構造を明らかにすることができるようになった。
第二次世界大戦後は、さらに電子顕微鏡の発達によって、金属中における結晶格子の食い違い、各種の欠陥の存在、不純物の形態などが原子的な段階でわかるようになった。また、走査型の電子顕微鏡が1970年代に実用化され、破壊、腐食などに伴う金属材料の表面組織の変化を数十倍から数万倍の拡大率で観察することができるようになった。また電子線、X線を利用する技術の発達により、金属の微量不純物、微小部分の組成、表面の酸化物の形態などが知られるようになった。さらに放射線で照射して微小不純物を放射化して測定する放射化分析、プラズマを利用した分光分析、原子吸光分析など成分分析の手段も格段に進歩し、ppm、ppbの桁(けた)で不純物や成分が知られるようになり、金属の研究は格段の発展を遂げるようになった。
[長崎誠三 2015年4月17日]
金属の将来
青銅時代から鉄の時代へ、そして20世紀に入ってからアルミニウムが、また最近ではチタンが登場した。銅は電気用以外では大幅に他の材料にとってかわられ、鉄も構造材、電磁気材料としては不動の立場を保っているものの、一般用品ではアルミニウムやプラスチックに相当の分野を明け渡した。
アルミニウムも、その軽さ、耐食性、加工性によって建材、食器、家庭用品、航空機材料としてはいまだ確固とした立場を保っているが、航空機では耐熱性の点でチタンにかなりとってかわられている。胴体などでは最近の炭素系の新素材にかわっている。また、最近は希土類金属をはじめとする新しい金属が製錬技術の進歩により比較的容易に単体として得られるようになり、各種の合金元素用としてもてはやされている。
マンガンはけっして新しい金属ではないが、深海底に無限に近い埋蔵量があるといわれ、その利用が論議されている。しかしマンガンはその加工性、変態の複雑さなどからみて単独の金属材料として使われる可能性はなく、せいぜい合金元素の一つとして、またその酸化物は電池材料として、そのほか無機薬品としての用途があるにすぎない。
ニオブやタンタル、ジルコニウムなどの金属も超伝導材料、原子炉材料、高温耐熱材料など特殊な用途に有用であって、アルミニウムや鉄などにとってかわる構造用材ではない。
鉄、銅、アルミニウムなど、いわゆるコモンメタル(普通金属)は、それぞれの使用量、使われ方に多少の変動はあっても、将来にわたってわれわれの技術文明を支える金属材料としての重要性を失うことはないであろう。しかし、資源は有限であり、鉄のように非常に豊富に思えるものでも、品位の高いものは少なくなり、また、製錬のために必要な強粘結炭は乏しくなってきている。多くの金属材料は循環再生使用が可能であるから、有効なリサイクルが必要である。
コモンメタルと対照的に「レアメタル(希金属)」または「レスコモンメタル」という金属の分類がある。これは金属を使用の歴史、生産量、用途などを同じ視点からグループ化して扱うもので、コモンメタル、ベースメタル(通常金属)、レアメタル、マイナーメタル、貴金属などの仕分けがあるが、これらの分類には地球化学的視点と実用的視点が混合しているので厳密な定義は不可能である。それでも新材料開発の分野ではレアメタルのもつ特異な物性を活用したさまざまな機能素材がつくられている。数例をあげると、強磁性、超伝導、半導体、電池、高温耐熱性、耐食性、光電変換、熱電変換などである。
[長崎誠三 2015年4月17日]
金属利用の歴史
金属の利用の歴史は、その金属を鉱石から取り出すという冶金的操作の困難さに依存している。自然金、自然銀、自然銅といったものも産出するが、金属は多くの場合、酸化物、硫化物の形で産出してくる。これらの化合物の結合が強いほど冶金的操作で金属を抽出することはむずかしくなる。金、銀、銅、そして鉄が古くから知られ、続いて鉛、スズ、より下って亜鉛、さらに近世になってアルミニウムが抽出されるのは、この結合力の強弱によっている。
自然金や自然銅あるいは隕鉄(いんてつ)は4000~5000年も前から利用されていたと考えられるが、人類が製錬をして金属をつくりだしたのも有史以前のかなり古い時代と思われる。初めは、たき火をしていた場所にたまたま還元されやすい鉱石があって、それが熱と還元性の炎のために還元され、金属や合金(青銅や黄銅)が得られたのであろう。
銅は5000年ないし6000年前にメソポタミア地方で、さらにエジプトで鉱石が採掘され製錬されたという。中国では4000年前といわれ、日本に銅が渡来したのは約2000年前と推定されている。日本で初めて銅がとれたのは7世紀末ごろである。埼玉県秩父(ちちぶ)地方から銅が献上されたので和銅と年号を改めたのは708年のことで、この年に初めて和同開珎(わどうかいちん)の銅銭がつくられた。
下って江戸時代には足尾、別子など各地で銅鉱石が採掘され、オランダや中国との貿易で大量に輸出された。元禄(げんろく)(1688~1704)のころの日本の銅の産出額は年に約6000トンともいわれ、当時としては世界一の産銅国ではなかったかという。
銅鉱石とスズや鉛を含んだ鉱石を混ぜておき、それを還元する方法で青銅がつくられる。これは硬く、また鋳込んで器物をつくれる有用な合金として古代オリエントからヨーロッパに、そして中国はじめアジア各地に、さらに日本へと伝わり、精鋭な武器や宗教的儀式用の器、像、鏡などがつくられた。古代中国では、銅とスズの配合の割合によってその合金の性質の変わることを心得ていて、それに応じて各種の器具をつくったと考えられているが、当時の冶金の知識からいって、どの程度の理解であったか疑問もある。
青銅は銅にスズと鉛を種々の割合で含んだ合金である。この鉛を手掛りに、中国、朝鮮、日本の古銅器の材料の鉱石の産地や、日本製の鏡であっても、その材料が舶載品であるか、あるいは日本産の鉱石であるか、などを明らかにする研究が行われている。これは鉛の同位体(204、206、207、208の4種がある)の存在比が産地により異なるのを利用したものであるが、このような研究がしだいに金属と人類とのかかわりを科学的に明らかにしていくと思われる(馬淵文夫ほか著『古文化財の自然科学的研究』〈1984〉参照)。
製鉄が、まず鉱石のある所で始まったことは、どこでも共通のことといえる。日本には古くから中国山脈一帯の砂鉄を中心としたたたら製鉄や、岩手地方の磁鉄鉱(餅鉄(もちてつ)といわれる)を利用した製鉄があるが、これらによる産出量はごく限られ、もっぱら刀剣などの武器に使われた。
鉄鉱石と木炭および石炭を原料とする洋式高炉が江戸末期から明治にかけて導入され、岩手県の釜石(かまいし)を中心に製鉄が行われたが、1901年(明治34)に近代的規模の製鉄所が北九州の八幡(やはた)に設立され、初めて近代的な工業的製鉄が始まったといえる。これはアメリカで当時世界最大の鉄鋼業USスチール社が成立した年でもあった。
古代・中世の技術では鉄鉱石を溶かして還元するに足る高温を得られず、半溶融状態の鉄に鍛錬を加えて鉱滓(こうさい)を絞り出し、鉄を圧接してさまざまな形のものに加工する方法がとられていた。14世紀初期に水車を利用した送風による木炭高炉が開発され、これにより溶けた鉄が得られるようになるが、この方法は木材資源の大量消費を招き、その結果18世紀ごろから石炭が使われるようになり高炉を大規模化した。しかし高炉から得られる銑鉄は炭素を吸っているので、鋳物にはなったが鍛錬することはできなかった。炭素を減らした鍛錬できる鉄は、1784年イギリスのH・コートによるパドル法の発明によって得られるようになった。さらに19世紀のなかばにH・ベッセマーが、溶鉄中に空気を吹き込んで酸化させて鋼とする方法を開発し、続いてS・G・トーマスにより転炉が発明され、また電気炉の利用も行われるようになり、19世紀後半から鋼の時代の幕が開くのである。
金属としてのアルミニウムの歴史は非常に新しい。1782年にフランスの化学者ラボアジエが明礬(みょうばん)石の中に新元素アルミニウムの存在することを示唆したが、金属として取り出されたのは1825年デンマークの物理学者エールステッドによるといわれる。2年後の、1827年にはドイツのウェーラーも金属アルミニウムの抽出に成功したが、針の頭ほどの微細な粉であったという。1854年にフランスのサント・クレール・ドビルHenri Étienne Sainte-Claire Deville(1818―1881)がウェーラーの方法を改良した還元法で、アルミニウムをより多く、安くつくることに成功した。当時のフランス皇帝ナポレオン3世の援助で1856年パリ郊外に工場をつくったが、当時は白金に匹敵するほど貴重で高価なものであった。1886年にアメリカのC・M・ホールとフランスのP・L・T・エルーとがそれぞれ独立に、氷晶石を使った溶融塩電解法によりアルミニウムを抽出する方法を発明し、アルミニウムは初めて工業的に利用できる金属となった。
日本では1894年(明治27)に大阪の砲兵工廠(こうしょう)で1キログラムのアルミニウム地金が溶かされ軍用品をつくったのが加工の初めという。当時は銀のように美しく、しかも軽いので「軽銀(けいぎん)」と称して珍重された。工場規模の製錬に成功するのはより近年のことで、1934年(昭和9)長野県大町の日本電工(現、レゾナック・グラファイト・ジャパン)においてである。アルミニウム合金であるジュラルミンの製造は1919年(大正8)住友伸銅所で試作され、住友軽銀と称され、翌1920年から生産されたが、さらに第一次世界大戦の賠償としてドイツから技術が導入された。
なお、古代中国ですでに金属アルミニウムが知られていたという報文が中国から出て話題をよんだが、これは何かを誤認したものであったという。
金属としての亜鉛が取り出されるのも比較的新しく、17世紀から18世紀にかけてのことといわれている。中国を経由して日本に亜鉛が知られるのは18世紀に入ってからのことと考えられる。
ヨーロッパでは鉱石の関係で、古くから銅と亜鉛の合金である黄銅(真鍮(しんちゅう))製品がつくられているが、中国や日本で亜鉛を含んだ銅合金がつくられるのはごく近世になってからのことである。中国、日本の古い銅器、青銅器には亜鉛は痕跡(こんせき)程度にしか含まれていない。したがって亜鉛を1%以上含んだ青銅製品は近世の贋作(がんさく)と断定されている(アメリカのフリヤ博物館の報告には多くの青銅器の分析例と真贋(しんがん)の鑑定が掲載されている)。ヨーロッパの古い文献(『旧約聖書』『新約聖書』など)には黄銅と青銅とが記載されているが、はたしてはっきり別種の合金として意識されていたかどうかは疑わしいという(スミスBertie Webster Smith著『銅の6000年』Sixty centuries of copperによる)。紀元前3000年ごろのエジプトの遺物から鉛製のおもり、耳環(みみわ)などがみつかっているが、大量に使われるようになるのは紀元前後のローマ時代からである。当時のローマでは水道管や建築物にも鉛を用い、鉛とスズの合金であるはんだの知識もあったといわれる。鉛の毒性については当時すでに警告されていたが、青銅は給水管として使うには高価すぎたので、弁などに一部使われただけであるという。日本に鉛がいつ渡来したかは明確ではないが、正倉院文書などから7、8世紀のことではないかと推測されている。
チタンや希土類金属などの新しい金属、あるいはゲルマニウムやシリコンなどの半金属が工業材料として登場してくるのは第二次世界大戦後のことである。これらの新顔の登場により金属材料の世界は多種多様なものとなったが、やはり主役は鉄鋼であり、多少影は薄くなったとはいえ銅である。また新しいものとしてはアルミニウムである。
鉄には3通りの変態があり、また炭素をその結晶格子の中に取り入れて鋼とし、加工や熱処理や、わずかの合金元素の添加によってさまざまな機械的性質をもつ何万という種類の材料を生み出す特性をもっており、しかも安価に大量に入手できる。またニッケル、コバルト以外の金属にはみられない強磁性という特異な性質を有している。アルミニウムあるいは他の無機・有機材料によって代替される部門もあるが、構造材料としてのその重要性が失われることはないであろう。
銅も銀に次ぐ高い電気伝導性と熱伝導性、容易に多様な合金を得られるという特性や接合性の良好さなど、多くの優れた特徴をもっている。使用量は減っても、その存在意義は失われないであろう。
[長崎誠三 2015年4月17日]
『幸田成康編『100万人の金属学 基礎編』(1965・アグネ/復刻版・2003・アグネ技術センター)』▽『三島良績編『100万人の金属学 材料編』(1965・アグネ)』▽『金属術語辞典編集委員会編『金属術語辞典』(1965・アグネ)』▽『長崎誠三編『金属物性基礎講座1 金属物性入門』(1977・丸善)』▽『『金属を知る事典』(1978・アグネ)』▽『廣根徳太郎編『100万人の金属学 科学編』第2版(1990・アグネ)』▽『長崎誠三編『金属用語集』改訂増補版(1995・日本金属学会)』▽『金属用語辞典編集委員会編著『金属用語辞典』(2004・アグネ技術センター)』
改訂新版 世界大百科事典 「金属」の意味・わかりやすい解説
金属 (きんぞく)
metal
古代からの文明史が石器時代,青銅器時代,鉄器時代と材料素材で区分されていることからもわかるように,人類の文明は金属技術の発展を土台としてつくりあげられてきたといってもよいであろう。われわれは青銅器6000年,鉄器4000年の歴史をもっている。とくに鉄器を使用する時代になって金属の真価が発揮されるようになった。ソロモンの壮大な石造の宮殿の建造は鉄製の道具の使用ではじめて可能となったのである。ローマ時代には7種の金属が知られ,七つの天体に擬せられてそれぞれローマの神格を与えられていた。これらは金(太陽),銀(月),鉄(火星),水銀(水星),スズ(木星),銅(金星),鉛(土星)である。日本では中国の影響で,あおがね(鉛),あかがね(銅),きがね(金),しろがね(銀),くろがね(鉄),の五金が,この順に木火土金水の五行と対応づけられていた。明治になって化学が輸入されたときに固有の元素名をもっていた金属は,五金のほかにはスズ,水銀,亜鉛,白金の4種のみであり,他の金属は現在,原音の片仮名書きで記述されている。
古くから金属は変形加工の容易な(展性,延性に富む),特有の光沢をもつ(光をよく反射する),硬い固体(変形させるには外力を必要とする)であり,熱および電気の良導体であるという性質を兼ね備えている物質として定義されてきた。しかも合金化,鍛造(加工),熱処理といった手段を組み合わせて,これらの性質を使用目的に合わせて改良できるという特質をもっている。
現在では金属と呼ばれる物質の結晶の内部構造や結晶内部での電子の挙動がはっきりとつきとめられている。科学的には金属結合をもつ物質が金属と呼ばれているが,金属結合の特徴は自由電子を結晶内部にもっているということである。金属原子は球を最も密に充てんしたときつくる対称性の高い構造が結晶をつくり,各原子の最外殻の電子は個々の原子からは遊離して特定の原子には所属しない自由電子として,結晶内部に充満する。つまり,負の電荷をもつ電子の群れの中に,電子を失った金属原子(正イオンの状態)が互いに最も密になるように規則正しく並んでおり,金属原子どうしがこのように自由電子を仲介として互いに強く凝集しているのが金属結合である。金属中の電子のふるまいの記述は量子力学によってなされるが,金属の特質である金属光沢,展性・延性,電気および熱に対する高い伝導度などが自由電子に結びつけて理解される。また展性・延性に富むという性質は,合金化や熱処理による性質の変化とともに原子のつくる結晶構造に密接に関係する。
金属の結晶構造は体心立方晶,面心立方晶,最密六方晶の3種に限られるといってよい。例外はインジウム,スズ,テルル,タリウム,ビスマスなどの非金属に近い特殊なものに限られる。現実の金属材料は微細な結晶粒の集合体としての構造をもっている。
次に金属に関して常用される分類について述べる。
非金属nonmetal
自然界に存在が知られている92種の安定元素(人工的な超ウラン元素は除く)のうち非金属元素は,水素,不活性気体元素(He,Ne,Ar,Kr,Xe,Rn),ハロゲン元素(F,Cl,Br,I,At),酸素,硫黄,セレン,テルル,窒素,リン,ヒ素,炭素,ケイ素,ホウ素の22元素である。残りの70元素が金属である。
非鉄金属nonferrous metal
鉄以外の金属という意味である。現在,材料として使われる金属の重量の約95%は鉄および鉄系合金であり,実用的には鉄は他の69の元素と区別されるだけの特別な地位を占めている。
重金属と軽金属heavy metal and light metal
実用材料としてはチタン(比重4.50),アルミニウム(2.70),ベリリウム(1.85),マグネシウム(1.74)を軽金属と呼んでいる。ほかにもカルシウム(1.55),ストロンチウム(2.6),ナトリウム(0.971),カリウム(0.86)などがあり,あとの二つは水に浮く。他の金属は重金属であるが,金(19.3)は鉄(7.86),銅(8.92)の倍以上の比重をもっている。最も重い金属はオスミウム(22.57)で,イリジウム(22.42)がこれに次ぐ。
貴な金属と卑な金属noble metal and base metal
元素の化学的性質の一つである水溶液中での標準電位系列(イオン化傾向序列の逆)で水素よりも高い電位にある金属を一般に貴な金属といい,金,銀,白金,水銀,銅などが含まれる。他の多くは卑な金属である。装飾的な用途では金,銀,白金およびその合金を貴金属precious metalという。金,銀,銅は貨幣として用いられるところから貨幣金属coinage metalとも呼ばれる。
量産金属
現代における金属の工業的生産量の割合は鉄鋼が格段に大きく(約95%),現在は依然として鉄鋼の時代であるといえる。アルミニウムはフランスで1854年に,日本では1933年になって工業的に生産されるようになった比較的新しい金属であるが,鉄鋼に次ぐ第2位の生産量を示している。銅,亜鉛,鉛の古くから知られた金属は現在でも広く用いられている。これらの鉄鋼,アルミニウム,銅,亜鉛,鉛あたりまでをコモンメタルcommon metalと呼んでおり,量産金属,普通金属などと訳している。
希少金属rare metal
量産金属以外の金属で工業的に重要な金属を総称して希少金属または希有金属と呼ぶ。現代の高度な工業技術水準を支えるのに必要不可欠な金属といった意味で使われ,定義にはあいまいなところが残される。チタンが最も新しく工業生産された金属で,アメリカでは1948年,日本では52年にはじめて生産された。第2次大戦後のジェット飛行機,ロケットなどの発達とともに,重量当りの強度が大きい(高比強度)材料として注目された。またその優れた耐熱性,耐食性を利用して化学装置材料としても重要なものとなってきている。新しい材料としての金属は今後にもさまざまな可能性を秘めている。
→金属材料 →金属組織 →合金
執筆者:増子 昇+伊藤 邦夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「金属」の意味・わかりやすい解説
金属【きんぞく】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
化学辞典 第2版 「金属」の解説
金属
キンゾク
metal
金属元素のことであるが,実用金属の地金,合金を含めて金属とよぶこともある.金属性(展延性,熱,電気の良導体,金属光沢など)をもつ元素で,化学的には陽イオンになりやすく,非金属元素および酸と反応してイオン性の塩をつくる.金属,非金属(金属と化合するもの:メタロイド)の区別は物性の両極面をいうものであるから,化学元素のうちには半金属元素とよばれ,金属,非金属の中間の性質をもち,その結晶構造により金属あるいは非金属いずれの性状も示すものがある.元素が金属性を示すことは,金属結合とよばれる原子間の化学結合により説明され,金属性は周期表中で元素の帰属を定める重要な性質である.アルカリ金属元素のほうが,日常代表的な金属と思われている金,銀,銅などより化学的に金属の反応性が大きく典型的な金属性をもっている.
出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「金属」の意味・わかりやすい解説
金属
きんぞく
metal
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
栄養・生化学辞典 「金属」の解説
金属
世界大百科事典(旧版)内の金属の言及
【固体】より
…原子が集まって固体をつくるときには,原子間に電子のやりとりが起こる。そのやりとりのしかたによって,固体はイオン結合物質,共有結合物質,金属結合物質に分類される。イオン結合物質の典型的な例としては,食塩の主成分である塩化ナトリウムNaClをあげることができる。…
【半導体】より
…金属のような導体(電気伝導度104~106Ω-1cm-1)とガラスや磁器などのような絶縁体(10-20~10-12Ω-1cm-1程度)に対し,弱いが若干の電気伝導性(例えば10-10~102Ω-1cm-1程度)を示す一群の物質を半導体と総称する。しかし半導体の特徴は,その電気伝導度の大きさよりも,むしろその電気的性質が温度や微量の不純物の存在などによって大きく変化することであり,これがさまざまな応用にもつながっている。…
※「金属」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...