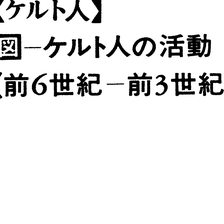改訂新版 世界大百科事典 「ケルト人」の意味・わかりやすい解説
ケルト人 (ケルトじん)
Celts
西ヨーロッパの歴史世界を構成する民族の一つ。ギリシア語でケルトイKeltoi,ラテン語ではケルタエCeltaeまたはガリGalliと呼ばれた。広域にわたる分布のため,人種的特性は一定しない。史上重要な地位を占めながら,その評価は長い間なおざりにされてきたきらいがある。その事情は以下にみるとおりであるが,近年,再評価の気運が高まり,西欧文明の一翼を担ったありさまが,考察の対象となってきている。
ケルト人は,インド・ヨーロッパ語系諸族の一支族として,前1500年ころまでには,ドナウ,ライン川沿岸の森林地帯に移動し,定着したとみられる。前9世紀以降,これらケルト人は,ヨーロッパ大陸各地に居住地を拡大し始め,その後数世紀間に,ライン下流を含むガリア全土,イベリア半島,ブリテン島,さらには北部イタリアから,一部は小アジアにまで達した。前750年から前500年にかけての時期に,ヨーロッパを覆ったハルシュタット文化が,ケルト人を主要な担い手とするか否かについては,見解が分かれるが,いずれにせよその時期に,ケルト人は鉄器使用の段階に入った。前5~前1世紀中葉にわたるラ・テーヌ文化によって,ケルト人は地中海文明とりわけギリシア古典文明との接触を深め,装身具,戦闘用施設,武器において高い水準に達した。ここに,のちにヨーロッパと呼ばれる地理的版図の大部分は,ケルト世界に統合された。前5~前4世紀のギリシア本土侵入,都市国家ローマの略奪は,こうしたケルト人の勢力拡張の一側面である。なお,ケルト人(ケルトイ)の呼称は,ギリシア人の用語法に由来するもので,彼らの自称ではない。
前58年に始まるカエサルのガリア進攻は,このケルト世界に対するローマの圧迫の開始を告げた。ガリアのケルト諸族は抗戦ののち,前1世紀末までにローマの支配下に入った。その際,ケルト人の英雄ウェルキンゲトリクスのアレシア(中部ガリア)における抵抗は,長く歴史のなかで記憶された。ついでイベリア半島,ライン・ドナウ地方のケルト人がローマ人のもとに降って,同化への道をたどった。ラ・テーヌ期にブリテン島に渡ったケルト諸族は,大陸のケルト人とその文化的差異を明らかにし始め,ここに〈島のケルト〉と〈大陸のケルト〉の二分が生じた。前者のうち,ブリテン島南部のものは,ローマ人に同化したものもあるが,多くはローマ支配下においても独自の発展を示し,もしくはブリテン島北部,西部,およびアイルランドに逃れてローマの支配を拒んだ。紀元後,ゲルマン人の侵入もあって,〈大陸のケルト〉はその独自性を失い,少なくとも表面上は,南方のローマ世界と北方のゲルマン世界の対抗のなかに埋没していった。他方,〈島のケルト〉はアングロ・サクソン人の進出にも抵抗したが,〈アーサー王伝説〉はその際の民族的記憶が結晶したものであると考えられる。スコットランド,ウェールズ,アイルランドはケルト世界のうちにとどまり,またブリテン島から逃れた一部の部族は,大陸に渡ってガリアのブルターニュ地方に入った。この部族はブルトン人として,現在まで独自のケルト文化を保ちながら,その地に居住している。8世紀末以降のノルマン人の進出は,フランク王国のようなゲルマン人国家にとってと同様に,ケルト人に対して大きな打撃を与えたが,10世紀末までにはその脅威は去った。
以上のように,ケルト人は先史時代から古代,中世にかけてのヨーロッパにおいて中心的役割を果たしたが,単一の民族としての現実的な統合や,観念的な民族意識をもっていたわけではない。諸部族は相互に競合・闘争を繰り返しており,内的差異は小さくはなかったであろう。また古代における諸部族のケルト人同定には不確実なものもある。さらには,地中海世界にもたらされた情報にもとづいて記述されたケルト人像(たとえば,ストラボン,リウィウス,カエサルによる記述)は,実像とかけはなれるところが多いであろう。これらの多面性や不明点は,近年ヨーロッパ考古学界の発掘作業の進行にともなって,急速に解明されつつある。
この段階におけるケルト人の社会では,古典作家たちが記述したように,部族ごとに社会統合が進みつつあり,支配身分たる貴族の固定化が明らかになっていたと思われる。自由身分の戦士と不自由身分とが存在し,これに加えて,特異な身分としての神官(ドルイド)が存在した。祭祀者たるドルイドは,特権身分として世襲され,ケルト人の文化的伝統の体現者として,政治・社会を指導していた。ローマの脅威が表面化した時期以降,〈島のケルト〉の間には,複数の王国的統合が顕在化し,各地に割拠してケルト人社会の枠組みを構成した。封建制,農奴制,キリスト教会など,新たに導入される社会・文化的制度は,これらケルト人国家のもとで受けいれられた。〈アーサー王伝説〉に表現されるような戦士集団の特異な構成や,後世のスコットランドで知られるクラン集団など,ケルト人の特異な社会的特質が温存され,もしくは助長された。
ケルト文化は初期ヨーロッパにおいて,指導的な地位を占めた。ストーンヘンジやメンヒル,ドルメンなどの巨石記念物を,ケルト人とりわけドルイド神官の創設に帰する憶測は,現在では否定されたが,それらの祭祀的使用,装飾造形技術には見るべきものがあった。のち7,8世紀に,ケルト世界で制作された彩色装飾写本(たとえば《ケルズの書》)のように,ヨーロッパが誇る文化遺産が生まれた。また,吟遊詩人(バード)による詩編は,中世ヨーロッパに大きな影響を与えた。ケルト人は文字化された知識体系を残さなかったが,口承による多くの神話・伝承を作り上げていった。
キリスト教は,ドルイド神官の祭祀に対抗しつつ,ケルト世界に導入された。パトリックのアイルランド伝道は,その一道標をしるした。6世紀に地中海世界からもたらされた修道制は,アイルランドで独自の発展をみた。コルンバヌスに率いられたアイルランド修道制は,スコットランド,イングランドから,ヨーロッパ大陸にもたらされ,その厳格な禁欲苦行の修道にケルト的伝統をしるしながら,ヨーロッパ・キリスト教世界を席巻した。その隆盛が過ぎたのちも,ケルト世界はローマ・カトリック教会に包摂されながら,独自の文化を守りつづけた。
中世以降にあって,〈大陸のケルト〉の存在は,もはや識別不能であり,他方,〈島のケルト〉の諸国家は西方からの強い圧迫を受けるようになる。ウェールズは13世紀にイングランド王国に,ブルターニュは16世紀にフランス王国に併合された。アイルランドは17世紀に植民地化されたのち,1800年にイギリスに合併,またスコットランドも同君連合ののち18世紀初めに合併した。社会と文化の独自性は,それにともなって急速に希薄になっていった。
ケルト人およびケルト文化への着目が唱えられ,復権が語られるようになるのは,主として19世紀以降のことである。アイルランドの政治的独立を求める運動は,ケルト人の自覚を促し,19世紀後半に〈アイルランド文芸復興〉と呼ばれる民族文化運動が興った。20世紀にアイルランドが独立してのち,ウェールズ,スコットランド,ブルターニュにおける政治的・文化的運動が,ケルト民族のアイデンティティを模索し始めた。やがて,このようなケルトからの自己確認作業は,ヨーロッパのなかに知的刺激を与えるにいたった。それ以前にも,好事家の間で,ケルト神秘主義への嗜好から,説明困難な文化事象をドルイド信仰に帰する試みが行われたが,近代学問のなかであらためて科学的検証に耐えうるケルト再評価が唱えられている。そこでは,太古,古代,中世にケルト人が果たした役割の重視だけではなく,ケルト人が時代をとおして,自然,超自然,人間に対して抱いてきた観念や心性,思考の分析の必要性が主張される。考古学,神話学,民俗学,歴史学など多分野にわたるこれらの作業の成果は,今後を待つべきところが多いが,それをとおして,西ヨーロッパの歴史世界が黙殺し,忘却したヨーロッパ的価値の固有の一端を発掘し,ひいてはヨーロッパ理解への新たな経路を見いだす可能性が開けてきたと言うべきであろう。
執筆者:樺山 紘一
神話と伝承
ケルト人の神話は,総じて自然の神格化であるギリシア・ローマの神々がつくっているような,役割の明確な,体系化された神話世界とは異なり,神々と人間と妖精とが自在に交渉し,神と人間と鳥と動物とが,さまざまに転身する流動的な神話世界である。その底には,霊魂不滅と生命の転生思想とが,色濃く流れている。まずヨーロッパ大陸に拡散した〈大陸のケルト〉の神話体系については,カエサルが《ガリア戦記》のなかで,〈ガリア人は父なる神ディス(ガリアではケルヌノスで,闇と死と地下の神)の子孫であると信じており,神話はドルイドによって語りつがれていた〉と言っている。ヨーロッパ大陸のケルト人は,早くからローマ化されたためもあって,ドルイドのバード(語り部)が伝えていた口碑伝承は記録されておらず,したがって天地創造神話や体系だった神々の話は現存していない。後世の研究者は,ケルト人の信仰的勒記や伝承記録から374柱(おもなもの69柱)の神を集めたというが(G. ヘルム《ケルト人》1975),ローマの神々に該当するテウタテス(ローマのメルクリウス),ベレノス(アポロ),エスス(マルス),タラニス(ユピテル),ケルヌノス(プルト),ブリギド(ミネルウァ)などがおもなもので,神像がつくられて神殿に祀られ,ある神は生贄を捧げてあがめられていた。
一方,アイルランドやスコットランド,ウェールズに定着した〈島のケルト〉がもつ神話は,吟遊詩人たちに口碑によって伝えられたものが,7世紀から12世紀の間に現在のような形になったが,それらはアイルランドに渡来したパトリックと修道僧たちの筆写による古文献として残っている。おもな古書としては,アイルランドの《侵略の書》(10世紀),《赤牛の書》(11世紀),《レンスターの書》(12世紀),《バリモートの書》(14世紀),《レカン黄書》(14世紀),スコットランドでは《ディーアの書》(11,12世紀),《リズモアの書》(16世紀),ウェールズでは《カーマーゼン黒書》(12世紀),《マビノギオン》を含む《ハーゲスト赤書》(14世紀)などである。
《侵略の書》によれば,前1500年ころ,相次いで5部族(パーソロン,ニュブズ,フィルボルグ,トゥアハ・デ・ダナーン,マイリージア)が渡来したと伝えられ,各部族の戦いによる支配交代の歴史が,古代神話を形づくっている。なかでもアイルランドの祖先といわれるマイリージアに敗れたトゥアハ・デ・ダナーンTuatha Dé Danann(女神ダヌーの種族の意)がしだいに神格化されていった。ダヌーDanuは豊饒と富の女神,ルーLughは太陽・光・知恵の神,リルLirは息子マナナンMananannと共に海の神であり常若(とこわか)の国の王である。またダグザDagdaは大地の神であり,オグマOgmaは雄弁・詩歌の神で,ケルト最古の文字オガム(オガム文字)の発明者とされ,エーンガス・オグAngus Ogは美・若さ・愛の神で,ヌアザNuadaは戦いの神でありモリガンMorriganは死と血を求め戦場を飛び回る戦いの女神とされ,これらの神々にまつわる話がさまざまに伝えられている。またこのダーナ巨人神族(女神ダヌーの種族の別名)は,マイリージア族に敗れると,海のかなたに逃れて〈常若の国〉をつくって住み,また土塚や円形土砦の遺跡,あるいは石壕や墳丘に隠れ,地下に楽園をもつ妖精シーsidhとなり,目に見えない種族としていまも存在すると信じられている。またダーナ巨人神族は人間と交渉をもって英雄を生み,例えば太陽神ルーは蠅に変身して女王の盃に入り,飲まれて子宮に落ちてクホリン(クフーリン)Cuchulinnとなり,一方,戦いの神ヌアザの末裔に,フィンFionやその息子オシーンOisin,孫オスカーOscarらの英雄たちが現れている。それらの英雄神話は,二つの系列に分けられる。
(1)1世紀ころのアルスターを中心に,コンホバル・マックニェッサ王に仕えた英雄クホリンたち,すなわち〈赤枝の戦士団〉の物語群。これは《クーリーの牛争い》が中心の物語で,コナハトの女王メイブが夫のアリイルと財産くらべの末,アルスターの赤牛を手に入れようとして起こした両国の間の戦いの物語である。超人的な活躍ぶりを繰り広げる英雄クホリンの生誕から終焉までの物語や,ディアドラとニッシャの悲恋,エーディンの求婚の話などがおもなものである。(2)3世紀の英雄王フィン・マクウァル王とそれに仕えるフィアナ騎士団の物語で,なかでもフィンの息子で詩人のオシーンと妖精王の娘金髪のニアブとの恋や,《トリスタンとイゾルデ》の基ともみなされるディルムッドとグラーニアの悲恋や勇敢な武人たち,ファーガスやオスカーの挿話がある。
これらの話を近代になってマクファーソンが翻案集大成して《オシアンの詩》(1762-63)として世に出したため,ワーズワースをはじめゲーテ,シャトーブリアンら各国の詩人作家たちに影響を与えた。また古文書を基にアイルランドのオグレーディStandish James O'Grady(1846-1928)が書いた《アイルランド史》(1878-80)は,19世紀のW.B.イェーツ,グレゴリー夫人,J.M.シング,エー・イーAE(本名George William Russell,1867-1935)らを刺激して神話を題材としたさまざまな作品を書かせ,アイルランド文芸復興運動を促進させた。
→ガリア →ケルト語派 →ケルト美術
執筆者:井村 君江
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「ケルト人」の意味・わかりやすい解説
ケルト人
けるとじん
Celts
インド・ヨーロッパ諸族の一派。紀元前5世紀から前1世紀にヨーロッパ中部および西部で活躍した民族。ギリシア語でケルトイ、ガラトイ、ラテン語でケルタエ、ガリイ(ガリア人)とよばれた。
[長谷川博隆]
初期
原住地、起源については議論があるが、南西ドイツ、スイス、東フランスの青銅器文化の担い手であり、初期鉄器時代のハルシュタット後期、後期鉄器時代のラ・テーヌ最初期に、シャンパーニュ、ザール、モーゼル、中部ライン地方において、民族としてのケルト人が形成されたと思われる。なお、ギリシア、エトルリア文化との交流も明らかな北西アルプス地方のハルシュタット文化は、彼らが担ったと推定される。ついで、前5世紀の、初期ラ・テーヌ時代のシャンパーニュ、中部ライン地方の貴族の墳墓および出土品は、初期ケルト美術の精華を示してくれる。
[長谷川博隆]
移動期
(1)「西方のケルト人」 イタリアに侵入したケルト人は、前387年(または390年)のアッリアの勝利後、ローマを荒らし(ケルト人の侵寇(しんこう))、その後、北イタリアのアドリア海岸に定着した。一派のインスブレス人はメディオラヌム(ミラノ)を首邑(しゅゆう)とし、ボイ人はエトルスキの町フェルシナをボノニアとした。またアドリア海岸にはセノネス人が定住する。前293年にローマ軍に敗れたのちは、北イタリアのケルト勢力も衰えたが、ローマも各地に植民市を設けてこれに相対した。ケルト人のスペインおよびブリテン島侵入の時期については諸説あるが、ラ・テーヌ期にさかのぼると推定される。ガリアの地の大部分のケルト化も進み、イベリア半島では、先住のイベロ人と混血してケルト・イベロ人が形成され、一方、大陸からのたび重なるケルト人の渡来によりブリテン島のケルト化も進み、現在でも、アイルランド語、スコットランド・ゲール語、ウェールズ語として、ケルト語は生き続ける。(2)「東方のケルト人」 前4世紀ごろ、一派はボヘミア(ボイ人からきた名称)、モラビア、ハンガリーを経てルーマニア北部に入り、他の一派はノリクムを経てダルマチアに移動した。前279年ごろにはデルフォイを侵寇している。北に転じた一派はシンギドゥヌム(ベルグラード)を建て、別の一派はトラキアに入って王国を建設し、その影響力は南ロシア平原まで及び、ケルト、スキタイ混交文化も生まれた。さらに、小アジアのビテュニアの王位継承に干渉した一派は、その後、前3世紀初めフリギア高原に定着し、ガラティアとよばれる地域をペルガモン王から与えられ、小アジアの地にケルト人社会の伝統を保持し続けた。
[長谷川博隆]
後期
前1世紀には、いわゆるオッピドゥム(城市)文化が中部ヨーロッパの戦士、農耕民のケルト人の世界に確立した。しかし、カエサルのガリア戦争に対して続けられた自由を求める闘争も、前52年に終止符を打ち(ウェルキンゲトリクスの率いる大蜂起(ほうき))、前16~前10年には、大陸の最後のケルト人の拠点もローマの支配下に入り、ケルト人の地、ガリアは完全にローマ化する。
[長谷川博隆]
政治・社会・文化
ガリアやブリテン島では、政治的には、段階的なクリエンテス制(上下の保護隷属関係)に基づく一種の貴族制的体制が保たれたが、ついに統一国家を形成することはなかった。経済的基盤は、古くは血縁的な共同体に属する土地にあり、貨幣の鋳造も行われた。一般に、ケルト人の世界は、王、神官、戦士貴族および自由農民からなったが、城市や貴族の墳墓の発掘によって、その社会構成も明らかにされつつある。城市の建設、商・工業の発展によって貴族の権力が確立、伸長してゆくが、それとともに神官(ドルイド僧)層の力も、宗教、文化、政治に及んでゆく。ドルイド教の教義、儀式は、文字化されず口伝によるため、ギリシア・ローマ人の叙述、遺物、伝承によって再構成せざるをえない。彼らは、インド・ゲルマン人的な宇宙神を中心とする独特の神の体系をもっていたと推定されるが、霊魂不滅を信じ、自然崇拝が盛んで、聖樹、聖獣、聖泉、聖山信仰などもみられた。抽象的、記号的性格の造形感覚をもち、その美術は、抽象文様、形態のリズム化を特徴とし、木偶(もくぐう)などの木彫、装身具・武具としての金工細工などに卓越した才幹を示した。
[長谷川博隆]
『ゲルハルト・ヘルム著、関楠生訳『ケルト人』(1979・河出書房新社)』
百科事典マイペディア 「ケルト人」の意味・わかりやすい解説
ケルト人【ケルトじん】
→関連項目アイルランド[島]|イギリス|ウェールズ|英語|ガリア|カルニュクス|ゲルマン人|ゴール語|フランス|ブリトン人|ブルターニュ|ラ・テーヌ文化
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ケルト人」の意味・わかりやすい解説
ケルト人
ケルトじん
Celtae; Keltoi; Celts
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
山川 世界史小辞典 改訂新版 「ケルト人」の解説
ケルト人(ケルトじん)
Celts
インド・ヨーロッパ語族の一つ。人種的には一定しない。前10~前8世紀頃原住地のライン川,エルベ川,ドナウ川間から出て,前5~前4世紀頃ガリア,ブリタニアに広まり,前3世紀にはアナトリアにも至った。牧畜経済社会で,冶金術による鉄,そのほかの金属武器を使用し,好戦的。多数の首長制団体に分かれる。ガリアでは前1世紀,ブリタニアでは後1世紀にローマの支配下に入り,5世紀以降はゲルマン民族の圧迫を受けた。その言語・風習は,今日アイルランド,ウェールズ,ブルターニュに残存する。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
旺文社世界史事典 三訂版 「ケルト人」の解説
ケルト人
ケルトじん
Celts
ゲルマン人が侵入する以前の西ヨーロッパを支配した。原住地は南ドイツと考えられるが,前7世紀までに現在のフランス・イタリア・スペイン・アイルランドなどに広がり,前4世紀にはバルカンにも達した。ローマ人がガリアと呼ぶのがこれである。最盛期はラ−テーヌ文明時代で特異な鉄器文化をもち,馬具や戦車の車などが出土している。カエサルの侵攻に始まるローマの圧迫に対して抵抗したウェルキンゲトリクスは,民族的英雄とされるが,前1世紀にはローマの支配下に置かれ,同化されていった。現在ゲーリック語などのケルト語派は,使用地域・人口とも非常に限られている。ケルト社会は,ドルイドと呼ばれる神官が社会の指導者であったとされており,また彼らの伝説的英雄を題材とした『アーサー王物語』は騎士道物語の名作として名高い。
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内のケルト人の言及
【アイルランド美術】より
…中でもニューグレンジNewgrangeのそれは豊富な幾何学文装飾のゆえに名高い。青銅器時代に入り,その抽象表現は,金属という展延性をもつ素材によって大いに発達するが,その高度な開花をみたのはケルト人と共に到来した鉄器文化の時代であった。ローマ帝国の進出と共に大陸やブリテン島のケルト人がローマ化したのに対し,ローマ征服を免れたアイルランドのケルト人は,黄金やエマイユ(七宝)の色彩への興味とその抽象的造形本能とを保持し,いっそう展開させた。…
【イギリス】より
… グレート・ブリテン島にもともと住みついていたケルト系の民族と,北ヨーロッパ大陸から海を越えて侵入して来たゲルマン人(アングロ・サクソン人と呼ばれる)とは,はじめは対立抗争していたが,しだいに和解し融合していった。イギリス人といえばすぐにアングロ・サクソン人と考えたくなるが,文化,芸術の面から見ると,先住民族ケルト人の果たす役割が非常に大きい。例えば,イギリスのみならずヨーロッパにまで広く及んでいる〈アーサー王伝説〉は,本来ケルト民族の生み出したものであり,それが地中海沿岸地方から渡来して来たキリスト教思想と混合して変質したと考えられる。…
【イベリア半島】より
… 前1000年,イベリア史は再び大きな変革期を迎える。ピレネー経由でケルト人が鉄器を携えて渡来し,後にギリシア人がイベレスと呼んだ半島先住民と混血した。同じ頃,南部沿岸には東方からフェニキア人が特にスズ(錫)を求めて来航,今日のカディスやマラガの前身を築いた。…
【ガリア】より
…古代ローマ人が〈ガリGalliの居住地〉に与えた名称で,ガリとは,ギリシア人がケルタイと呼んだケルト人のことである。フランス語,英語ではゴールGaule,Gaul。…
【ゲルマニア】より
…ガリア北東部のライン左岸,ラインラントのローマ化はカエサルによる占領に始まった(前58‐前51)。ラインラントからベルギーにかけては,トゥングリ,トレウェリおよびネルウィイなど,ケルト人と混血した〈ライン左岸のゲルマン人Germani cisrhenani〉が定住し,アルザスからブルゴーニュ東部では,ヘルウェティイ,ラウラキおよびセクアニなどのケルト人に占められていた。皇帝アウグストゥスのガリア行政区の設定(前16)では,属州ゲルマニアはいまだ存在しないが,彼の軍事行動はライン川を越えてエルベ川まで延び,兵站(へいたん)基地のラインラントのローマ化を促した。…
【地名】より
…このような民族移動にともなう地名の歴史的層序は,島嶼(とうしよ)国で数度の移動の波が及んだイギリスで特に顕著に読みとれる。 イギリスに明瞭な最古の地名を残したのはケルト人であり,多くの地域にまたがるゆえに単一の定住者の従属物でない河川名(例,エーボン川),長く定住者をひきつけなかった丘陵名(例,モルバーン丘陵)に古いケルト地名が残存している。ケルト人のイギリスを征服したローマ人の場合は,その支配の性格から都市名にいくつかの痕跡を残し,ラテン語のcastra(陣営),colonia(植民市)に由来するチェスターChester,リンカンLincolnなどが誕生した。…
【ドルイド】より
…古代のケルト人の信仰をつかさどった聖職者,司祭階級。前7世紀ころから明確に姿を現す。…
【フランス】より
…メンヒルやドルメンに代表される巨石記念物は彼らの所産であり,その分布状態からも,彼らがガリア諸地域に広範に定着していたことがわかる。 フランス人がしばしば自分たちの最も古い祖先と考えているケルト人は,実は,前9世紀ころより,ドナウ川流域から移動してきた新しい集団であった。彼らは優れた鉄器文化をもち,前5世紀ころには,ラ・テーヌ文化の名で知られる最盛期を現出した。…
【ブリトン人】より
…インド・ヨーロッパ語系諸族のうちのケルト人の一派でキムリ人Cymryともいう。前4~前2世紀にヨーロッパ大陸からグレート・ブリテン島南部に移動し,多数の小部族王国をつくって定着した。…
【ブルターニュ】より
…この巨石文化は,アイルランドやウェールズから大西洋岸沿いに南下し,地中海にまで及ぶ広大なひろがりをもつものであるが,ブルターニュは,その豊かな遺跡群を今日にまで伝える最も重要な地方の一つである。 ブルターニュに深い痕跡をとどめることになるケルト人がこの半島にまでやって来たのは,はるかのちの前6世紀のことであった。ここにケルト時代が始まるわけであるが,誤解されてはならないのは,このケルト文化が,そのまま中世にまで続いたのではないことである。…
【もてなし】より
…〈ゼウスは嘆願者とよそから来た者のための報復者で,旅人の神,敬虔な旅人を見守りたまう神〉(同),〈他国の人の守り神なるゼウス〉(同),〈神々は異国の人に身を変え,ありとある様に身をやつして,人間の非望と分別とを取調べに町々を歩き回る〉(同)。 ケルト人における旅人の接待についてとくに特徴的なことは,その共同体的な性格である。ケルト社会では王・族長は,親族的なものと信ぜられた共同体の長であり,彼らは族民を支配するが,同時に共同体成員の困窮者を扶養する義務を負い,しばしば定期的な宴に族民を招待しなければならなかった。…
【ラ・テーヌ文化】より
…1857年,鉄製の武器や装身具など多量の遺物が発見された,スイスのヌシャテル湖北岸のラ・テーヌLa Tène遺跡によって命名された。ギリシア,ローマの古典時代作家の記録や,カエサルの《ガリア戦記》に登場するケルト人の残した文化とされている。 この文化に特有の遺跡としては,初期に多い首長墓と,後期に属するオッピドゥム(オピドゥム)oppidumがある。…
※「ケルト人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...