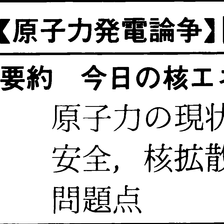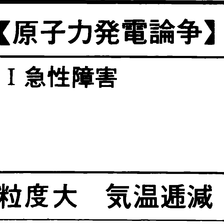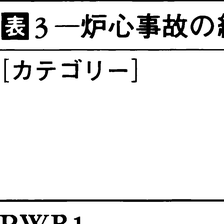改訂新版 世界大百科事典 「原子力発電論争」の意味・わかりやすい解説
原子力発電論争 (げんしりょくはつでんろんそう)
原子力発電をめぐる論争には膨大な論点が含まれている。表1は1977年にアメリカの有力なシンクタンクであるマイター社が作成した報告書〈原子力をどうするか--その課題と選択Nuclear Power Issues and Choices〉の見出しである。この報告書はカーター政権の原子力政策の青写真となったもので,その重点は核拡散問題におかれているが,原子力をめぐる論争点がいかに複雑かつ広範なひろがりを有するものであるかを示している。このような果てしない論争の生じる根拠は,原子力技術が不確実なものである一方,核エネルギーのもつ巨大な可能性について大きな期待がもたれていることによる。
こうして論争には必然的に政治,経済,社会,道徳にまで及ぶあらゆる側面が関与することとなり,それらが先端的技術でありながら不確実な技術であるために,科学者間でも評価の一致しない問題として展開されることとなる。本項目ではおもに安全性にかかわる問題について述べ,他は問題点の指摘にとどめる。
安全性
原子力発電の安全性は,核エネルギーの利用に関する論争の中心的課題である。原子力発電の潜在的危険性の巨大さを否定する人はほとんどいない。現在,世界の原子力発電の主流となっている軽水炉を例にとってみると,その1基当りの平均的電気出力は100万kWであるが,この規模の原子炉では1日当り約3kgのウラン235が核分裂し,したがって約3kgの核分裂生成物(死の灰)が蓄積される。広島原爆は約1kgのウラン235の核爆発であったと推定されているので,1日当り3kgの死の灰の危険の巨大さはほぼ想像できるであろう。たとえば電気出力110万kWの加圧水型炉(PWR)を約1年間連続運転した後の蓄積最大放射能量は約170億キュリー(1キュリー=3.7×1010Bq)にも達する。大気圏内の原水爆兵器実験により全地球にばらまかれたストロンチウム90の量は約920万キュリーと推定されており,一方,電気出力100万kWの原子炉を約1年運転した後のストロンチウム90の蓄積量は500万キュリーである。また,希ガスなどの揮発性の核分裂生成物は全放射能量の2割もあり,これらは環境にもっとも漏洩しやすい。原子力発電所の工学的安全性(=危険性)とは,この閉じ込められた膨大な放射能が平常時および事故時に,人間あるいは環境への影響を考慮して決められるある定められた基準以上に環境に放出されないように保証されることである。したがって,安全をめぐる論争は,この基準そのものの適否,万一の場合に備えて設けられた安全装置や,事故を局限するための格納容器などの性能や完全性をめぐって生ずることとなる。
許容量
人間に放射線障害をひき起こす可能性のある最小被曝線量については,現在でも科学者間の論争は続いている。急性障害については早くから認められていたが,受ける放射線がある量以下であれば害はないものと考えられていた。その量を許容線量と呼んだが,許容線量の最初の国際勧告値は1日当り0.2レントゲン(1レントゲン=2.58×10⁻4C/kg)という高いものであった。広島,長崎の原爆によるそれまで考えられなかったほど多数の人々の集団被曝,核実験にもとづく放射性降下物による全地球的汚染とそれにもとづく低線量被曝など核エネルギーの軍事利用と核軍拡競争の過程で発生した放射線障害についての調査研究の結果,少なくとも障害防止のためには,いかに微量であっても放射線はそれなりの危険性をもつと考えるべきであるとする〈比例説〉が大多数の見解となった。こうして許容量とは,武谷三男の〈やむをえず放射線の照射をある利益のためにがまんする量〉であるという考え方が国際的にも認められた。
しかし概念の確立は決して論争の消滅を意味しない。原子力発電の普及に伴って原子力産業人口の増大,原子力発電所周辺人口への影響の考慮の必要性など,従来の限られた職業人に対して考えられた許容量とは異なる評価を行う必要が生じたからである。また利益の評価は当然,推進者側と批判者側とでは異ならざるをえないため,複雑な論争を生むことになった。1969年にアメリカのゴフマンJohn W.GofmanとタンプリンArthur P.Tamplinは,放射線照射によって癌発生率が自然発生率の2倍となる線量(倍加線量という)を求め,それから1958年の国際放射線防護委員会(ICRP)などの勧告で推定した晩発性障害の値が低すぎることを指摘し,許容線量を100分の1に切り下げねばならぬとした。2人がどちらもアメリカ原子力委員会U.S.Atomic Energy Commission(AEC)所属の研究者であったことが,この論争を先鋭化させた。連邦放射線審議会はアメリカ科学アカデミーと連邦研究会議に依頼して,この問題の再検討を行い,72年にゴフマンとタンプリンの指摘を大筋において追認する〈電離放射線による生物学的効果に関する諮問委員会報告〉を提出した。しかし低線量被曝にもとづく晩発性障害や遺伝的影響の研究は,全体として困難な研究分野であり,論争は継続されることとなろう。
これらの論争の成果として,原子力発電所周辺の環境基準を年間5ミリレム(1ミリレム=10⁻4Sv)以下とすることが目標値として設定されるようになり,いわゆる許容量はこの半世紀間に最初の勧告値からみれば1万分の1以下に切り下げられたことになる。現在は前記諮問委員会報告の結果が環境影響評価によく用いられているが,核燃料サイクルのあらゆるステップにおける放射線影響の評価はきわめて不十分である。いままでもっとも信頼できるデータとされてきた広島,長崎の被曝影響評価のデータについて,最近とくに照射線量の推定値について根本的な見直しが必要なことが明らかとなり,日米両国の協力で再検討の作業が進行しつつあることはきわめて注目に値する。
災害評価研究と損害賠償法
1954年アメリカは原子力法を改正し,いわゆる原子力平和利用政策を推進,政府の保有する核情報の一定の解除とともに原子力産業への民間資本の進出が奨励されることとなった。しかし原子炉の潜在的危険性の大きさは当然予想されたため,もし大事故の際の損害賠償が事業者の責任とされるなら,通常の損害保険の範囲を超え補償不能となることが想定された。アメリカの上下両院合同原子力委員会は,AECに対して原子炉事故の災害評価研究を行うよう要請した。この結果57年に〈大型原子力発電所における重大事故の理論的可能性とその結果〉と題する報告が公表された。この報告書は研究を行った研究所名にちなみ,一般に〈ブルックヘブン報告〉と呼ばれる。この調査が想定したもっとも重大な事故では,熱出力50万kWの原子炉に含まれる放射性物質の50%が放出されると,最悪の気象条件下で(住民退避に24時間を要するとして),死者0~3400人,負傷者0~4万3000人,汚染区域は18~15万平方マイルに及び,財産損害は70億ドルに達すると推定していた。
この報告はその後の原子力発電論争において,批判派によって原子力発電の危険性の根拠とされるにいたった。これに対する推進派の代表的反論は,〈この報告は時代おくれであり,最近の原子炉は安全のための甲冑一そろいを組み込んでいる……〉(レイDexy Lee Rey。74年当時のAEC委員長)といったものであった。57年にはイギリスのウィンズケール原子炉で事故が起こり,大量のヨウ素131などが環境に放出された。いずれにせよ〈ブルックヘブン報告〉は民間企業の懸念を深めるものであったから,社会に対する責任負担という危険を冒すことなく民間企業を原子力産業に参加させる方式を見つけることが必要であると考えられ,その結果,同年連邦議会はプライスMervin Price上院議員とアンダーソンClinton P.Anderson下院議員の提案になる,原子力損害における企業の責任を限定し,民間の保険業者が負担する額を超える分について政府が補助金を支出することを内容とする法案(プライス=アンダーソン法)を採択した。日本も61年にこれとほぼ同じ考え方の原子力損害賠償法を制定している(原子力災害補償)。この制定に関連して科学技術庁は原子力産業会議に〈大型原子炉の事故の理論的可能性及び公衆損害額に関する試算〉を委託した。試算に用いられた仮想発電所の立地条件,災害評価の結果を表2に示す。
このようにして制定されたプライス=アンダーソン法などは,その存在そのものが安全論争の焦点となった。批判派の主張は,もし原子力発電の安全性が推進派の主張するように高いのなら,国の援助は不要なはずであるという点にある。アメリカでは同法が10年の時限立法であったため,10年後に延長すべきか否かが議会論争の焦点となった。〈原子力産業はまだベービーで,国の乳房が必要なのか〉といった批判は,原発推進派議員からさえ出された。これに対し推進派の主張は,万一の災害に際し公衆を防護するための他の方法では不可能な利点が得られるという点にある。〈統計的データがないような分野では民間保険は正常に機能しないから,政府の介入が必要で,過去においても収穫保険,銀行預金保険,船舶保険,失業保険等の例がある〉というのが産業界側の主張であった。67年に同法は延長されたが,注目すべきは65年に当時のシーボーグAEC委員長が議会に対し同法の継続を要請したことであった。
AECは64年〈ブルックヘブン報告〉の見直しを計画,報告書を準備したが発表されなかった。この報告書は73年になって〈憂慮する科学者同盟Union of the Concerned Scientists(UCS)〉の手により,情報公開法を活用してその全容が明らかにされた。そこでは,原子力発電所が大型化したため,災害の規模も大きくなり,汚染区域の大きさはペンシルベニア州(日本の面積の約1/3)に匹敵し,かなりの規模の核兵器のそれより深刻であるとされていた。同時に明るみに出たAECの内部資料は,内部で激しい異論があったことを示していた。こういう事情は原発批判派のAECの中立性に対する疑惑を強め,いわゆる信頼性ギャップを形成することとなり,74年AECを解体してアメリカ原子力規制委員会U.S.Nuclear Regulatory Commission(NRC)とアメリカ・エネルギー研究開発局U.S.Energy Research and Development Administration(ERDA(エルダ))を新たに発足させる原因ともなった。AECは63年末から,原子炉動特性の研究,一次系の安全性研究,事故解析,核分裂生成物の挙動の研究,安全性テスト実験計画の5項目からなる安全性研究を計画していた。この最後の項目に関係するのが冷却材喪失事故の実験でLOFT(ロフト)(Loss of Fluid Test)計画と呼ばれ,非常用炉心冷却系(ECCS)の作動実験を含んでいた。これらの実施はおくれ,71年にECCSの模擬テストが行われたが,その結果,注入した水がうまく炉心を冷却しないということが判明した。この発表は軽水炉のもっとも重要な安全装置が不確実であることを示すものであったから,アメリカのみならず軽水炉を導入した世界各国に衝撃を与え,ECCS論争をまき起こした。
アメリカでは72年から73年にかけてECCS公聴会が開かれ,激しい論議が行われた。公聴会終了後,推進側はあらゆる論議が出されECCS問題は基本的に解決したと主張したが,問題は安全研究計画以前にECCSつきの軽水炉を実証済み炉として大量に建設してしまったことであった。こうして批判派の原発反対運動はこの時期から全国的に拡大し,75年から76年にいたって各州での住民投票を含むさまざまなイニシアティブ運動へと発展し,その結果,州民投票や州議会で規定された条件を満たさないかぎり原子力発電所の新規建設を認めない州は11に達した。ネーダーらの消費者運動もベトナム反戦運動以後の最大の市民運動と位置づけて取組みを強化した。
ラスムッセン報告とルイス報告
NRCは1975年10月,〈原子炉安全性研究--アメリカ商業用原子力プラントにおける事故の危険性の評価〉と題する報告書を発表した。これは72年にAECがマサチューセッツ工科大学のラスムッセンNorman Rasmussenを主査とする研究チームに委託して行った研究(計算)を取りまとめたものであり,〈ラスムッセン報告〉とも呼ばれる。従来の災害評価が事故がどのようにして発生するかについては立ち入らなかったのに対し,この報告は確率論的手法を用いて予想される原子炉事故の経過を分析し,事故の発生確率をある前提のもとに計算したものである。実際には事故を加圧水型炉(PWR)について九つ,沸騰水型炉(BWR)について六つのカテゴリーに分類し(表3),それぞれの発生確率を計算した。その結果,最大級の事故であるPWR-1やBWR-1などの発生確率は100万年に1回以下であるとされた。この結論が推進派によって金科玉条のごとく引用されたことはむしろ当然であったかもしれない。なぜなら,もっとも恐るべき炉心溶融事故(〈ラスムッセン報告〉ではそれを2万原子炉年に1回と計算)に対しての唯一の安全装置であるECCSの作動の確実性に疑惑がもたれ,暫定基準で安全審査に対処していた事情や,応力腐食割れの多発やその他のトラブルにもとづく稼働率の低下など,軽水炉の安全性に対し強い疑惑がもたれ,安全性論争は高揚の一途をたどっていたからである。
こういう状況を背景に両院合同原子力委員会はAECに対し原子力発電の安全性に関する技術の現状についての総合報告の作成を求め,AECは《原子力安全性ハンドブックThe Safety of Nuclear Power Reactors(Light Water-Cooled)and Related Facilities》を改組直前の73年にまとめて公表していた。このなかでAECは,ゴフマン=タンプリンの所論に対する批判や環境グループ,UCSなどに対する批判を行っている。UCSはマサチューセッツ工科大学のケンドールHenry W.Kendallを中心に,元ゼネラル・エレクトリック社の原子力技術者であったハバードR.B.Hubbardらも含むチームをつくり,〈ラスムッセン報告〉の全面的批判を行った。この過程でUCSが情報公開法を活用して,内部告発とあいまってAECなどの膨大な内部資料を入手し公表したことは注目に値する。一方,アメリカ物理学会においてもカリフォルニア工科大学のルイスH.W.Lewisらのチームにより原子力発電の安全性について独自の検討を行い,《Review of Modern Physics》の特集号に結果を公表した。連邦議会下院はルイスに〈ラスムッセン報告〉の再評価作業をあらためて委託した。〈ルイス報告〉は確率論的手法の事故解析における有効性を評価しながらも,事故確率の絶対値には根拠がないとした。NRCは〈ルイス報告〉を考慮して〈ラスムッセン報告〉の序文,すなわち事故発生の確率が小さいという部分を支持しないとする決定を79年1月に公表した。2ヵ月後にスリー・マイル・アイランド原子力発電所事故が起こったことを考えれば,NRCはからくも面目を保ったことになる。
スリー・マイル・アイランド原発事故
1979年3月28日,アメリカのペンシルベニア州スリー・マイル・アイランド原子力発電所2号炉で発生した大事故は,周辺8km内の住民中の妊婦や幼児の避難といった事態にまで発展した。炉心溶融はかろうじて回避されたものの,推定では炉心部にある40%の燃料棒はばらばらになるなど,商業用原子力発電史上最大の事故となって全世界に衝撃を与えた。事故後5年経過した84年現在でも,同炉は修復はおろか,炉心損傷の調査さえ未着手という状況である。カーター大統領はスリー・マイル・アイランド事故調査特別委員会(委員長ケメニーJohn G.Kemeny)を発足させ,事故原因の徹底的調査を始めた。〈アメリカ大統領スリー・マイル・アイランド事故調査特別委員会報告書〉(ケメニー報告)は,軽水型原子力発電技術の不完全さ,安全基準の不適切,規制行政の欠陥,防災計画の欠如など,まさに従来の原子力安全論争において問題となったあらゆる側面についての厳しい批判を含むものであったが,何よりも〈原子力発電の危険性を直視すること〉が必要であり,安全規制当局や原子力産業界の態度,すなわち事故は起こりえないとする態度の根本的変更こそが必要であるとするものであった。NRCの委託で行われた〈ロゴビンMitchell Rogobin報告〉は技術的細部にわたる調査を行っているが,炉心溶融が起こりえたことを示唆している。NRCはまた安全規制強化のための研究プロジェクトをスタートさせた。しかし肝心の事故炉の科学的調査は始まったばかりで,それに必要な資金を賄うため日本,西ドイツなどへの共同参加が呼びかけられた。その結果は原子力発電の危険性についてのもっとも貴重な客観的データとなるであろう。
スリー・マイル・アイランド事故は安全論争の重大な結節点をなすものであると同時に,〈安全を確保できる魔法の杖は発見できなかった〉(ケメニー報告)ので,安全論争は質的に新しい発展段階に入るべきはずである。NRCの委託でオーク・リッジ国立研究所が行った〈ASP報告〉と通称される報告書は,〈ラスムッセン報告〉と同じ手法によりながら,運転経験にもとづく事故,故障のデータを用いて,炉心溶融事故の発生確率を222~588原子炉年に1回とした。これは〈ラスムッセン報告〉が2万原子炉年に1回とした計算に比べれば著しく高い。産業界からのクレームで,最近の運転実績データを用いてその確率は4000年に1回となったが,いずれにせよ現実の事故発生という事実の重みは,従来の評価の再検討を促しているのである(ちなみにスリー・マイル・アイランド事故発生までの軽水炉の運転経験は約1000原子炉年であった)。また各原子炉ごとに災害評価を行い防災計画を立案すべき--あるいは不適当な立地条件にあるものは停止させよ--だとする〈ケメニー報告〉の指摘の線に沿って,サンディア研究所はアメリカにおける91の原子炉についての災害評価を行っている。その結果はセーレム2号炉Salem-2(PWR。電気出力105万kW)などの最悪のケースでは死者10万人,損害額3000億ドルというショッキングなものである。ともかくもアメリカにおいてはこのように〈ケメニー報告〉の指摘する方向で原子力発電の安全性の再検討が進行し,論争も質的に高い段階に入りつつあるといえよう。そして原子力発電所建設費の高騰,経済不況と電力需要の伸びの鈍化などの諸要因との相乗効果によって原子力産業界は深刻な停滞と混迷に陥りつつある。
これに反し,フランスや日本などでは反省は深刻ではなく,スリー・マイル・アイランド原発事故の影響の風化を推進派は期待しているかのように見える。しかし日本でも日本学術会議と原子力安全委員会が79年11月26日に合同で開いた学術シンポジウムは,わずか1日の討議ではあったが,多くの再検討を要する問題点を提起した。それらのおもなものを列挙すると,(1)深層防御概念は有効か,(2)確率論的手法の再吟味,(3)最大想定事故と単一故障指針という従来の評価法の不十分さ,(4)巨大機械体系と人間との接点--マン・マシン・インターフェース問題,(5)ジルコニウム-水反応のような基礎的研究の不足,(6)原子力発電所周辺の低人口地帯概念の再吟味,すなわち立地基準と工学的安全施設の有効性の矛盾,(7)防災計画,などである。これらはいずれも今後ひきつづき論争されるべき諸問題である。
核燃料サイクル
原子力発電の安全性は原子炉そのものの安全性に限らず,ウランの採掘に始まり,放射性廃棄物の最終処分にいたる核燃料サイクルのすべての過程が問題となる。最大の放射線影響は,もし原子炉が平常運転中ならば,ウランの採掘にもとづくラドンなどの放出により生ずる。世界でも有数のウラン産出国であるオーストラリアでは,1970年にウラン鉱床が発見されると,その直後よりウラン採掘の是非が国論を二分する論争テーマとなってきた。またその鉱床地帯が原住民(アポリジニー)の聖地であったこととも関連して,論争は技術問題の範囲を超えて社会的・政治的論争に発展した。
ウラン採掘についで大きな環境汚染を生じやすいのは核燃料再処理工場である。そこから放出されるクリプトン85の大気中濃度は1950年以降顕著に増加し,現在15~16ピコキュリー/m3に達しているが,このまま規制が行われなければ2000年ころには皮膚障害を生ずる恐れがあると警告されている。また排水中の放射能濃度規制がルーズであったために,50年代末より操業を開始したイギリスのセラフィールド(旧ウィンズケール)再処理工場によるアイリッシュ海の汚染は著しく,従業員ならびに付近住民の放射能障害が発見されるにいたって83年ころより重大な政治問題となっている。
放射性廃棄物の処理・処分問題は,とりあえずはタンク貯蔵などがなされているため,未解決の問題であるにもかかわらず原子炉の安全性ほどの論争点とはなっていなかった。スウェーデンはもっとも先進的に処分問題に取り組み,廃棄物の安全取扱いと最終貯蔵計画を示さない原子力発電所の運転は許可しないとする法律を制定していたが,スリー・マイル・アイランド原発事故後に全政党の合意のもとに国民投票が行われ,〈運転中および建設中の12基の炉はその技術的寿命の期間まで使用するが,それ以外の原子炉の導入はもはや認めない〉と決定された。注目すべきはこの決定と同時に,2020年ころからの運用を目標に高レベル廃棄物の深層貯蔵施設のための研究開発計画その他の廃棄物処分計画が実施に移されたことである。
一方,低レベル廃棄物の海洋処分については,1974年の海洋汚染の防止に関するロンドン条約が成立し,高レベル放射性廃棄物の海洋投棄は禁止されることとなった。しかしある基準以下の廃棄物は一定の手続きを経て海洋投棄が認められており,OECD諸国は北大西洋での投棄を行っている。日本は太平洋での投棄を予定していたが南太平洋諸国の強い反対に遭遇して,陸上処分計画に変更のやむなきにいたっている。技術的安全性を強調する日本の説明に対し,大国の核兵器実験のために被害を受けた南太平洋諸国民の核廃絶の主張とはまったく食い違ったままであった。原子力発電の放射性廃棄物をめぐる論争は,スウェーデンの例のように原子力発電が中止されても,あるいは核兵器が廃絶されても残る問題で,今後原子力論争の中心に位置することになるものと考えられる。
環境保護
現在の原子力発電所(軽水炉)では電気出力のほぼ2倍に相当する熱を環境に放出している。欧米では内陸に建設される発電所が多く,河川や湖水に熱を放出するとたとえ大河川でもその影響が無視できないため,冷却塔から大気中に放出される。一方,海が近くにある地域では,この熱を温排水として海に放出している。この温排水の環境への影響と平常時の微量の放射性物質の環境影響は,原子力発電所立地にあたって必ず問題となり,論争のテーマとなった。生態系への影響は解明が困難であるが,最近の研究では冷却水中の魚卵や稚魚は発電所から放出されるまでに100%死滅するものとされ,したがって温度差のみならず取水量そのものの制限が必要なことが認識されつつある。このように重大な環境影響が生ずるにもかかわらず,原子力発電所の安全審査にあたっては放射能汚染以外は無視されていたために,環境保護団体などの原発反対運動を激化させる原因となっていた。アメリカで1970年1月に制定された国家環境政策法National Environmental Policy Actはこの事情を一変させた。すなわち71年7月アメリカ巡回高等裁判所は,建設中のカルバート・クリフスCalvert Cliffs原子力発電所に対してなされていた周辺住民からの差止請求訴訟において,AECは同法を軽侮しており,チェサピーク湾への環境保護を怠っているとして,工事の中止と計画変更を命じたからである。この判決を受けてAECは同年11月,〈環境影響報告書〉の作成を原子力発電所立地にあたって義務づける新しい措置を公示し,この問題は一転機を画したのである。
核拡散防止と核物質防護
原子力産業で用いられる濃縮ウランやプルトニウムなどの核分裂性物質はもともと核兵器用に作られたものであった。原子力産業の発展は必然的にこれらの特殊核物質の世界的拡散を生ずることとなり,原子力技術情報の拡散とあいまって,それらが軍事転用される危険が生ずることとなる。それを防ぐことを目的とする条約が核不拡散条約であり,それを批准した国々では国際原子力機関との間で保障措置協定を結び,自国の原子力産業に対する査察を認めることとなる。米ソ両大国の合意のもとに成立したこの条約は,両大国の核軍拡をまったく規制することなく,他の国々が核兵器を持つことを防止し,かつ原子炉等の輸出なども妨げないという矛盾に満ちた内容をもっている。国際的な政治論争の対象とならざるをえないことは宿命的でさえある。こうして1977年カーター大統領の提案にもとづいて国際核燃料サイクル評価会議International Fuelcycle Evaluation(INFCE(インフセ))が開かれ,最終的には59ヵ国,6国際機関が参加する大会議となった。この会議は各国の技術専門家による非政治的共同研究の場とされたが,実際は各国の政治的・経済的利害と思惑を背景に複雑な論争が行われた結果,その結論は玉虫色ならざるをえなかった。しかしこの論争はあらためて原子力技術と核兵器技術の親近性を示し,その意味で核軍縮をめぐる論争とも密接に関連することとなる。ストックホルム国際平和研究所は従来から原子炉輸出を兵器輸出の一環として扱っていたが,評価会議の結論はもっと広範に重水,黒鉛などの材料の輸出や,同位体濃縮や再処理技術などにも規制が必要なことを示したといえる。何よりも高濃縮ウランやプルトニウムの軍事転用を防止することが眼目となるが,その手段として採られる計量管理システムの確立や物理的防護などの措置は,産業機密の侵害,原子力施設従業員への管理強化や人権侵害,ひいては社会全体の管理化をもたらすとする論争が,核テロリズムの防止に関連して行われている。問題の性質上,それは際限のない政治的・イデオロギー的論争へと発展する傾向がある。
経済性
原子力発電の経済性にかかわる論争には大別して二つの問題がある。その第1はエネルギー経済に関する諸問題であって,エネルギー需要の将来予測,エネルギー節約の有効性,代替エネルギーの選択といった問題である。第2の問題は原子力発電のコスト,すなわち資本費,燃料費,運転維持費,補助金の役割等についての他の発電方式との比較にかかわる問題である。第1の問題についての原子力発電を支持する人々の主張は,エネルギー供給の拡大が生活水準の改善に不可欠であることと,非核燃料の供給がますます不足し,またエネルギー消費形態が将来ますます電力へ移行するという点にある。また原子力か石炭かという点については,石炭の露天掘りによる環境破壊や深部採炭による炭鉱事故の危険などの点から,原子力のほうが明らかに安全であるとする。これに対する反対派の主張は,エネルギーの節約と,非核技術の開発に置かれている。不確実かつ危険な原子力に頼らなくとも,石炭を基本にしたエネルギーサイクルは将来のエネルギー需要を賄うのに十分であるとする。発電コストをめぐる問題は複雑である。原子力発電と石炭・石油火力発電を比較すると,前者は多くの資本費を要するが燃料費,運転維持費の点で有利であり,後者はその逆である。中東戦争による石油危機以後の原油の急上昇は,原子力発電コストを一時的に有利にしたのみならず,エネルギー安全保障という点からも原発支持派を助けたといえる。しかし原油の値上がりは,機器費や建設費などの高騰を招き,結局資本費の急上昇となってコストを増大させたから,原子力発電の有利性は一時的なものにすぎなかった。さらに経済不況の長期化や高金利政策は,電力需要そのものの低迷をもたらすなど,単純なコスト比較は困難である。原子力発電の場合には安全規制の強化にもとづく機器の追加などによる工期の延長,建設管理の良否の影響などにより建設コストは同型の原子力発電所でも2倍以上も異なるのは普通である。また稼働率によっても当然コストは大きく左右される。過去の実績は確実なコスト計算を可能にするほど原子力技術は成熟したとはいえないことを示している。一方,石炭火力の場合には,排煙洗浄装置の技術進歩によるコストの切下げいかんが競争に大きく影響するものと考えられる。
日本における原子力発電論争
日本の原子力発電論争は1950年代に始まり,その論争の中から原子力平和利用三原則が生まれた(原子力三原則)。また原子力研究の開始と,ビキニ環礁における第五福竜丸の被災事件(ビキニ水爆実験)とが同時であったため,原水爆禁止運動とも当初から深いつながりをもつことになった。警告線量(がまん線量)としての許容量という武谷三男の主張は,アメリカ原子力委員会のリビーLibbyらとの論争の中で生まれたものである。原発反対運動の一定のひろがりの後にようやく核兵器反対運動への転化が見られるアメリカの運動とはこの点で異なっている。しかし原子力発電論争の萌芽でもあったコールダー・ホール型原子炉導入をめぐる論争には,エネルギー問題,資源問題,安全問題,発電原価問題などすべての側面が含まれていた。
本格的な論争のひろがりは60年代の後半,電力業界がアメリカからの軽水炉の大量導入を推進するとともに生じた。71年末,社会党は原子力発電反対を決定し,他の野党もそれぞれ批判的方針をかかげたため,73年から74年を頂点に国会を舞台に原子力発電の安全性論争が展開されるようになった。日本学術会議,日本科学者会議,日本原子力研究所労組その他総評,同盟,中立労連などのナショナル・センターや社会経済国民会議などの民間団体もそれぞれの立場から活発な発言を行った。また武谷三男らの原子力安全問題研究会は《科学》誌に,星野芳郎,久米三四郎らは伊方(いかた)原子力発電所の行政訴訟を支援するかたわら《技術と人間》誌に原子力発電批判の論文を精力的に発表した。高木仁三郎らの主宰する原発闘争情報誌,原子力問題全国情報センターの原子力ニュースも定期に発行され批判的論陣を張っている。これに対し推進派は,日本原子力文化振興財団を組織して広報・宣伝につとめ,また政府も政府公報費を用いて原発の安全キャンペーンを強化している。しかし論争のテーマ,データなどは現在でもアメリカに依存する点が多いのはやむをえないことと思われる。すなわちアメリカにおける論争と共通する点が多いので,以下には日本における特徴的な事項について簡単に述べることとする。
英国炉導入問題
1956年原子力委員会が発足したばかりの時,イギリスからコールダー・ホール型原子炉を早期に導入することにより原子力発電の推進を図ろうとした初代原子力委員長正力松太郎の方針に対し,基礎研究の積上げによる自主開発路線を主張する湯川秀樹委員をはじめとする核物理学者が反対し,湯川は結局辞任するにいたった。その後英国炉の早期導入は産業界の支持のもとに強行されたが,その過程で安全性,経済性,行政のあり方など多岐にわたる論争が展開された。安全性にかかわる技術問題としては,耐震設計,正の温度係数,アルゴン41の放出と気温逆転層,中空燃料,最大想定事故と放射能放出量,立地基準とファーマーFrank Reginald Farmer論文,ウィンズケール原子炉事故,格納容器(コンテナー),近接射爆場などの問題があり,さらに安全審査基準の不備,審査委員の中立性への疑問,企業機密と資料公開など行政への不信に属する論争もこれに加わった。着工後完成までに予想外の技術的トラブルや難工事のため工期は大幅に遅延し,その結果もあってイギリス側が売込みにあたって強調したkWh当り2円52銭などという発電原価はまったくの宣伝文句にすぎないことが明らかとなった。電力業界が高い授業料を払い,苦心のあげくに全出力営業運転にようやくこぎつけたのは71年のことであるが,その時はすでにせっかくのガス炉についての経験はただ1基だけで放棄され,新たにアメリカからの軽水炉導入路線に乗り換えつつあった。
法廷論争
埼玉県大宮市に三菱原子力工業が原子力船〈むつ〉の原子炉に使用する核燃料を試験する目的で設置した臨界実験装置(法律上原子炉と同じ扱いを受ける)の撤去を要求して住民が起こした訴訟が,日本における原子力法廷論争の始まりである。企業秘密をたてに資料公開を拒む三菱側に対し,裁判所が強制提出を命令するに及び,会社側は撤去に同意し住民側と和解する道を選んだ(1974年7月)。1978年4月25日に判決がなされた四国電力の伊方発電所の原子炉設置許可処分取消請求事件は,4年半にわたり大規模な科学論争を法廷で展開した。行政訴訟という性質上,論争は国側の安全審査の適否に集中することになり,その過程で安全審査の実態や,従来明らかにされていなかった内規などが公開されたのは大きな成果であった。周辺住民には利害関係がないから原告として不適格であるとして却下する門前払い論を裁判所がとらないかぎり国側の不利は免れないとの予想に反し,裁判所は国側の行政裁量権の妥当性を認め,違法はないとして住民の請求を棄却した。同様な行政訴訟が日本原子力発電の東海発電所と東京電力福島第2原子力発電所に対して提起された。国側は伊方の経験に学んで,まず原告不適格を強く主張し,そのため事実審理に入るまでに6年が費やされ,また審理に入っても技術論争を回避するために,国側の科学者証人を1人に限定し,安全審査の適法性を主張するだけにとどめているのが特徴的である。
〈むつ〉をめぐる論争
1974年9月に起きた原子力船〈むつ〉の放射線漏れ事故をめぐって生じた一連の事態は,日本の原子力開発体制のずさんさ,安全審査の欠陥性などを一挙に暴露する結果となった。またすでにその年の1月の国会予算委員会で共産党の不破哲三議員が,科学技術庁の委託で環境放射能の分析を行っていた日本分析化学研究所の測定データに多数の捏造データが含まれていることを暴露し,原子力安全行政のずさんさを指摘していた。これらの事件の結果,国民の原子力行政への不信は増大し,政府側も原子力安全委員会の新設,原子力発電行政の通産省への移管など一連の行政体制の改革を行って対応せざるをえなかった。しかし〈むつ〉の処置をめぐる論争は,佐世保での修理,修理後の青森県むつ市大湊港への再回航といった事態の展開ごとにくり返され,政府はそのつど地元の県や市および漁業団体などとの間で協定を結び,しかもしばしばそれを守れなくなるという失態を演じた。与党自民党内からさえ廃船論が強く主張され,政府は苦慮しつつもその処置を決めかねていた。世界に例を見ない論争というべきであろう。
電源三法と漁業者
カルバート・クリフス原子力発電所をめぐる裁判の争点とまったく同じ温排水問題が,日本では原子力発電所立地当初から存在した。ただアメリカと異なり日本には国家環境政策法といった保護法は存在しておらず,環境アセスメント法案さえ産業界の反対で成立できないでいる。一方,日本のほとんど全海岸線には漁業権が設定されているから,原子力発電所の立地に先立って漁業権の消滅(電力会社による買取り)を行っておくことが法制上も必要となっている。しかもアメリカ同様,安全審査では温排水などの環境影響は審査対象外とされていたから紛争は一層激化した。論争点としては,漁業権の消滅範囲を決定するためにも温排水の拡散範囲の算出法がまず問題となり,ついで取水・排水に伴う復水器内での魚卵や稚魚などの漁業資源への影響,温度上昇による魚種の変化などの生態系への影響,温排水に希釈されて放流される低レベル放射能の生物濃縮など多岐にわたっている。さらにこれらの技術的論争の本質的背景として,一次産業に依存する地域開発の展望の問題が存在することに注目すべきであろう。しかし1974年田中角栄内閣の時に制定された電源三法は,電源立地推進のために露骨な金権的政策を実施することを可能とし,その結果財政難に苦しむ地方自治体は原子力発電の安全性に対する不安はそのままに受入れに傾くこととなり,安全論争は後景に退きつつある。
執筆者:中島 篤之助
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報