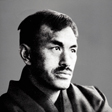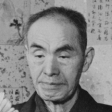精選版 日本国語大辞典 「土井晩翠」の意味・読み・例文・類語
つちい‐ばんすい【土井晩翠】
20世紀日本人名事典 「土井晩翠」の解説
土井 晩翠
ドイ バンスイ
明治〜昭和期の詩人,英文学者 第二高等学校名誉教授。
- 生年
- 明治4年10月23日(1871年)
- 没年
- 昭和27(1952)年10月19日
- 出生地
- 宮城県仙台市北鍛冶町
- 本名
- 土井 林吉(ツチイ リンキチ)
- 学歴〔年〕
- 東京帝大文科大学英文科〔明治30年〕卒
- 主な受賞名〔年〕
- 文化勲章〔昭和25年〕,仙台市名誉市民
- 経歴
- 質商を営む旧家に生まれ、幼時より「八犬伝」「太閤記」「日本外史」等に親しむ。立町小学校教師佐藤時彦に漢籍を教わった後、家業に従事しつつ書籍を耽読、「新体詩抄」や自由民権思想の影響を受ける。21年、仙台英語塾から第二高等中学校(のち二高)に編入卒業、27年上京。帝大在学中の29年、「帝国文学」第2次編集委員として漢語を用いた叙事詩を発表、藤村と併び称される詩人となった。30年郁文館中学の教師。31年「荒城の月」を作詞。32年処女詩集「天地有情」を出版。外遊後、37年二高教授となり、大正13年には東北大講師を兼任し、英語・英文学を講じ、昭和9年退官。一方、カーライルやバイロンの翻訳を発表、またギリシャ文学に興味を持ち、15年ホメーロスの「イーリアス」「オヂュッセーア」を全訳出版。この間家族を次々に失い、心霊科学に興味を持つ。20年7月空襲で蔵書3万冊余を焼く。ほかの代表作に「星落秋風五丈原」「万里長城の歌」、詩集に「暁鐘」「東海遊子吟」「曙光」「天馬の道に」がある。25年文化勲章受章。没後、45年顕彰会が晩翠賞と晩翠児童賞を制定した。
出典 日外アソシエーツ「20世紀日本人名事典」(2004年刊)20世紀日本人名事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「土井晩翠」の意味・わかりやすい解説
土井晩翠(どいばんすい)
どいばんすい
(1871―1952)
詩人、英文学者。姓は本来「つちい」と読む。本名林吉。明治4年10月23日仙台・北鍛冶(かじ)町の旧家に生まれた。晩翠の筆名は宋(そう)の詩人范質(はんち)の詩句に由来する。仙台英語塾を経て、第二高等中学に入学、1894年(明治27)に帝国大学英文科に入学。在学中に『帝国文学』の編集委員となり作品を発表。97年に大学卒業、一時郁文館(いくぶんかん)中学の教職につく。翌98年東京音楽学校が『中学唱歌』(1901刊)を編んだとき、『荒城(こうじょう)の月』を作詞、滝廉太郎(れんたろう)の作曲で普及した。99年処女詩集『天地有情(うじょう)』を博文館から出版。「星落秋風五丈原(ほしおつしゅうふうごじょうげん)」など、漢語を駆使した悲壮・哀感漂う叙事詩をつくりだし、以後長く愛唱された。翌1900年(明治33)二高教授として帰郷。32年(昭和7)に長女照子を、翌年長男英一をともに病気のために失った。34年に二高教授を退く。そのころから心霊研究に傾いた。45年の空襲にあい、敗戦後の48年(昭和23)妻に先だたれた。49年仙台名誉市民になり、翌50年文化勲章を受章した。昭和27年10月19日没。英雄や歴史を冥想(めいそう)的にうたったものに特色があり、島崎藤村(とうそん)の叙情詩とともに明治浪漫(ろうまん)主義に色彩を添えた。詩集はほかに『暁鐘(ぎょうしょう)』(1901)、『東海遊子吟』(1906)、『曙光(しょこう)』(1919)、『天馬の道に』(1920)、『アジアに叫ぶ』(1932)、『神風』(1937)、また詞華集『晩翠詩集』(1919)などがある。
[古川清彦]
『『日本詩人全集3 土井晩翠他』(1968・新潮社)』▽『『日本近代文学大系18 土井晩翠他集』(1972・角川書店)』
百科事典マイペディア 「土井晩翠」の意味・わかりやすい解説
土井晩翠【どいばんすい】
→関連項目新体詩|薄田泣菫
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
改訂新版 世界大百科事典 「土井晩翠」の意味・わかりやすい解説
土井晩翠 (どいばんすい)
生没年:1871-1952(明治4-昭和27)
明治期の詩人,英文学者。仙台生れ。本名林吉。1934年〈つちい〉を改称。第二高等中学(後の第二高等学校)を経て1897年東京帝大文科大学英文学科を卒業。在学中から雑誌《帝国文学》の編集委員となり,99年第1詩集《天地有情(てんちうじよう)》を世に問うて好評を博した。なかでも〈荒城の月〉(滝廉太郎作曲)が最も広く知られているが,《三国演義》に材をとった叙事詩〈星落秋風五丈原(ほしおつしゆうふうごじようげん)〉も名高い。第2詩集《暁鐘》(1901),1901年から04年の外遊の産物《東海遊子吟》(1906)などで東西文化の融合を歌い続けた。34年まで第二高等学校教授を務めた。仙台市名誉市民(1949),文化勲章受章(1950)。ギリシア語原典から訳した《イーリアス》《オヂュッセーア》など翻訳の仕事もある。
執筆者:野山 嘉正
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「土井晩翠」の意味・わかりやすい解説
土井晩翠
どいばんすい
[没]1952.10.19. 仙台
詩人,英文学者。本名,林吉。 1932年頃姓の「つちい」を「どい」と改音。 1897年東京大学英文科卒業。在学中から雑誌『帝国文学』の編集に従事,同派の詩人として名をなした。 98年東京音楽学校編『中学唱歌』のために『荒城の月』を作詞。 99年高山樗牛の協力で処女詩集『天地有情』を刊行,集中の代表作『星落秋風五丈原』 (1898) で,漢詩調による悲壮美の表現に独創性を示した。これにより男性的な調べの叙事詩人としての声価が決定的となり,対立的な詩風の島崎藤村と並んで新体詩の代表的詩人と目された。ほかに詩集『暁鐘』 (1901) ,『東海遊子吟』 (06) ,『曙光』 (19) など。ホメロスの『イーリアス』 (40) ,『オヂュッセーア』 (43) など翻訳もある。芸術院会員。 1950年文化勲章受章。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「土井晩翠」の解説
土井晩翠 どい-ばんすい
明治4年10月23日生まれ。32年「天地有情(うじょう)」で新体詩人の地位を確立。漢文調の叙事詩にすぐれた。「荒城の月」を作詞。二高教授をつとめ,「イーリアス」などを翻訳。昭和25年文化勲章。昭和27年10月19日死去。80歳。宮城県出身。東京帝大卒。本名は土井(つちい)林吉。詩集に「暁鐘」「曙光」など。
【格言など】春高楼の花の宴 めぐる盃かげさして 千代の松が枝わけいでし むかしの光いまいづこ(「荒城の月」)
山川 日本史小辞典 改訂新版 「土井晩翠」の解説
土井晩翠
どいばんすい
1871.10.23~1952.10.19
明治~昭和期の詩人・英文学者。仙台市出身。本名土井(つちい)林吉。1934年(昭和9)以降「どい」と称した。幼時から史書・漢籍などに親しむ。東大卒。大学在学中から詩作。1899年(明治32)第1詩集「天地有情(てんちうじょう)」を刊行。漢語脈の叙事詩風の詩編により,和語脈の島崎藤村と併称される存在となる。「荒城の月」の作詞者。二高教授。1950年文化勲章受章。詩集「東海遊子吟」「天馬の道に」「アジアに叫ぶ」。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「土井晩翠」の解説
土井晩翠
つちいばんすい
明治〜昭和期の詩人・英文学者
本名林吉。後年は「土井」を「どい」と改音。宮城県の生まれ。東大英文科卒業後,母校二高(現東北大学)の教授となる。在学中より詩を発表し始め,1899年詩集『天地有情』発表以来,島崎藤村と並称された。その漢詩調・男性的詩風は寮歌・校歌に影響を与えた。バイロン,ホメロスの翻訳でも著名である。1950年文化勲章受章。代表作に『荒城の月』『星落秋風五丈原』など。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
367日誕生日大事典 「土井晩翠」の解説
土井 晩翠 (どい ばんすい)
明治時代-昭和時代の詩人;英文学者。第二高等学校教授
1952年没
出典 日外アソシエーツ「367日誕生日大事典」367日誕生日大事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の土井晩翠の言及
【土井晩翠】より
…明治期の詩人,英文学者。仙台生れ。本名林吉。1934年〈つちい〉を改称。第二高等中学(後の第二高等学校)を経て1897年東京帝大文科大学英文学科を卒業。在学中から雑誌《帝国文学》の編集委員となり,99年第1詩集《天地有情(てんちうじよう)》を世に問うて好評を博した。なかでも〈荒城の月〉(滝廉太郎作曲)が最も広く知られているが,《三国演義》に材をとった叙事詩〈星落秋風五丈原(ほしおつしゆうふうごじようげん)〉も名高い。…
※「土井晩翠」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...