日本大百科全書(ニッポニカ) 「農産物価格」の意味・わかりやすい解説
農産物価格
のうさんぶつかかく
一般的には、農産物について形成される価格をいう。それはさらに、農業生産者が直接受け取る庭先(農場)価格のほかに、包装、保管、流通、輸送、加工などの諸過程での価格が加わり、最終的には消費者価格として形成される。
一般に、経済が発展するにつれて、農産物は加工、輸送、流通などの価格構成部分が増大し、原料農産物の価格部分が減少する。農林水産省が2000年(平成12)夏に国内産の野菜・果物について調査したところによると、小売(消費者)価格は農家の庭先価格の2.78倍に達しており、両者の開きが近年拡大する傾向にあるとしている。
[暉峻衆三]
価格形成の一般理論
いまかりに完全な自由競争社会にあって、農業も資本主義経営が支配的で、すべての経営が技術的、資本的に均等な条件のもとにあるとしよう。このような条件が工業で実現しているとすれば、特定の商品を生産する部門では、生産されるすべての商品の価値水準は均等となり、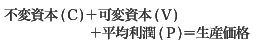
がその商品の需給均衡価格として形成されるといっていい。
不変資本とは物財費に相当するもので、原料や肥料など、1回の生産で全部新たな商品に価値移転する流動資本部分と、機械や建物のように、何年かの耐用年数があり、1回の生産で部分的に新たな商品に価値移転する固定資本の減価償却部分からなる。また可変資本とは、労働力の購入にあてられた資本部分で、労働費に相当する。
ところが土地を基礎的生産条件とする農業部門では、たとえ前記のように技術と資本条件が均等であったとしても、それぞれの土地に豊度や市場への位置の差があるために、それぞれの土地で生産される農産物の価値水準が不均等になるという問題が発生する。いま問題をごく単純化して考察することにしよう。AとB2種類の同一面積の土地があり、Aは優等地、Bは劣等地としよう。双方に同じ100万円の資本を投下し、Aでは100キログラム、Bでは50キログラムの米がとれたとし、ちょうど150キログラムの米で社会の需要が満たされ、そこで需給均衡価格が成立するとしよう。社会的平均利潤率が10%、投下資本はすべて流動資本だと仮定すると、そこでは、米1キログラム2万2000円(劣等地Bでの生産を基準とした、100万円÷50キログラムに平均利潤率の10%を加えた額)が需給均衡価格であり、B地の農業資本家はその価格で、投下した資本(C+V)を回収したうえに平均利潤を確保することができる(生産価格は、米1キログラム当りでは2万2000円、経営全体では110万円)。ところが、優等地Aの資本家も需給均衡価格で米を売ることができるから、100キログラム×2万2000円=220万円で、B地の110万円とくらべて110万円多く利潤を得る。すなわち彼はその資本投下に対して、平均利潤を超える超過利潤(110万円)を得ることができる。これが、土地の豊度差に基づいて生じた差額地代部分(DR)となる。もし優等地Aの資本家が、そのA地の所有者であれば差額地代分をそっくりポケットに入れることができる。しかしながら、地主からの借地経営であれば、農業資本家間の競争によって生産価格を超える部分は地代として地主の手に移行することになる。市場への位置の差に基づく差額地代発生のメカニズムも豊度差の場合と同じである。
また農業の場合、最劣等地の経営もしくは最劣等投資が地主からの借地のもとで行われるときには、土地所有の独占に基づいてなにがしかの地代(絶対地代、AR)の支払いを地主から求められ、最劣等地もしくは最劣等投資の農産物の生産価格の水準以上に農産物の価格が、ある程度高められざるをえないことがある。
[暉峻衆三]
小農経営が支配的である場合
農業は一般に土地・自然に依拠しつつ生物体(動植物)の育成を行う産業である。天候、水、土壌、動植物の生育状況などの変化に応じて臨機応変に人間が対処しなければならない。機械工業のもとで資本主義的生産が急速な発展を遂げることができたのと異なって、農業では、ブロイラーや養豚など工業生産に近い部門は別として、作物育成といった土地利用型農業部門を中心に家族労働力を基礎とする小農経営による生産が支配的、もしくは優勢である。
いま、農業で技術的、経営規模的に均等な小農経営が支配的であり、資本主義的工業部門でも自由競争が貫徹しており、農工間の労働力の移動も自由に行われるものと仮定しよう。この小農経営が自作地で営まれているとすれば、小農民は自分の土地を自分に貸し付ける小地主であり、経営主として自分の農機具などの生産手段をもって自分自身の労働力を雇う小資本家であるとともに、小資本家である自分自身に雇われる賃金労働者でもあるという、三位一体(さんみいったい)的性格をもっているということができる。この場合、小農経営にとって土地所有の独占は事実上存在せず、また経営を継続する最低限の条件は、一般に、不変資本(C)に相当する「本来的費用」を差し引いたのちに、自分自身に支払われる労賃部分(V)が確保されることであり、利潤の確保をかならずしも求めないことから、ここでの農産物価格の形成は次のようになる。最劣等地における小農経営の費用価格(C+V)の水準、がそれである。最劣等地の小農は、地代(R、絶対地代もしくは差額地代)や平均利潤(P)が得られなくても経営を継続しうることになる。社会はRとPに相当する部分だけ、小農が生産した農産物を安く手に入れることができる。RやPを必要とする資本制経営下の農産物に対して、小農経営下の農産物が市場で案外強い競争力を発揮できるのはそのためである。自作小農経営のもとでも、より優良地には差額地代(DR)が発生するが、それは費用価格を超える超過部分として小農自身の手に入る。
もし、小農経営が小作地で行われるものとすれば、最劣等地にもなにがしかの絶対地代(AR)相当分の支払いが求められ、そこでの農産物の価格は、一般に、C+V+ARの水準に形成されるといっていい。それに対応して、より優良地の地代も増大し、費用価格を超える全超過部分が地代として地主に支払われることになる。
[暉峻衆三]
現実への接近
以上は抽象的次元のもとでの農産物価格形成の一般理論であるが、現実には、より具体的条件を盛り込みながら考察しなければならない。そのうち、いくつかの条件を入れて考えてみよう。
土地・自然に依拠して生産が行われる農業では、生産と労働投下の期間に季節性がある。稲作を例にとると、それはおよそ冬期を除く4月から10月にかけて生産が行われる。この生産期間内にも農繁期と農閑期の別があり、稲作のための労働投下が行われる期間(労働日)はさらに限定されている。いままでの抽象的次元では、稲作が自作小農経営で行われているとすれば、米の価格は最劣等地の費用価格(C+V)の水準で決まるものとした。そして、その場合、小農民が自家労賃として得るVは、彼およびその家族が1年間の生活をまかないうるものとしてとらえられていた。
だが、もし日雇いあるいは季節雇いの形での労働市場(労働力の「切り売り」)が展開して、小農民もその市場に包摂されるようになると、農民は農閑期に自分の経営外の日雇いに従事することによって、農産物の価格は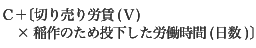
で決まることになる。農民は稲作から得られる自家労賃で、1年の生活費の一部分をまかなえるだけになる。さらに、いままで小農民は技術や資本条件が均等だと仮定してきたが、現実には市場をめぐる競争の波にもまれて、上昇する者(一般に少数)と下降する者(一般に多数)とに分解することが多い。しかも農民の場合は土地や、機械・家畜など、なにがしかの資産をもっているので、農業から容易に撤退しないで小土地と小経営にしがみつこうとする傾向が強い。さらに、資本主義経済のもとでの過剰人口の農村部での滞留が、過小農経営の分厚い滞留と結合して現れることも多い。このような状況が、工業や流通部門における独占(寡占)資本の形成と結び付くと、利潤とともに労賃についても著しい格差構造が形成され、過小農の「切り売り労賃」ないし自家労賃は極度に低い水準に押し下げられることになる。ここでは、過小農民は優れた技術と資本力によってではなく、極度の低賃金と貧困によって市場競争に参画することになる。
[暉峻衆三]
日本の状況
近年の日本では、以下のような状況がみられる。製造業の企業規模(雇用労働者数でみて)によって大きな賃金格差が存在している。そのなかにあって農家が兼業として行う「切り売り賃労働」は格段の低賃金の部類に属する。そして、農家が平均的に農産物価格から得る時間当り農業所得(=自家労賃)はその「切り売り労賃」すら下回るほどの水準に低下している。1983年でみると、時間当りの賃金は、500人以上の規模の製造業を100とすると、農家・臨時的賃労働は40以下であり、農業所得はさらに低く30以下である。この傾向は1990年以降も変わっていない。農民にそのような農業所得しかもたらさないほどに農産物価格は農民にとっては低い(安い)といえる。
1970年代以降1990年代にかけての農業所得の低下は次のような諸条件によってもたらされた。1950~1960年代の米価をはじめとする農産物価格支持政策のもとで食糧が増産されたが、1970年代以降、米についても過剰傾向が強まり、米価と米の生産がともに抑制されるようになった。1970年代以降、円の価値がドルに対して高くなり、ガット体制下の貿易自由化の急進展のもとで、安い外国農産物が大量に輸入されるようになり、その点からも日本国内の農産物価格が抑えられる傾向が強まった、などである。
[暉峻衆三]
経済の高度化と食生活構造の変化
一般に、一国経済が高度な発展水準に達し、食生活もまた高度化・多様化するなかで、国民が食生活に支払う価格総額のうちの原料農産物に支払う価格部分は低下する傾向がある。日本でも1970年代以降経済大国化と国民の食生活の高度化・多様化が進むなかで、同様の傾向となった。いま、1995年に日本国民が支出した最終飲食費総額()のなかで「生鮮食品」の割合をみると、それは20%(1975年は31.6%)を占めるにすぎず、「加工食品」が50.5%(1975年は45.7%)と過半に達し、「外食」も29.5%(1975年は22.7%)と生鮮食品を大きく凌駕(りょうが)している。年次的推移をみると、生鮮食品の比重が漸減して、外食と加工食品が増大している。日本人は食生活のために、ますます加工食品や外食に多く支払うようになっている。また、それぞれの経費の内訳()をみると、1995年には「生鮮食品」についても生鮮農水産物は59.6%(1990年は65.9%)で、残り40.4%は流通経費で占められており(1990年は34.1%)、前者の漸減、後者の漸増傾向をみることができる。原料食料の比率は、「加工食品」になると18.9%(1990年は25.0%)、「外食」で25.7%(1990年は27.1%)にすぎず、ここでも漸減傾向がみられる。食生活の高度化は、国民が加工食品や外食に支払う部分をますます増大させていくことを意味するといっていい。
[暉峻衆三]
農産物価格政策
工業に比べて農業は、一般に小農経営が多いなど経営規模が小さく、独占(寡占)が形成されやすい工業に比べて市場条件が不利である。また、土地・自然に依拠する生産が行われることから、土地改良事業などにみられるように、資本投下が土地に合体されてしまう、といった特徴をもつ。また、土地をはじめ「家の資産」という性格が強い。そのため、市場(価格)条件が悪いからといって、すぐに資本を農業から引き上げて他に移すことが困難な場合が多い。このような条件が前述の農業部門での過剰人口の滞留などと結び付いて農産物価格形成を長期にわたり不利にすることが多かった。
小農民を多く抱えた資本主義国家は、しばしばこの農産物価格形成の不利を是正し、統治体制を安定させるために、農業保護政策の一環として農産物価格支持政策を採用した。それによって農業生産の増進を図ることもあった。農業部門に地主制度が存在するような場合には、この政策は地主の経済的、政治的地位をも補強する意味をもった。
19世紀末、西ヨーロッパは長期農業不況にみまわれた。運輸手段の発達と結び付いたアメリカ大陸からの大量で安価な農産物の流入がそれを加重した。ドイツをはじめ、一連の国は農産物輸入関税を賦課し、国内農産物価格の支持を図った。
さらに1929~1930年には世界大恐慌が資本主義諸国を襲い、農産物価格も激落して多数の農業経営が破綻(はたん)し、農民の困窮も極度に深まった。この深刻な恐慌を契機に主要な資本主義国は、管理通貨制のもとで国家が経済過程に積極的に介入して景気と内需を回復し、統治体制の安定を図る政策を採用するようになり、その一環として農産物価格を直接支持する政策も採用されるようになった。これによって農業所得を一定程度維持し、恐慌による農業者の打撃を緩和して、農村の体制的安定を図ろうとした。
日本でも、たとえば国民の主要食糧である米について、1931年(昭和6)の米穀法の改正によって米価を一定の水準に維持するために政府が介入して米の買入れ、売渡しを行うことになり、さらに1933年の米穀統制法によって一段と米価に対する政府の統制力が強化された。その後、戦時体制に突入して、新たに食糧増産と国民生活の維持が重要な課題となるなかで、米のみならず麦など国民の主要食糧を対象とする「食糧管理法」が1942年に制定された。それは、政府が食糧を管理し、その需給や価格を調整し、配給の統制を行うことを目的としていたが、この食糧管理体制のもとで、米などの増産を図るべく生産者(政府買入れ)価格が、他方、国民生活を保持すべくその消費者(政府売渡し)価格が政府によって決められることとされた。
第二次世界大戦終了後も、戦後復興のもとで食糧増産が課題となるなかで、それに対応した農産物価格政策が採用された。やがて戦後復興が終わると、1950年代の半ば以降、1960年代にかけて、一連の先進諸国で資本主義経済の高度成長が展開されるなかで、食糧需要の高度化(畜産物や果実・野菜などの需要増)とともに、農業と工業の間の所得格差の拡大(前者の立ち遅れ)といった問題が現れた。戦後民主主義の理念に照らして、農工間所得格差を是正しつつ、需要の高度化に対応した農業生産力の増進を図ることが求められた。そのための重要な政策手段として農産物価格支持政策が採用された。西ヨーロッパでは共通農業政策のもとで、また、日本では1961年制定の「農業基本法」のもとでそれは展開されたが、日本では米価や、乳価をはじめとする畜産物の価格支持政策が1960年代に積極化した。
だが、このような価格支持政策は農業生産力を増進させた反面で、ガット体制下の貿易自由化の進展にも促されて、やがて重大な農産物過剰問題を引き起こすことになった。そして、1980~1990年代にかけて市場原理主義が主潮流になり、ガットのウルグアイ・ラウンド発足(1986年)から世界貿易機関(WTO)の設立(1995年)を経て農産物を含め貿易自由化が一段と進展するなかで、農産物価格形成も市場原理にゆだねるべきだとする政策志向が先進国を中心に世界的に強まった。そのもとで、政府介入による農産物価格支持政策は後退し、農業者に対する所得保障は別途、直接の所得保障政策として行うという方向に転換していった。日本でも、従来の米を中心とする主要食糧に対する価格支持政策遂行の柱となってきた食糧管理法が廃止され、それにかわって1994年(平成6)に「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(通称「食糧法」)が制定された。そして、価格支持政策をはじめ、政府の関与のもとでの政策遂行の重要な根拠とされてきた1961年制定の農業基本法も廃止されて、WTOの貿易自由化体制に照応する「食料・農業・農村基本法」が1999年に新たに制定された。こうしたなかで、政府による農産物価格支持政策は全体として大きく後退することとなった。
[暉峻衆三]
『佐伯尚美著『農業経済学講義』(1989・東京大学出版会)』▽『暉峻衆三編著『日本資本主義と農業保護政策』(1990・御茶の水書房)』▽『井野隆一・田代洋一著『農業問題入門』(1992・大月書店)』▽『荏開津典生著『農業経済学』(1997・岩波書店)』▽『増田萬孝著『現代農業政策論』(1998・農林統計協会)』▽『北出俊昭著『日本農政の50年――食料政策の検証』(2001・日本経済評論社)』



